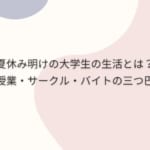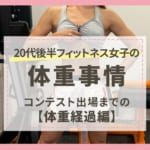私は早稲田大学に早稲田大学本庄高等学院という附属校から内部進学しました。
いわゆる“エスカレーター進学”というやつですね。一般受験を経ずに大学に進学したことを話すと「それって楽なんでしょ?」とよく言われます。
でも、実際はそんな単純な話ではありません。
今回は、附属校から早稲田に進学したリアルな体験を、メリットもギャップも包み隠さずお話しします!内部進学という選択肢がどんなものなのか、興味がある方にとって少しでも参考になれば嬉しいです。
附属校からの進学制度ってどうなってるの?
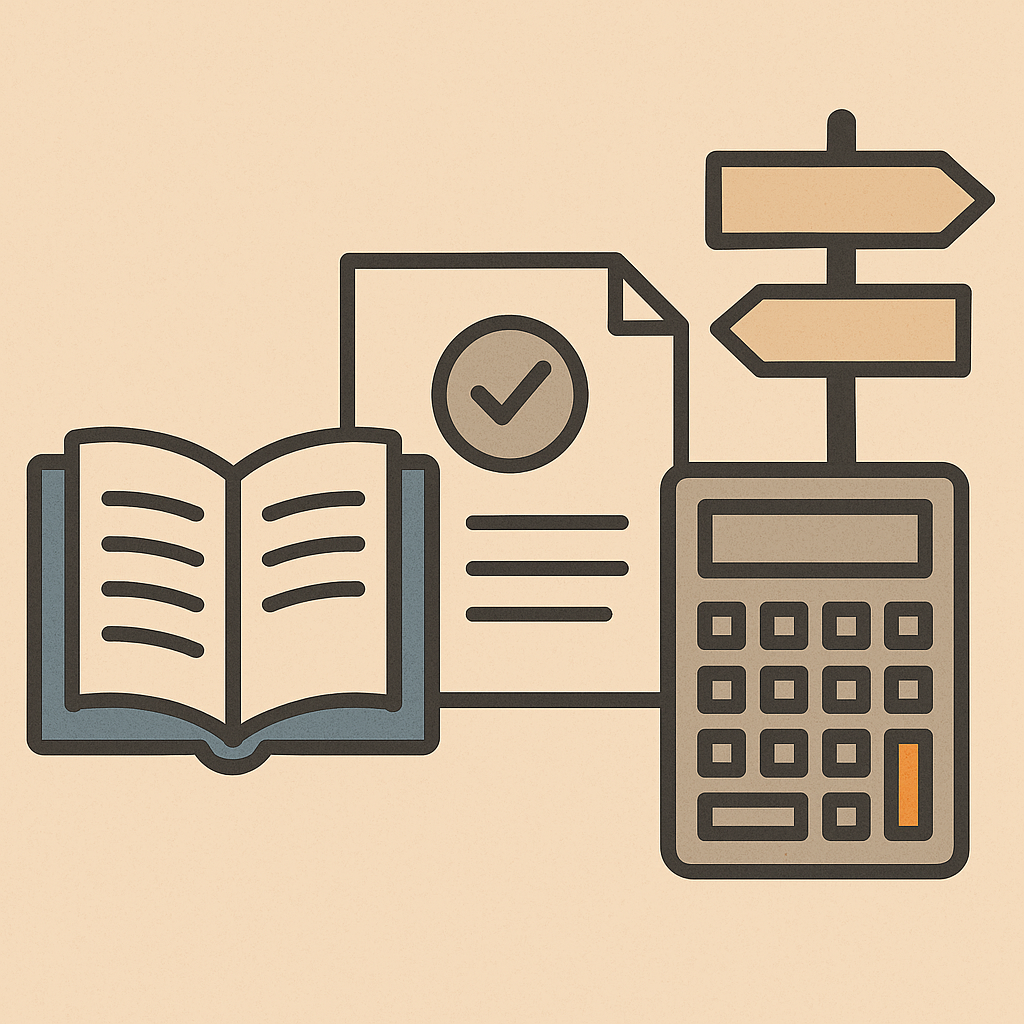
早稲田大学本庄高等学院では、普通の高校と同じように定期テストがあり、その成績によって進学先が決まります。
テストは100点満点の採点で評価され、60点を下回ると赤点扱いとなってしまい、単位が取得できません。赤点を取りすぎると留年の可能性もあるので、エスカレーターとはいえ気は抜けません。
実際、1年生のときからコツコツと勉強を積み重ねないと、成績が下がるリスクがあります。実際に、留年する生徒は毎年必ず数人はいて、多い年には20人ほどが留年することもあります。
また、卒業要件として卒業論文(約2万字)の提出も必須となっています。高校生にとって2万字という分量はなかなかのハードルで、テーマ設定から資料集め、執筆までかなりの労力が必要です。
ただ、この卒論の評価自体が大学の進学先に大きく影響することはあまりなく、進学においては日常の定期テストなどの成績が重視されます。それでも、論文を通して「自分で考えて深掘りする力」を養う経験ができるのは、大きな意味があると感じました。
進学に関して一番大きいポイントが「成績順で学部が選べる」ということ。早稲田本庄からは早稲田大学のほぼ全学部に進学することができますが、人気の学部にはもちろん成績上位の人しか進めません。
特に政治経済学部は毎年大人気で、成績の平均点が75〜80点以上ないと進学は難しいと言われています。これは科目によって配点が異なることもあり、得意・不得意のバランスも問われます。
実際には、成績表だけでなく、進学希望調査や志望理由書の提出などもあり、ただ成績がいいだけではなく、意欲や相性もある程度見られていた印象です。
先生方との面談などを通じて、「この学部に向いているか」「この進路に合っているか」といった話をする機会もありました。
もちろん、一般受験のような緊張感や模試のプレッシャーは少ないかもしれませんが、「内部進学ならではの競争」や「確実性のなさ」は確かに存在していました。
勉強面の「楽さ」と「大変さ」
附属校というと「勉強が楽そう」と思われがちですが、実際はそんなこともありません。特に政経を狙う場合、3年間コンスタントに高得点をキープしなければならないので、定期テスト前にはかなりの緊張感がありました。
たった1回のテストで成績が大きく動いてしまうこともあり、常に気を張って過ごす日々だったと記憶しています。

一般受験と違い、短期間で一気に追い上げることは難しく、日々の積み重ねがものを言います。つまり「最後の追い上げで何とかする」という作戦は使えず、真面目に毎回の授業を受けて、提出物や課題もきちんとこなす必要があります。
しかも、授業で扱う内容も決して簡単ではなく、進度も速かったので、テスト前は普通に徹夜することもありました。
ただし、一般受験生のような「浪人リスク」や「偏差値競争」からはある程度自由だったことも事実です。その点では精神的な余裕は多少あったかもしれません。
部活や行事、課外活動にも時間を割けたのは、附属校ならではの良さだったと感じています。私自身も文化祭の実行委員をやったり、バンドサークルで活動したりと、高校生活を満喫しながらも、しっかり勉強にも向き合うことができました。
精神面・人間関係のギャップ
附属校から大学に進学するときに感じたのは、精神面や人間関係でのギャップです。高校時代は周りも同じように内部進学を目指していたので、ある意味で「競争しながらも安心感のある空間」でした。
しかし大学に入ると、全国から集まった一般受験組と一緒になります。みんながそれぞれ異なるバックグラウンドを持ち、異なる価値観を持っていることを実感しました。
最初は「自分は受験してないのに…」という引け目を感じる瞬間もありました。

また、受験を通じて得た経験や知識に対するリスペクトもあったので、「自分はその苦労をしていない分、頑張らなきゃな」という気持ちで大学生活をスタートしました。特にゼミやディスカッションの場では、一般受験組の知識量や論理的思考に圧倒されたこともあります。
一方で、大学生活が始まると同じ附属校出身者同士で自然とグループができる場面も多く、そこに安心感を感じたのも事実です。でも時間が経つにつれて、徐々に一般組との垣根もなくなり、最終的には「誰が附属か」なんて気にする人はいなくなりました。サークルやアルバイト、授業でのグループワークなどを通じて、多様な人と関わるうちに、「出身校」は次第に小さな要素になっていきました。
一般受験と比べてどう?周囲との距離感

附属校出身であることを伝えると「距離を感じる?」と聞かれることもあります。結論から言えば、大学に入ってしまえばあまり距離感はありません。
特に2年生以降は、サークルやゼミ、バイトなどで多様な人と関わるようになり、出身校は関係なくなっていきます。実際、私もWebライターの長期インターンを通じて、他大学の学生ともたくさん交流することができました。
ただ、大学1年生の初めのころは、同じ附属校出身者で固まって行動することも多く、クラスやサークルの中で「この人も内部生かな?」と探り合うような雰囲気もありました。最初はどうしても出身校という共通項に頼ってしまうものですが、それが悪いことだとは思いません。徐々に自分の世界を広げていけばいいのです。
実際に関わってみると、一般受験で入ってきた人たちの中にも、自分に近い価値観や感覚を持っている人はたくさんいましたし、「内部だから」「一般だから」といった壁は、自分の気持ち次第でいくらでも乗り越えられるものだと感じました。むしろ、異なる視点を持つ人と出会えることが大学の面白さでもあり、それが成長のきっかけにもなりました。
エスカレーター進学と聞くと“楽”に聞こえるかもしれませんが、そこには独自のプレッシャーや葛藤もありました。それでも、早稲田本庄という環境でのびのびと学びつつ、大学進学への道を切り開けたことは、私にとって大きな財産です。