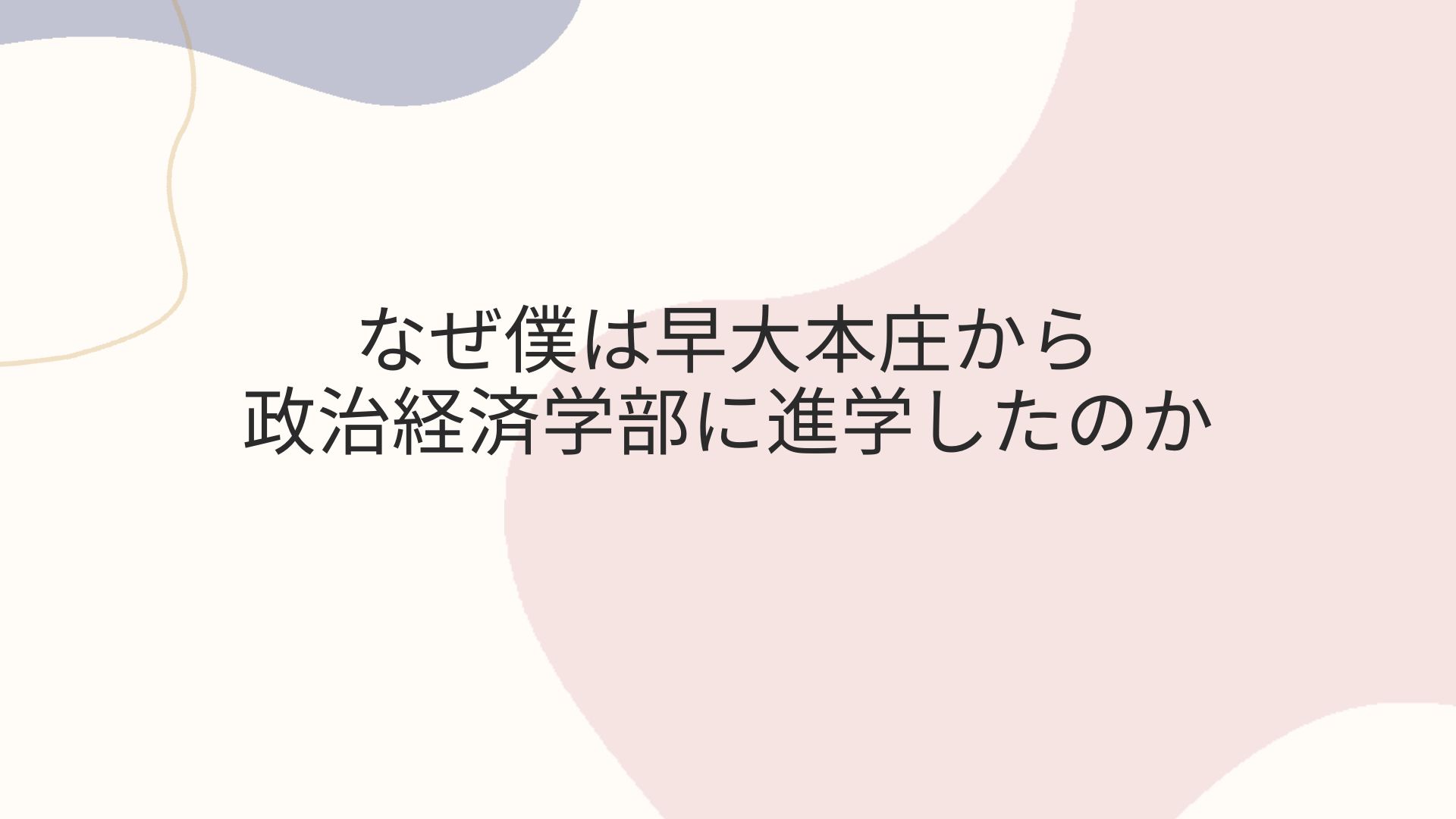私は早稲田大学本庄高等学院という附属校から、いわゆる”内部進学”のかたちでこの学部に進みました。
附属校からの進学というと「成績が良ければどこでも行けるんでしょ?」「なんとなく政経を選んだのでは?」といった声も聞こえてきそうですが、僕にとって政経への進学は、わりとしっかりと悩んで、考えて、自分なりに選んだ道でした。
この記事では、僕がなぜ早稲田の政経を選んだのか、その理由を高校時代の経験や学び、そして価値観とともに振り返りながら書いてみたいと思います。
受験や進学で悩んでいる高校生や、附属校に興味がある人にも参考になれば嬉しいです。
目次
学部選び=人生選び?そんな重圧があった
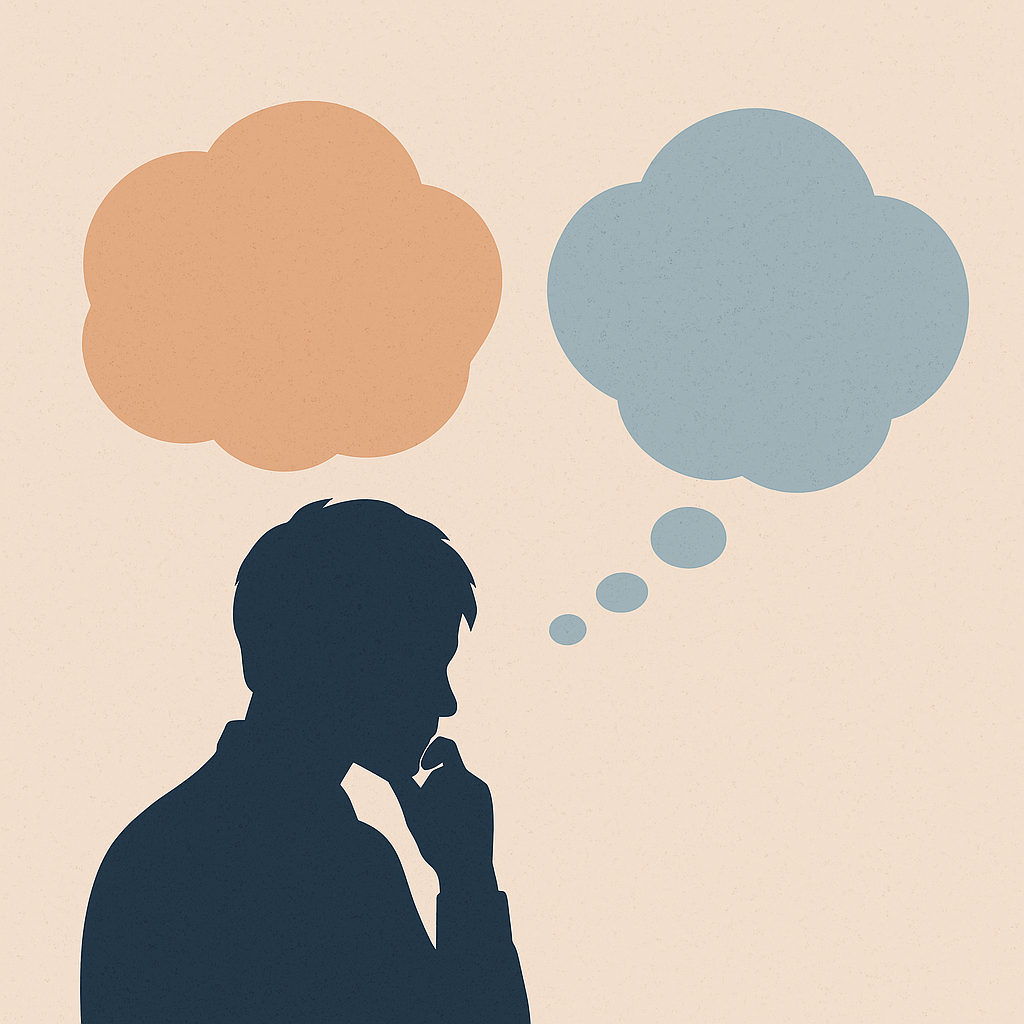
早大本庄では高校3年間の成績が、進学できる学部に直結します。
特に政経学部は附属校の中でも一番人気。狙うためには、平均75点〜80点以上が必要で、日々のテストの点数が命運を分けると言っても過言ではありません。だからこそ、学部を決めるタイミングでは「本当にここでいいのか?」と何度も自分に問いかけました。
一般受験では「とりあえず早稲田に受かった学部に入ってから考える」という選択もあるかもしれませんが、内部進学は成績順で希望を出すシステムなので、学部選び=進路選び=人生の選択のような重さがあります。
「興味がある」「将来の役に立ちそう」「なんかかっこいい」—いろんな気持ちが入り混じる中で、最終的に政経を選んだ背景には、いくつかの明確な理由がありました。
世の中の仕組みに興味があった
僕が政経に興味を持ったのは、高校2年のとき
現代社会や政治経済の授業で、日本の財政や選挙制度、世界経済の構造などを学ぶ中で、「どうしてこんな制度になってるんだろう?」「政治や経済って、実はめちゃくちゃ生活に直結してるんじゃないか?」と気づく瞬間が何度もありました。

たとえば、消費税が10%になった背景や、その影響が家計にどう及ぶか。円安が進んだときのニュースを見て、なぜそれが海外旅行に関係するのか。
こんな風に、一見バラバラに見える出来事や政策が、じつはひとつの”構造”でつながっていることに気づいてから、「もっと知りたい」「深く理解したい」と思うようになりました。
社会の仕組みを知ることは、自分の意見を持つことにつながるし、それがやがては誰かに影響を与える行動にもなり得る——そんな感覚を得たのが、政経を選んだ一番の理由です。
先生の一言が背中を押してくれた
もうひとつ、政経を目指す決定打となったのが、高2のときの担任の先生の言葉でした。ある日の進路面談で、僕が「将来、何をやりたいかまだはっきりしていなくて……」と悩んでいたときに、その先生がこう言ってくれました。
「将来がまだ見えなくても、”考える力”と”社会を捉える視点”を養える学部に進むのは悪くないと思うよ」(うろ覚え)
この言葉に、すごく救われました。確かに、政経は就職にも強いと言われるし、選択肢を狭めるどころか広げてくれる学部でもある。だからこそ、”今決まっていなくても、ここでなら将来につながる何かが見つかるかもしれない”と、前向きな気持ちで選ぶことができたんです。
政治経済学部って、実際どうなの?
進学してからというもの、「やっぱりここを選んでよかった」と思う瞬間は何度もありました。授業では、政治学・経済学・哲学・歴史など、いろんな学問が交差していて、「考えることが好きな人」にとっては本当に刺激的な環境です。
特に印象的だったのは、1年生のときに受けた「公共政治」という授業。ロールズやハーバーマスといった現代思想の巨人たちの議論を通して、「正義とは何か」「公共とは何か」といったテーマを深く考えさせられました。自分の意見を文章にして提出する課題も多く、ただ知識をインプットするだけでなく、それを使って思考を広げる訓練ができる点も魅力です。
また、周囲の学生も「社会に対して関心がある人」が多くて、会話の内容が自然と時事や国際問題に向かうこともしばしば。そういう環境に身を置けたことで、自分の視野も自然と広がったように感じます。
まとめ:迷ってもいい、でも「納得できる理由」があれば強い
政経を選んだ理由は、最初から明確だったわけではありません。むしろ、いろいろと迷って、不安も感じて、それでも自分なりに「なぜここに行きたいのか」を考え抜いたことが、進学後の充実につながっている気がします。

附属校から進学する場合、周りの期待や見えないプレッシャーもあるかもしれません。でも、最終的には「自分がどう感じているか」「何を大切にしたいか」が一番大事なんだと思います。
進路選びは、自分の未来への投資。だからこそ、迷いながらも納得できる選択ができるよう、できるだけ多くのことを知り、自分自身と向き合ってみてくださいね。この記事が、その一助になれば嬉しいです。