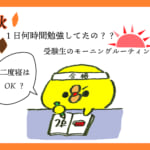皆さんこんにちは!早稲田大学国際教養学部のせうです!
海外留学ってワクワクするけど、実際どこに行くべきか迷いますよね。治安、費用、語学、環境、キャリアへの影響……。考えることが多くて、最初の一歩が踏み出せないという人も多いはず。
この記事では、実際にアメリカ・ボストンで1年間の留学を経験した私が、「留学前に知っておきたかったこと」や「行ってよかった理由」をすべて詰め込みました。実体験を交えながら、留学先選びのポイントから、おすすめの国や都市、リアルな学生生活まで、他ではなかなか読めない情報をお届けします。
目次
留学の目的を明確にしよう
私は、大学で国際関係を学んでいたため、「多文化環境でのディスカッション力を身につけたい」「日本ではできない経験を通じて自己成長したい」という思いがありました。そのため、アカデミックレベルが高く、多様な価値観に触れられる環境として、アメリカ・ボストンを選びました。
目的が明確になると、選ぶべき国・都市・大学も自然と絞れてくるはずです。
留学先を選ぶポイント5つ
長期間、日常生活のすべてを過ごす場所だからこそ、自分の希望や性格、学びたい分野との相性をしっかり考えることが大切です。ここでは、実際に私がボストンを選ぶときに重視した視点を含めて、留学先を選ぶ上で大切な5つのポイントを詳しく解説します。
教育の質・専門性
まず注目すべきは、その国・その大学が自分の「学びたい分野」にどれだけ強みを持っているか。
私が選んだボストンは、ハーバード大学やMITといった名門大学が集中する「学問の街」。街全体が学生と研究者で構成されているような雰囲気で、日常の会話の中にも知的な刺激があふれていました。「どうせ行くなら、最高の環境で学びたい」という気持ちが、ボストンという選択を後押ししてくれました。
治安
特に女性の一人暮らしや夜遅くまでの通学がある場合、「安心して歩けるかどうか」は生活の質に直結します。
アメリカというと「危険」というイメージを持たれがちですが、実際には州や都市によって大きな差があります。ボストンは比較的治安が良く、特に大学周辺や住宅街では警察のパトロールも多くて安心でした。私は夜9時くらいに図書館から帰ることもよくありましたが、怖いと感じることは少なかったです。
留学前には、実際に現地に住んでいる日本人や留学生のブログ・SNSを見て「リアルな声」を調べておくのがおすすめです。
生活費・物価
例えば、私が留学したボストンはアメリカの中でも比較的物価が高い都市のひとつで、シェアハウスでも月10万円前後は当たり前。外食はチップ込みで1食2,000円以上することもあります。一方で、カナダやドイツなどは生活費が比較的リーズナブルな都市も多く、長期滞在には向いている場合も。
「予算の中でどこまで学べるか?」という視点はとても重要。事前に現地の物価を調べて、1カ月の生活費をざっくりシミュレーションしてみましょう。
気候・生活環境
意外と見落とされがちなのが「気候」。でも実は、これが日々のモチベーションや健康に大きく影響します。私がボストンで初めて経験したのは、マイナス15℃の極寒!ダウンコートに手袋・マフラーは必須で、地下鉄のホームでは息が白くなりました(笑)。でもその分、紅葉の美しさや雪景色の幻想的な風景には感動しました。
もし寒さが苦手なら、オーストラリアやカリフォルニアなど温暖な地域を検討した方が良いかもしれません。反対に、四季の変化が好きな人は東海岸やヨーロッパ圏の方が合うでしょう。
また、都市か田舎かでも大きく違います。便利さ・刺激を求めるなら都市部、落ち着いて学びたいなら地方都市や自然に近い場所がベストです。
言語・文化の違い
英語圏といっても、アメリカ英語・イギリス英語・オーストラリア英語では発音や言い回しがかなり違います。初めて聞いた時、「同じ英語なのに何言ってるか分からない…」と感じたこともありました。
また、文化や宗教、価値観の違いにも戸惑う場面が多くありました。例えば、アメリカでは「自分の意見をはっきり伝える」ことがとても大事にされていて、授業中でも教授と学生が対等に意見をぶつけ合います。最初は勇気が要りましたが、次第にその自由な雰囲気に馴染み、自信を持って発言できるようになりました。
「この文化、性格的に自分に合いそう?」と想像しながら国を選ぶことも、実はすごく大事なステップです。
おすすめの留学先7選(体験談+比較)
アメリカ(ボストン)★私の留学先!
ハーバード大学、MIT、ボストン大学など、世界屈指の教育機関が集まる「学生の街」。治安も良く、移民国家ならではの多様な価値観に触れられます。インテリで落ち着いた雰囲気もあり、勉強にも集中できる最高の環境でした。
カナダ(バンクーバー)
フレンドリーで親切な国民性が魅力。自然も多く、都市機能も整っており「初めての海外生活」として非常に過ごしやすいです。語学学校も充実。
イギリス(ロンドン)
歴史と伝統に包まれたヨーロッパ文化を学びたいなら。日本との文化的距離がありつつも、英語環境なので学びやすいです。学費は少し高め。
オーストラリア(シドニー)
自然と都市が融合した生活。ワーキングホリデー制度があり、英語を学びながら働くことも可能。生活費は少し高めですが、開放的な文化が魅力。
ニュージーランド(オークランド)
落ち着いた環境で自然に囲まれながら学びたい人に最適。医療・教育の質が高く、治安も良いため安心して暮らせます。
ドイツ(ベルリン)
英語で学べるプログラムが豊富かつ学費が安い。工学・音楽・哲学分野が特に人気。物価も安く、ヨーロッパ旅行にも便利です。
韓国(ソウル)
日本から近く、文化的にも馴染みやすい。K-POPや韓国ドラマなどカルチャーをきっかけに韓国語を学ぶ人が増加中。費用も比較的リーズナブル。

私のボストン留学体験記
ボストンでの1年は、留学生活というより「人生を再設計する時間」だったと感じます。
最初の数週間はすべてが新鮮で、毎日が発見の連続。小さなスーパーで買い物をすること、バスに乗ること、大学のカフェで注文すること……どれも慣れるまでに時間がかかりました。でもその分、少しずつ「この街で生きている」という実感が湧いてきました。
大学では毎日が刺激的でした。教授たちの授業スタイルは日本と大きく違い、学生の発言が歓迎され、ディスカッション中心。私も最初はうまく発言できず悔しい思いをしましたが、勇気を出して発言を重ねるうちに、だんだんとクラスの中でも「自分の存在感」を持てるようになりました。留学前には考えられなかった成長です。
友人関係にも大きな学びがありました。クラスメートは世界中から集まっており、宗教、文化、価値観の違いを体感できる日々。
ある日、授業後に友人と宗教観について深く語り合い、「信仰ってこんなにも人を強くするんだ」と心から感動したこともあります。
また、寮でのルームメイトは中東出身の女の子で、彼女からはイスラム文化や伝統料理をたくさん教えてもらいました。お互いの違いを尊重しながら過ごした1年間は、教科書では絶対に得られない「生きた多文化理解」の時間でした。
生活面では、日本との違いに戸惑うこともありました。例えば、冬の寒さは想像以上で、雪が腰の高さまで積もることもしばしば。外を歩くだけでも大変な日もありました。でも、近くのカフェでホットチョコレートを買って友人と語り合う、そんな日常の一コマが心に残っています。
休日には、美術館や図書館、公園などを巡って、ボストンの文化と自然を楽しみました。特にハーバード大学の図書館や、チャールズ川沿いの風景は、今でも目を閉じれば思い浮かぶほど印象的です。秋には紅葉が街を彩り、歩いているだけで気持ちがリセットされるような感覚になりました。
一方で、ホームシックや授業についていけない焦り、人間関係の難しさも経験しました。だけど、その一つひとつを乗り越える中で、自分が少しずつ強くなっていくのを実感できました。失敗しても、助けてくれる人が必ずいる。そう思えたのは、ボストンという街の優しさと、支え合う文化のおかげです。
留学を通じて得られたもの
留学を終えた今、もし1年前の自分に「留学してどうだった?」と聞かれたら、私は迷わず「行って本当に良かった」と答えます。英語力や知識の向上はもちろんですが、それ以上に「人間としての土台」がぐっと強くなったと感じています。
まず、行動力と自己主張の力。
ボストンでは、授業でも日常生活でも、自分の意見を伝えることが求められます。たとえ英語が完璧でなくても「私はこう思う」と伝える勇気が評価される文化がありました。最初は「間違えたらどうしよう」とためらっていましたが、黙っていては何も伝わらないという現実に直面し、失敗を恐れず話すことを覚えました。
今では、相手が誰であっても堂々と話せるようになりましたし、その変化は就職活動やプレゼンの場面でも大きな武器になっています。
次に得たのは、多様性への理解と受容力です。
特に印象的だったのは、ある授業で「貧困と教育格差」をテーマにディスカッションをしたとき。アフリカ出身のクラスメートが、自国の教育制度について語った内容に衝撃を受けました。「教科書が1冊もない学校もある。でも、勉強したくて毎日2時間歩いて通う子どもがいる」と。自分の中の「当たり前」が大きく揺さぶられ、「自分が学べる環境にいることは、当たり前ではない」と心から思った瞬間でした。
そして最後に挙げたいのが、人とのつながりの大切さです。
留学中、何度も助けられました。言葉が通じず困っていたときに手を差し伸べてくれた現地の学生、文化の違いに戸惑っていた私を気遣ってくれた寮のルームメイト、そして「大丈夫?」と頻繁に連絡をくれた日本の家族や友人。どんなに遠くにいても、温かい気持ちはちゃんと届くんだということを実感しました。
この1年間で得たものは、「英語力」や「異文化体験」だけではありません。
「自分ってこういう人間なんだ」と、等身大の自分と向き合う時間を持てたこと。
「私も、誰かを助けられるような人になりたい」と思えるようになったこと。
そういった“目に見えない力”が、これからの人生で一番の支えになっていくと信じています。
留学前にしておいてよかったこと・しておけばよかったこと
よかったこと
- 日常会話のリスニングを事前に鍛えていきました
- 留学経験者に話を聞いて準備しました
- お気に入りの日本食(味噌汁・ふりかけ)を持っていきました
- 語彙力・文法の強化:留学前に基本的な英語力を身につけておいたおかげで、現地での授業や生活にも早くなじめました。特にリスニング力を鍛えておくのは重要
- プレゼンやレポートの練習:日本の大学でも英語プレゼンを経験しておいたことで、現地の授業で戸惑うことが少なかったです
- 現地の文化について調べたこと:アメリカのマナーや文化、宗教的配慮などを事前に学んでいたため、トラブルも避けられました
- SNSで現地の生活情報を収集:YouTubeやInstagramで現地の学生生活を知ることで、実際の生活のイメージを持って渡航できました
しておけばよかったこと
- スピーキング力の強化(アウトプット不足を痛感)
- 現地での交通機関のルール確認(バスの乗り方がわからず迷子に)
- 渡航前に現地での銀行口座開設やSIM事情を調べておくべきだった
- 日本から持っていく衣類の「季節バランス」調整(冬の装備足りなかった…)

ボストンでの1年間の具体的なイベントやエピソード
特に印象深かったのが「Japan Fes」というイベントへの参加です。
このイベントは、ハーバード大学やMITなどの名門大学が集まるボストンで開催され、例年10万人規模の来場者がある大規模な日本文化紹介イベントです。私はこのJapan Fesの中で、学生実行委員会の立ち上げからリーダー就任までを経験しました。
もともと、学生に任されていたのはSNSでの広報活動のみ。しかし、学生たちの中から「自分たちでフードブースを出したい」という声が上がり、私はその声を形にすべく動き出しました。
まず、実行委員会の中で唯一の学生代表として、ビジネスパーソンや大学教授で構成された大人たちと交渉する役割を担いました。そして、もう一つの大きな役割が、40名以上に及ぶ学生実行委員をまとめあげ、プロジェクトを円滑に進めることでした。
私たちが挑戦したのは、3000ドルという高額な出店費用をかけた完全新規のフードブース。勝算を得るために注目したのは、ボストンの食文化。現地にはベジタリアンが多く、既存の他ブースの出店メニューは炭水化物に偏っていました。そこで、私たちは「野菜×つまめるおかず」をテーマに据え、日本食としても親しみやすい「餃子」を販売メニューに決定。
このビジョンを事業計画として作成し、私は実行委員会でプレゼンを行いました。その結果、実行委員長からの高評価を得て、出店費用の援助を引き出すことに成功。まさに学生の“想い”が、大人の“資金”を動かした瞬間でした。
イベント当日は、販売計画の上限として想定していた1,500食をすべて完売。売上は1万ドルに達し、見事に黒字化を達成しました。これは、Japan Fesの歴史の中でも過去最高の来場数と売上規模だったそうです。
この経験を通じて私は、「想いを行動に変える力」「多様な人と交渉する力」「チームを率いる力」の重要性を肌で学びました。そして何より、ボストンという土地の多様性や寛容さが、こうした学生主体の挑戦を後押ししてくれたと感じています。
留学前後の英語力の変化や就職活動でどう活きたか
出発前はTOEFLスコアが70点台で、会話もスムーズではありませんでした。しかし、現地では「英語を使わざるを得ない環境」に毎日身を置くことで、リスニングとスピーキング力が飛躍的に伸びました。帰国時にはTOEFL iBT 90点以上、日常会話もほぼ問題なしに。
英語力だけでなく「異文化適応力」「プレゼン能力」「自己表現力」も鍛えられ、それが就活でも大きな強みになりました。実際、グローバル人材を求める企業の面接では、ボストンでの経験や、自分の変化を具体的に話せたことで評価されたと思います。
また、チームで何かを成し遂げる力や、初対面でも臆せず話せる対人力など、社会人になってからも活きるスキルが身についたと感じています。
何よりも、前章で述べた “Japan Festival Boston”でリーダーを務めた経験は、チームで何かを成し遂げることが好きという、自身のやりがいを感じる瞬間を再確認でき、就職活動で非常に役立ちました。
語学力だけでなく、私自身が渇望していた唯一無二の経験をしたことで、留学で得た経験全てが自身の強みになったと確信しています。
まとめ
私が1年間過ごしたボストンは、世界トップレベルの教育機関が集まり、学びに対する熱意と多様性にあふれた場所でした。Japan Fesのような大規模イベントに学生リーダーとして参加できたのも、ボストンという土地だからこそだったと感じています。異なる背景を持つ人々と協働し、一つのプロジェクトをやり遂げた経験は、今後の人生において大きな財産になっています。
もちろん、どの都市・大学にもメリットとデメリットがあります。でも大事なのは、「自分に合うかどうか」を見極めること。
迷っているなら、まずは一歩踏み出してみてください。行動することでしか見えない世界が、きっとそこにあります。