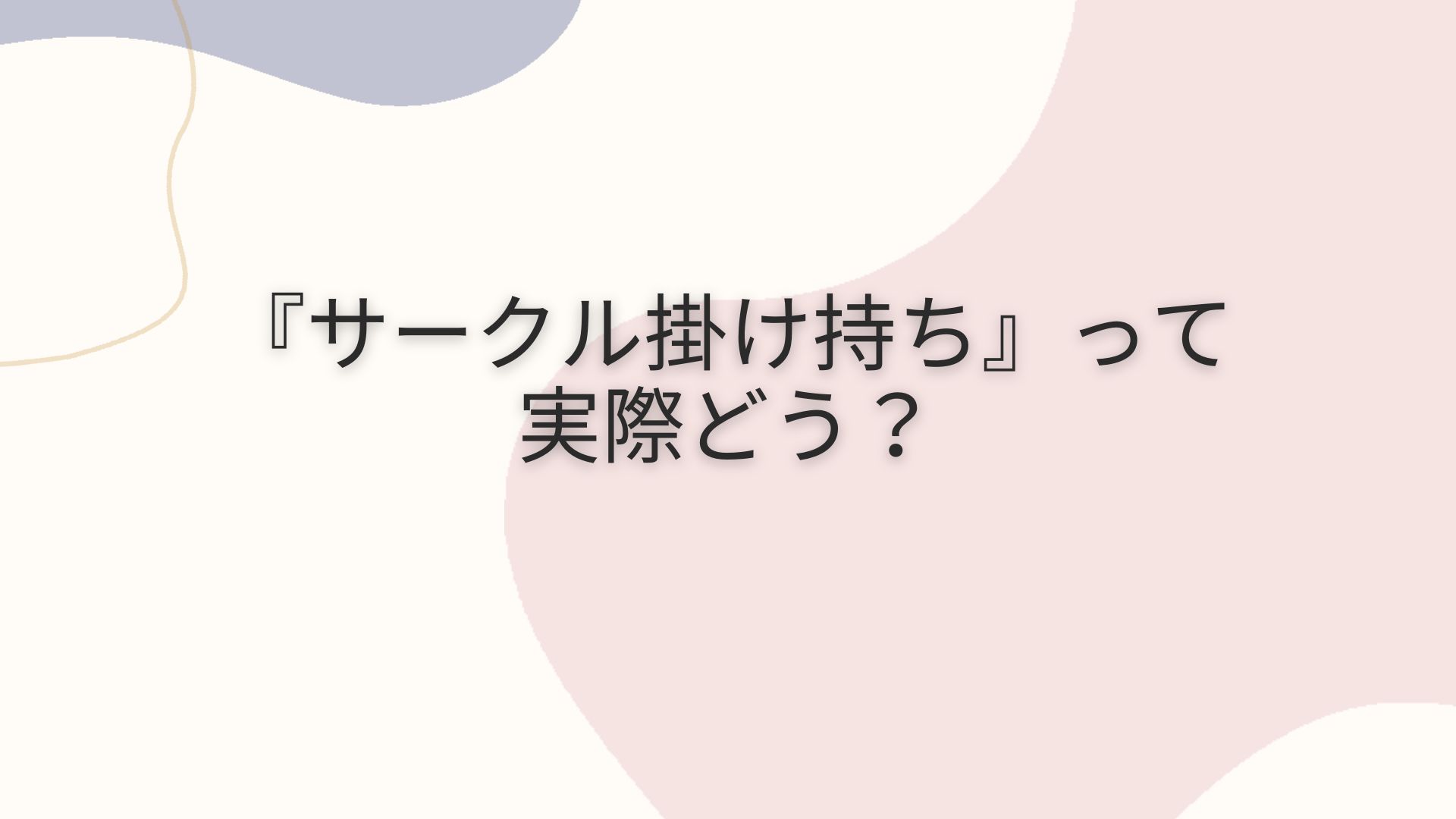大学に入ったらやってみたいことのひとつ「サークル活動」。
でも、あれもこれも気になって一つに絞れない……そんなあなたに浮かぶのが「掛け持ちってアリ?」という疑問。
実は、早稲田をはじめとするサークル文化が盛んな大学では、複数サークルに所属する学生も少なくありません。
本記事では、アコースティックバンドサークル「ヨコシマ。」とお菓子作りサークル「Ws.dolce」の2つを掛け持ちしてきた筆者が、掛け持ち生活のリアルを赤裸々に紹介します。
目次
サークル掛け持ち、ぶっちゃけどうなの?
「サークルって、ひとつに絞るべき?それとも掛け持ちってアリ?」
大学生活が始まると、多くの新入生が一度は直面するこの悩み。
特に早稲田のようにサークル数が圧倒的に多い大学では、どれも魅力的に見えて「一つに決めきれない!」という人も多いのではないでしょうか。
実際に新歓期間中は、昼休みも放課後も、キャンパスのあちこちでビラ配りや演奏、勧誘の声が飛び交い、つい色んなサークルに顔を出したくなるものです。
私自身も例外ではなく、大学入学後に複数のサークルに参加し、そのまま「ヨコシマ。」というアコースティックバンドサークルと、「Ws.dolce」というお菓子作りサークルの2つに所属しています。
もちろん、サークルを掛け持ちすると、その分活動の幅も広がりますし、いろいろな人と出会えて楽しいこともたくさんあります。でも一方で、
- 掛け持ちって本当に両立できるの?
- 活動が被ったときはどうするの?
- バイトや授業との兼ね合いは?
- どちらのサークルにもちゃんと馴染めるのか不安……
といった疑問や不安を抱える人も少なくないと思います。特に大学生活が始まったばかりの頃は、何にどれだけ時間がかかるのか、どのくらいの負荷なのか、自分でもまだよくわかっていないものです。
だからこそこの記事では、私の実体験をベースに、
- 掛け持ちのリアルな生活ってどんな感じ?
- 掛け持ちしてよかったこと、しんどかったこと
- 続けるための工夫や向き・不向きの判断基準
などを包み隠さずお伝えしていきます。
「大学生活をもっと充実させたい」「やりたいことが多すぎて困ってる」「でも失敗したくない」と感じているあなたに、少しでもヒントを届けられたら嬉しいです!
掛け持ちのリアル|実際にやってみて感じたこと
実際にサークルを掛け持ちしてみると、「意外と両立できるじゃん」と思う時もあれば、「これはちょっとキャパオーバーかも…」と感じる瞬間もありました。
「ヨコシマ。」と「Ws.dolce」の2つのサークルを掛け持ちしている私の体験から、リアルな日常と感想をお伝えします。
掛け持ちスケジュール、こんな感じでした
ざっくりとした1週間の過ごし方は以下の通りです。
- 月曜・木曜:ヨコシマ。の練習(週2回)
大学の教室や音楽スタジオを借りて、1〜2時間ほどアンサンブルの練習を行っていました。活動は自由参加型に近く、他の予定との兼ね合いで無理なく参加できるのが魅力でした。 - 隔週日曜:Ws.dolceのスイーツ制作会
お菓子作りの会は月に1〜2回程度で、事前にレシピを決めて材料を用意し、みんなで協力しながらケーキや焼き菓子を作ります。こちらもゆるやかな雰囲気で、楽しみながら参加できました。 - 平日昼:空きコマで友達とご飯 or バイト or 課題タイム
- 土曜:バイト(Webライターのインターン)
- 日曜夜:休憩 or レポート・予習の時間
ライブ前2週間は修羅場だけど、それ以外はゆるめ
ヨコシマ。は、ライブの直前2週間になるとさすがに忙しくなります。
スタジオでの全体練習、パートごとのリハーサル、タイムスケジュールの確認や、当日運営の準備などで一気に予定が詰まっていきます。演奏以外の裏方作業もあるため、その時期は自然と「ヨコシマ。中心の生活」になりがちです。
ただ、それ以外の時期はそこまで負担は大きくなく、比較的自由度の高い活動スタイルでした。参加・不参加の強制もなく、「今週はバイトが忙しいのでお休みします」みたいなやり取りも普通にOKな空気感です。
掛け持ちの壁|たまに感じる“罪悪感”
活動がバッティングしないようにうまく選んだつもりでも、試験期間や課題ラッシュ、バイトの繁忙期が重なると、どうしてもサークル活動が後回しになってしまう週もあります。
そんなときは、「今週どっちにも行けてない…」「名前だけの幽霊部員になってるかも…」という軽い罪悪感がじわじわ湧いてきます。
特に、イベントの準備時期などでみんなが頑張っている空気を感じると、自分が貢献できていないことに対して後ろめたさを感じてしまうのも事実です。
それでも「やってよかった」と思える理由
とはいえ、掛け持ちにはそれを上回る価値がありました。
音楽とお菓子、まったく異なるジャンルに触れられることは、日々の気分転換になりましたし、2つのサークルでまったく違うタイプの友達ができたのも楽しかったです。
何より、「自分の大学生活を、自分らしくカスタマイズしている感覚」がありました。「あれもやってみたい」「こっちも楽しそう」という好奇心に素直に動けたことは、今でも良かったと思っています。
結論:掛け持ちのリアルは「波がある」
掛け持ち生活は、ゆるい時期と忙しい時期の差が大きいのが特徴です。
サークルのカラーや時期によって負担感も変わるため、「常に大変」ではなく、「時期によってうまく乗り切る工夫が必要」といったイメージが近いかもしれません。
掛け持ちのメリット
サークルを掛け持ちすると、「大変そう」という印象を持たれることもありますが、実際にやってみて感じたのは、得られるものの多さです。
異なるコミュニティで、異なる自分に出会える
まず何よりも感じたのが、コミュニティが増えることで人間関係の幅が一気に広がるということ。
「ヨコシマ。」では音楽好きが集まっていて、練習終わりにライブ映像を見ながら盛り上がったり、ギターのコード進行について語り合ったりと、趣味を深められる仲間ができました。
一方、「Ws.dolce」ではお菓子づくりを通じて協力し合う中で、自然と打ち解けていく柔らかい雰囲気がありました。
このように、全く異なる属性の人たちと関われることは、自分の視野を広げてくれるし、人間関係の“逃げ道”にもなるんです。
片方のサークルでちょっと疲れたときに、もう一方に行くと自然とリフレッシュできたりすることも多々ありました。
気分転換になる、生活にリズムが生まれる
ひとつのことに集中するのも大事ですが、時には気分が煮詰まってしまうこともあります。
そんな時、掛け持ちしていると「今日はこっちの活動に集中してみよう」「今週はゆるくスイーツだけ楽しもう」と自分のテンションや状況に応じて選べる自由さがあるのは、非常にありがたいです。
「音楽」と「お菓子」という全く毛色の違う活動を行き来することで、自然と気分転換になり、生活のリズムが整っていく感覚がありました。
サークルごとの文化・運営方法が学べる
また、サークルによって運営体制や雰囲気、ルールなどが全く異なるため、「組織を見る目」が鍛えられるのも思わぬメリットでした。
例えば「ヨコシマ。」ではライブ運営や新歓イベントなどに携わる中で、縦のつながりや役割分担の重要性を学びました。
一方「Ws.dolce」では少人数でのチームワークや準備の効率化が鍵となる場面が多く、また違った学びがありました。
これらの経験は、就職活動の面接でも具体的なエピソードとして活かすことができましたし、何より「自分はこういう組織の雰囲気が合うな」といった自己理解にもつながりました。
「所属が多い」ことは話のネタにもなる
地味に助かったのが、「サークル何やってるの?」という大学あるあるの質問に対して、ネタが多いこと(笑)。
「ギター弾いてるし、ケーキも作ってるよ」と答えると、ほぼ必ず「えっ、どっちも!?」と驚かれ、その後の会話が広がりやすくなります。新しい友達づくりのきっかけとしても、話題のストックがあるのは大きな強みだと感じました。
掛け持ちのデメリット・注意点
ここまで掛け持ちの良い面について紹介してきましたが、実際にやってみると「ここはちょっと大変だったな」と思う瞬間も多々ありました。
スケジュール調整が地味にしんどい
サークルを2つ掛け持ちしていると、予定が被ることは避けられません。とくにイベント前などは、どちらのサークルも活動が活発になるため、スケジュールがパンパンになることもあります。
その最たる例が、早稲田祭の時期でした。
「ヨコシマ。」では、4年生として迎える引退ライブの準備が大詰めを迎えており、演奏の最終リハーサル、ライブ当日のタイムスケジュール調整、機材の搬入計画など、運営メンバーとしてやることが山積み。
一方、「Ws.dolce」では、早稲田祭名物の模擬店(お菓子系の屋台)出店の準備に追われていました。


ちなみに、この文字は僕が書いたものです。
試作会から材料発注、当日のシフト調整、店の装飾や看板づくりまで、こちらもメンバー全員でフル稼働。
結果的に、「日中は屋台で販売、夕方からライブ準備、夜はリハと会議」というハードスケジュールで、ほぼ毎日キャンパスに朝から晩までいる生活が続きました。
正直、心身ともに限界ギリギリだったと思います。
どちらにも“中途半端”になってしまうことがある
イベントが重なると、どうしてもどちらかにしわ寄せがいきます。例えば、ヨコシマ。の練習を優先すればWs.dolceのミーティングに出られず、逆に屋台の仕込みに集中すると、ライブパートの調整に支障が出てしまう。
どちらも大事にしたいのに、「どっちにもちゃんと貢献できていない気がする」という罪悪感が積もっていきました。
メンバーの中には、私の忙しさを理解してくれている人もいましたが、それでもやっぱり「中途半端な人」という印象を与えてしまっていないか不安になる瞬間もありました。
バイトや授業との両立が難しくなることも
早稲田祭のような大型イベントの前は、当然バイトとの両立もかなり難しくなります。
私はWebライターの長期インターンをしていたので、納期のある原稿作成やミーティングなども重なり、スケジュールが完全に破綻寸前でした。
こうしたピーク時には、「睡眠時間を削る」しかないという日も出てきます。冷静に考えれば何かをセーブすべきなのですが、「どちらもちゃんとやり切りたい」という思いが強いぶん、体力的にも精神的にもきつくなってしまうんですよね。
サークルのカラーによっては、掛け持ちが歓迎されないことも
また、すべてのサークルが掛け持ちに寛容というわけではありません。
中には、「他に所属している人は幹部にできない」など、暗黙のルールがあるところも。
私が所属していたサークルでは運よく寛容な雰囲気でしたが、他大学の友人からは「掛け持ちを理由にフェードアウトさせられた」という話も聞いたことがあります。入会前に掛け持ちについて確認することはかなり大切です。
こうしたデメリットや困難な場面は、事前に知っておくだけで対策が立てられます。
特に、早稲田のようにサークル文化が活発な大学では、イベントの時期やサークルの役割に応じて負担が大きくなる時期があることを踏まえて、自分の余力をうまくマネジメントする力が求められると感じました。
掛け持ちを続けるコツ・判断ポイント
サークルを掛け持ちすると、たしかに楽しいことが増える一方で、両立に工夫が求められる場面も多々あります。
ここでは、実際に私が掛け持ち生活を通して見つけた「続けるためのコツ」や「掛け持ちに向いているかを見極めるポイント」を紹介します。
サークルの「活動頻度」と「柔軟性」は事前チェックが大事
掛け持ちを始める前にまず確認しておきたいのが、各サークルの活動頻度と、参加の自由度です。
私が「ヨコシマ。」と「Ws.dolce」を無理なく両立できたのは、それぞれの活動頻度が週1〜2回程度、かつ出欠が比較的柔軟だったから。
固定の練習日がある一方で、「今週は行けません」と言いやすい空気感だったのは本当に助かりました。
逆に、毎週のように全員参加が必須なサークルを2つ選ぶと、スケジュールが完全に破綻します。見学時や新歓期に、「どのくらいの頻度で活動してる?」「来れない日があっても大丈夫?」と聞いてみるのがおすすめです。
目的を明確にすることで“優先順位”がつけやすくなる
サークルを掛け持ちする場合、それぞれのサークルに対して「自分は何を求めているのか」を明確にしておくと、迷った時の判断がしやすくなります。
たとえば私の場合、
- 「ヨコシマ。」→音楽を続けたい、ライブを本気でやりたい、運営にも関わりたい
- 「Ws.dolce」→お菓子作りを楽しみたい、人とのんびり関わりたい
と、目的が少し違っていたので、イベントや時期によって「今はこっちを優先しよう」という判断がつけやすかったです。
どちらも“主戦場”にする必要はなく、ひとつは“趣味的にゆるく楽しむ”のでも全然OK。自分のキャパや生活リズムに応じて、力の入れ方を調整していくことが大切です。
掛け持ちをするなら「自分で自分を管理できる人」向き
正直なところ、掛け持ちが向いている人・向いていない人はいます。
- 予定をうっかり忘れがちな人
- 「全部ちゃんとやらなきゃ」と思いつめてしまう人
- 人間関係に過敏で、断ることが苦手な人
こういったタイプの人は、掛け持ちを始めると気づかないうちにストレスが溜まってしまうかもしれません。
逆に、
- Googleカレンダーで予定管理ができる
- 状況に応じて断ることができる
- 人間関係の「距離感」をうまく調整できる
といったタイプの人は、複数のサークルをうまく使い分けて、むしろ大学生活の充実度を高められる可能性が高いです。
「やってみてダメだったら戻せばいい」くらいの気持ちでOK
最後に伝えたいのは、掛け持ちは“失敗してもいい”ということです。始めてみて「やっぱり一つに絞ったほうが楽しいかも」と思ったら、それは全然アリ。むしろやってみたからこそ、そう思えたということです。
最初から「どちらも完璧にやろう!」と思いすぎると苦しくなるので、「とりあえずやってみて、しんどかったら方針を変えよう」くらいの柔軟な気持ちでいることが、長く楽しく続けるコツだと思います。
結局、サークル掛け持ちはアリ?ナシ?|“自分らしく”大学生活をデザインしよう
ここまでサークル掛け持ちのリアルな体験を紹介してきましたが、結局のところ、サークルの掛け持ちは「人による」というのが正直な答えです。
でも、それだけではもったいないので、あえて一歩踏み込んで「こんな人にはおすすめ!」「こんな人は要注意!」というポイントをまとめてみます。
掛け持ちが“アリ”な人
- 好奇心が旺盛で、いろんなことにチャレンジしたい人
- 自分の時間をある程度コントロールできる人
- 趣味や価値観の違う友人を作りたい人
- 忙しい時期にも前向きに工夫できるタイプの人
こういった人にとって、サークルの掛け持ちはまさに大学生活を豊かにする最高の手段になります。
私自身、「音楽」と「お菓子」という異なるジャンルを行き来したからこそ、多様なコミュニティに所属できて、世界が広がった実感があります。
掛け持ちが“ナシ”かもしれない人
- 一つのことに集中して極めたいタイプ
- 忙しくなるとパンクしがちな人
- 「全部ちゃんとやらなきゃ」と抱え込んでしまう人
- 時間やスケジュールの自己管理が苦手な人
こういうタイプの人は、無理に掛け持ちをしようとすると、どちらのサークルにも疲れてしまいかねません。1つのサークルで深く関わることにも、掛け持ちとは違った価値があるというのもまた真実です。
大事なのは「自分のペースを知ること」
結局、サークルの掛け持ちは“正解”があるものではなく、自分の大学生活にどう組み込むかの選択肢のひとつです。
私にとっては、掛け持ちによって出会えた人、広がった経験、充実感はかけがえのないものでした。そして、忙しさの中で自分の限界や向き不向きを知るきっかけにもなりました。
これから掛け持ちを考えている人には、ぜひ「やってみたい!」という気持ちを大切にして、一歩踏み出してほしいと思います。
そして、もし「ちょっときついな」と感じたら、方向転換もまったく問題なし。大学生活は“失敗して気づける”場でもあるのです。
おわりに
サークルの掛け持ちには、楽しいこともあれば、しんどい瞬間もあります。でもその分、大学生活が少しだけ豊かになり、自分の世界が広がるチャンスでもあります。
「なんかやってみたいことがいっぱいある」
「いろんな人と関わってみたい」
そんなあなたにとって、掛け持ちはきっと、大学でしかできない冒険のひとつになるはずです。