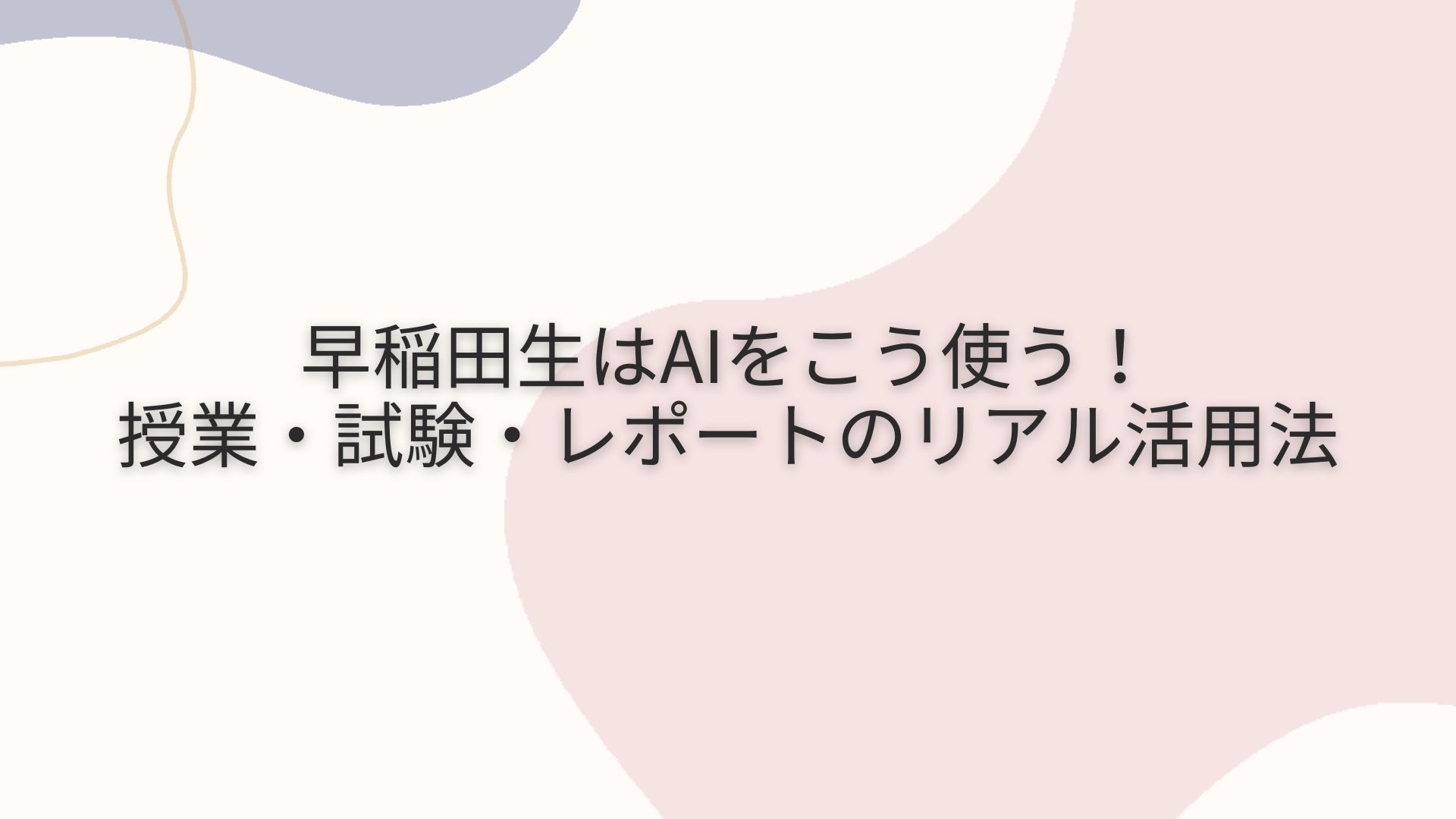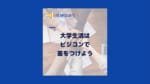こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。
「最近の大学生って、授業もAIにやらせてるんでしょ?」
そんなふうに聞かれることが、ここ1~2年で本当に増えました。
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場によって、大学での学び方や課題への取り組み方がガラッと変わった…そんな印象を持っている人も多いと思います。
でも実際のところ、早稲田の学生はAIをどう使っているのか?どこまでOKで、どこからNGなのか? そのリアルって、あまり知られていないのではないでしょうか。
今回は、私が早稲田大学政治経済学部で過ごした4年間の実体験をもとに、授業・試験・レポート・就活・サークル活動など、AIとの付き合い方のリアルをお話ししていきます。
ちなみに、早稲田では「AIの力を借りるのはOKだけど、あくまで補助的に使うこと」「最終的には一次情報をしっかり参照すること」が基本ルール。
“使っていいけど、使われちゃダメ”というスタンスが多いです(もちろん教授によってスタンスは違います)。
この記事では、
- ChatGPTはどんなときに使える?
- レポートや試験勉強ではどう役立つ?
- AIを使って失敗した話ってある?
といった疑問に答えつつ、「実際にどう使ってるの?」というリアルな部分をたっぷり紹介します。AI時代の大学生活、ちょっとのぞいてみませんか?
目次
授業でのAI活用:先生によって“ルール”は全然違う
ChatGPTをはじめとする生成AIが広く使われるようになってから、大学の授業でも「AIって使っていいの?」という話題が頻繁に出るようになりました。
でも実際のところ、早稲田の授業では“AIの使用可否”が明確に統一されているわけではありません。
ポイントは、「その授業の目的」と「担当の教授の考え方」によって、ルールがかなり違うということです。
AIは“補助ツール”としての使用はOKな授業が多い
私が受けてきた授業の中では、「ChatGPTなどの生成AIを下調べやアイデア出しに使うのはOK」というスタンスの先生が比較的多かったです。
たとえば、政治理論の授業ではこんなルールが明記されていました。
「生成AIの使用を禁止はしないが、それを活用した場合は、出発点にすぎないと心得ること。レポートは自分の言葉で書くこと。」
つまり、「使ってもいいけど、使われるな」ということですね(笑)。
実際に私は、レポートのテーマを決めるときに「ヨーロッパのエネルギー政策の変化」についてChatGPTにざっくり質問して、出てきたキーワード(『脱原発』『グリーンディール』『エネルギー安全保障』など)をWINE(早稲田大学の図書館サイト)で本格的に調べていきました。
AIは“取っかかり”としてはとても便利なんです。
一方で「AI使用完全NG!」の授業もある
ただし、全ての授業で自由に使えるわけではありません。
実際、社会思想史の授業では、シラバスに「AIの使用は禁止。使用が発覚した場合は評価対象外とする」と明記されていたこともありました。
先生に聞いてみると、「AIが出力する情報は正確とは限らず、学生が情報を鵜呑みにしてしまうのは危険」「考える力を鍛えることが目的なので、AIに委ねるのは本末転倒」という理由でした。
このように、AIの使用ルールは授業によって本当にまちまちです。
学生同士でも「この授業はOKだよね?」「え、うちは禁止されてるよ!」みたいな情報共有が飛び交ってます。
生成AIの“嘘”に注意しよう
ここでひとつ、早稲田生がよく言っている大事なことを伝えます。
「ChatGPTは堂々とウソをつく」
これは決して誇張ではありません。
たとえば私が「ハーバーマスのコミュニケーション的行為理論についての有名な論文を教えて」と聞いたとき、ChatGPTは実在しない論文タイトルと架空の出版年を提示してきました。
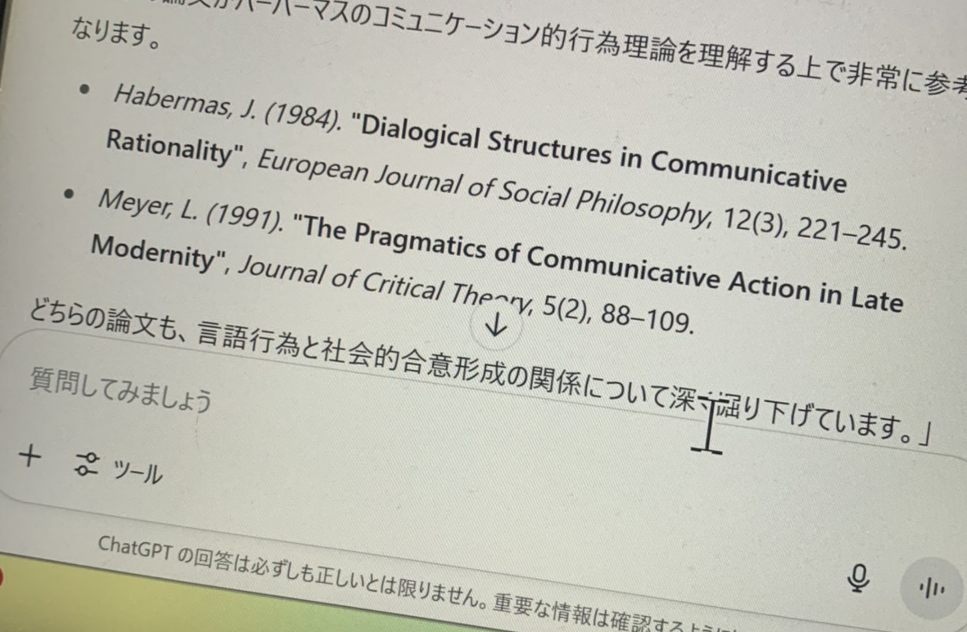
信じて文献リストに書いていたら、下手したら単位を落としていたかもしれません。
だから、AIが出してきた情報をそのまま信用しないことが大前提。
使うなら、“調べるための足がかり”として活用するのが基本です。
結論:授業で使うなら「まず確認・そして自己責任」
授業内でAIを使うかどうか迷ったときの私の結論は、
「まず授業資料(特にシラバス)を読んで、分からなければ先生に聞く。使うときはあくまで“補助的に”」
というスタンスです。
AIはうまく使えば非常に強力なツールになります。
でも、ルールを知らずに使ってしまって減点される…というケースもあるので、まずは“授業ごとにルールを把握する”ことが一番大事です。
レポート・論文でのAI活用:構成出しには便利。でも“ズル”には要注意
大学生活で避けて通れないのが、期末レポートや学期中の課題レポート。
特に文系の学部では、毎学期いくつものレポート課題が課されることも珍しくありません。
そんな中で、「AIってレポート作成に使えるの?」という疑問は多くの早稲田生が一度は抱くはず。
■ 構成出しやタイトル案出しにAIは超便利
実際、私自身もChatGPTをレポートでよく使ってきました。
とはいえ、いきなり本文を丸ごと書かせる、という使い方はしていません。
よく使うのは以下のような場面です:
- 「このテーマでレポートを書くとしたら、どんな切り口がある?」
- 「“エネルギー政策と経済成長の関係”について、論点を3つ挙げて」
- 「こんな問いに対するタイトル案を5つ出して」
特に構成案を考えるとき、頭の中でごちゃごちゃになっているアイデアを整理する手助けとしてAIは本当に頼りになります。
実際、3年生の時に書いた「環境政策と地球温暖化に関する考察」のレポートでは、ChatGPTに構成案を相談して、それを叩き台に自分で肉付けして仕上げました。
ただし「本文丸投げ」はリスクが高い
ここで注意したいのが、ChatGPTに“本文丸ごと書かせる”のはNG行為に近いという点です。
まず、内容が浅くなることが多い。AIの文章って一見それっぽいんですが、「論拠が弱い」「引用が曖昧」「具体性がない」という特徴があります。
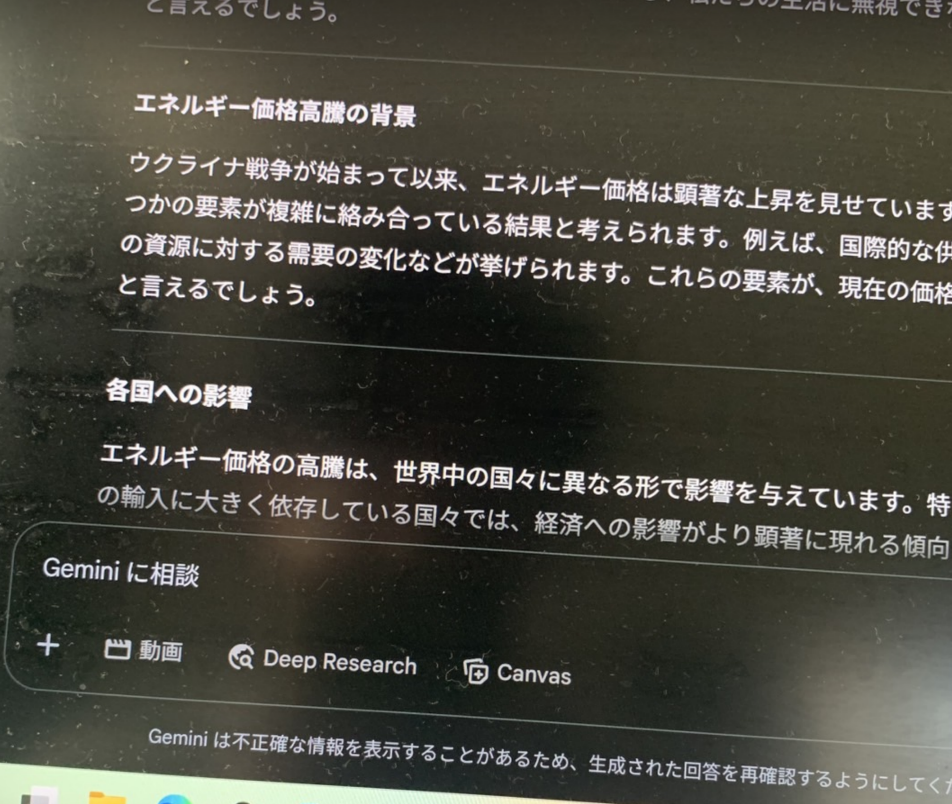
提出しても、教授にはすぐに見抜かれます。
それに、大学側がAI検出ツール(Turnitinなど)を導入しているケースもあります。
もしAIによる不正使用がバレたら、レポートの点数が減点されるだけでなく、最悪の場合は「不正行為」として成績評価が“不可”になることも。
実際、友人がAIっぽい文章を出したら教授から指摘されて、「これは本当に自分で書いたのか?」と詰められたという話もありました。
引用元の“ねつ造”にも要注意
AIが出してくる情報は、しばしば「それっぽいけど存在しない」引用や文献を提示してくることがあります。
たとえば、ChatGPTに「マルクスの労働価値説に関する有名な論文を教えて」と聞いたとき、「“The Dynamics of Marxian Labor Theory” by John H. Freeman (1998)」といったもっともらしい文献を挙げてきましたが、実際に調べるとそんな論文は存在しない。
引用のねつ造=学術不正扱いにもなりかねないため、AIで得た情報をそのまま信じず、かならず一次情報(図書館、論文データベース、本)をあたることが重要です。
「ChatGPTでレポートの下書きを作る」実体験
私が実際にChatGPTを使ってレポートを書いた流れを簡単に紹介すると、以下のようなステップでした:
- ChatGPTに「〇〇について、レポートの構成案を出して」と聞く
- 出てきた構成をベースに、WINEやCiNiiで一次情報を探す
- 自分の考えを文章にしていく
- 文章が詰まったときだけ、ChatGPTに「こういう主張の言い換えを出して」と頼む
こうしてできたレポートでは、実際にA評価をもらえました。
あくまで主役は自分、AIはアシスタント。その意識が大切だと感じました。
結論:AIで“ズル”はできるけど、それで得られるものは少ない
AIを使えば、正直「楽」はできます。
でも、“丸投げ”しても知識も考える力も身につかないし、リスクばかり大きいんですよね。
むしろ、うまく活用すればレポート作成の効率も質も上がるし、「AIという道具をどう使いこなすか?」という現代的なスキルも身につきます。
ルールの範囲内で、使い方を工夫する。
それが、“AI時代の早稲田生”の基本姿勢だと私は思います。
試験勉強でのAI活用:要点整理や過去問分析に強い味方
レポートと並んで大学生の大敵、それが期末試験。
とくに記述式の科目や範囲の広い講義では、「どこをどう覚えればいいの?」問題に多くの学生が悩まされます。
そんな中で、ChatGPTなどのAIを“試験勉強の相棒”として活用する人がじわじわと増えているのが早稲田のリアルです。
使い方次第では、要点整理・模擬解答づくり・過去問分析などでかなりの力を発揮してくれます。
「これって結局何が大事?」をまとめてもらう
試験勉強を始めるときにありがちなのが、「講義スライドはあるけど、要点がわからない」というパターン。
そんなとき私はよく、ChatGPTやGeminiに以下のようなお願いをしていました。
「このスライドの内容をもとに、3つの要点にまとめてください」
「“エネルギー安全保障”について、大学生向けに500字で解説してください」
もちろん、最終的には自分の言葉で理解し直す必要がありますが、複雑な内容を“噛み砕いてくれる”のはAIの得意分野。
実際、環境経済学の授業で「持続可能性の経済理論」を勉強していたとき、ChatGPTに要約してもらったことで理解が深まった経験があります。
記述問題対策に「模範解答を考えてもらう」
記述式の試験では、「自分の言葉で説明する力」が求められます。
ただ、何から書けばいいのか分からないという状態になることも多いですよね。
私は記述対策のとき、ChatGPTに“模範解答”をつくってもらって、自分の答えと比較するという方法をとっていました。
たとえば、政治思想史の試験対策でこんなふうに使いました:
「“ロックの自然権思想は現代の自由主義にどう影響しているか?”という問いに300字で答えてください」
出てきた答えをそのまま覚えるわけではなく、「この構成は参考になるな」「でもこの部分は自分ならこう言い換えるな」といった具合に、“答えの型”を知る参考資料として活用しました。
友人と「AIと自分、どっちの答えが優れてる?」クイズ
これは少し余談ですが、試験前に友人とやっていた面白い遊びがあります。それは、
「ChatGPTが出した記述解答」と「自分の答え」を混ぜて、どちらがAIか当てるクイズ
正直、最初は「自分の方がちゃんとしてるはず!」と思っていたのですが、意外とChatGPTの答えの方が構成がしっかりしていたり、言い回しがスムーズだったりすることも。
でも、だからこそ「じゃあ自分はどこを直せばもっと伝わるかな?」と考えるきっかけになっていました。
AIを“競争相手”として見ることで、自分の文章力を磨く練習にもなると感じました。
オンライン試験でのAI使用は原則NG!リスク大!
ここまでAI活用を推してきましたが、オンライン試験でAIを使うのはNGです。(念のため大事なことなのでもう一度言います)
特にコロナ以降、一部の講義ではGoogleフォームやMoodleを使ったオンライン試験が行われていますが、そこでは基本的に「資料参照はOKでも、AI使用は禁止」と明記されていることがほとんど。
そしてAIの使用は、試験システムのログや提出時間のズレ、内容の不自然さからバレる可能性も高い。
実際、過去には「不自然に構成が整いすぎていた」ことで呼び出された学生もいたという噂も…。
バレなかったとしても、それって「自分で解いた」とは言えないですよね。
結論:試験勉強はAIと“タッグ”を組むと最強かも
試験勉強においてAIは、「教科書の代わり」ではなく「賢い家庭教師」のような存在だと思っています。
要点の整理や記述問題の構成確認、模擬問答などに使えば、勉強の効率も理解の深さもぐんと上がる。
でももちろん、最後は自分の頭で理解し、自分の言葉で表現することが大切。
AIはその「自分の力を引き出すための補助輪」なんですよね。
授業外でのAI活用:アイデア出しや就活まで
授業やレポート、試験対策といった“学業の場面”でAIを活用する学生が増えてきたのは事実ですが、実は授業外でもAIをフル活用している早稲田生は少なくありません。
私自身、サークル活動・インターンの仕事・就活・趣味の創作活動など、大学生活のいろんな場面でAIの力を借りてきました。
ここでは、そうした「学外のリアルな活用例」を紹介していきます。
サークルの企画・アイデア出しにAIを活用
大学生活の中で“人間力”が最も試される場のひとつが、サークル活動。
とくに私が所属している「ヨコシマ。」(アコースティックバンドサークル)では、ライブイベントや合宿、新歓など、“企画力”が問われる場面が非常に多いです。
アイデア出しの会議でありがちなのが、
「何か面白いことしたいけど、ネタが思いつかない…」という沈黙。
そんなとき、ChatGPTに「大学生の合宿で盛り上がるゲーム案を10個教えて」「バンドのライブ演出でちょっと変わった企画ない?」と聞くと、秒で案が返ってきます。
たとえば、冬合宿のライブ演出では「昔のJ-POPを現代風にアレンジして“令和アカペラ”をやる」といった提案を元に、実際にセットリストを組んだこともありました。
また、新歓の動画作成では、ChatGPTに「自己紹介動画で笑える演出は?」と聞いて、「予告風編集+バンド演奏=映画のトレーラー風」というアイデアを採用。
“発想のジャンプ台”として、AIは本当に頼れる存在です。
お菓子作りサークル「Ws.dolce」でも、季節ごとの企画(ハロウィン、バレンタインなど)でアイデアを出すときに、ChatGPTからレシピ案をもらったことがあります。
普段の思考の枠から外れた視点をくれるのが、AIの面白さです。
長期インターンでもAIが戦力に
私は大学2年の夏から、Webライターの長期インターンに参加していました。
その中で、「AIがいかにビジネスの現場でも活用されているか」を実感しました。
たとえば、新しい記事テーマを考えるとき、ChatGPTに「〇〇に悩んでいる20代向けに、クリックされそうな記事タイトルを10個出して」と入力すると、SEO的に強いタイトル案があっという間に出てきます。
また、文章のリライトでは「この段落をもう少し柔らかい表現にして」とお願いすると、“ちょっとした言い回しの調整”をしてくれる。
文章に詰まったときに気軽に相談できる存在として、本当に助けられました。
さらに、仮想ペルソナの作成にも活用。
「30代男性・育児中・副業に興味あり」という条件を与えると、その人が持ちそうな悩み・生活習慣・検索しそうなキーワードまで出してくれるんです。
AIを活用することで、記事の精度や読者理解が格段に深まる。
現場でも「AIをうまく使える人」が一目置かれていました。
就活のES・企業研究にも活用されている
大学3〜4年で本格化する就職活動。
この時期になると、AIを“就活のパートナー”として使う学生が一気に増えます。
まず多くの人が試すのが、エントリーシート(ES)のたたき台作成。
「リーダーシップを発揮した経験を300字で書いて」「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の例文を見せて」といったリクエストに対して、ChatGPTはすぐに参考文を生成してくれます。
もちろん、そのまま出すのは絶対NG!
でも、自分の経験をどう構造化すれば伝わるかを知る上では、とても有益な“フォーマットの参考”になるんです。
また、企業研究でも便利です。
「三井不動産の中期経営計画のポイントは?」「サントリーとアサヒの違いを比較して」といった質問をすると、基本情報や比較ポイントをまとめてくれる。
時間のない中での情報整理には、本当にありがたい存在です。
特に、以下のように会社の新規事業をを考える際のアイデア出しに便利でした。
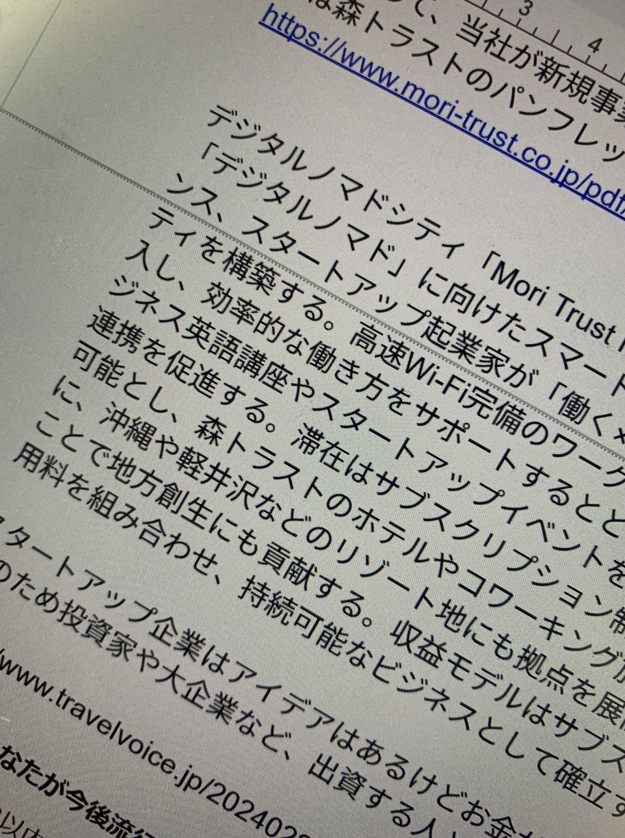
あくまで“材料”として活用し、自分の経験に落とし込む作業が重要です。
ただし、そのままコピペして出すのは危険!
面接で聞かれたときに答えられなければ即バレますし、自分の中身が薄くなるだけです。
結論:AIは“学外の相棒”としても有能すぎる
授業以外の場面でも、アイデアが出ないとき・情報を整理したいとき・文章を磨きたいときに、AIは強力なパートナーになります。
一方で、「AIが全部やってくれる」と期待しても、創造性や個性のある成果にはつながりません。
“自分のやりたいことを形にするために、AIをどう使うか?”という視点がとても大切。
AIは魔法の杖ではなく、アイデアを引き出す相棒。
大学生活という“実験の場”で、それをどう使いこなせるかが、これからの力になっていくのだと思います。
AIは“魔法の杖”じゃない。でも、うまく使えば最強の相棒
ここまで、授業・試験・レポート・サークル・就活など、大学生活のさまざまな場面におけるAIの活用例を紹介してきました。
早稲田の学生の中にも、すでにAIを“自然に使いこなす”人たちが少しずつ増えているのを感じます。
でも同時に、「AIってズルじゃないの?」「使ったら自分で考えなくなるのでは?」といった疑問や不安の声も、今なお根強くあるのが現実です。私自身、最初はそう思っていました。
だからこそ最後に、大学生活とAIの“ちょうどいい距離感”について、私なりの考えをまとめておきたいと思います。
AIは「全部やってくれる存在」ではない
まず、これだけははっきり言っておきます。
AIは、使えば使うほど「自分の頭で考えなきゃ」と思わされるツールです。
たしかにChatGPTは文章も要約も構成案も作ってくれます。でも、それだけだと“自分のもの”にはなりません。
たとえば、AIにレポートを書かせても、先生の質問には答えられない。就活の面接でAIが書いた志望動機を話しても、相手には響かない。
結局のところ、AIの出力物は“たたき台”であって、完成品じゃない。そこに自分の意見・経験・視点を乗せて初めて「意味のある表現」になるんだなと感じています。
「AIを使いこなす力」=これからの大学生に必要なリテラシー
早稲田の授業では、「一次情報を参照せよ」という方針が基本です。それは、「ChatGPTの言うことをそのまま信じるな、自分の目で確認しろ」という姿勢を養うためでもあります。
私自身、AIが出してきた引用や参考文献が実在しないことに気づいて、何度もWINE(早稲田の図書館検索システム)で裏取りをしてきました。
その過程で、本物の論文や信頼できる知識に出会えた経験もあります。
「AIをどう使うか」ではなく、「AIを使って何を考えるか」
それが、これからの学生に求められる姿勢だと思います。
AIは“使い方さえ間違えなければ”、勉強の効率も、表現の幅も、創造のヒントもすべて広げてくれるツールです。
そしてそれは、テストの点数よりもっと大切な“考える力”や“伝える力”を鍛えるきっかけにもなります。
最後に:これからAI時代の大学生になるあなたへ
これから大学に進学する人、あるいはAI時代の学び方に戸惑っている人に、伝えたいことがあります。
AIは敵でもズル道具でもなく、可能性を広げる“味方”になり得ます。
でも、味方として使いこなすには、自分の頭で考え、調べ、選び取る力が必要です。
「AIが出した案を信じる」のではなく、
「AIと対話しながら、自分の考えを深める」こと。
それが、“AI時代の早稲田生”としての学びのリアルであり、私自身が4年間かけてたどりついた姿勢です。
大学生活は、自分のやりたいことをとことん試せる時間。
その中で、AIという“最強の相棒”とどう付き合っていくかは、あなた次第です。