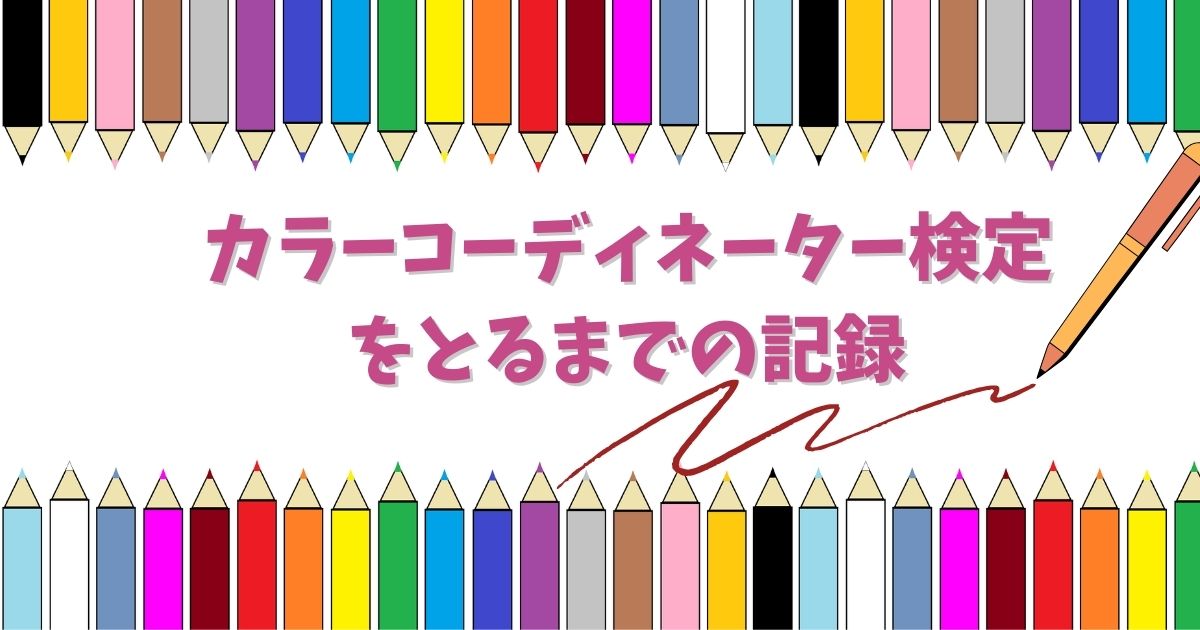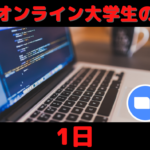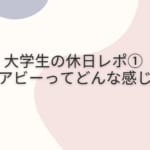受験生の皆さんこんにちは!
早稲田大学4年のぱおです!
突然ですが、みなさん、「カラーコーディネーター検定」って聞いたことありますか?
私は大学2年生のとき、色彩検定の勉強を始めたと同時にこの検定にも興味を持ちました。
結局、色彩検定3級・2級と同時進行でカラーコーディネーター検定も受けることに。
なんでそんなに頑張ったの?ってよく聞かれるんですが、理由は意外とシンプル。「どうせ勉強するなら効率よく、いろんな視点で色彩の知識を身につけたかったから」です。
色彩検定については別の記事で詳しく説明しています!
この記事では、カラーコーディネーター検定ってどんな資格なのか、そして私が実際に体験した勉強方法や受験の流れを紹介していきます。
重なる内容がらあるかもしれませんが、同時進行で資格勉強に挑戦していたからこそ感じたことやアドバイスもお伝えするので、気になっている方の参考になればうれしいです!
目次
【1. カラーコーディネーター検定とは?】
まず、カラーコーディネーター検定の基本情報を簡単にまとめますね。
この資格は、東京商工会議所が主催している試験で、色彩の知識を「ビジネスや日常生活に応用する力」を問われます。
ここがポイントで、色彩検定が学問的な広い知識を扱うのに対して、カラーコーディネーター検定はより実践的。
たとえば、インテリアやファッション、商品企画の現場で役立つような色彩の使い方が学べます!!
色彩検定は3級から1級と試験が分かれていましたが、カラーコーディネーター検定には、スタンダードクラスとアドバンスクラスという2つの区分があります。
• スタンダードクラス:色彩の基本知識を身につけるレベル。初学者でも安心して学べます。
• アドバンスクラス:より専門的な知識を求められる中上級レベル。深い理解が必要です。
この資格の魅力は、「色の知識が実生活でそのまま使えること」。
たとえば、インテリアを選ぶときや、服の配色を考えるときに「この色はこういう効果があるから…」と理論的に判断できるようになります。
私自身もこの実践的な部分に惹かれて受験を決めました。
私は、カラーコーディネーター検定の簡単な方、スタンダードクラスを受験します。

色彩検定との違い
実際に勉強して感じたのは、色彩検定は「色そのものの学問」、カラーコーディネーター検定は「色の応用」という違いです。
色彩検定
色彩検定は、文部科学省の後援を受けている公的な資格で、色彩に関する基本的な知識や理論を学ぶことができます。初心者向けの3級から上級者向けの1級まであり、ファッション業界を中心に活躍したい人におすすめです。
個人的に色彩検定では、自然界の色の仕組みとか光のスペクトルまで学べたりして、こんなことまで学ぶんだ!と「理系っぽいな~」と感じました。
カラーコーディネーター検定
一方、カラーコーディネーター検定は、東京商工会議所が主催する資格で、色彩の知識を実践的に応用する能力を評価します。商品開発や企画、美容業界など幅広い分野で活躍したい方に適しています。
たとえば、色彩検定で色相環やトーンを学んだ後、カラーコーディネーター検定ではそれを使って「お客さんが好むデザインを提案するにはどうすればいいか」を考える感じ。
この違いを知ったとき、「両方学べばバランスが取れるな」と思ったんです。
どっちがいいかは人それぞれだけど、個人的には「色について深く知りたいなら色彩検定」「色を仕事や日常に役立てたいならカラーコーディネーター検定」って感じで選ぶのがいいと思います!
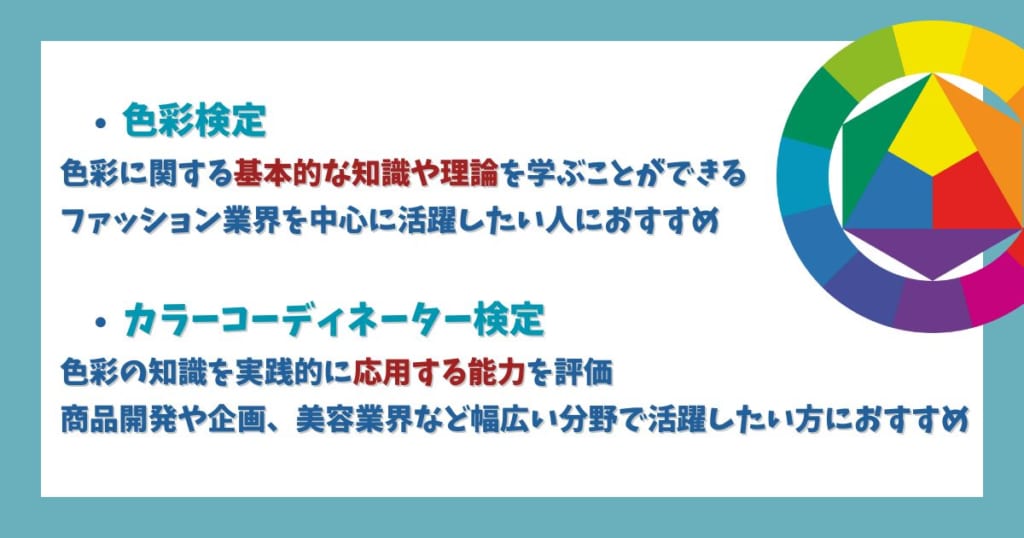
【2. 受験を決めたきっかけ】
色彩に関する資格を調べていたとき、最初に目にしたのは色彩検定でした。
でも調べていくうちに、「カラーコーディネーター検定」というもう一つの資格があることを知って、「どうせなら両方取ろう!」と欲張ったのが始まりです。理由は大きく3つあります。
1. スキルを幅広く身につけたい
色彩検定だけでも十分かもしれないけれど、より具体的にビジネスや日常生活で使える知識を補完したいと思いました。
たとえば、私は映像系の学生でアメリカのホラー映画が好きでこのテーマで卒業論文を書こうと思っていました。
作品の分析をする過程で「映画の色彩が観客に与える影響」に興味があったので、それをより深く知る手がかりになると思ったんです。
2. 就活でアピールできるポイントが増える
この頃から「将来どんなスキルが役立つかな?」と考えていて、資格は具体的なアピールポイントになると気づきました。
特にカラーコーディネーター検定はビジネス寄りの資格なので、「実際に働くときに即戦力になれる!」と感じたんです。
3. 同時並行で学べる効率の良さ
色彩検定とカラーコーディネーター検定って、基礎的な知識に重なる部分が多いんです。
たとえば、「色の三属性(色相・明度・彩度)」や「色彩心理学」など。
同時進行で勉強すれば、片方で覚えた知識がもう片方の試験にも役立つので、一石二鳥だと思いました。
次の章からは、実際にどんな方法で勉強したかを詳しくお話ししていきます!
【3. 勉強方法とスケジュール管理】
次に、色彩検定3級・2級とカラーコーディネーター検定を同時並行で進めた私の勉強法についてお話しします。
これがなかなか大変で、最初は「本当に両方間に合うのかな?」と不安でしたが、工夫をしながら進めることで乗り切りました!
スタート時の計画
同時進行で資格を取ると決めたとき、最初にやったのがスケジュール作りです。
勉強に使える時間は大学の授業やアルバイトの合間だったので、効率重視で進める必要がありました。
1日の流れ
• 朝:カラーコーディネーター検定の動画を見る(30分~1時間)
• 午後:色彩検定の参考書で問題演習
• 夜:両方の復習とノートまとめ
スケジュールを立てるときは、「どの資格が先に試験日を迎えるか」も考慮しました。
幸い、色彩検定の試験日が先だったので、最初は色彩検定に重点を置き、後半でカラーコーディネーター検定に集中する形に。
使用した教材
両方の資格に役立ったのが、「資格のキャリカレ」という通信講座です。
この講座の良いところは、動画と参考書を自由に組み合わせて使える点でした。具体的には、、、
• 色彩検定用の教材では、基礎知識や理論を動画でサクッと学習。
• カラーコーディネーター検定では、日常やビジネスに直結する応用部分を参考書で確認。
特に「キャリカレ」の動画はスマホでいつでも見られるので、通学中の電車の中やバイトの休憩時間などちょっとした隙間時間を活用して学べました。
YouTubeの無料解説動画との比較
- メリット:基礎的な内容を短時間で学べる。具体例が多くて理解が進みやすい。
- デメリット:動画の質がバラバラで、信頼性が低い情報も混ざっていることがある。
ポイントは「切り替え」
色彩検定とカラーコーディネーター検定には共通点も多いですが、それぞれ異なるアプローチが求められます。たとえば、
• 色彩検定では、色の基礎的な理論を徹底的に覚えることが重要。
• カラーコーディネーター検定では、それを「どう使うか」を考える必要がありました。
だからこそ、1日で扱う分野を変えることで、勉強の切り替えを意識しました。
たとえば、「午前は理論を覚える時間、午後は実践的な問題を解く時間」という感じです。
無理なく進める工夫
同時進行で資格勉強をすると、どうしてもストレスや疲労を感じる瞬間があります。そんなときは:
1. 休憩をきちんと取る
• 無理に続けても効率が落ちるだけなので、30分勉強したら10分休憩を挟む「ポモドーロ・テクニック」を活用しました。
2. 勉強場所を変える
• 同じ場所で勉強し続けると、マンネリ化して集中力が落ちてしまうことがあります。そこで、私は図書館、カフェ、そして大学のラウンジなど、気分によって勉強場所を変えるようにしました。
静かな図書館ではテキストの読み込みや論理的な問題の解答に集中でき、一方でカフェでは適度な雑音があることでリラックスしながら暗記作業が進みました。また、自宅では「この机で勉強する」と決めた場所を作ることで、場所を変える手間がない日でも集中しやすい環境を整えました。
後ほどおすすめの場所を具体的に説明します!
3. モチベーションを保つ目標を設定
• 「合格したら好きな映画を観に行く!」など、小さなご褒美を用意していました。また、進捗を可視化するためにカレンダーに勉強時間を記録し、日々の積み重ねを確認するのも励みになりました。
試験の2週間前になると、両方の資格勉強を一層集中して進めました。
具体的には、毎日タイムスケジュールを細かく決めて取り組みました。例えば、
• 朝:色彩検定の過去問を解いて知識を固める時間
• 昼:カラーコーディネーター検定の応用問題を解く練習
• 夜:間違えた箇所を復習し、関連する理論を再確認
過去問や模擬試験を活用すると、試験本番での時間配分や問題傾向がつかめて、安心感が生まれました。
おすすめの勉強場所
勉強を進める上で、環境の影響は大きいですよね。私は次のような場所を使い分けました。
• 自宅:集中力が必要な暗記や理論の確認に最適。特に早朝は周りが静かで、深く考える作業がはかどります。また、私は家と駅が離れていたので起きてすぐに勉強が始められるのは多きなメリット!しかし自宅はその分誘惑が多いです。誘惑に負けないようにしましょう(笑)
• 大学の図書館:資料を探しながら勉強したいときに便利でした。落ち着いた雰囲気も◎。大学には図書館が沢山あるので、もし1箇所の図書館が空いてなくても移動すればどこかしらが空いてます!
• カフェ:音が気になる場合、ノイズキャンセリングイヤホンを使って、リズミカルに作業を進めました。適度な雑音が逆に集中力を引き出すこともありました。
スケジュールの重要性
資格の勉強を同時進行する場合、スケジュール管理が鍵です。
私は「1週間ごとの目標を設定する」「進捗を見える化する」などの方法を使いました。具体的には、
• ホワイトボードやアプリを使って、どこまで進んだかをチェック。進捗が見えるとモチベーションが上がります。
• 試験直前の1週間は、どちらの資格にも重点を置く日を分けました。例えば、月・水・金は色彩検定、火・木・土はカラーコーディネーター検定という具合
試験直前のルーティン
試験まで残り1週間を切ると、過去問と模擬試験を徹底的に繰り返しました。
特に、苦手分野を集中的に潰していくように意識。試験当日のシミュレーションも大事で、実際の試験時間に合わせて問題を解く練習をしたり、間違えた箇所だけをまとめた「弱点ノート」を何度も見返しました。
また、夜更かしや詰め込みは厳禁! 試験前日は早めに就寝し、頭をすっきりさせて本番に臨みました。
試験会場には1時間前に到着するようにして、直前にノートを読み返すことで落ち着けたのを覚えています。
同時進行のメリットとデメリット
正直、色彩検定とカラーコーディネーター検定を同時に勉強するのは、かなりハードでした。ただ、基礎知識が重なる部分が多いため、効率よく学べたのも事実です。
同時進行のメリット
1. 知識が相互補完される
• 色彩検定で学んだ色彩理論を、カラーコーディネーター検定の応用問題で活かせることが何度もありました。
2. 資格が増えることで就活のアピール材料が豊富になる
• 「色彩」という分野で幅広く学んでいる印象を与えられるので、企業に興味を持ってもらいやすくなります。
同時進行のデメリット
1. スケジュールがタイトになる
• 1つの資格に集中する時間が減るため、余裕を持つことが難しくなります。計画的に進めないとパンクする可能性も。
2. 混乱しやすい
• 特に初めて勉強する場合、検定ごとの試験範囲や重点ポイントが曖昧になりがちです。参考書や過去問をきちんと分けて整理するのが大切だと思いました。
勉強を終えて感じたこと
同時進行で資格の勉強をするのは大変でしたが、計画的に進めることで十分に乗り越えられるという自信がつきました。特に、共通する部分を活用して効率よく学べた点や、実際に取得した資格を就活で活かせたのは大きなメリットでした。
振り返ると、両方の勉強を通じて「色の知識は本当に生活の中で役立つ」という実感を得ました。
たとえば、インテリアの配色を考えるときや、好きな映画を観るとき、色がもたらす効果を理論的に説明できるようになり、趣味がさらに楽しくなりました。
次の章では、実際の試験の様子や私が工夫したポイントを紹介していきます!
【4. 試験当日の流れと工夫したポイント】
試験当日の準備
試験当日ってやっぱり緊張しますよね。私は、準備不足やミスを防ぐために、以下のことを心がけて臨みました
• 試験前日の夜に持ち物を確認
受験票、筆記用具、腕時計、あとは小腹が空いたとき用のお菓子などを前もってバッグに入れました。余裕を持つと当日の不安が減ります!
• 朝ごはんをしっかり食べる
試験が長時間に及ぶ場合、エネルギー切れが心配だったので、バナナやパン、ヨーグルトなど軽くて消化に良いものを。
• 会場へ早めに到着
試験会場には1時間前に到着して、少し散歩をしたり、ノートを読み返したりしてリラックス。
試験本番の心構え
試験が始まったら、まずは深呼吸して落ち着くことを意識しました。私が特に気をつけたのは、
1. 問題用紙全体をざっと確認
時間配分のミスを防ぐために、最初に問題のボリュームをチェックしました。「どこに時間をかけるべきか」「どの問題が得意分野か」を見極めるのが大事です。
2. 難問に固執しない
解けそうにない問題は一旦スルーして、簡単なものからどんどん解く戦略を取りました。「この問題が解けない…」と焦る時間が一番もったいないですからね!
3. マークミスに注意
マーク式の試験では、回答をずらして記入してしまうミスがよくあるので、最後に必ず見直しをしました。
試験後の感想
正直、色彩検定とカラーコーディネーター検定を同時進行で勉強したことはかなりプレッシャーがありました。
でも、両方の試験が終わった後は、達成感でいっぱいでした!「ここまでやり切ったんだ!」という自信につながり、その後の就活や日常生活でも役立つ知識を手に入れたと感じています。
次の章では、取得後に感じた資格のメリットや活用方法について詳しくお話しします!
【5. 資格取得後の活用とその価値】
資格取得後に変わったこと
色彩検定とカラーコーディネーター検定を取得して感じたのは、「色」への意識が大きく変わったこと。資格勉強で得た知識が、普段の生活や学業、就活に活きる場面がたくさんありました。
例えば、大学の映像制作の課題では、配色や画面構成に対して論理的に考えられるように。以前は「なんとなくいい感じ」で決めていた色の組み合わせも、今では「補色を使ってコントラストを強調しよう」など、具体的な理由を持って選べるようになりました。
日常生活での活用
資格で学んだ知識は、日常生活でも意外な形で役立ちます。
• ファッションコーディネート
色彩検定で学んだ色相環の知識を使って、アクセントカラーを意識した服選びができるようになりました。以前は白や黒など無難な色ばかり選んでいたけど、今では「今日はモノトーンにピンクを差し色にしてみよう」なんて楽しんでいます!
• インテリア
部屋の模様替えでは、暖色系で部屋を温かく見せたり、寒色系でリラックスできる空間を作る工夫が。カラーコーディネーターの勉強では、家の家具についての配色についても学べるため、自分の部屋をあれこれいじるのがとても楽しくなりました!家族からも「センスが良くなったね」と褒められました。
就職活動での活用
資格を取得して特に感じたのは、就活での武器になるということです。
面接では「色彩の知識をどう活かしていくか」という質問がありましたが、取得した資格と具体的な学びを説明できたことで、アピールにつながったと思います。
• ポートフォリオ作成
映像作品のプレゼンでも、「なぜこの配色にしたのか」を根拠を持って説明できるので、説得力が増しました。
しかし、資格を持っているだけでは、特に色彩やデザイン系の専門職以外では即戦力として認められることが少ないように感じました。
たとえば、ファッションやインテリア業界では実践経験が重視されることが多く、資格が直接的なアピールポイントにはなりにくい面もあります。この資格をどう活かしていくかは、結局自分次第という印象を受けました。
しかし、何も無いよりは色彩に関する知識を持っているという一種の証明にはなりそうです!
資格が与えてくれた自信
資格を取ったことで得た一番のものは、「やればできる」という自信です。
色彩検定もカラーコーディネーター検定も、最初は範囲が広くて不安でしたが、計画的に取り組んで合格をつかむことで、どんな挑戦にも臨めるようになりました。
受験が終わってすぐは、いろんな資格をとるぞーー!と意気込んでいても、実際大学生になるとサークルだったり楽しみがどんどん増えて勉強が疎かになってしまうことはよくあります。
実際に周りでも資格勉強をしている人はあまりいないように思います。
そんな中で「資格」という武器を身につけられるのは大学生活の中ではきっと大きい意味があると思っています。
実際に検定を受けて感じたデメリット
カラーコーディネーター検定を受験してみて、たくさんの知識を得られる素晴らしい経験ではありましたが、正直に言うとデメリットに感じる点もいくつかありました。その中でも特に気になったのが、お金がかかることです。
まず、受験料自体がそれなりに高額です。受験級にもよりますが、カラーコーディネーター検定の受験料は1級になるとさらに値段が上がり、学生の身には少し負担に感じる金額でした。
そして、それに加えて試験対策用の参考書や問題集も必要で、これらの教材費が意外と積み重なります。特に公式テキストは必須と言える内容ですが、セットで購入すると数千円〜1万円近くする場合もありました。
さらに、独学が難しいと感じた場合は、対策講座やスクールに通うという選択肢も出てきますが、これもまた費用がかかります。忙しい日常の中で、独学だけでは不安を感じることもあるため、こうした追加費用を検討する必要が出てくることもありました。
また、資格取得後に実際に仕事や趣味で活かそうとしたとき、色の知識を実践に結びつけるためのさらに専門的なツールや勉強(たとえばカラーチャートやコンサルティング用の資料)にもコストが発生することがあります。
資格そのものだけでは終わらず、後々の活用やスキルアップにおいてもお金がかかる点は大きなデメリットに感じました。
そのため、カラーコーディネーター検定を受験する際には、事前にどれくらいの費用が必要になるのかをしっかり把握しておくことが大切だと感じました。受験料や教材費だけでなく、その後のスキルアップの費用も含めて計画を立てることで、無理なく勉強を進められると思います。
お金はかかるものの、それに見合う知識やスキルを得られると考えれば、決して無駄ではありません。ただし、費用面の負担を感じる方は、早めに予算を組んで計画的に準備をすることをおすすめします!
カラーコーディネーター検定を受験する際、以下の費用がかかります。
受験料:
- アドバンスクラス:7,700円(税込)
- スタンダードクラス:5,500円(税込) 東京商工会議所検定
公式テキスト:
- アドバンスクラス公式テキスト:5,830円(税込)
- スタンダードクラス公式テキスト:3,410円(税込)
また、受験料は一度支払うと返金や振替ができないため、申し込み前に十分に検討することをおすすめします。
最後の章では、資格取得を目指す方へのアドバイスや、これからの目標についてお話しします!
【6. 資格取得を目指す方へのアドバイスと今後の目標】
これから資格取得を目指す方へ
私の経験から、色彩検定やカラーコーディネーター検定を目指す方に、いくつかアドバイスをお伝えします。
1. スケジュール管理が命!
早めに試験日から逆算して計画を立てましょう。特に同時進行で勉強する場合は、どちらにどれだけ時間を割くかを明確にするのが大切です。
2. 基礎を固めることが合格への近道
色彩検定やカラーコーディネーター検定は、どちらも基本的な理論をしっかり押さえていれば対応できる問題が多いです。焦らず、基礎を丁寧に積み上げてください。
3. 自分に合った教材を選ぶ
私が使った「資格のキャリカレ」のように、自分の生活スタイルに合わせた教材や講座を選ぶのも重要。特に動画教材はスキマ時間を有効活用できるのでおすすめです。
4. 実生活に結びつけて学ぶ
ただ試験対策として勉強するのではなく、ファッションやインテリア、趣味の分野で学びを活用すると、楽しみながら知識が深まります!
これからの目標
資格を取得したことで、色彩に関する知識を持つだけでなく、「学ぶ楽しさ」も実感しました。
将来的には、映像制作や広告業界など、色の知識を活かせる仕事に就きたいと考えています。
また、色彩の奥深さをもっと追求するために、スタンダードクラスの上、アドバンスクラス取得にも挑戦してみたいと思っています!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
大学生は時間が沢山あるので、自分が好きな分野で好きな資格を取得することが出来ます。
これから資格取得を目指すみなさんも、自分のペースで楽しみながら頑張ってくださいね。
私も引き続き色彩の勉強を進めたいと思います!