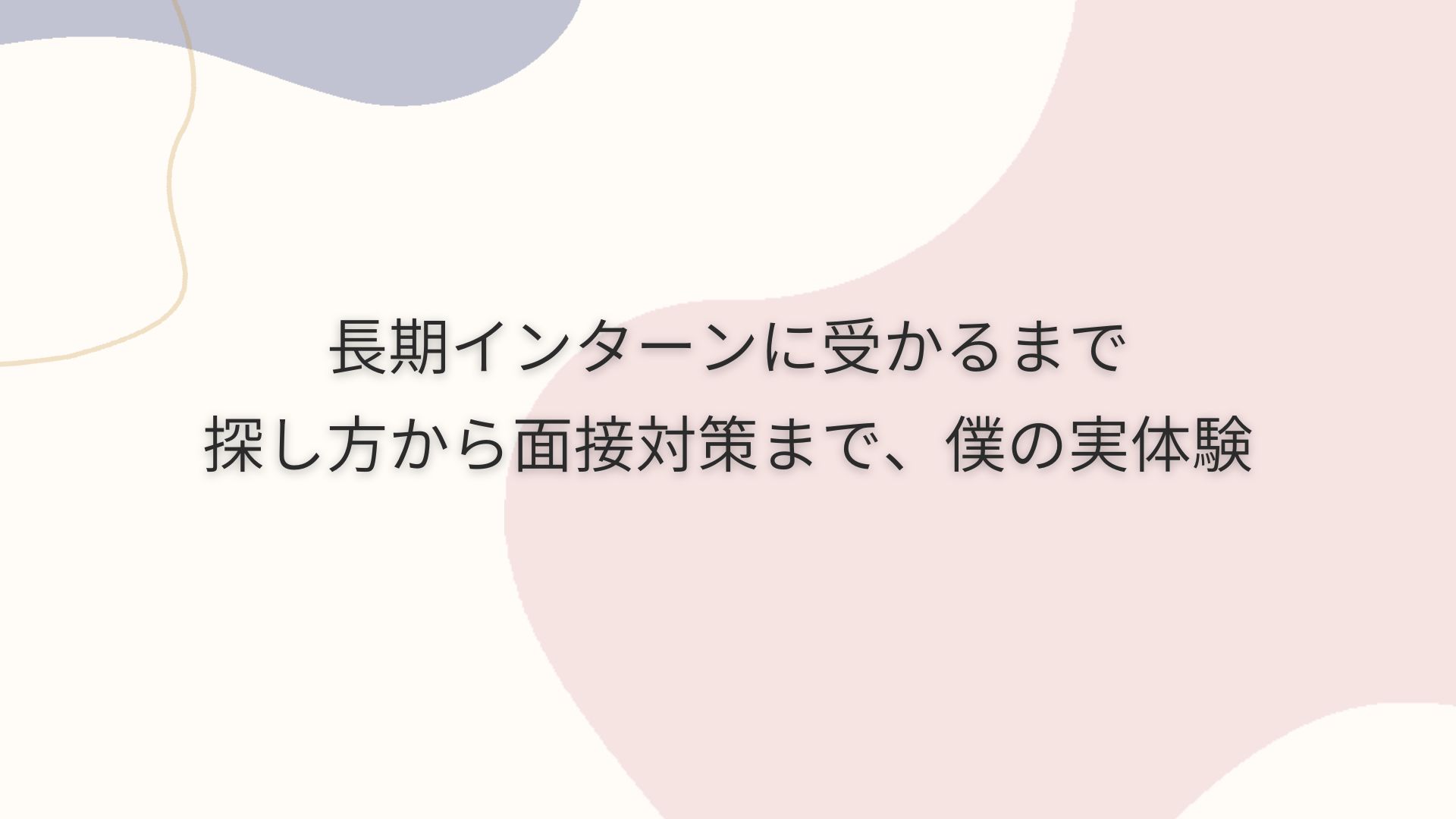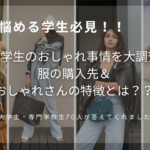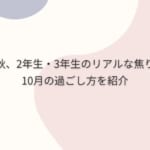こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。
「長期インターンに興味はあるけど、どこで探せばいいのか分からない」「志望動機ってどう書けばいいの?」「面接で緊張しすぎてうまく話せる気がしない…」
近年インターンという言葉が身近になってきた一方で、実際どのようにインターンを始めるの?
そう疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
僕自身、大学2年の頃にInfraインターンというサイトを使って、Webメディアの長期インターンに応募しました。
文章を書くことに興味はあったものの、「スキルなんてないし、本当に自分にできるのか…」という不安でいっぱいだったのをよく覚えています。
でも、求人の探し方や企業とのやりとりのコツを押さえて、面接ではとにかく元気にはきはきと話すことを意識した結果、無事インターンに参加することができました。
そして今振り返ると、あの時一歩踏み出して本当に良かったと思っています。
この記事では、インターンの探し方、応募前の準備、面接での受け答え、そして合格後にやっておいてよかったことまで、すべて僕の体験ベースでお伝えします。
同じように悩んでいる人の背中を、少しでもそっと押せたら嬉しいです。
目次
STEP1|インターンの探し方:Infraインターンをどう使ったか
長期インターンに挑戦するにあたって、まず最初のハードルになるのが「どこで探せばいいの?」という部分。
僕も最初はまったく分からず、ひたすら「長期インターン 大学生」などと検索していました。
そんな中で使ってみて良かったのが、Infraインターンという学生向けのインターン求人サイトです。

Infraインターンを選んだ理由
Infraインターンは、大学生向けに特化したインターン情報がまとまっていて、「未経験OK」の求人が多く掲載されているのが大きなポイントでした。
加えて、検索フィルターが充実していて、
- 勤務形態(リモート可・出社必須)
- 職種(ライター、マーケ、エンジニアなど)
- 勤務頻度(週2~、フルタイムなど)
- 学年別(1年生歓迎、2〜3年生向けなど)
…といった条件で、自分の生活スタイルや興味に合った求人を絞り込みやすかったです。
求人の説明もシンプルで、「どんな業務を担当するか」がしっかり書かれていたので、「実際に働くイメージ」を持ちやすかったのも助かりました。
実際にどう選んだか?
僕が応募したのは、Webメディアでライターを募集している企業でした。
当時は文章力に自信があったわけではないですが、「文章で誰かに何かを伝える仕事」に興味があり、ライターや編集に関わる求人を中心に見ていました。
選ぶ際に重視していたのは、
- 勤務頻度が週2~3日程度で、大学の授業やサークルと両立しやすそうなこと
- 初心者にも研修やフィードバックがある職場かどうか
- 「単純作業だけ」ではなく、自分で考えて提案できる環境かどうか
といった点です。企業紹介文の中で、「社員と一緒に企画を考える」「インターン生が記事を任されています」などの記述があると、「ここはチャレンジできそうだな」と前向きになれました。
メッセージ機能と“即レス”の大切さ
Infraインターンでは、気になる求人にエントリーすると、企業と直接チャットでやり取りできるメッセージ機能があります。
このときに、僕がとにかく意識していたのが、「即レス(できるだけ早く返信すること)」です。
企業側からすると、「やる気がある学生かどうか」を見る最初のポイントは、意外とこうしたやり取りの中にあります。
返信が遅いと、「本気度が低いのかな?」と思われてしまうこともあるかもしれません。
実際、面接後に「このあと◯日までに〇〇を提出してください」と言われたときも、なるべくその日のうちに対応するようにしていました。
早めに動くことで、信頼が生まれる。
これは社会に出ても大事なスキルだと感じます。
応募の時点で不安なことがあっても、大丈夫
最初は、「こんな自分でも応募していいのかな」と不安に思うかもしれません。
でも、多くの企業は“未経験でもやる気があればOK”というスタンスで学生を募集しています。
だからこそ、まずは勇気を出して一件応募してみる。
それが何より大切です。
僕も、初めてメッセージを送るときは緊張しましたが、応募の時点では完璧さより「誠実さ」「やる気」を見せることが何よりのアピールになると思います。
STEP2|志望動機・自己PRの考え方:完璧じゃなくてOK。でも軸は必要
インターンに応募すると、ほとんどの場合「志望動機」や「自己PR」を書くことになります。
ここで「え、何書けばいいの?」「スキルなんてないし…」と不安になる人も多いと思います。
僕もそうでした。
特別な資格もないし、文章力も人よりあるとは思っていなかった。
でも実際に選考を通過した経験から感じるのは、完璧な内容よりも、「今の自分の素直な気持ち」と「成長したいという姿勢」を言葉にできるかが大切だということです。
志望動機は“好き”や“興味”から出発してOK
志望動機というと、「社会課題に貢献したい」とか「御社の理念に共感して…」みたいなきれいな言葉を並べなきゃいけないと思いがちですが、インターンの段階ではそこまで求められていません。
大切なのは、「なぜその仕事に興味を持ったのか?」という“自分目線のきっかけ”を言語化すること。
僕の場合は、「文章を書くことが昔から好きだった」「情報を整理して、誰かに分かりやすく伝えることにやりがいを感じる」といった理由から、Webメディアのライター職に興味を持ちました。
それを志望動機にするときは、以下のような流れでまとめました。
昔から文章を書くことが好きで、大学ではサークルのブログや新歓資料なども担当してきました。誰かにとって有益な情報を、わかりやすく届ける仕事に挑戦してみたいと考え、応募しました。
正直な動機でOKです。「やってみたい」「ここで成長したい」その気持ちをしっかり伝えることが、最初の一歩です。
自己PRはスキルよりも“姿勢”を伝える
インターンの選考では、「実績」や「スキルの高さ」よりも、“どんな姿勢で働いてくれるか”が見られています。
だから、自己PRでも「今の自分にできること」だけでなく、「わからないことにも前向きに取り組みます」という柔軟さや学ぶ意欲を伝える方が効果的です。
僕は、次のような自己PRを用意していました。
文章を書くことに関してはまだ勉強中ですが、構成や見出しの工夫、SEOの知識などをしっかり吸収して、読者にとって価値のある記事を作れるよう努力したいと思っています。フィードバックを受けて改善していくことにやりがいを感じるタイプです。
このときも、“今の自分”と“これからの自分”をセットで見せることを意識しました。
企業と自分の“重なる部分”を意識する
もし余裕があれば、応募先企業の特徴や方向性と、自分の関心がどうつながるかも一言加えると、より伝わりやすくなります。
たとえば、メディア系の企業で「若者向けのライフスタイル情報を発信している」会社であれば、
私自身も、SNSやブログで「同世代に役立つ情報をシェアすること」に関心があり、貴社が発信している記事のトーンや読者目線に共感しました。
というように、相手との接点を見つけることで、ただの「やる気」だけではなく、「ここに入りたい理由」が一層伝わります。
迷ったら、“素直な言葉”がいちばん刺さる
もしどうしても言葉がまとまらないときは、「どう見られるか」よりも、「自分はなぜこれをやりたいのか」「この仕事のどこが気になるのか」といった素直な気持ちに立ち返るのが大切です。
採用担当の方も、「大学生らしい視点」を求めています。多少拙くても、心のこもった言葉は必ず伝わると僕は信じています。
STEP3|面接当日のリアル:見られていたのは「中身」より「姿勢」だった
応募して書類選考を通過すると、次はいよいよ面接。
「何を聞かれるんだろう…」「うまく話せるかな」と緊張する人も多いと思います。
僕も、最初の面接ではとにかくドキドキして、前日の夜は何度も質問例をシミュレーションしていました。
でも、実際に面接を受けてみて感じたのは、見られているのは「完璧な受け答え」ではなく、「姿勢や雰囲気」だということ。
面接前にやってよかったこと|余裕を持つと心も整う
まず、当日はとにかく早め行動が大事です。
僕はいつも、面接の30分前には現地最寄り駅に到着するようにして、近くのカフェで一息ついてから向かうようにしていました。
息を整える時間を少し取るだけで、面接中の言葉の出方や表情が全然違ってくるんです。

もしオンライン面接なら、10分前にはZoomを開いてネット環境や背景をチェック。部屋の明るさやマイクの音質も確認しておくと安心です。
実際に聞かれた質問とその意図
僕が受けたWebメディア企業の面接で、実際に聞かれた質問は以下のようなものでした。
- 「なぜうちを選んだのですか?」
- 「大学ではどんなことをしていますか?」
- 「普段、どんな記事を読んでいますか?」
- 「記事を書くうえで大切にしたいことは何ですか?」
- 「どんなテーマで記事を書いてみたいですか?」
内容は決して難しいものではありません。
でも、「ちゃんと考えているかどうか」が伝わるかどうかが大事。
僕は、あらかじめ企業のメディアをいくつか読んで印象的だった記事をメモしておき、面接ではその中の一つを挙げて「この構成がわかりやすかった」と伝えました。
それだけでも、「読んでくれているんだな」というリアクションが返ってきたのを覚えています。
面接で一番見られていたのは「マナー」より「元気さ」
面接というと、服装や言葉づかいなどの「マナー」が気になるかもしれません。もちろん、最低限の清潔感や丁寧な言葉遣いは必要です。
でも、僕が体感として強く感じたのは、「元気よく、素直に話せること」こそが何より大事だということ。
- 声ははっきりと大きめに(少し緊張していても声を出すだけで印象が変わる)
- うなずきやリアクションをしっかりと(共感力・素直さを見せられる)
- 分からない質問には「分かりませんが、調べてみます」と正直に答える勇気
僕はそこまで滑舌も良くないし、敬語も完璧ではなかったですが、とにかく誠実に、前向きに話すことを意識しました。
結果的に「明るくて素直そうだったから」と合格理由を教えてもらえたこともあります。
逆質問は“働く姿勢”を伝えるチャンス
面接の最後に、「何か質問はありますか?」と聞かれることがあります。
このときは、相手に興味を持っていることを素直に伝えるチャンスです。
僕が実際にした逆質問:
- 「インターンの方は普段どんなふうにフィードバックをもらっていますか?」
- 「これまでに活躍されたインターンの方って、どんなタイプでしたか?」
形式的なことよりも、「自分がこの環境でどう頑張れるかを考えている」姿勢が伝わると、面接官の印象もグッと良くなります。
面接は、スキルを測る場というより“仲間としてやっていけるか”を見る場
選考が終わったあと、僕が一番強く感じたのは、面接は「できるかどうか」ではなく、「一緒に働きたいかどうか」を見る場だということでした。
だからこそ、完璧である必要はありません。素直で前向きであれば、それだけで十分に合格ラインを超えられます。
STEP4|合格後にやっておいてよかったこと:スタートダッシュの鍵は“準備と素直さ”
面接を終えて無事にインターンに受かると、次はいよいよ実務のスタートです。
とはいえ、「いきなり仕事なんてできるの?」「他のインターン生はもっとできる人ばかりだったらどうしよう…」と不安になるのは当然。
僕自身、最初の業務日にはガチガチに緊張していましたし、実際にわからないことだらけでした。
でも、そんな中でも「やっておいて良かったな」と思える準備や心構えがいくつかあります。
過去の記事や会社の発信を“読み込んでおく”
ライター職として参加することが決まったとき、まず最初にやったのは、会社が運営しているWebメディアの記事を片っ端から読むことでした。
- どんなトーンで書かれているのか
- 見出しの付け方や構成はどうなっているか
- 読者は誰を想定しているのか
といった点に注目して読むことで、「この会社が求める書き方」の肌感がつかめるようになります。
書き始めてからも、似たテーマの記事を参考にできるので、これは本当に助けになりました。
“真似ること”から始める|YouTubeやSNSも活用
自分にライティングスキルがあるわけではなかったので、最初はとにかく「真似る」ことを意識しました。
たとえば、ライター系YouTuberの動画を見て、
- 記事の構成テンプレート
- SEOの基本的な考え方
- 読者の離脱を防ぐ冒頭文の作り方
などをメモして、実際に自分の執筆にも取り入れたりしていました。
(僕の場合は、「リュウジのバズレシピ」的なノリで、まずは“プロの型”を借りることから始めた感じです)
スケジュール管理|授業・サークルと無理なく両立するには?
長期インターンは週2〜3日程度の出勤や作業が求められる場合が多く、学業・サークル・アルバイトとの両立が課題になってきます。
僕は、授業が少ない曜日に作業日を集中させたり、科目登録で半日休みや全休を意図的に作るといった工夫をして、無理なく続けられるスタイルを組みました。
もし「毎週この時間は出られません」などがあれば、早めに相談しておくことが大事。多くの企業は学生生活への理解があるので、柔軟に対応してくれるケースがほとんどです。
分からなくて当たり前。でも、“素直さ”と“レスの早さ”は武器になる
実際に業務が始まると、「初めて聞く単語」「慣れない指示」「時間の見積もりミス」など、とにかく戸惑いの連続です。
でも、そんなときに意識していたのは、とにかく「素直に」「早く」反応すること。
- 分からないことはすぐ聞く
- 指摘されたら感謝してすぐ修正する
- レスポンスは当日中に返す(難しい場合はひとこと報告)
この2つを守るだけで、「信頼できる人だな」と思ってもらえるようになります。
スキルがなくても、“姿勢の良さ”でちゃんと戦えるというのは、インターンで得た大きな学びの一つでした。
まとめ|最初の一歩は怖い。でも、一歩踏み出せば景色は変わる
長期インターンという選択肢は、決して「就活のためだけ」のものではありません。
確かに、ガクチカとして語れるような経験を得られる、企業の仕事を体感できる、社会人との接点が持てる…といった実利的なメリットも多くあります。
でも、実際にインターンを経験した僕が一番強く感じたのは、「自分の価値観が大きく変わった」ということでした。
最初は、「記事ってどう書くの?」「チャットの返信ってこれでいいの?」「このミス、めちゃくちゃ怒られるんじゃ…?」と常にビクビクしていました。
でも、やっていくうちに、
- 分からないことは恥ずかしいことじゃない
- ちゃんと謝って、次に活かせばいい
- 相手の時間を大切にすることが信頼につながる
という「社会人としての基本姿勢」を、自然と身につけていくことができました。
これは授業でもサークルでもなかなか得られない、実務の中だからこそ体感できる学びです。
また、インターン先で働く大人たちの姿を見る中で、「こんなふうに働きたい」「こういう人にはなりたくない」といった、自分なりの“将来像”が少しずつ輪郭を帯びてきたのも、大きな収穫でした。
もちろん、長期インターンがすべての人にとってベストな選択肢というわけではありません。
大学生活の中でしかできない経験──部活やサークル、留学、学園祭、趣味に全振りした日々だって、同じくらい価値があると思います。
だからこそ最後に伝えたいのは、「なんとなくみんなやってるから」ではなく、自分が何を得たいのかを考えて動くことが大切ということ。
一歩踏み出せば、見える景色が変わる。その一歩を、応援しています。