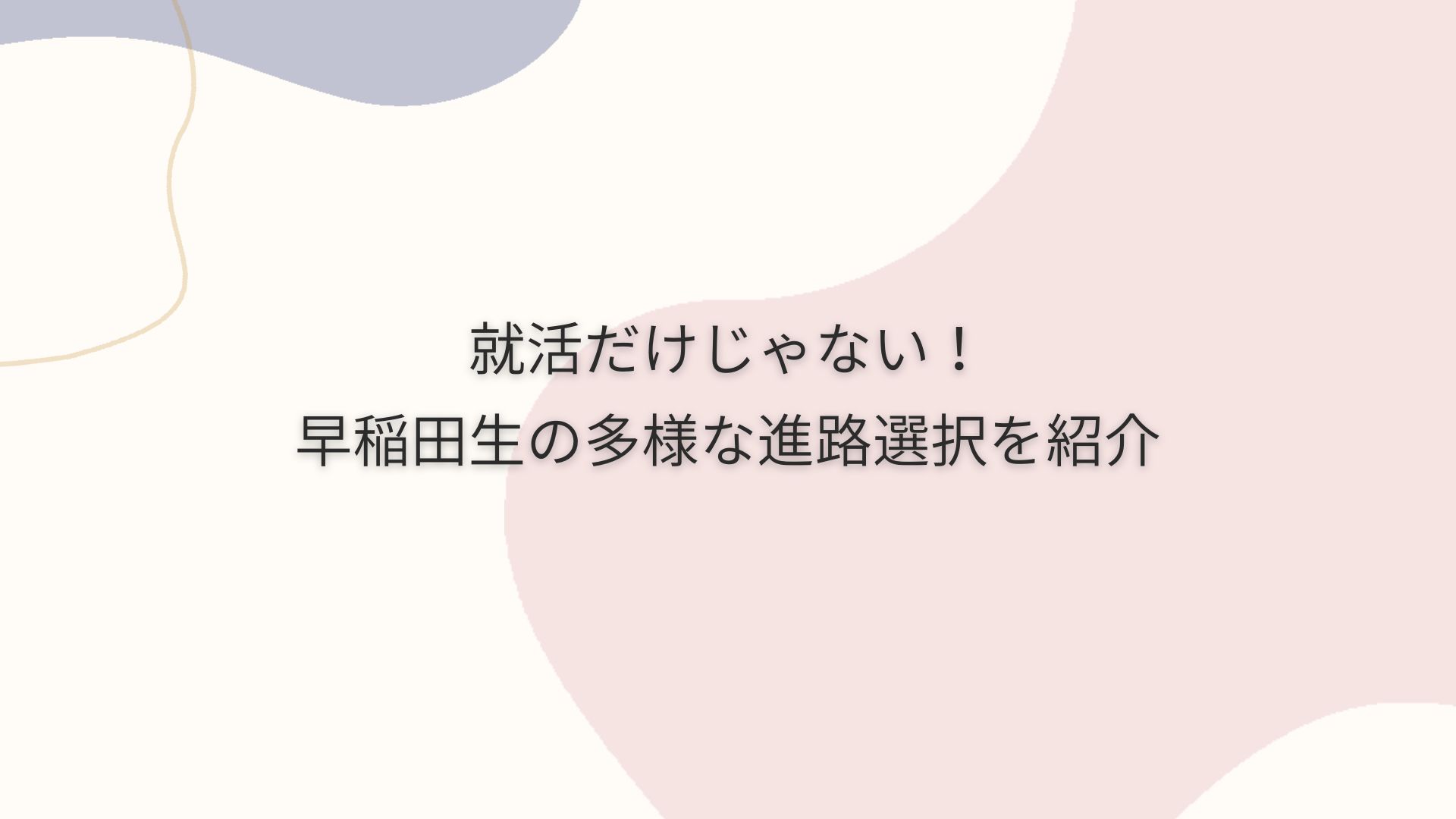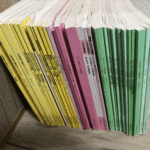こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。
「大学に入ったら、みんな就職活動をして会社に入るんでしょ?」
高校生のうちは、そんなイメージを持っている人も多いと思います。確かに大半の学生は就職活動をして社会に出ていきますが、実際の大学生の進路はもっと多様です。
たとえば、理系では大学院進学がほぼ当たり前だったり、文系でも専門性を極めたい人が海外の大学院に挑戦したり。
留学で視野を広げる人もいれば、司法試験や公認会計士といった難関資格の勉強に専念する人もいます。中には起業に挑戦したり、芸術や研究の道に進む人だって。
「就活」という道が大きな選択肢であることは間違いありません。

でも、大学で出会う仲間の中には全く違う進路を選ぶ人もたくさんいて、その多様さこそ大学生活の面白さのひとつだと感じます。
この記事では、早稲田生のリアルな事例を交えながら、就活以外の進路の選択肢を紹介していきます。
高校生のみなさんにとって「大学のその先」を考えるきっかけになれば嬉しいです。
目次
院進学:特に理系では当たり前の選択肢
理系では院進学が“王道ルート”
まず知っている方も多いかもしれませんが、理系の学生にとって大学院進学はほぼ標準的な選択肢といえます。
特に先進理工学部や基幹理工学部などでは、学部卒の段階では研究経験が浅く、研究職や専門職を目指すには不十分とされることが多いです。
メーカーの研究職や、AI・バイオ・化学などの先端分野に関わる仕事は「修士卒」が事実上の応募条件になっていることも珍しくありません。
僕の理系の友人も「周りはほぼ全員院に進む」という雰囲気だったそうで、学部卒で就職を選んだ人はむしろ少数派。
彼自身も修士課程まで進学し、研究テーマを深めることで自分の専門性に自信がついたと話していました。
文系でも院進学を選ぶ人がいる
一方で、文系は就職が多数派ですが、少数ながら大学院に進む人もいます。
例えば、政治経済学部で学んだ内容をさらに深め、公共政策の研究者を目指すケースや、文学研究を極めたい人が博士課程に進んで研究者の道に進むケースです。
海外の大学院を目指す学生もいて、「国際機関で働きたい」「グローバルなキャリアを築きたい」といった明確な目標を持つ人が挑戦しています。
僕の先輩には、在学中に英語力を磨いてヨーロッパの大学院に進学した方がいます。
修士号を取得した後は国際NGOに就職し、まさに「大学院進学がキャリアを開いた」成功例でした。
経済的・時間的コストという課題
もちろん、大学院進学は良いことばかりではありません。
一番の課題は経済的な負担です。修士課程で2年間、博士課程まで進めばさらに3年以上の学費と生活費がかかります。
奨学金を利用する人も多いですが、卒業時点で数百万円の借金を背負うケースもあります。
また、時間的な制約も大きいです。院に進むと「授業+研究室での活動+学会発表」という生活になり、学部時代のようにサークルやアルバイトに割ける時間は激減します。
僕の理系の友人は「研究室に毎日通うからサークルには全然行けなくなった」と話していて、ライフスタイルが大きく変わるのを感じました。
大学院進学のメリット
それでも大学院に進む価値は大きいです。
- 就職の幅が広がる
修士号を持つことで、研究職・技術職・専門職といった学部卒では難しい求人に応募できるようになります。特に大手メーカーやIT系の研究部門は修士卒が前提になっている場合が多いです。 - 自分の興味を徹底的に掘り下げられる
大学院は「自分の好きなことに没頭できる時間」です。学部では幅広く学ぶ必要がありますが、院では自分の研究テーマに集中できます。友人も「2年間、好きな研究に打ち込んだこと自体が一生の財産」と言っていました。 - キャリアとしての信頼感
専門性があるというだけで、社会に出たときに「この人は知識の裏付けがある」という評価を受けやすいのもメリットです。
高校生のみなさんに知っておいてほしいのは、「大学=就職」と決めつける必要はない、ということです。
特に理系では院進学が当たり前であり、文系でも本気で専門性を高めたい人には大学院という道があります。
もちろん時間やお金の負担は大きいですが、その分得られる経験やキャリアの可能性は広がります。
「大学院に行く=遠回り」ではなく、自分の興味を追求し、キャリアの選択肢を広げる進路だと考えてみてください。
留学:憧れは大きいけれど現実的な壁も
留学を志す人は多い
大学に入ると「せっかくだから海外に出てみたい」と考える学生はかなり多いです。
高校生の頃から「大学生=留学」というイメージを持っている人も少なくないでしょう。
早稲田でも国際教養学部以外の学部の学生が留学に興味を持つケースは多く、サークルや授業でも「いつか海外に行ってみたい」と話題になることがあります。
僕の周りでも「英語を現地で使えるようになりたい」「海外の大学の授業を受けて視野を広げたい」と考えて、留学を視野に入れている友人は珍しくありません。
実際に留学する人はそこまで多くない
ただし、実際に長期留学まで踏み切る人は意外と少数です。
その最大の理由は経済的な負担。半年〜1年の交換留学だと、現地での生活費や渡航費を含めて100万円以上かかることもあります。
奨学金制度はあるものの、全員が受けられるわけではなく、金銭面で諦めざるを得ない学生もいます。
また、所属する学部や研究室との兼ね合いも大きなハードルです。理系の友人は「研究室に所属したら長期留学は難しい」と話しており、文系と比べてさらに選択肢が限られてしまうケースもあります。
国際教養学部は“必修で留学”
早稲田の国際教養学部は、留学がカリキュラムに組み込まれているのが特徴です。
ほぼ全員が在学中に1年間海外へ行くので、留学経験者の割合は圧倒的に高いです。アメリカやイギリスといった英語圏だけでなく、アジアやヨーロッパの大学を選ぶ人もいて、卒業後は外資系や国際機関に進む人も少なくありません。
実際、国際教養学部の友人は「留学が必修だからこそ、準備もサポートも充実していて安心だった」と話していました。留学が学部の文化として根付いているのも特徴です。
ただ、内部進学した僕にとって、高校からの友人の多くが一斉に留学に行ってしまうのは寂しいものです。
短期留学や交換留学という選択肢
長期の1年留学だけがすべてではありません。
早稲田には夏休み・春休みを利用した短期留学や、半年程度の交換留学も用意されています。
僕の知り合いは、2年生の夏休みにアメリカの大学で3週間の語学研修に参加しました。費用は長期留学に比べて抑えられ、かつ「海外で生活する」という体験を得られたので「自分の将来を考えるきっかけになった」と話していました。
また、大学の協定校を通じた交換留学なら、早稲田の学費を払い続けつつ現地大学で学べるので、経済的な負担を減らせるのも魅力です。
留学が就職や将来にどうつながるか
「留学って就職に有利なの?」とよく聞かれます。確かに英語力や海外経験は強みになりますが、ただ行っただけでは評価されにくいのも事実です。
企業が評価するのは「留学で何を学び、どう成長したか」。つまり、留学をキャリアや将来のビジョンにつなげられるかが大切なんです。
実際に僕の先輩で、留学をきっかけに国際ビジネスに関心を持ち、外資系企業に就職した人もいます。
逆に「楽しかったけど、就職活動では特にアピールできなかった」という人もいて、留学の成果は自分の取り組み次第だと感じます。
高校生の皆さんに伝えたいのは、留学は誰にでも開かれたチャンスではあるけれど、現実的な壁もあるということです。
経済的負担や学部のカリキュラムによって難しい場合もありますが、短期留学や交換留学など柔軟な制度も整っています。
「大学生になったら必ず留学しなければいけない」というわけではありません。
ですが、興味があるなら大学選びの段階から留学制度に注目しておくと、後悔のない選択につながると思います。
難関資格を目指す人たち
「就活」ではなく「資格」を選ぶ進路
大学生の中には、普通に就職活動をするのではなく、資格取得をゴールにして進路を決める人たちがいます。
特に有名なのは、法曹を目指すための司法試験や、公認会計士試験、国家公務員総合職の試験です。
これらは難易度が非常に高く、合格までに数年単位で勉強が必要になりますが、その分合格すれば専門職として安定したキャリアを歩むことができます。
法曹を目指す学生
早稲田には法学部があり、司法試験合格を目指して勉強する学生が一定数います。
司法試験を突破するには法科大学院への進学が必要で、学部時代から「法曹コース」と呼ばれるカリキュラムで基礎を固めている人もいます。
僕の知り合いの法学部生は、3年生の時点でサークル活動をほぼ辞め、1日10時間以上勉強する生活に切り替えていました。遊ぶ時間やバイトの余裕はほとんどなく、まさに資格勉強に人生をかけている様子でした。
実は、法学部以外から法曹や法科系公務員を目指す学生も少なくないです。
僕のゼミは政治経済学部にもかかわらず法学系の学習をしているのですが、メンバーの3割ほどは法曹or法科系公務員を目指していました。
公認会計士を目指す学生
公認会計士は文系・理系を問わず人気の資格のひとつです。
会計や監査のプロとして、大手監査法人や企業の財務部門で活躍できます。
本キャンのすぐ近くには資格学校「TAC」があり、そこに通って会計士の勉強をしている学生も多いです。
僕のサークルメンバーも知っているだけで4名ほどが公認会計士を目指していて、毎日授業が終わったらすぐにTACに行き、深夜まで勉強。
サークルには全然来られなくなってしまいましたが、後に無事合格し、大手監査法人への就職を決めていました。
彼らの姿を見て「資格勉強は本当に大変だけど、合格すれば人生が大きく変わる」と実感しました。
国家公務員を目指す学生
また、国家公務員総合職を目指す学生もいます。
こちらも難関試験で、法律や経済など幅広い知識を問われます。合格すれば各省庁に配属され、日本の政策形成に関わることができます。
僕のゼミの先輩で総合職を受けた人は、就活はほとんどせずに1年間ほぼ勉強漬けだったそうです。
結果的に合格し、官庁に進んでいきましたが、「勉強をやめてしまったら落ちる」というプレッシャーの中で生活するのは相当なストレスだと話していました。
資格勉強の大変さと得られるもの
こうした難関資格の勉強は、サークルやアルバイトとの両立が難しく、どうしても「資格一本」に絞った生活になります。
僕の周りでも、資格を目指す友人は遊びの誘いに来なくなり、空き時間も常に参考書を開いていました。
一方で、合格した後の道は非常に広く、安定したキャリアや高い専門性を手に入れることができます。
就活のように「どの企業に受かるか」と悩むのではなく、資格合格という明確なゴールがあるのも、この進路の特徴です。
高校生のみなさんに知っておいてほしいのは、「就活だけが安定への道ではない」ということです。
難関資格は時間もお金もかかりますが、合格すればその分大きなリターンがあり、社会からの信頼も厚いです。
ただし軽い気持ちで挑戦できるものではなく、強い覚悟が必要になります。
「自分は本当にこの道を選びたいのか?」をじっくり考えることが大切です。
起業に挑戦する学生
学生起業という選択肢
大学生活の進路の中で、少数派ではあるものの「起業」という道を選ぶ人もいます。
近年はSNSやアプリ、ECサイトなど初期費用の少ないビジネスモデルが増えており、大学生でも挑戦しやすくなっています。
「せっかく自由な時間の多い大学生だからこそ、自分のビジネスをやってみたい」という考えを持つ学生は確かに存在します。
慶應との違いと早稲田の現状
学生起業というと、やはり慶應義塾大学が有名です。
データを見ても、慶應の方が起業率は高いと言われています。その背景には、三田会(慶應の強力なOBネットワーク)の存在が大きく、資金や人脈の面で有利に働くからです。
一方で早稲田でも、起業に挑戦する学生は一定数います。
近年は大学としても「起業家育成プログラム」を整備しており、授業やインキュベーション施設でビジネスの立ち上げを支援しています。ただ、やはり割合としては就職や大学院進学に比べれば圧倒的に少数派です。
学生起業のリアル:挑戦とリスク
起業は華やかに見えますが、成功率は非常に低いのが現実です。
アイデアは良くても資金が足りなかったり、メンバーが続かなかったりして、途中で頓挫してしまうケースも多いです。
僕の知り合いでも、友人と一緒にアプリ開発を始めた人がいましたが、勉強やサークルとの両立が難しく、半年ほどで頓挫してしまいました。
その経験を通じて「挑戦自体は学びになった」と話していましたが、やはり本気でやらなければ続かない厳しい世界だと感じました。
起業に挑戦する人の特徴
起業に挑戦する学生にはいくつかの共通点があります。
- 挑戦心が強い:周りが就活していても「自分の道を行く」という覚悟を持っている
- 情報発信に積極的:SNSやピッチイベントで自分のアイデアを売り込む
- 行動が早い:思いついたらまず動いてみる行動力がある
- 失敗を恐れない:うまくいかなくても次の挑戦に活かそうとする
こうした姿勢は、たとえ起業が失敗に終わったとしても、就職やキャリアの面で評価されることも多いです。
挑戦する価値はある?
起業はリスクが大きいものの、大学生のうちに挑戦する価値は十分にあると僕は思います。
なぜなら、社会人になってからは生活の安定や家族のことを考えてリスクを取りにくくなるからです。大学生のうちは時間も自由もあり、仮に失敗しても「いい経験だった」と切り替えられる環境があります。
また、実際に起業に挑戦した学生の中には、その後ベンチャー企業に就職したり、自分の経験を武器にキャリアを築いていった人もいます。
高校生の皆さんに伝えたいのは、起業は決して身近なものではないけれど、選択肢として存在するということです。
「起業するなんて一握りの人だけ」と思うかもしれませんが、早稲田のように起業支援制度が整った大学も増えており、挑戦しようと思えばチャンスは十分にあります。
もちろんリスクは大きいですが、「挑戦心」や「行動力」を磨く場としては、起業は最高の舞台かもしれません。
その他の進路:研究・芸術・フリーランスなど
大学の枠を超えた進路
これまでに紹介した「就活」「院進学」「留学」「資格」「起業」以外にも、大学生には実にさまざまな進路があります。
早稲田は学生数が多く、学問分野や活動の幅も広いため、王道ではないけれど魅力的なキャリアを歩む人も少なくありません。
研究者の道へ進む人
特に理学部や文化構想学部などでは、研究者を目指す学生もいます。学部・修士・博士と進み、大学や研究機関で教員や研究員になることを目標にしています。
僕のゼミの先輩には「将来は大学の先生になりたい」と話していた人がいて、卒業後もそのまま博士課程に進みました。
研究の世界は競争が激しく、ポストに就くのも簡単ではありませんが、「知の最前線で生きる」という道を選ぶ人も確かにいます。
芸術やクリエイティブの道
早稲田は芸術系の学部はないものの、サークル活動や個人活動を通して芸術の道を志す学生もいます。
演劇サークルや映画制作サークルから役者や監督を目指す人、写真や美術の個展を開く人など、表現の世界に挑む学生は意外と多いです。
僕の知り合いの中には、在学中からインディーズバンドとして活動し、そのまま音楽一本で生きていくと決めた人もいました。
周りからすると「リスクが大きい」と思うかもしれませんが、本人にとっては夢を追う大切な選択肢なんです。
フリーランスとして働く人
近年増えているのが、フリーランスとして働き始める学生です。
Webライター、デザイナー、動画編集者、エンジニアなど、スキルがあれば大学在学中から仕事を請け負うことが可能です。
僕自身も大学でWebライターの長期インターンを経験しましたが、そのままフリーランスとして活動を続ける人もいます。
就職をせず「自分で稼ぐ」ことを選ぶ人はまだ少数ですが、インターネットを活用すれば十分に実現可能な進路になっています。
実際、サークルの先輩の1人は就職はせず、フリーのエンジニアとして生きる選択を取った人がいます。
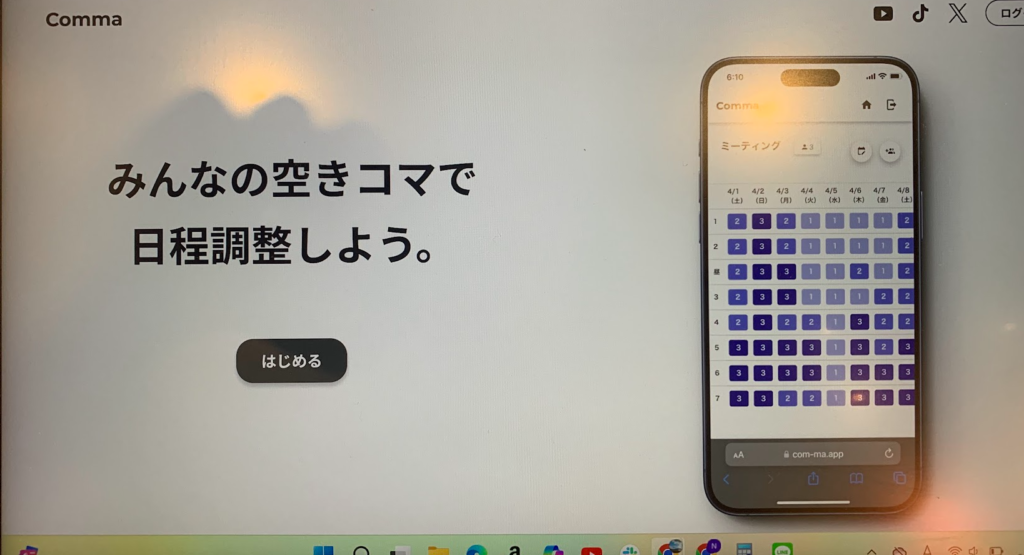
海外でのチャレンジ
もうひとつのパターンが、海外で活動を始める学生です。
留学という形ではなく、現地で働いたり、ボランティアやNPO活動に飛び込むケースです。
僕の知り合いの中には、大学卒業後にアフリカで教育支援をする団体に参加し、そのまま海外を拠点に生きていくことを選んだ人もいます。
普通の就職や大学院進学とは全く違いますが、グローバル化が進む中で確かに存在する進路です。
高校生のみなさんに知ってほしいのは、「大学の進路=就活」ではないということです。
もちろん多くの人は企業に就職しますが、研究・芸術・フリーランス・海外挑戦など、選択肢は思っている以上に多彩です。
大切なのは「自分は何を大事にしたいのか」を考えること。安定を取るのか、挑戦を取るのか、自分らしいキャリアをどう描くかは人それぞれです。
まとめ:進路は人の数だけある
大学生の進路といえば「就活して企業に入る」というイメージが強いかもしれません。
確かに、それが一番多いルートであり、安定したキャリアを築くうえでは安心感のある選択肢です。ですが、実際には大学生の進路は人の数だけ存在します。
理系では院進学が当たり前になっていたり、留学を目指して挑戦する人がいたり、難関資格の取得に人生をかける人もいます。
中には起業という大きなリスクに挑む人もいれば、研究や芸術の道、フリーランスや海外活動といった多彩な道を選ぶ人もいるのです。
僕自身も早稲田でいろいろなタイプの学生を見てきましたが、本当に「正解は一つじゃない」と実感します。
むしろ、多様な生き方が認められているのが大学の世界であり、早稲田のように学生数が多い大学では特にそれを強く感じます。
高校生の皆さんに伝えたいのは、「就活しない=道がない」ではないということ。
院進学や資格取得、挑戦や夢の追求など、選べる進路は想像以上に豊かです。そしてどの道を選んでも、そこには学びや成長のチャンスがあります。
これから大学進学を考えている人は、ぜひ「自分はどんなことを大事にしたいのか」「何をしているとワクワクするのか」を考えてみてください。
周りに流されず、自分の価値観に合った進路を選べば、きっと後悔しない大学生活とその先の人生につながるはずです。