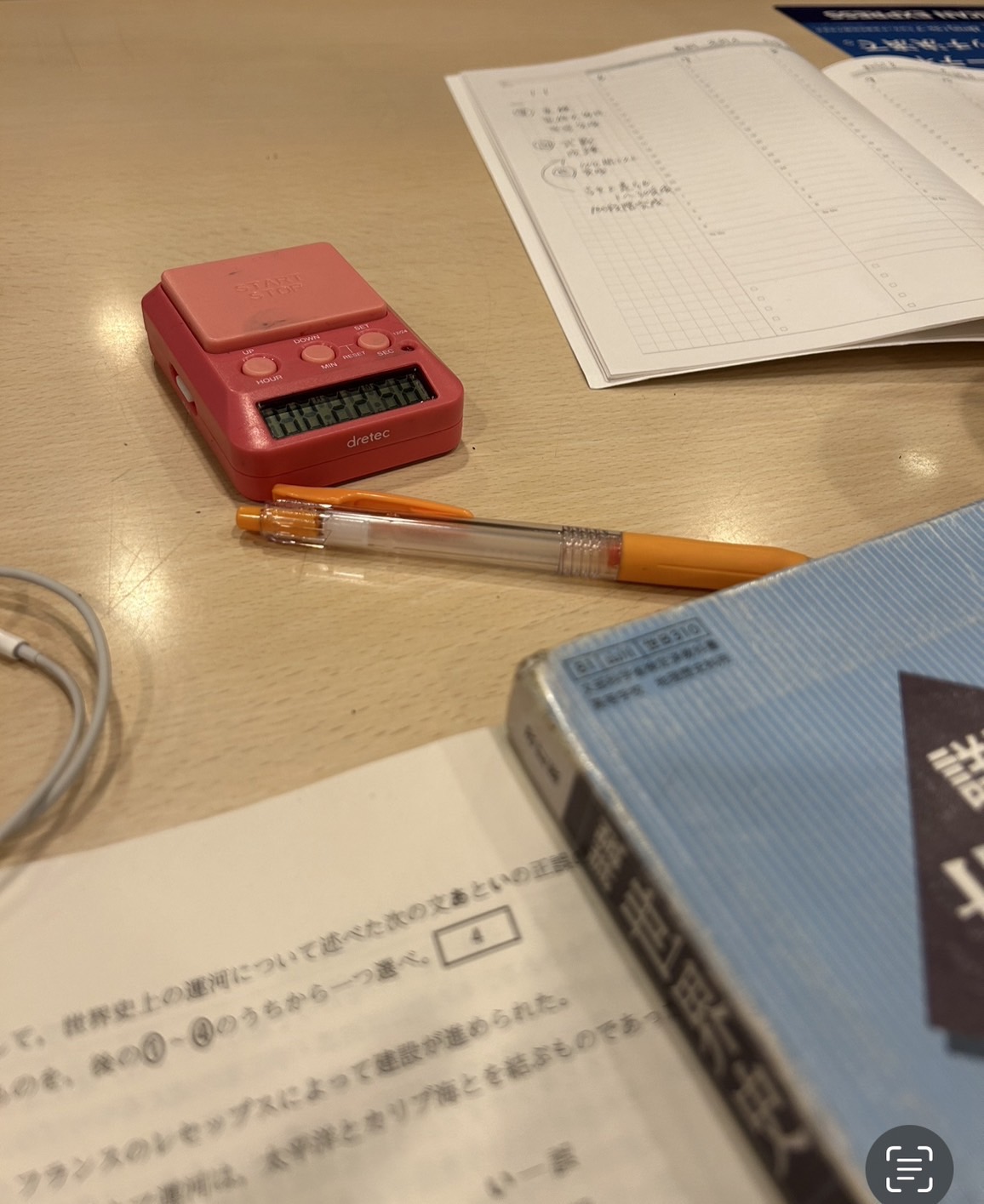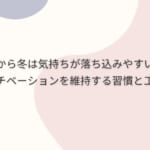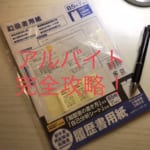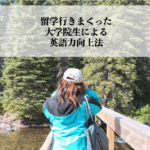こんにちは!現役大学生のだにえるです。
近年、大学進学率が増えている一方で、「奨学金」の問題がよくニュースに取り上げられていたりと、「大学進学事情」について悩みを持つ高校生・その親御さんも少なくないと思います。
特に、高校生にとっては学費のことはもちろんですが、そもそも「大学に行く意味が見いだせない」とか「大学生活があんまりイメージつかない」がゆえに進路に迷っている人もいるのではないでしょうか。
私自身も、身近に大学に進学した親族がいなかったこともあって、いまいち「大学生活」のイメージが付かずに悩んだ経験があります。とりあえず「将来のため」という仮の目標のもと勉強をしていたのですが、なかなかそれだとモチベーションを保ちにくいときもありました。
そこで!今回の記事では、大学2年生として今まで大学生活を送っていた私が思う、「大学に進学してよかったと思う理由5選」をご紹介します!
目次
就職前にいろんなことを経験できる
大学生活は、「社会に出る前の助走期間」と言われることもあります。
実際、私も今まで大学生活を過ごしてきて、そうなんだろうなあと思います。
というのも、大学生活は色々なことに挑戦できるチャンスがたくさん転がっていたり、時間がとれたりすることから、自分の得手不得手や好き嫌いの傾向を知ることができるからです。
例えば、私は大学で経営学・国際経営学を専攻していて、日頃から「グループワーク」の多い授業を必修で受けています。具体的には、4、5人くらいの学生で一緒に、先生に出されたビジネスのお題に合わせた「ビジネスプラン」や「広告アイデア」を、授業の内容を踏まえてプレゼンします。
元々私はそういう「プランを考える」とか、「アイデアを考える」ようなことが好きで、それを伸ばせると思ってこの専攻を選んだのですが、「グループでやる」となるとそれ以前に協力することや、人との円滑なコミュニケーションが求められるので、思っていたより大変です。メンバーによっては勝手に色々進めてしまうとか、アイデア出さない割に文句しか言わないとか、コミュニケーションをとるのが難しく、思うように自分の力が発揮できない。
逆に、自分一人で自由に考えてやっていい課題では高評価をもらえることが多く、自分でも納得した仕上がりのものを作ることができます。
もちろん、今後社会に出てからは「人と協調していく」ことが求められる場面も少なくないはずなので、今のうちに「人と折り合いをつけてよいものを作る」という練習はたくさん積んでいきたいと思います。
しかし、私が一番力を発揮できるタイミングは、「自分で自由に動いている時」なのかも。なんてことに気が付くきっかけになりました。
そのほかにも、私は大学に入ってから「せっかくだから華の大学生活を楽しむんだ!」と色々なサークルや団体に入ったのですが、全部合わなくてやめました。つらい。結構落ち込みました。私ってどこにもなじめないのかな、みたいな。
それでも、逆に私は一人で色々行動できるタイプ。頑張ってバイトをして台湾やベトナムに一人旅に行ったら、現地の人と仲良くなってご飯を食べながら片言の英語で恋バナをしたりと、私だからできたであろう経験もできました。その話を面白い!と聞いてくれる人もたくさんいますし、最近始めたバーのバイトなんかでお客さんに話すと超ウケます。
多分、大学に入らずにそのままストレートで就職していたら、「私は人と組織の中で協力してやっていくのが得意なタイプだ!」とか、ちょっと勘違いしたまま社会に出て、職場のミスマッチを起こしていた気がします。
今のうちに「授業」、「サークル・部活・学生団体」、「バイトやインターン」、「旅」などなど色々経験することで、就職先を探す前に自分の得手不得手・好き嫌いの方向を知ることができること。これは大学生の特権だと思います。
色々なアルバイトを経験できる
大学生活で得られたものの一つに、「さまざまなアルバイトを経験できたこと」があります。高校生の頃は学校と家の往復で、関わる人のほとんどが同年代でしたが、大学に入ってからはキャンパスを飛び出して、まったく違う世界の人たちと接する機会がぐっと増えました。
私がこれまで経験してきたアルバイトは、「ディスカウントストアの品出し・レジ打ち」「コンセプト居酒屋のホール」「WEBライター」「塾講師(オンライン含む)」「バーのバーテンダー」など、本当にバラバラです。それぞれの職場で求められるスキルや空気感もまったく違っていて、最初は戸惑うことばかりでした。でもそのぶん、短期間で多くのことを学べた気がします。
たとえばディスカウントストアでは、とにかく体力勝負。朝早くから重い商品を並べたり、お客さんのレジ対応をテキパキこなすことが求められました。レジではクレーム対応に追われることもあり、接客の厳しさと、それでも笑顔で応対する難しさを学びました。
居酒屋のホールでは、逆に「エンタメ性」が重要で、お客様を楽しませるサービスや、元気な声かけが必須でした。忙しい時間帯には同僚との連携プレーも求められ、「周りを見る力」や「チームで働くことの大切さ・むずかしさ」を実感しました。
オンラインの塾講師は現在進行形で進めているのですが、生徒一人ひとりに合わせた対応が必要で、授業の進め方にもコツが必要です。特にオンラインでは空気感がつかみにくく、言葉の選び方や表情の作り方など、対面以上に気をつけることが多かったです。それでも、生徒の成長に直接関われるやりがいもありました。なにより場所に囚われない「オンライン」なのは私に合っている気がします。
そしてここ最近始めたのが、バーのバーテンダーの仕事です。お客さんと対話しながら、その場に合った空気をつくるのがとても面白く、また、年齢も仕事も全く違う人たちと話す中で、社会を知るきっかけにもなっています。ミュージックバーなこともあって、趣味が合うお客さんもたくさん。私よりも詳しい人が多いので、色々教えてもらえます。忙しい時間帯はオーダーをとったり、お酒を造ったりと大変ですが、時間があるとお客さんとの会話も楽しめるので最高です。
こうした多種多様なバイト経験を通じてわかったのは、「どんな職場でも基本的に求められる社会スキルは同じ」だということです。「報告・連絡・相談」や「挨拶」、「笑顔」、「落ち着いて対応すること」。これらがちゃんとできていれば、基本何とかなります。多分。
そして、どんな職場でも、人との関係性がすべての基本になっているということ。年齢も学歴も性別も関係なく、いろんな人と関わって、認められたり、反発を感じたり、失敗して落ち込んだりしながら、自分なりのコミュニケーションの型が少しずつ育ってきたと思います。
大学は、学内だけでは学びきれない“社会の一歩手前”を知るチャンスにもなります。アルバイトという「小さな社会」の中で得た経験は、私の中で確実に大きな財産になっています。
興味を伸ばせる環境
大学では、高校とは大きく違い、「自分の興味のある授業」を自由に選んだり、「自分が専攻したい学科」を決めたりできる自由があります。これは大学の大きな魅力の一つであり、自分の関心や将来の目標に合わせて学びを深められる環境が整っているからこそ可能になることです。
高校のときは、クラス単位で授業が組まれており、自分で科目を選ぶ自由はほとんどありませんでした。そのため、自分の興味とは少しずれた内容でも受けざるを得ない部分が多かったのですが、大学では自分の興味や将来のキャリアに沿って、学びたい分野を選べるのが新鮮であり、非常にやりがいを感じています。
私の専攻と大学生活
私が専攻しているのは「国際経営学」という分野で、具体的には「マーケティング」「マネジメント」「リーダーシップ(コミュニケーション)」「ファイナンス」「英語」といった科目を中心に勉強しています。これらは全て、グローバルなビジネスの世界で活躍するために必要な知識やスキルであり、どれも私の将来に直結する重要な学問分野です。特に英語力の向上と、リーダーとしてのコミュニケーション能力を身につけることに強い関心を持っており、これらを体系的に学べるこの専攻を選んだことに満足しています。
私は立教大学の経営学部国際経営学科に通っています。この学科を志望した理由は二つあります。一つ目は「英語をもっと深く学びたい」という思いです。高校時代は国際系の学校に通い、英語の勉強に力を入れてきました。将来的にも英語を使った仕事や国際的なコミュニケーションに関わりたいという希望が強く、そのために大学でも英語のスキルを磨きたいと考えました。二つ目は「リーダーシップ」を学びたいということです。高校の文化祭や体育祭の行事でリーダー役を務める機会が多く、その経験から組織をまとめることやチームを引っ張ることに興味を持ちました。そこで、経営学の中でも特に人の動かし方やコミュニケーションに関する理論や実践を体系的に学べるこの学科を選びました。
実際に入学してみると、思っていた勉強内容とは少し違う部分もありました。例えば理論的な部分が多く、すぐに実践的なスキルに結びつかないこともありましたが、自分の目的意識をしっかり持ちながら授業を選び、興味のある分野に絞って学ぶことで、自分なりの学びを深めています。大学ならではの良さは、やはり「自分の興味を自由に追求できる」ことにあります。
最先端を駆ける教授、同じ志を持つ仲間
授業の前後には、その分野を専門に研究しているプロフェッショナルな教授に質問できる機会も多くあります。特にゼミや少人数制の授業では、教授とより密に関わることができ、より深く学問を理解したり、具体的な課題に取り組んだりできます。私は現在ゼミには所属していませんが、少人数授業で深く関わった先生からは、ビジネスに必要な思考法や、チームでうまくやっていくための方法を教わりました。今でも時々その先生に相談に乗ってもらうことがあり、大学での人との繋がりが自分の成長を支えてくれています。
さらに、大学のもう一つの特徴は「同じ興味や志を持つ仲間が集まっている」ことです。私の専攻する国際経営学科は、国際ビジネスに興味がある人が多く、英語に対して高い意欲を持つ学生が集まっています。そのため、授業のレベルも高く、日々周囲から刺激を受けていると感じます。お互いに切磋琢磨し合いながら、英語の勉強やビジネスの知識を高めていける環境は非常に恵まれていると思います。
学科に限らず、経営学部全体を見ると、ビジネスに強い興味を持つ学生が多いです。積極的に起業を目指したり、インターンシップに参加したりと、実践的な経験を積むことに熱心な人も多く見られます。また、自分の趣味や特技を将来のビジネスに結びつけたいと考えている学生も少なくありません。例えば、私の友人には将棋や書道、ライター業、スポーツに打ち込んでいる人たちがいます。彼らはそれぞれの分野で高いレベルを目指しつつ、将来はそれらを活かしたビジネスを展開したいという目標を持っています。そうした多様な夢や志が大学には溢れていて、自分自身も大きな刺激を受けています。
このように、大学は自分の興味に合わせて学べる自由があり、またその自由を活かして深く学べる環境と仲間が揃っている場所です。私はこの環境を最大限に活用して、自分の将来に繋がる学びを続けていきたいと思っています。
充実した設備・システム
大学に行くことの大きなメリットの一つが、「充実した設備・システム」です。多くの大学では、専攻の学びや、課外活動をサポートしてくれる設備やシステムがたくさんあります。
図書館
どの大学でもだいたい図書館は充実しているイメージです。
実際、私も大学の図書館を初めて訪れたとき、まずその広さと本の多さに驚きました。立教大学は、高校の図書室とは比べものにならない専門書、研究論文、海外の資料、雑誌、DVDまで揃っていて、まるで知識の宝庫です。しかも、自習ブースやグループ学習用のスペースもあり、静かに集中したい時も、友達とプレゼンの準備をしたい時も自由に使えます。テスト前には朝から夜遅くまで開いているので、自宅よりもずっと集中できる場所になっています。
自習スペース、パソコンルーム等

図書館だけではありません。多くの大学のキャンパス内には自習室、学習スペース、パソコンルーム、プレゼンテーションルームなど、多様な学びの場が用意されています。最近ではモニターやホワイトボード付きの打ち合わせスペースや、プロジェクターの使える練習ルームまで使えるようになり、学ぶ手段が格段に広がりました。自分のノートパソコンを持ち込んで、静かに作業したり、グループで課題に取り組んだりできる空間が、いつでも用意されているんです。もちろん、Wi-Fiや電源も完備です。
音楽室・ジム・劇場等
また、大学は課外活動に関する施設・設備も充実している傾向にあります。サークルや学生団体のための活動スペース、貸し会議室、音響や照明設備のあるホール、さらにはポスター作成用のプリンターなど、「やりたい」と思ったことをすぐ形にできる環境が整っています。しかも、予約制で無料で使えるものが多く、学生の“やる気”をちゃんと後押ししてくれる仕組みになっています。
私は1年生の時「軽音サークル」と「ダンス系サークル」に所属していました。軽音サークルの方では、部室棟の地下にある無料の音楽室をサークルで借りれたので、そこでバンドメンバーと練習をしていました。一方、ダンス系サークルの方では、大きな鏡がある部屋を使って練習していました。こういった設備は、お金はないけど、時間だけは有り余ってる学生に大きな可能性を与えてくれますよね。
学割
そして大学生ならではの「学割」や「学生向けイベント」も、実は大きなメリットです。電車や映画館、美術館などの割引はもちろん、地域のイベント、就活セミナー、企業インターン、キャリア講座など、学生限定で参加できるものが数え切れないほどあります。これらを通じて社会との接点が増え、「将来こんな仕事もあるんだ」「この分野って面白いな」と気づけることが何度もありました。
学校によっては、外部から学生向けにアルバイトや就活・ボランティア・イベント情報などが届くので、普段過ごしているだけで色々なチャンスが舞い降りてきます。
設備や制度が大充実な大学生活
こうした設備や制度の一つひとつが、私たちの学びと挑戦を“本気で支えてくれる存在”になっているのを実感しています。言い換えれば、「何かを始めるためのハードルがとても低い」のが大学という場所です。そしてその背景には、国や大学が「若者に投資している」という事実があります。これは、社会に出てしまうと簡単には手に入らない支援や環境でもあります。
今、もし「大学って行く意味あるの?」と感じている人がいたら、「自分の可能性を試すチャンスを、安心して得られる場所」だという視点で考えてみてほしいです。ただ授業を受ける場所、というだけではありません。充実した設備と制度があるからこそ、自分の興味や夢に向かって、一歩踏み出すことができる。そんな「今しかない特権」が、大学には確かにあります。
大学生活の価値は、学力や偏差値だけで決まるものではありません。どんな環境に身を置くかで、自分の未来への選択肢は大きく変わっていきます。ぜひそのことを知ったうえで、自分にとってベストな進路を選んでほしいと願っています。
自分と向き合う時間がある

大学生の特権、それは「とにかく時間がいっぱいあること」だと思います。これが正直一番大きいんじゃないかな。
私自身、高校までの生活は、常に授業や部活動、課題、模試、受験勉強に追われていて、立ち止まって考える時間はあまり多くありませんでした。ですが、大学に入ってからは、自分の時間を自分でどう使うかを自由に決められるようになりました。その自由さに最初は戸惑いもありましたが(今もどう使っていいものか逆に焦ることはある)、今では「自分の将来について考える」「自分と向き合う」時間に昇華できていると思います。
ノートや記事に書きなぐってみる
授業がない平日や、長期休暇のようにまとまった時間が取れるとき、ふと「自分はどんな人間なんだろう」と考えることが増えました。元々そういうことをくよくよと考えがちな特性を持つ私。暇な時間が増えるほど、永遠に考え続けてしまいます。
そんな時、誰かと話すわけでもなく、ひとり大学近くのカフェでノートを開いて、これまでの出来事や自分の感情を整理する時間は、自分にとってとても大切な時間になっています。特に、周囲と比べて焦ったり、自信をなくしたりすることがあると、自分自身に問い直す時間が心を支えてくれます。
最近自分の価値観を洗い出したり、自分の本音と向きあう「ジャーナリング」なんてものが流行っていますが、私がよくやっているこれは一種のジャーナリングなんだと思います。
読書の時間
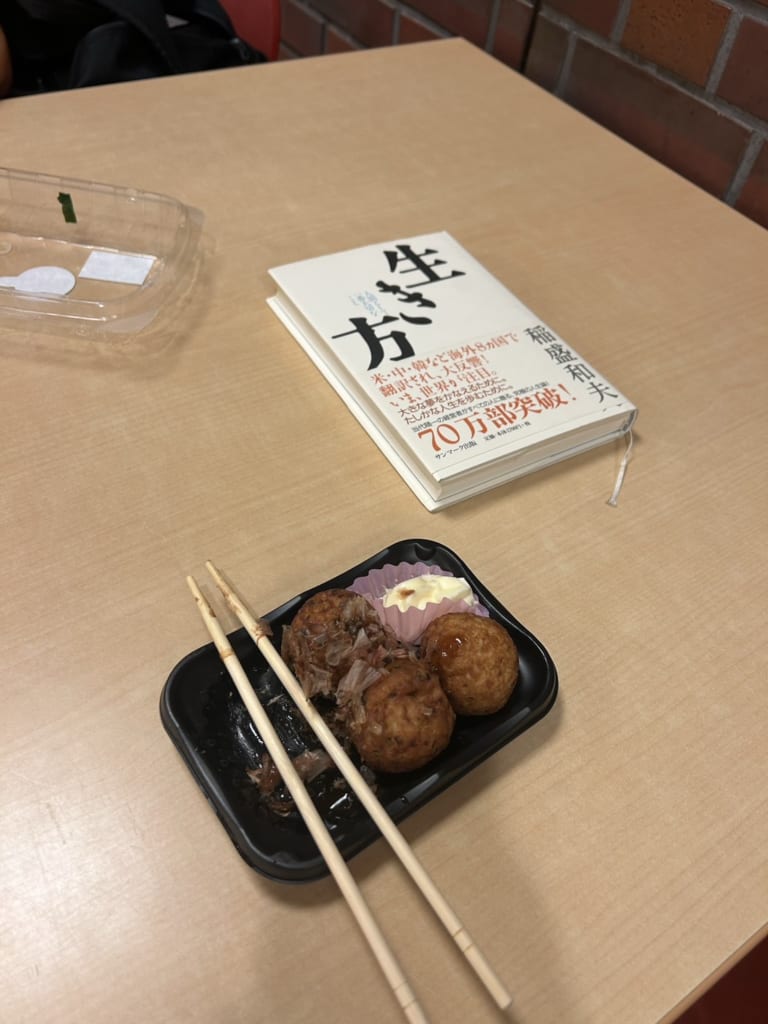
本を読むことも、自分と向き合うことだと思います。物語に没頭することで、自分では体験できない人生や考え方に触れることができるし、読書を通して自分が何に共感し、何に違和感を持つのかに気づくことがあります。そういった小さな発見を通じて、「自分」というものの輪郭が少しずつはっきりしてくる気がします。
大学に入って、一人の時間が増えたと同時に、読書に費やす時間も増えました。ここ最近は、毎週5冊くらい適当な興味のある本を図書館で借りて、暇さえあれば読む生活をしています。今私が読んでいるのは、まさしく「大学生活をどうあ過ごすか」といった内容の本。大学生活ってたくさんの機会や設備・システム、時間に恵まれている一方で、どう過ごしていいのか正直わからないところもあります。自分の納得した大学生活のため、大学生活自体の研究も欠かせません。
大学に入ってから小説でいえば、村上春樹の小説にはまっています。
「ノルウェイの森」「アフターダーク」「海辺のカフカ」この辺が好きでした。特に「アフターダーク」は比較的短めで読みやすいし、なにより内容が面白いのでおすすめです。私は一晩で読み切ってしまいました。
一人旅
また、最近は一人旅にも魅力を感じています。大学に入ってから、「台湾」「ベトナム」「沖縄」を一人で訪れました。
知らない土地を訪れて、誰も自分を知らない場所で過ごすと、普段の自分から少しだけ離れられる気がするからです。他人の視線を気にせず、自分の感情や感覚に集中できるこの時間もまた、自分と向き合うための貴重なチャンスだと思います。
今年の3月のベトナム旅行では、孤独がゆえに色々考えすぎてしまい、落ち込んで空港で動けなくなってしまうことがありました。当時はもう大変でしたが、今となっては、なかなかできない経験ができたなあって感じです。まだ似たようなことで悩んではいるのですが、逆にそこまで悩まなくなりました。・・・いや、そんなこともないか。
散々向き合って見えてきたこと
もちろん、未来に対する不安はあります。こんな私でも就職できるのか、とか、この選択は正しかったのか、10年後の自分は笑っていられるのか──そんな問いが頭をよぎることはたくさんあります。でも、その不安から目を背けずに、自分の気持ちと丁寧に向き合う時間があるからこそ、「まあ大丈夫」と思えるようになってきました。答えが出なくても、「考え続けること」を大事にしたいと思えるようになったのは、大学生活の中で得られた大きな成長のひとつだと思います。
将来のことを真剣に考えるのは怖いことでもあるけれど、自分の価値観や願いに耳を傾ける時間を大切にすることで、自分自身への信頼が少しずつ育っていく気がします。大学生活という、ある意味で「余白」の多い時期に、こうした時間を持てたことは、自分にとって本当にありがたいことだと思う。
“自由”と“責任”を学べる
大学生活を通じて、私は「自由」と「責任」という二つの大切な概念を身をもって学ぶことができました。
高校までは、授業時間や宿題、試験のスケジュールが厳格に決められており、ある意味で「自由」よりも「指示」に従うことが求められていました。しかし、大学に入ってからは自分で時間割を組み、授業を選び、課題に取り組むスタイルに変わります。この環境の変化は、一見すると自由が増えたように見えまるが、実はその自由の裏には大きな責任が伴っていることに気がつきました。
単位取得・スケジュール管理
大学では、授業をサボると単位が取れず、自分の成績に直結します。誰かが強制してくれるわけではなく、結果はすべて自分に返ってきます。最初のうちは「基準に満たなければ落単!」という重めの責任にプレッシャーを感じることもありましたが、逆に言えば「自分で決められる自由」があるからこそ、その責任を受け止められるようになったのだと思います。自由は無制限なのではなく、自分の選択に伴う結果を自分で引き受ける覚悟が必要だと理解しました。
また、タスクやスケジュールの管理能力もこの経験の中で磨かれました。授業の課題、アルバイト、サークル活動、友人との時間など、多様な予定が重なることも多いです。これらをただこなすだけではなく、優先順位をつけて計画的に進めなければならないため、スマホのスケジュールアプリを活用したり、手帳に書き出して見える化したりしながら、自分の時間を効率よく管理する方法を試行錯誤してきました。時に体調を崩したりと失敗もありましたが、その過程で計画を立てる力、時間を意識する力が少しずつ身についてきた気がします。
社会人になる前の準備?
さらに、この「自由」と「責任」の経験は、社会に出る前の大切な準備になっていると感じています。社会に出れば、仕事も人間関係も自分で選ぶことはできない部分もありますが、基本的には自分で問題を解決し、結果に責任を持つことが求められていくんだと思います。大学で学んだ自律的な行動や自己管理の力は、まさに「自分で生きていく力」の基盤になっていると実感しています。
もちろん、自由に失敗することも許される大学生活だからこそ、この学びが深まった面も大きいです。もし社会人になってすぐに同じミスをしていたら、大きな問題になっていたかもしれない。なんてこともあります。ですが、大学の環境はそうした失敗を経験し、反省し、次に活かす安全な場所でした。だからこそ、私は大学生活の中で「自由と責任」をじっくりと身につけることができたのだと思います。
この自由と責任の両立は一生続くテーマだと思います。どんなに年齢を重ねても、自分の選択と行動に対して責任を持つことは欠かせません。その意識を持つための土台を、大学生活で築けたことは大きな財産だと思います。これからもそのバランスを意識しながら、成長し続けていきたいです。
まとめ
「大学に行く意味」は、人それぞれ違います。誰かが決めた正解があるわけでもありませんし、他人と比べて「こうあるべき」と自分を縛る必要もありません。大学での時間の過ごし方や学び方は本当に多様で、どんな選択をしてもそこには価値があります。
私自身、大学生活を振り返ると、決して順風満帆だったわけではありません。というか、現在進行形で迷うことや失敗も多く、時には自分の選択に自信が持てない時も少なくありません。それでも、そんな時間も含めて、この数年間は“自分を育ててくれた”と強く感じています。
大学は単に勉強をする場ではなく、自分の得意や不得意、好き嫌いを知り、自分のあり方を模索できる貴重な場所です。色々な経験を通じて、自分の強みや弱みを理解できるようになり、将来社会に出るときに自信を持って歩める土台を築くことができました。
もし高校時代の自分に声をかけられるなら、こう伝えたいです。「迷ってもいいから、一歩踏み出してみて」と。失敗や戸惑いを恐れて立ち止まるよりも、小さな挑戦を重ねることで自分の道が見えてくるはずだからです。大学生活は長いようであっという間です。だからこそ、自分のペースで、自分の興味や関心に正直に取り組んでほしいと思います。
そして、今まさに進路や大学生活に迷っている人へ。
「迷い」は決して悪いことではありません。むしろ、それは自分を見つめ直す大切なサインかもしれません。焦らずに、自分の気持ちと向き合いながら、少しずつ前に進んでいってほしい。私の経験が、その背中を押す小さな力になれたら、とても嬉しいです。
大学は「答え」を教えてくれる場所ではなく、「自分で答えを見つける」場所です。誰もが同じ答えを持っているわけではなく、それぞれの道を歩むことが尊重されます。だからこそ、あなた自身のペースで、自分にとっての「意味」を見つけていってください。
この文章を読んでいるあなたも、きっと色々な思いを抱えながら毎日を過ごしていると思います。でも、大学生活は一人ひとりの成長のステージです。どんな経験も無駄ではなく、未来のあなたを形作る大切なピースになるはずです。だから、自分のペースを大切にしながら、一歩ずつ進んでいきましょう。