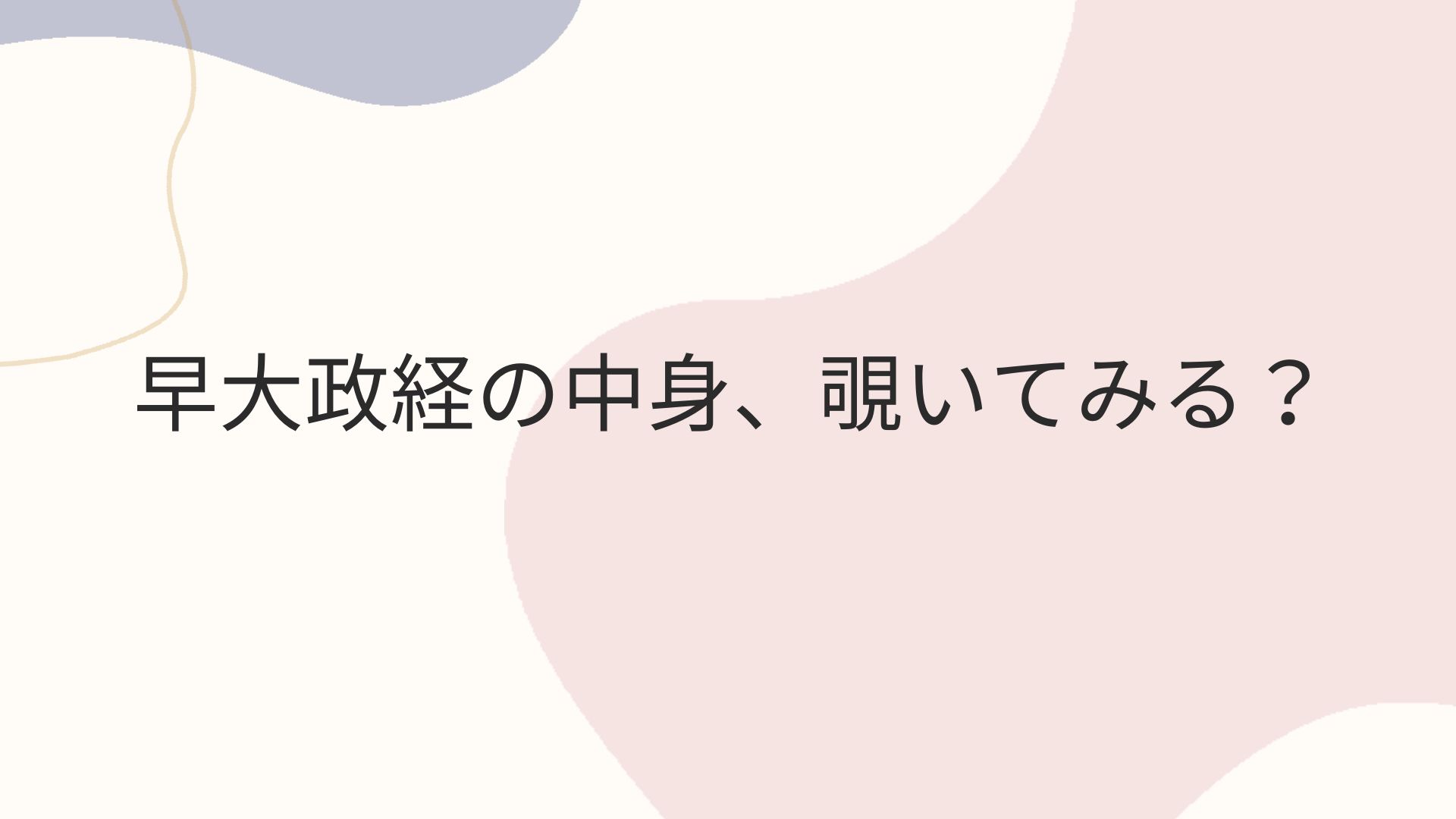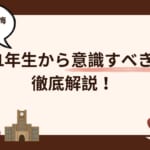僕が早稲田大学政治経済学部に進学してから感じた“意外な一面”について、赤裸々に綴ってみます。
進学前は「政経ってエリートの巣窟なんでしょ?」「ガチガチの勉強漬け?」「意識高い系が多そう……」など、さまざまなイメージを抱いていました。
でも、実際に足を踏み入れてみると、いい意味でも悪い意味でも、そのイメージはガラガラと崩れていったのです。
講義スタイルの違いに驚き!
最初に驚いたのが、講義のスタイルそのもの
。高校までは「先生が黒板に板書→生徒が写す→試験で再現する」というスタイルが基本だったのですが、政経の講義はまったく違いました。

多くの授業がパワーポイントと講義音声中心で進み、板書はほとんどありません。さらに、教授の話す内容が非常に抽象的かつ理論的で「なんとなく聞いてるだけ」では全く理解が追いつかない。
特に1年生の春学期に受けた「ミクロ経済学」や「政治理論入門」は、自分の思考回路をフル稼働させないとついていけない内容でした。
また、早稲田ではオンデマンド型の講義も多く、自分の好きなタイミングで視聴できるという自由さがあります。これは本当にありがたくて、サークルやバイト、他の予定との調整がしやすく、自分のペースで学習を進められます。
しかし、その自由さがゆえに「あとで観よう」と思っていたら出席期限を過ぎてしまっていた、なんてことも……。これは僕自身も何度か経験があり、しっかり自己管理が求められるポイントです。
自由であるがゆえに、自分に甘くなるとそのツケが回ってくるというのは、オンデマンド授業ならではの難しさでした。
一方通行の講義だけでなく、学生同士でディスカッションを行う形式の授業も少なくありません。グループワークやプレゼンも多く、”聞くだけ”では成績に繋がらないのが政経のリアル。
これは高校までの受け身な授業とは大きな違いで、最初は戸惑いましたが、慣れると「考える力」がついていくのが実感できました。
講義スタイルの多様性に対応する柔軟性と、自分で学びをデザインする力が求められる——それが政経の講義の一番の特徴だと思います。
周囲の学生は意外と意識高くない!
政経に入る前は、「周りは全員めちゃくちゃ優秀なんだろうな……」「討論バチバチな毎日かも」と少しビビっていました。でも、実際にクラスメイトと接してみると、そんなことはありませんでした。

授業の出席率に関しても、興味深い現象がありました。どの授業も最初はほぼ満席でスタートするのですが、回を追うごとに出席率がじわじわと減っていくことも少なくありません。
特に出席点がつかない授業やオンデマンドでの視聴が可能な講義では「今日はいいか」と思ってしまう人が多くなる傾向にあります。
実を言うと、僕自身も出席点がない講義では何回か欠席してしまったことがありました。自由な環境だからこそ、自分で自分を律することが求められるのが政経の授業スタイルなんだと思います。
もちろん、すごく優秀で視野の広い学生もたくさんいますが、それと同時に「普通にゆるく大学生活を楽しみたい人」や「授業よりサークルやバイトがメイン」という人も多いです。良い意味で、政経は多様性のある空間だと感じました。
授業中に寝てる人もいれば、1限に遅刻常習の人もいるし、単位ギリギリで卒業を目指してる人もいる(笑)。もちろん、学業に真剣に取り組む人が大半ですが、「意識高い系」ばかりではないというのが、入ってみて一番ホッとした部分でした。
この多様性こそが、早稲田政経の魅力なのかもしれません。自分らしくいられる場所であり、他人と違っていても許される空気感があります。
想像以上に自由な学び
政経に入って強く感じたのは、学びの自由度の高さです。カリキュラムにはある程度の必修科目はありますが、それ以外は選択肢が非常に広く、自分の関心に沿ってカスタマイズできるのが特徴です。
同じ政治経済学部でも、ある人は「政治理論」や「公共政策」を中心に履修していて、別の人は「開発経済学」や「データ分析」に夢中だったりします。経済学の中でもミクロ派・マクロ派がいたり、政治系では法哲学にどっぷり浸かる人も。
こうした多様な学びが可能なのは、政経が“政治学部”でも“経済学部”でもなく、「政治経済学部」であるからこそ。学際的な学びを軸に、自分の興味に合った知識を自由に探求できる環境が整っています。
また、必修以外の授業では、他学部からの履修も可能で、僕も教育学部の心理学の授業を取っていたことがあります。
早稲田全体の幅広い学問資源をフルに活かせるのも、政経の強みの一つです。
文系なのに数学!?経済学の現実…
これは完全に盲点でした(笑)。
「文系だし、もう数学とは無縁だろう」と油断していた高校生の僕に教えてあげたい。政経、とくに経済学系の科目はがっつり数学を使います。
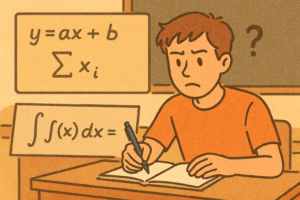
たとえば、ミクロ経済学では需要・供給曲線を使った最適化問題、マクロ経済学ではGDPやIS-LMモデルなどの方程式。
統計学や計量経済学になると、ExcelやRなどのソフトを使ってのデータ分析まで登場します。
特に1年次に履修する「ミクロ経済学」は、多くの学生が苦戦する鬼門の科目。
数列、微分、関数など、高校数学の延長線上にある内容ですが、説明のスピードが速く、途中で置いていかれる人も多数です。
「数学が苦手なんだけど経済学に興味がある…」という人は、ある程度覚悟しておいた方がいいかもしれません。ただ、反対に理系的な思考が得意な人にとっては、非常に面白い分野でもあります。
実際、僕も最初は抵抗感がありましたが、慣れてくると「論理で社会を読み解く面白さ」に目覚めていきました。
政経は、想像以上に“自由でリアル”な場所だった
政経に入って驚いたこと・ギャップを振り返ると、最初に抱いていたイメージと、実際の中身にはかなりの違いがありました。でも、それが逆に良かったと思っています。
自分のペースで学びたい人も、がっつり学問を深めたい人も、どちらも受け入れてくれるのが政経の懐の深さ。そして、自由だからこそ、自分で考えて動かないと成果が出ないという厳しさもあります。
そういうリアルな環境の中で、僕自身も少しずつ「自分が何をしたいのか」「どう学びたいのか」が見えてくるようになりました。
政経は、そんな“思考の旅”を後押ししてくれる場所なのかもしれません。