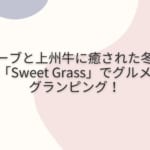こんにちは!立教大学経営学部国際経営学科2年生のだにえるです。
立教大学は「留学」や「国際交流」に力を入れていることで有名な大学。
実際、それを目当てに入学した現役立教生も少なくないはず。私自身もそうです。
私は今年の秋学期から2学期間、経営学部の学部間留学プログラムでドイツに行ってきます。
今は数か月後の渡航に向けて準備に忙しくしているのですが、手続きやお金の用意など、既に予想外のことが多くて大パニック!家族を巻き込み、友達を巻き込み大変な日々を過ごしています(周りの人がかわいそう)
そこで、今回は「長期留学が気になっている立教生」向けに、私が経験してきた出願スケジュールや、お金の準備のこと、事前にやっておいた方がいいこと、覚悟しておくことなどをざっくりと紹介してみようと思います。
※あくまで個人の経験や知見に基づく記事なのと、年によって色々変わってきそうなところではあるので、ちゃんと私の記事のファクトチェックはご自身で行ってください。責任は一切取れません。
※立教大学が公式で出している情報ではありません。
「留学っていつから準備を始めればいいの?」「何が必要なの?」「面接ってあるの?」など、初めて挑戦する人にとっては分からないことだらけなみなさんは必見です。
準備は「気になるなあ」と思い始めたその時から始めてください。
目次
学部間留学と大学間留学制度の違い

立教大学には、「学部間留学」と「大学間留学」という2つの主要な留学制度があります。どちらも正規のプログラムとして提供されており、在学中に海外留学を目指す学生にとっては重要な選択肢です。
一見似た名前ですが、この2つには制度そのものの設計や、求められる目的意識に違いがあります。
まず、学部間留学は「学びたい専門分野を海外で深める」ことを前提とした制度です。対象となるのは、自分が所属する学部の専門分野に関連する授業で、その分野の知識をグローバルな視点から学び直すようなイメージです。英語や現地語で専門知識を学ぶことが求められるため、語学力だけでなく、学問への関心や目的意識が重視される傾向があります。
一方、大学間留学は「国際経験」や「語学力の向上」など、より幅広い動機を受け入れている制度です。学部を問わず応募できるので、「とにかく海外に出てみたい」「異文化の中で自分を試してみたい」という学生にも門戸が開かれています。語学力や学業成績も選考の対象にはなりますが、「国際的な視野を持って主体的に行動したいか」という熱意や行動力が重要視される点が特徴です。
つまり、どちらが「優れている」というよりも、留学で何を得たいのか、どんな時間の使い方をしたいのかによって、適した制度は変わってきます。例えば、「将来海外の大学院に進学したい」「英語で専門を学ぶ経験が欲しい」という人には学部間留学が向いていますし、「新しい環境で視野を広げたい」「語学力を伸ばして国際的な仕事に活かしたい」という人は大学間留学のほうが自由度も高くフィットするかもしれません。
言語や学ぶ内容の違い
留学制度を選ぶうえで、まず注目したいのが「授業の言語」と「学べる内容」の違いです。この点は、学部間留学と大学間留学の大きな分かれ道と言っても過言ではありません。
学部間留学の場合、授業は基本的に英語で行われることが多く、自分の学部や学科の専門をより深く学ぶことが前提になります。つまり、英語を使って「今自分が大学で学んでいる分野をさらにレベルアップさせる」のが主な目的。例えば経営学部の学生であれば、提携先の海外のビジネススクールでマーケティングやマネジメントの授業を受けるといったケースが多いです。国際的な専門知識を英語で身につけたい人、将来的に英語で仕事をしたい人にとっては、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。
一方で大学間留学では、授業の言語はその国の現地語であることが多く、英語だけでなくドイツ語、フランス語、スペイン語など、多様な言語環境の中で学ぶことになります。そのため、大学間留学には語学力に対する柔軟な対応力が求められる場面も多いです。また、大学間留学では「この分野を専門に学ばなければならない」という制限が比較的少なく、幅広い分野の授業を履修できるという自由度の高さが特徴です。語学だけでなく、興味のある多様な分野を少しずつ試してみたい、専攻外の視野も広げたいという人には、非常に合っているプログラムと言えるでしょう。
このように、同じ「留学」でも、学部間留学と大学間留学では学び方も求められるスキルも全く異なるのです。「英語で専門を学びたい」のか、「現地の言語を使って広い分野を経験したい」のか、自分の目的に合った制度をしっかり選ぶことが、留学を成功させるカギになります。
単位兌換制度
留学を考える際、気になる人も多いのが「留学したら卒業が遅れるのでは・・・?」という点ではないでしょうか。
確かに、海外での学びは魅力的ですが、日本の大学での卒業に必要な単位とどれだけ結びつくのかは、しっかり確認しておく必要があります。特に立教大学では、留学の種類によって単位認定の扱いが大きく異なるため、事前にしっかり情報を集め、計画的に進めることが大切です。
まず、「学部間留学」と呼ばれる制度では、留学先で履修した授業が、卒業に必要な単位として認定されやすい傾向があります。これは、立教大学と提携する各学部の海外大学がカリキュラムをある程度調整しており、「単位互換制度」が比較的整っているからです。そのため、しっかりと履修計画を立てれば、留学しても4年での卒業が十分可能です。ただし、履修する科目の内容や評価方法によっては、認定されないケースもあるため、事前に留学センターや所属学部とよく相談しておくと安心です。
一方で、「大学間留学」は少し様子が異なります。大学間留学は、より自由度が高く、選べる国や大学の幅も広いのが魅力ですが、その分、留学先で取得した単位が日本の卒業単位として認定されにくいという側面があります。そのため、卒業を1年遅らせるか、休学扱いにして留学する人が多いのが現状です。
学部間の方は、留学先で学んだ自分の専攻の授業が、自分の所属している立教大学の学部の選考の授業の単位に兌換され、卒業要件単位に含んでもらえるけど、大学間の方はその辺の兌換制度がないから、帰ってきてから卒業要件単位分の単位を日本でとらないと卒業できないよーってことです。
どちらの制度が「正解」かは、人によって異なります。将来のキャリアプランや、大学卒業までのスケジュール感、自分の性格や目的と照らし合わせて、無理のない留学スタイルを選ぶことが大切です。「どうしても4年で卒業したい」という人は、早めに単位計画を立てること、「大学在学中に海外経験をしたい」という人は、休学も含めて柔軟に考えると、より納得のいく選択ができると思います。
提携校の数、選択肢の幅

先ほども少し触れましたが、立教大学の留学制度には「学部間留学」と「大学間留学」の2種類があり、それぞれに違った特徴と魅力があります。なかでも注目したいのが、「提携校の数」と「選べる国や地域の幅」の違いです。自分の希望する国・地域や学びたい内容がある程度決まっている人にとっては、この点が留学先を決めるうえで非常に大事なポイントになります。
まず、学部間留学は、それぞれの学部が独自に提携している大学との間で実施される制度です。そのため、当然ながら提携している大学の数には学部ごとに差があります。例えば、異文化コミュニケーション学部や文学部、経営学部、観光学部などは、比較的多くの大学と提携している印象があります。実際に募集要項を見ても、行ける国や大学の選択肢が多く、専門分野を英語で学ぶ機会が充実しています。
一方で、社会学部や法学部などは、学部間提携校が少なめで、「自分の学部にはあまり選択肢がない」という声も聞きます。このように、学部によって留学先の幅に差があるというのは、学部間留学のデメリットの一つかもしれません。
そこで選択肢に入ってくるのが、大学間留学です。大学間留学は、全学部を対象にした制度で、学部に関係なく応募できるのが大きなメリット。しかも、提携校の数も非常に多く、アジア、ヨーロッパ、北米、オセアニアなど、国や地域のバリエーションも豊富です。「とにかく海外で学びたい」「多様な国から選びたい」という人には、まさにうってつけの制度です。
ただし、大学間留学では専門科目の単位互換が難しいこともあるため、自分の専門分野やストレート卒業等よりも語学力向上や異文化体験を重視したい人に向いている傾向があります。逆に、専門分野を海外で深めたい人には、やはり学部間留学のほうが適しているかもしれません。
ざっくりとまとめると、「英語で専門科目を学びたい人には学部間留学、語学や幅広い体験を求める人には大学間留学」がおすすめです。それぞれの制度に魅力があるからこそ、自分の留学の目的を明確にして、どちらが自分に合っているかをじっくり比較・検討してみてくださいね。
| 項目 | 学部間留学 | 大学間留学 |
|---|---|---|
| 授業言語 | 英語が中心 | 現地語が中心(英語の場合もあり) |
| 学ぶ内容 | 自分の学部・学科の専門分野 | 専門外の分野も履修可能 |
| 目的の傾向 | 専門知識の深化・国際的な学術経験 | 語学力の向上・異文化体験 |
| 単位互換 | あり(卒業単位に含められる授業が多い) | 一部あり/基本的に卒業単位に含まれないことも多い |
| 卒業までの年数 | 基本的に4年で卒業可能 | 休学扱いで5年在学するケースもあり |
| 提携校数 | 学部・学科によって差が大きい | 全学部共通で提携校が豊富 |
| 選べる国・地域 | 限定的(学部ごとの提携先) | より幅広い選択肢から選べる |
| 参加対象 | 各学部の学生(学部ごとの条件あり) | 全学部の学生対象 |
| イメージ | 専門+英語で学ぶ“実学型”留学 | 語学&自由度高めな“探究型”留学 |
留学までに準備すること・基準
とりあえず留学にはいきたい!と思ったものの、何から準備していいのか、どこにいつ何をしに行けばいいのかなど、わからないことまみれだと思います。
とりあえず、まず留学に少しでも興味を持った人が、今からしておくべき準備をご紹介します。
GPAをキープする
留学の出願を考えるうえで、まず第一に必要となるのがGPA=大学での成績の平均点です。立教大学では、ほとんどの留学プログラムにおいてGPA2.5以上が出願の最低条件とされています。
「2.5?そんなに高くないじゃん」と思った方、ちょっと注意が必要です。GPA2.5は確かに飛び抜けて高い数字ではありませんが、気を抜いて授業を受けていたり、出席や課題をサボっていると、あっという間に下回ってしまうラインでもあります。特に1年生のうちは履修ミスや、大学の授業スタイルに慣れないことで成績が安定しづらい時期なので、油断は禁物です。
ちなみに私は、出願時に提出したGPAが「2.58」でした。
ギリギリセーフ・・・!
何回も成績を見直しては、「これ落としてたら終わってたな・・・」と冷や汗をかきました(笑)。「留学行くんだよね」とよく話をしていて、おまけで高めの成績をつけてくれた先生のおかげでなんとか生き残りました。
この数字を見てわかる通り、「ちょっと頑張れば大丈夫でしょ」と思っていたら危ないんです。2.5は“最低ライン”であり、そこをギリギリで通過しても、倍率の高い学校・国だと書類選考で不利になることもあります。実際私も、より成績やIELTSが高い友達に第一志望だった大学をとられています。彼の努力の結果ですから、仕方ないですね。
特に、人気の高い国や大学(アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど)を希望している場合、GPA3.0以上をキープしておくのが安全圏だと思います。選考基準には語学スコアやエッセイも含まれますが、やはり成績も総合的に評価される要素のひとつ。普段の授業の積み重ねが、確実に留学のチャンスを広げてくれるのです。
だからこそ、1・2年生のうちからGPAを意識しておくことがとても大事です。
留学は成績だけで決まるものではありませんが、「出願資格を満たすため」そして「志望先を広げるため」にも、日頃からGPAを意識しておくことは超重要。留学を目指すなら、授業にも手を抜かず、計画的にがんばっていきましょう!
語学スコア(IELTS、TOEFL)を取る
語学力も重要な要素です。留学先の授業についていくためには、当然ですが一定の英語力が求められます。
- 大学間留学の場合:IELTS オーバーオール5.5以上、TOEFL
- 学部間留学の場合:IELTS オーバーオール6.0以上、TOEFL
このスコアが出願条件として設定されています。ちなみにTOEICではなく、TOEFLたIELTSが基準なので、早めに対策して受験しておくのがおすすめです。
IELTSはリスニング・リーディング・ライティング・スピーキングの4技能が評価されるため、偏りなく英語を伸ばす必要があります。
IELTS6.0のレベルはだいたい英検準1級と同じくらい。でも個人的には英検よりは取りやすく感じました。
前もってちゃんと対策すれば、立教生なら全然合格できるスコアなので、ちゃんと対策をしておきましょう。
出願のタイミングとスケジュールを把握する
立教大学の長期留学の留学出願は、年に1~2回のチャンスしかありません(短期留学や学部ごとのプログラムは他にもあるかも)。そして、ほとんどのプログラムで「事前説明会への参加が必須」とされています。出願資格としてカウントされるので、これに参加しないとスタートラインに立てません。
説明会の日程は、大学のメールやポータルサイトで案内されることが多いので、こまめにチェックして見逃さないようにすることがとても大切です。メールは埋もれてしまいやすいですが、「留学センター」や「Study Abroad」というキーワードが出てきたら、必ず目を通すようにしましょう。
また、出願には、意外と多くの書類が必要です。
たとえば、
・英語など語学力を証明するスコア(TOEFLやIELTSなど)
・エッセイ(志望動機)
・成績証明書
などが必要になります。学内の選考が済んだら、派遣先の大学に英語で履歴書や志望理由書を書いて改めて出願する必要があります。
語学スコアは受験から結果が出るまでに数週間かかることもあるため、直前の準備では間に合わない可能性も。だからこそ、早めにスケジュールを把握しておくことが成功のカギになります。
理想的には、1年生や2年生のうちから説明会に参加し、「いつ・何が必要か」をつかんでおくこと。たとえその時点で留学するか決まっていなくても、準備の流れや締切を知っておくことで、いざ行きたくなったときにすぐ動けるようになります。
お金を計画的にためておく
これ、本当に大事です!
正直に言うと、私は今けっこうお金の準備の面で苦労しています。
というのも、「留学にお金がかかる」こと自体は知っていても、いつ・何に・どれくらい必要なのかをしっかり把握していなかったからです。
私の場合はドイツに11か月間留学するのですが、ビザを取る際に「閉鎖口座」という形式で、160万円以上の残高証明を出さなければいけないと知って、かなり焦りました。
幸い、日本人はドイツにビザなしで90日間滞在できるため、資金準備や手続きの猶予が少しありましたが、国によっては渡航前にビザ取得が必須な場合もあります。そうなると、かなり早い段階でまとまったお金が必要です。
他の国に留学に行く人や、過去留学した人の話を聞いていると、ビザの取得に1か月以上かかったり、渡航に間に合わなかったりといったケースもあるらしく、みんなかなり苦労しています。
また、残高証明だけでなく、私の場合は
・航空券代(10〜20万円)
・大学の学期登録料(約2万円)
・保険料(日本とドイツの2つに加入する必要があるので2〜30万円)
などを払う必要があり、出発前に払うお金がとにかく多いんです。特に航空券は夏休みと被る時期に買うとかなり高くなるので、早めの購入が吉=早めにお金が必要ということ。
私自身は、現地でも既にやっているオンラインバイトで月5万円ほど稼ぐ予定なのですが、それでも「今」必要なお金は別で用意しなければいけません。
つまり、「向こうでなんとかする」では遅くて、渡航前から計画的に準備を始めることがとても重要です。
これでも、ドイツは比較的安く済む国です。それを見越して私はドイツを選んだところもあります。
また、私の場合奇跡的に留学先の大学で給付型の奨学金を少しもらえることになったので、少しは負担が減っています。ドイツ大好き。Dankeございます。
留学を考えている人は、できるだけ早い段階で「どのタイミングでどれだけお金が必要か」を調べておくことを強くおすすめします。そして、アルバイトや家族との相談などを含めて、しっかり準備しておきましょう。お金のことが原因でチャンスを逃すのは、もったいないですよ!
実際の私の留学準備スケジュール(経験談)

1年春学期
大学デビューに失敗し、漠然と海外逃亡を夢に見始める。バイトの失敗、大学のあらゆるコミュニティでの疎外感などを感じ、自分は日本の組織文化に向いていないのでは?などと思想を拗らせ、労働文化や組織文化が全然違うヨーロッパの国にあこがれを持ち始める。
とはいえ、両親からの資金援助は一切受けられないため、留学生向けの経済的支援が発展しているドイツ留学に絞って、留学を考え始める。留学センターから大学間や学部間の冊子をもらってきて、眺めてはドイツ人イケメン彼氏とビールをたしなむ妄想を繰り広げる。
大学のメールで案内が来た学部間留学のオンライン説明会に参加。zoomを開くと、独特な紫の背景に白髪という、平沢進のような担当の先生がスマホの画面いっぱいに広がり、元々あった留学への不安が増大する。
そして、大まかな出願スケジュールを知り、12月までにIELTS6.0を取得することを目標に勉強を始める。
1年夏
IIELTSの単語帳を買い、6.0レベルまでの単語を見るも、見たことがない単語が多くてびびる。対してちゃんと勉強することもなく、旅行に行ったり、人生に絶望したり、孤独とそれを紛らわすための読書で思想を拗らせ、どうしようもない夏休みを終える。
特に留学準備はしてないと思う。
1年秋学期
さすがにIELTSの勉強をガチで始めた
さすがにIELTSの勉強を始めた。過去問を買い、友達に教則本?みたいなものをもらい、解き始める。暇な土日はアメリカの大学に進学する予定の友達(高校留学に行っていたので、同級生だけど留年して高3をしていた)と一緒に勉強をするように。
ここで気づいた。やっぱり経験者から解き方や流れについては教わるのが一番早い。彼女に色々な情報をもらえたのが今回スコアをとる上で大きかったと思う。
あと、当時付き合っていた彼氏も留学に向けてIELTSを勉強していたから、一緒に情報交換したり、勉強したりしていた。
テストを受ける直前に、入学時点でIELTS6.5を取得しえていた友達からIELTSのスピーキング・ライティング専用の参考書を借り、全力でモデル回答を暗記しまくった。
試験2週間前からは毎日5から8時間ほどIELTSの勉強をし、受験生顔負けの日々を過ごした。留学反対派の両親に「お金は出さないでいいから絶対留学行かせて!」と強気で説得したり、「来年も同じような味気ない大学生活をすごしたくない!」みたいな気持ちが勉強のモチベーションを後押ししてくれたんだと思う。
最終的に12月の24日に試験を受け(もう少し早く受ければ無駄な一発勝負のプレッシャーを感じなくて済んだと思う。)、私至上最高に無機質なクリスマスイブを過ごした。結果は6.0。ぎりぎりだがなんとか出願要件を満たすスコアをとれてよかった。
この一見は、イブエルツ事件として私の周りで語り継いでいる。
留学出願
実際の交換留学の出願は1月初旬だった。
成績の証明書や志望大学と志望理由、IELTSのスコア証明書などを提出する。(学部によってもしかしたら少し違うかも。そして、大学間は10月とかに選考があった気がするのでより早めに準備しておこう)
面接はzoomで、相手は説明会の時と同じく平沢進(に似ている先生)ともう一人の先生だった。英語の面接で、志望理由についてや、成績の低さについてを詰められた笑 その数日後(1月末)には派遣先が決定し、メールで送られてくる。
私が出願したときは、提携校のポストの方が出願者よりも多かったため、よっぽど国や学校等にこだわりがない限りは全員が留学に行けるようだった。
私は第一志望、第二志望の大学共に落ちたが、なぜかスコア6.5必要なドイツの大学に派遣されることに決まり、そこにこの秋学期から留学する。
たまたまbaddyプログラムで仲良くなったドイツ人の母校だったため、色々な情報を聞いたり、現地で手伝ってもらえる(っていってた)みたいなのでむしろラッキーかも。知り合いがいるというのは心強い。
奨学金出願
11月から12月にかけては「トビタテ!留学JAPAN」の奨学金の選考に向け、めちゃめちゃ重めな志望理由書作りや、書類準備(済んでいる地域の役所に行ってわざわざ親の収入を証明する書類を用意しなければならない)で大忙し。
大学教員の推薦書も必要だったため、そのお願いや先生とのコミュニケーションも綿密にとる必要があった。
そして奨学金は大落下!選考で落とされた!(2月か3月に通知が来た)
どうしても両親からの資金援助が得られないかぎり、奨学金をなんとかしてもらわないといけない。11月から1月までは奨学金・IELTS・成績のプレッシャーでメンタルのコンディションはどん底を這いずり回っていた。
1年春休み
もうね、普通に遊びほうけていたのでほぼ準備はしていません。
ドイツの大学から奇跡的に奨学金をもらえるという推薦をいただいたので、それの手続きをしたり、足りないIELTSのスコアをなんとかするために先生に推薦書を書いてもらったり、あとは普通にドイツの大学とのやり取りをしていました。
普通に準備してたわ。嘘ついたわ。
この時は数か月後、本来もらえるはずだった給付型の奨学金が、突然半額になってしまうなんてことは夢にも思っていなかったから、貯金などまともにせず国内外あらゆる旅行を楽しんだ。
そうして私は地獄を見ることになる。
2年春学期
本格的な留学準備が始まった。
具体的には、
・留学に向けてとらなければならない授業をとる
・なるべくマックスで単位をとれるように授業をとりまくる(留学後どたばたしないため)
・奨学金準備
・寮やビザ等の手続き
などだ。
授業
学部間留学なので、経営学部以外の学部や大学間とは異なる可能性があるが、経営学部の場合、
・経営戦略系の授業で英語の開講科目をとる
・マネジメント系の授業で英語の開講科目をとる
・Financial Accountingをとる
・それ以外の英語開講科目を1つとる
といった指定がある。留学先で授業をとる際に、「既に各分野の基礎を学んだ前提」で話が進む場合が多いため、とる必要があるんだとか。
それ以外にも、「Global Study Pre-deperture」というオンラインで春学期の半期のみ(7回しか授業がない)の授業が自動登録で登録される。
意外な収穫としては、私自身あんまりファイナンスやアカウンティング系の科目に興味がないため、自由選択だったなら取らなかったであろう授業が、意外とやってみたら面白いかったなんてことを発見できた。
ビザや奨学金、寮の手続き
各派遣大学から定期的にメールが来て、それに合わせて動いていく。
ドイツはありがたいことに、日本人は入国後のビザ申請ができ、向こうの大学で手伝ってもらえるみたいなのでビザの心配は一旦大丈夫そう。
問題は寮と奨学金の手続きだ。
寮はとにかく早く申し込んだ方がいい。すぐに埋まってしまうし、この競争に負けたら条件の悪いシェアハウスや、とにかく家賃の高いアパート等に入居しなければならなくなるからだ。私は案内が来てからすぐ申し込んだのだが、申し込み確認のメールを見逃したため1からやり直し(毎日確認してたのに!)。今はwaiting listに載っているそうなのだが、とれなかったらどうしよう!ひやひやしている。
また、本来2学期分もらえるはずだったドイツの奨学金が、1学期分しかもらえないことが判明した。即座に確認のメールを送ったが、「なるべく多くの人に奨学金を渡したいので・・・」とか言われてしまい、ここでまたお金の用意のプレッシャーが発生する。
ビザの申請には留学期間分の生活費が証明できる残高証明が必要。いわゆる見せ金。これはどこの国も割と同じみたいなのだが、私の場合、貯金もない、家族からの支援もない、お金がなかったらここまで来て留学にいけない!ということでもう大パニック。40万円分の本来もらえるはずだったお金をプラスで用意しなければならない。
それが判明した6月には、もう多くの奨学金応募が締め切られていたため、奨学金に頼ることもできない。
散々悩んで、バイトしまくって、プレッシャーで高熱を出して寝込んでいたタイミングで、親戚が一部お金を貸してくれることになったため、なんとかこの問題はぎりぎりで解決できたが、本当に危なかった。
こんなこともあるので、とにかく留学が気になっているみんなは早め・多めの貯金計画をたてておくんだよ!!!
そうして、この記事執筆をしている現在に至るわけです。
これから夏休みが始まるけど、とにかく貯金!労働!(でも10代最後の夏休み、遊びも楽しむよ)の毎日になります。
まとめ
留学が気になる人は全員いますぐ留学センターに行くなり、お金を貯めるなり、IELTSの勉強を始めるなり行動を始めましょう!
私のように土壇場で動くと結構きついよ!!!!!
少しでもこの記事が参考になれば幸いです。