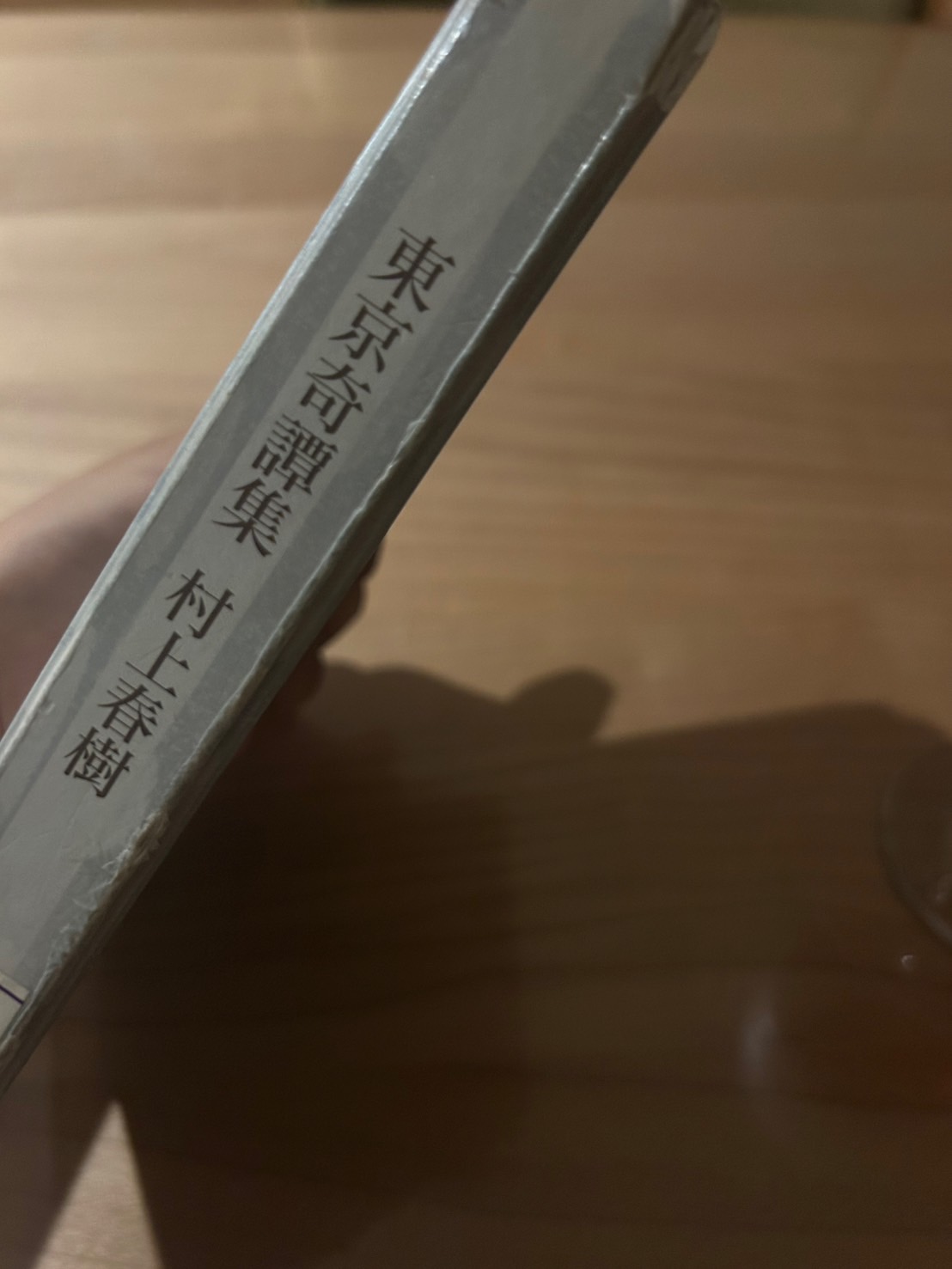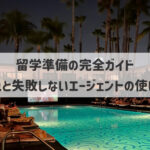そろそろ学生のみなさんは夏休みに入る頃だと思います。中高生は部活や塾、学校の課題などで忙しい日々を送っているかもしれません。
でも、大学生の夏休みは少し違います。
講義のない長期休み、バイト以外の予定が特にない日もあったりして、時間だけはやたらとある。そんなとき、ふとこんなことを思ったりしませんか?
「今のところ、バイトしか予定がないな」
「前半は楽しいけど、後半ってちょっと退屈になるんだよね」
「映画も観たし、旅行も行ったし、そろそろやることがないかも」
そんなふうに、時間はあるのに何をしたらいいかわからない——これって実は、ものすごく贅沢で、同時にちょっと切ない感覚でもあります。
だからこそ、ひとつ提案したいのが「読書」です。
読書って、やっぱりコスパが良いです。図書館を使えばお金はかからないし、エアコンの効いた静かな場所で、ひとり静かに物語の世界に入っていける。スマホやSNSの通知に追われる毎日から、ふと距離を取って、じっくり自分と向き合う時間を持つには最適な方法だと思います。
ちなみに、筆者も今は留学の準備でとにかく節約中。旅行にもライブにもなかなか頻繁には行けません。でも、その代わりに図書館にこもって本を読む日々がけっこう幸せです。本を読むと、自分の頭の中にだけ広がる「もうひとつの世界」ができるんです。静かな興奮というか、小さな冒険ができるような感覚。なかなかいいものですよ。
とはいえ、「本って何を読めばいいかわからない」という人も多いと思います。最近はSNSでも動画でも「おすすめ本リスト」はたくさん出回っていますが、それでもいざ書店や図書館に行くと、何を選んでいいかわからなくなる。そんなときに思い出してほしい名前があります。
それが、村上春樹。
名前は知っているけど読んだことがない、あるいは『ノルウェイの森』のイメージしかない……という人もいるかもしれません。
でも、実は村上春樹の小説って、学生世代の感性にジャストフィットするものばかり。長年大学生から愛されています。どこか現実離れしているけれど、ちゃんとリアルで、読みやすいのに奥が深い。読み終わったあとに、少しだけ心が静かになって、自分のことを考えたくなるような物語。
今回は、そんな村上春樹の作品の中から、「学生におすすめしたい5冊」を厳選してご紹介します。長編から短編まで、どれも今のあなたにしっくりくるものばかりです。
この夏は、ほんの少しだけ「読む夏」にしてみませんか?
私が村上春樹が好きな理由
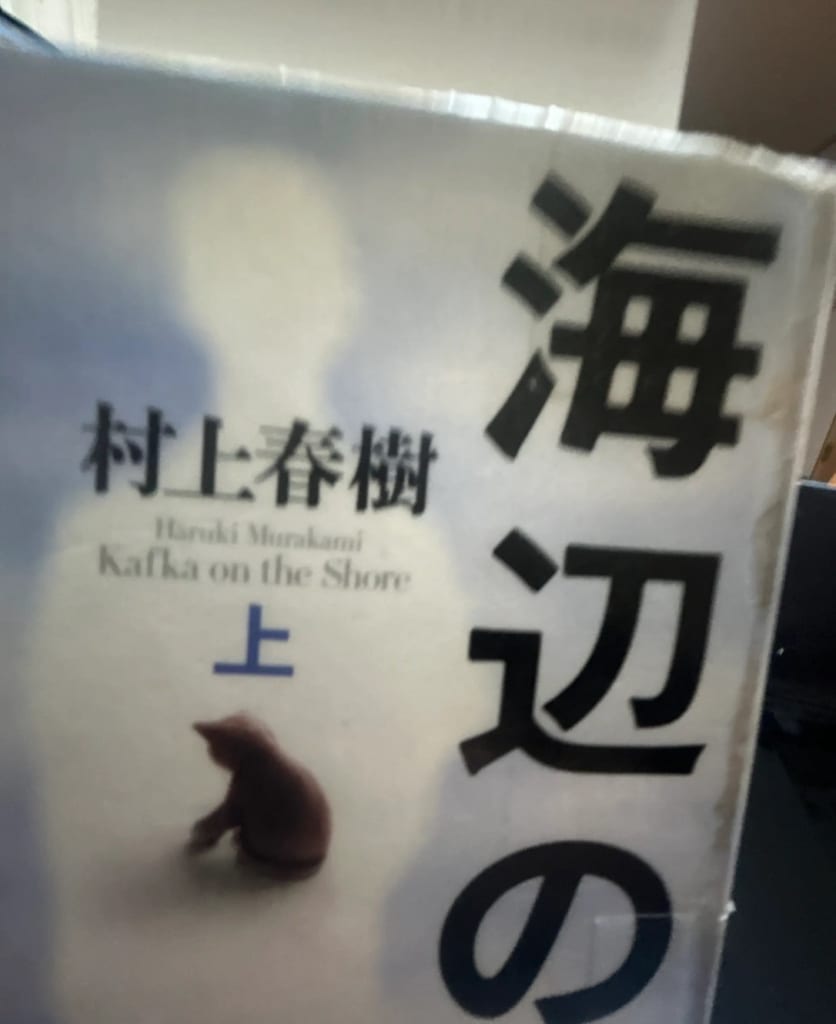
ちょうどよくロマンティックで、ちょうどよくリアル
村上春樹の小説には、「ちょうどいい不思議さ」があると思います。それは完全に空想の世界に入り込んでしまうのではなく、日常の中にそっと忍び込んでくるような不思議さ。
私はもともと、ファンタジーやSFのような、がっつりと異世界に入り込む物語が少し苦手です。というのも、設定が複雑だったり、現実との距離が遠すぎて、どうしても物語に夢中になりきれないんですよね。
でも、村上春樹の描く世界は、現実の延長にすっと現れるんです。幽霊が見えたり、見知らぬ猫と話ができたり。とはいえ、そんな描写は少しで、一人一人の登場人物のリアルな生きざまが描かれています。どの登場人物にも感情移入ができる。ロマンティックだけど、変にドラマチックじゃない。この塩梅が、本当に心地よく感じます。
人の動きの描写
彼の小説が好きなもうひとつの理由は、「人の動き」がとても丁寧に描かれているところです。たとえば、誰かがコーヒーを淹れる仕草、ドアを開ける瞬間、無言で窓の外を眺める時間。
そういったさりげない動きが、まるで自分の目の前で起きているかのように感じられます。まるで映画のワンシーンを見ているように、細かく、でも押しつけがましくなく描かれている。そのおかげで、登場人物たちがちゃんと「生きている人間」として感じられるんです。そこから登場人物たちの感情や性格を推測することもできます。
感情の描き方がリアル
感情の描き方もすごくリアルだと思います。表面的な喜怒哀楽ではなく、もっと曖昧で、説明しづらい感情をちゃんと描いてくれます。たとえば、「悲しいわけじゃないけど、胸の奥がぽっかり空いている」とか、「誰にも嫌われていないのに、どうしようもなく孤独を感じる」とか。
そういう気持ちって感じることはあっても、なかなか普段生活している中で言葉にしにくいし、表現できる語彙がなかったりでスルーしてしまいがち。
でも村上春樹の小説は、その曖昧な気持ちをすっと言葉にしてくれることがあるんです。それがすごくありがたいし、だからこそ読んでいて自分自身の感情にも素直になれるんです。
文章が読みやすい
あと、文章が読みやすいというのも大きなポイントです。語彙や表現がそこまでかたくないから、リズムよく読めます。会話のテンポも自然で、途中でつまずくことが少ない。人によっては「少し冗長だ」と感じることもあるみたいですが、私には合っています。じっくり読みたい人にとっては、ちょっと息切れしてしまう冗長さがシーンによってあるかもしれません。それでも、私にとっては、その少し回り道をしているような語り口がむしろ落ち着くし、味わい深く感じます。
村上春樹の小説は、読むたびに少しだけ自分の世界が広がるような気がします。現実と不思議のあいだにある、その絶妙な場所で、僕は何度でも彼の物語に出会いたくなる。
『風の歌を聴け』――村上文学の原点を辿る
作品紹介
この『風の歌を聴け』は、村上春樹のデビュー作。村上春樹の小説の中では短めの部類で、初めて読む人にも読みやすい一冊です。実際、私も初めて読んだ村上春樹の小説はこれです。
おすすめポイント
この小説のおすすめポイントとして、まず一番に挙げたいのは、主人公が大学生だということです。読んでいると、彼が過ごしている時間や悩んでいることが、今の自分とどこか重なって感じられます。将来のこと、人間関係の距離感、自分の存在の曖昧さ。はっきり言葉にできないけど確かに感じている「何か」に、そっと寄り添ってくれるような感覚があります。
小説としてのボリュームも比較的短めで、読むハードルが低いのも大きなポイントです。「村上春樹ってなんか難しそう…」と感じている人にとって、最初の一冊にちょうどいい存在です。断章形式なので、テンポよく読み進められ、途中で一旦区切るのも簡単。内容が重すぎず、文体も比較的やわらかいので、「なんか心に残る本を読みたいな」と思っている人にぴったりです。
どこかノスタルジックで、でも普遍的な青春の孤独とやさしさが詰まった一冊。大学生だけでなく、高校生にもおすすめできる、村上春樹の“原点”ともいえる作品です。
アフターダーク
作品紹介
『アフターダーク』は2004年に刊行された、村上春樹による比較的短めの長編小説です(村上春樹の小説はだいたい上巻、下巻の2冊で構成されるが、アフターダークは1冊で完結している)2006年には文庫化もされました。
村上はこの小説を通して、深夜の都会を「現実と非現実が交差する異界」として描き出しています。現実的な描写の中に、どこか夢のような静けさと緊張感が漂う一冊です。
おすすめポイント
私が一番好きな小説です。村上春樹以外の小説も含めて。夜の22時くらいに読み始めたのですが、止まらなくて朝方までかけて読み終えてしまいました笑
真夜中の東京という舞台
物語の舞台である「真夜中の東京」という設定も、都会に暮らす人も、地方に住んでいる人も、ちょっと憧れを感じるのではないでしょうか。夜のネオン、24時間営業の飲食店、終電が終わってもまだ動いている街……。そこには昼間とはまったく違う顔を持つ東京が描かれています。どこか眠らない都市の静けさ、孤独、そして少しの希望。実際に体験したことはなくても、「あ、わかる気がする」と思わせてくれる空気感があります。
人間味のある登場人物たち
「アフターダーク」の登場人物たちはとても人間味があります。主人公のマリは真面目でしっかり者の女子大学生。姉のエリは美人で人気のあるモデルで、一見悩みなんてなさそうな完璧人間だけど、ずっと眠り続けていて起きる気配はない。マリに話しかけてくる高橋は、音楽を愛する優しい大学生。ラブホテルのマネージャー・カオルや、中国から来て事件に巻き込まれる若い女性など、背景も年齢もばらばらの人々が、ひと晩のあいだに交差していきます。
彼らはそれぞれ、表には見せていない傷や悩みを抱えています。でも、誰ひとりとして「かわいそう」と一言で片づけられるような存在ではありません。みんな、それぞれの場所で静かに必死に生きている。読んでいるうちに、そんな彼らに自然と感情移入していって、「もし自分だったら」と考えてしまいます。
テンポの良い構成
そして、特別な出来事が次々に起きるわけではないのに、ページをめくる手が止まらない。なぜなら、この作品では時間が確実に流れているからです。物語は夜の11時56分から始まり、明け方の6時52分に終わる。章ごとに時刻が記され、そのあいだに静かに人の感情や運命が少しずつ動いていく。まるで、夜が明けるのをじっと見つめているような読書体験です。
私の場合、ちょうど夜に読み始めたのでリアルタイムで物語が進んでいくようでした。
特に、ちょっと夜が好きな人、静かな空間に魅力を感じる人、そして「誰かと深夜に静かに話したい」と思ったことのある人には、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
「東京の夜」へのあこがれが一層深まりました。
海辺のカフカ(上下)
作品紹介
『海辺のカフカ』は、村上春樹による10作目の長編小説で、2002年に新潮社から上下巻で刊行されました。この作品では、ギリシャ悲劇の要素と日本の古典文学のモチーフが交錯し、哲学的で幻想的な世界が描かれています。主人公は、15歳の少年カフカ・田村。家庭の問題や「父を殺し、母と姉と交わることになる」という謎めいた予言から逃れるようにして、ひとりで旅に出ます。彼の旅は、現実と幻想の境界を曖昧にしながら、心の奥深くにあるものと向き合っていくものとなります。
おすすめポイント
余白のある物語構成
まずひとつは、読者自身に考える余白を与える物語構成です。本作には、明確に「答え」と呼べるものがほとんど提示されません。謎めいた登場人物たち、夢と現実の曖昧な境界、神話的な要素や暗示的な出来事……そういったすべてが、「これは一体どういう意味なのか?」と読みながら考えさせられる仕組みになっています。この“わからなさ”こそが本作の大きな魅力であり、読み終えた後も長く心に残る要因です。
登場人物の個性と奥行き
次に注目したいのは、登場人物たちの個性と奥行きです。15歳の主人公・カフカ少年の孤独や決意には、若さゆえの脆さと強さがあり、多くの読者の共感を呼びます。また、猫と話せる不思議な老人・ナカタや、自由奔放で明るいトラック運転手・星野さんなど、どこか現実離れした人物たちも物語に深みと温かみを与えています。彼らは単なる脇役にとどまらず、それぞれの物語と人生を抱えながら、全体のストーリーに絡み合っていきます。
『海辺のカフカ』は、少年の旅と心の成長という普遍的なテーマを持ちながらも、現実と幻想、文学と哲学、愛と暴力といった多くの問いを内包した、非常に深い読書体験を提供してくれます。読むたびに新しい発見がある、まさに“読む人の数だけ解釈がある”物語です。初めて村上春樹作品に触れる人にも、深くじっくり味わいたい読書を求める人にも、自信を持っておすすめできる作品です。
東京奇譚集
作品紹介
『東京奇譚集』は、2005年9月に新潮社から刊行された村上春樹による短編小説集です。収録されている5つの物語は、いずれも2005年前後に文芸誌『新潮』に発表されたもので、後に英語に翻訳され、米国の文芸誌『ザ・ニューヨーカー』などでも広く紹介されました。多くの読者を魅了しました。
現代の東京という都市を舞台にしながらも、どこか異世界に足を踏み入れたかのような気分にさせてくれる、5つの「語られざる」物語たち。現実と夢のはざま、日常の背後にある“奇妙な物語”に耳を傾けたい人におすすめの一冊です。
おすすめポイント
村上春樹の短編集『東京奇譚集』は、日常のすぐ隣にある「奇妙で静かな物語」を丁寧に描き出す全5編からなる作品集です。どれも数十ページほどの短編ながら、深い余韻と独特の世界観を持っており、読む人の心に静かに染み込んでくるような読後感があります。
一番の魅力は、一つ一つの物語が短く読みやすいという点です。まとまった時間がなくても、一編ずつ読み進めることができるため、通勤中や寝る前などにもぴったりです。それでいて、一つの短編の中に物語の起伏や感情の揺らぎがしっかりと収まっており、読み終えたあとには小説を一冊読み切ったような充実感もあります。
また、登場人物たちの行動や選択に、その人“らしさ”がにじみ出ているのも本書の魅力です。言葉少なで静かな語り口でありながら、ふとした瞬間の仕草や反応から、その人物の背景や性格がじわじわと立ち上がってきます。たとえば、偶然の出会いがきっかけで家族との関係を見つめ直すピアノ調律師や、亡き息子を思い続けハナレイ湾を訪れ続ける女性など、それぞれが特別な体験を持ちながらも、どこか「自分にも似た部分がある」と感じさせてくれるのです。彼らの一歩一歩には、静かだけれど確かな感情が込められており、その描写に共感や発見を覚える読者も多いはずです。
さらに本作には、“喪失”や“再生”といったテーマが、決して重くなく、むしろ柔らかく描かれているという特徴もあります。誰しもが人生の中で経験するような、何かをなくす痛みや、何かに気づいて前に進む感覚。村上春樹はそれを、大げさな言葉を使わず、どこか幻想的なモチーフを交えながら静かに描き出します。だからこそ、読み終えた後には「日常の中にもこんな奇跡のようなことがあるかもしれない」と、少しだけ世界を優しい目で見られるようになる。そんな小さな変化が、読者の中にそっと芽生えるのです。
奇妙だけれど、妙にリアル。そして切なさと優しさを同時に抱えた5つの物語。心の深い場所に何かが残る、静かな短編集です。
女のいない男たち
作品紹介
『東京奇譚集』以来9年ぶりに発表された短編作品集であり、「文藝春秋」に掲載された4作、「MONKEY」に発表された1作、そして書き下ろしの1作を含む全6編から成る『女のいない男たち』。表題が示すように本書を貫くのは「女性の喪失」あるいは「女性の不在」を抱え込んだ男たちの姿。村上春樹が描く「男たち」は、世間知らずの学生から、仕事も私生活も充実したエリートまで、その姿は実に多様だ。しかし、どのような年齢や肩書を持っていようと、「愛する女性」を失った瞬間、彼らの心はあっけなく折れ、日常は静かに崩れていく。――彼らは、根本的に弱いのだ。
おすすめポイント
『男の弱さ』が新鮮な感じ
村上春樹の短編集『女のいない男たち』は、恋愛小説とも人生小説とも言える独特な質感をもつ一冊だ。登場するのは、さまざまな年代や職業の男性たち。ある人は成功した外科医であり、ある人は平凡な俳優、またある人は学生時代の恋を引きずる中年男だったりする。そんな彼らに共通しているのは、「女を失ったあと」に生きているということ。そして、その喪失をうまく抱えられず、静かに壊れていくという点だ。
この作品集の大きな魅力は、そうした「男の弱さ」が誇張されず、淡々と、しかし誠実に描かれているところにある。恋人や妻を失って、ふつうの生活を続けながらも、心のどこかにぽっかり穴が空いたような彼らの姿は、読む者にじんわりとした余韻を残す。男は強くあるべき、というイメージを知らず知らずに持っていがちな私たちにとって、その脆さや孤独に共感する感覚は少し新鮮だった。と同時に、女性である自分には決して体験できない「男の恋愛の痛み」に触れるようでもあり、面白く読めた。
恋愛にまつわる感情を、男という視点から覗いてみたい人にこそおすすめしたい一冊。心の奥で何かがじわっと溶けるような読書体験になるはずだ。
それぞれの小説がおすすめな人
5冊の村上春樹の小説をご紹介しました。
それぞれ物語の内容もボリュームもかなり異なってきますが、中でも「あんまり読書に慣れていない・久しぶりな人」「ライトに読んでみたい人」は短編集やアフターダークのような短めの作品がおすすめです。
また、露骨な性描写が苦手目な人には、この中だと東京奇譚集とアフターダークをおすすめします。
逆に、村上春樹のワールドをどっぷり楽しみたい人、他の村上春樹作品を既に読んでいる人、時間や体力がある人には海辺のカフカがおすすめです。文章のボリュームは、今回紹介した中だと海辺のカフカが一番多いのですが、その分読み終わったときの満足感が強いのもこの作品です。
地域の図書館や学校の図書館でもだいたいおいてあると思うので、金欠だけど時間が有り余っている学生は、図書館に走りましょう。
そして、この若くて生々しい感性を持つ学生の今、一緒に村上春樹ワールドを楽しみましょう。