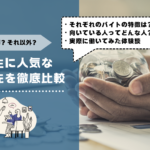こんにちは!ともみです。
大学生は夏休みが終わり、秋学期に入ると同時に学園祭へ向けた準備が一気に本格化する時期になってきました。キャンパス全体が慌ただしくなり、教室や廊下の至るところで看板を作ったり、ダンスや演奏の練習をしたりしている光景が見られるのも、この時期ならではです。
私自身も、所属する音楽サークルで3年間学園祭を経験しました。学園祭は普段の学生生活とは全く違う独特の雰囲気があり、非常に大きなイベントです。普段は授業やバイトでバラバラに過ごしているメンバーが「成功させたい!」という一心で一つになれる瞬間は、本当に特別なものでした。私もその雰囲気に乗せられて、準備から当日まで夢中になって活動していました。
そこで今回は、そんな学園祭の準備や当日のリアル、そしてそこから得られたものについてお話ししていこうと思います!大学の学園祭の雰囲気を少しでも鮮明に伝えることができればと思います。
準備ってどんなことをするの?
学園祭前に準備として取り組んできたことを、2つに分けてお話ししていきます。
1つ目はライブの準備、2つ目は先輩の引退プレゼントの準備です。
ライブの準備
私はサークル内で「ライブ係」という役割を担当していました。ライブ係の仕事は幅広く、ライブハウスの予約や機材の手配、当日の現場監督など、いわばライブ運営の中心的な役割を担います。
また、普段の月1回のライブであれば1日だけの開催ですが、学園祭ライブは特別です。3年生の引退という大きな節目を迎えるため、規模も大きくなり、2日間にわたっての開催となります。その分、仕事量も倍増。準備段階から気合いの入り方が全く違いました。
特に大変だったのは「会場が大学の教室」という点でした。普段はライブハウスを借りて、専門のスタッフの方に音響や照明をサポートしてもらうのですが、学園祭ライブではそうはいきません。ステージづくりから機材のセッティング、音響調整、照明の位置決めまで、すべてを学生だけでこなさなければならなかったのです。
さらに、学園祭実行委員とのやり取りも必要でした。教室を使うためのルールや音量制限、必要な備品の手配など、普段は考えなくてもいい細かい規定を一つひとつ確認していきます。ライブの成功はもちろん、大学全体のルールを守る責任もあり、常に緊張感がありました。
特に3年生にとっては「最後の舞台」となる大切なライブです。失敗は許されないというプレッシャーの中で、「全ての業務プラスアルファ」の仕事を担うのは本当に大きな挑戦でした。
先輩の引退プレゼントの準備
先ほどもお話しした通り、学園祭ライブは3年生にとって引退の舞台でもあります。だからこそ、私たち後輩にとっても「感謝をどう伝えるか」が大きなテーマでした。ライブの準備と並行して、先輩方のための特別なプレゼントづくりに力を入れていました。
サークル全体で準備したものは主に4つありました。
引退アルバムの作成
引退する3年生一人ひとりに、写真とメッセージを詰め込んだアルバムを作りました。アルバムには、後輩だけでなくOBからのメッセージも載せていて、先輩のサークル生活全体を振り返られるような内容になっています。
感謝の気持ちを丁寧に形にしたいと思って、1か月以上前から作業を進めていたのですが、細部にこだわりすぎてしまい、完成したのは本当にギリギリ。夜遅くまで作業していたのも今ではいい思い出です。
記念ムービーの作成
これも大きな見せ場でした。3年生の入学当初の写真や演奏風景、合宿での思い出動画を集めて編集し、後半には後輩からの感謝メッセージをサプライズで入れました。
さらに、なんとかバレずに3年生の親御さんに連絡を取り、親御さんからのメッセージ動画も加えました。上映中に涙ぐむ先輩の姿を見たときは「やってよかった」と心から思いました。
LINEスタンプの作成
3年生の写真や似顔絵を使って、オリジナルのLINEスタンプを作成しました。普段のちょっとした会話の中でも先輩を思い出せるように、という遊び心も込めています。
発表したときは、あまりに奇想天外だったのか、「こんなことまでやるんだ!」と先輩方も驚いていました。
オリジナル曲の作成
これは音楽サークルならではの取り組みではないかと思います。感謝の思いを言葉だけではなく音楽に乗せて届けたいと考え、サークルメンバーでオリジナル曲を作りました。
歌詞には「先輩から教わったこと」「一緒に過ごした日々への感謝」を盛り込み、最後は学園祭ライブのステージで披露しました。音楽で繋がった仲間だからこそ、最後まで音楽で送り出せたことは、双方にとって本当に特別な経験になったと思います。
大忙しな学園祭当日
準備段階だけでも膨大な仕事量でしたが、学園祭当日はその比にならないほど盛りだくさんです。まさに朝から晩までフル稼働でした。ここでは大きく3つに分けてお話しします。
ライブ会場の現場監督とライブ出演
先ほども触れたように、ライブ係の私は「会場監督」という大役を任されていました。具体的には、機材のセッティングや音響チェック、転換(出演バンドの入れ替え)のタイミング管理など、とにかくライブがスムーズに進むように気を配り続ける必要がありました。演奏中にトラブルが起きないよう、裏で常に準備や確認をしているので、気を抜く暇はまったくありませんでした。
それに加えて、自分自身も出演バンドの一員としてステージに立つ予定がありました。裏方として走り回りながら、合間を縫ってメンバーとリハーサルの最終確認をしたり、出番直前にチューニングを合わせたり。頭の中では「この後の進行」と「自分の演奏」の両方を同時に考えている状態で、心臓のドキドキがずっと止まりませんでした。
ただ、いざステージに立ってみると、緊張以上に「楽しい!」という気持ちが勝ちました。普段よりも観客が多く、学園祭特有の熱気の中で演奏できるのは本当に特別な経験です。裏方として支えているときとはまた違った達成感を味わえる瞬間でした。

サークルでの活動以外は?
現場監督の仕事は何人かでシフトを組んで担当していたので、ずっと自分のサークルに張り付いているわけではありませんでした。合間の時間には少し抜け出して、他のサークルの企画を見に行くこともできました。
学園祭当日は、大学中がまるでテーマパークのように変わります。別の教室ではバンドやアカペラサークルがライブをしていたり、屋外では模擬店で焼きそばやタピオカを売っていたり。普段は見慣れたキャンパスなのに、この日だけは全く違う雰囲気になるのが面白かったです。私も空き時間を見つけては、友達と一緒にライブを覗いたり、お店で食べ物を買ったりして、学園祭らしい時間を楽しんでいました。
ただ、心のどこかでは「もうすぐ自分の出番がある」とか「次の転換は大丈夫かな?」と考えていて、完全に仕事を忘れることはできませんでした(笑)。でも、その緊張感も含めて「学園祭ならでは」だったように思います。普段の大学生活では味わえない、非日常と責任感の両方が混じり合った独特の体験でした。
学園祭ライブ打ち上げの開催
学園祭ライブは特別なライブである分、その打ち上げも普段のものとは大きく違います。普段の打ち上げは気軽な大衆居酒屋でわいわい盛り上がるのですが、この日だけは特別です。雰囲気のあるバーを貸し切って、まるで式典のように行われるんです。
最初は自由に食事を楽しむ時間が設けられ、みんなが「リラックスした雰囲気で過ごします。しかし、セレモニーが始まると空気は一変します。3年生の幹部から最後の挨拶があり、次期幹部を発表する「引き継ぎ式」が行われます。その瞬間は、サークルにおける世代交代を実感する特別な時間でした。
さらに、後輩たちが準備した記念ムービーの上映が続きます。映像に映る懐かしいシーンや、親御さんからのサプライズメッセージに涙ぐむ先輩方の姿を見て、こちらも思わず胸が熱くなりました。そして、一人ずつ呼ばれて引退アルバムを手渡す場面では、多くの先輩・後輩が涙を流し、会場全体が感動に包まれます。
最後には、引退するサークル長が「これまで支えてくれてありがとう」と感謝を伝え、次期サークル長が「これからは自分が引っ張っていきます」と決意を語ります。その後、全員で1本締めをして、学園祭ライブの打ち上げは幕を閉じました。
学園祭の打ち上げは、ただの飲み会ではなく、笑いあり涙ありの「サークルの歴史の節目」と言える場でした。だからこそ、毎年この日を迎えると「サークルに入ってよかった」と強く実感できるのだと思います。

高校の文化祭との違いは?
自由度の高さ
大学の学園祭は、とにかく「自由度」が高いのが大きな特徴です。
場所や時間などの基本ルールさえ守れば、基本的にどんな企画でも実現できます。ステージでのライブやダンスはもちろん、模擬店や展示、さらには外部のお客さんを巻き込むようなイベントも可能です。
高校の文化祭では「これはやっていい」「これはダメ」と先生から細かく制約があることが多いですが、大学ではサークルごとの個性を思い切り表現できるのが大きな違いです。
責任の大きさ
自由度が高い分、責任も同じくらい大きくなります。
高校の文化祭では最終的に先生や学校側がフォローしてくれる部分も多いですが、大学では基本的にすべて自分たちで対応します。
例えば、会場のセッティングや音響トラブル、模擬店での金銭管理や衛生面のチェックまで、全部学生主体。いざという時に助けてくれる大人はいないので、その場で解決策を考え、判断して行動する必要があります。
規模と雰囲気の違い
大学の学園祭は、高校に比べて来場者の数も規模も圧倒的に大きいです。高校の文化祭は基本的に生徒やその保護者が中心ですが、大学では地域の人や他大学の学生も訪れるため、まるで「町のお祭り」のようなにぎわいがあります。有名な芸能人やアーティストが大学に来るということもよくある話です。
その分、サークルでの活動も「ただの学内イベント」ではなく、「大勢の人に見てもらう一大イベント」という意識が強くなります。
上下関係と役割分担
大学のサークルでは、先輩・後輩の役割分担がしっかりしているのも特徴です。
例えば、学園祭ライブでは3年生がメインで引退公演を行い、2年生がそのサポートや運営の中心を担い、1年生は裏方や雑務を通して学んでいきます。
高校の文化祭では「クラス全員で協力して一緒に作り上げる」イメージが強いですが、大学の学園祭は「サークルとして代々受け継ぎ、成長していく」色合いが濃いのが違いです。
学園祭の経験から学んだこと
このような学園祭の経験から、私自身たくさんの学びを得ることができました。その中でも特に印象的だったものを4つお伝えします。
主体性と責任感の重要性
高校の文化祭では、先生や大人が陰でサポートしてくれる場面が多かったのですが、大学の学園祭では基本的にすべて学生主体で動きます。
会場の手配から当日の運営、トラブル対応に至るまで、誰かが「やってくれるだろう」と思っていると、本当に何も進みません。だからこそ「自分がやらなきゃ!」という責任感が強く芽生えました。
この経験を通して、主体的に行動することの大切さを肌で感じました。
計画性と逆算思考で物事を進めることの重要性
引退アルバムや記念ムービーの制作は、完成までに想像以上の時間がかかります。写真や動画の収集、レイアウトや編集、メッセージの取りまとめなど、やることが山積みで「まだ時間あるし大丈夫」と思っていると、あっという間に期限が迫ってきます。
そのため、「逆算して今どこまで進めておくべきか」を考えながら動くことが必須でした。計画を立てる力や、段取りよく進める力が自然と鍛えられたと思います
周囲を頼ることや柔軟に対応することの大切さ
学園祭当日はトラブルがつきものです。出演者が遅刻したり、機材が思うように動かなかったり、予定通りにいかないこともありました。
そんな時に一人で抱え込むのではなく、仲間と声を掛け合って役割を調整しながら対応することが重要でした。
また、準備期間でもメンバー間で意見が食い違うことも多々ありましたが、「どうしたら全員が納得できる形になるか」を考えることで、自分の意見に固執することなく、柔軟に物事を考えることの大切さを学びました。
感謝の気持ちを形にする大切さ
先輩の引退セレモニーでは、アルバムやムービー、オリジナル曲など、色々な形で感謝を伝えました。単に「ありがとう」と言葉で伝えるだけでなく、自分たちなりに工夫をして形に残すことで、より思いが届きやすくなると実感しました。
先輩方の涙や笑顔を見たときに「やってよかった」と心から思えましたし、人に感謝を伝える方法には色んな形があるのだと学びました。
おわりに
ここまで学園祭の準備から当日、そしてそこから得た学びについてお話ししてきました。改めて振り返ると、学園祭はただの一大イベントではなく、自分自身の成長や仲間との絆を深めるきっかけだったと思います。
準備の段階では、自由度の高さゆえに責任の大きさを実感しましたし、計画性や主体性の大切さを身をもって学びました。当日もトラブルに直面しながら、仲間と協力して乗り越えた経験は、今でも大切な思い出になっています。そして、先輩方への感謝を形にして届ける場面では、人とのつながりの温かさを心から感じることができました。
学園祭を通して得た経験は、大学生活の中でも特に濃い時間であり、社会に出てからも役立つ学びが詰まっていたと思います。
高校生の方は、ぜひ大学生になったら、学園祭に精力的に取り組んでほしいと思います。きっと何か得られるものがあるのではないかと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!