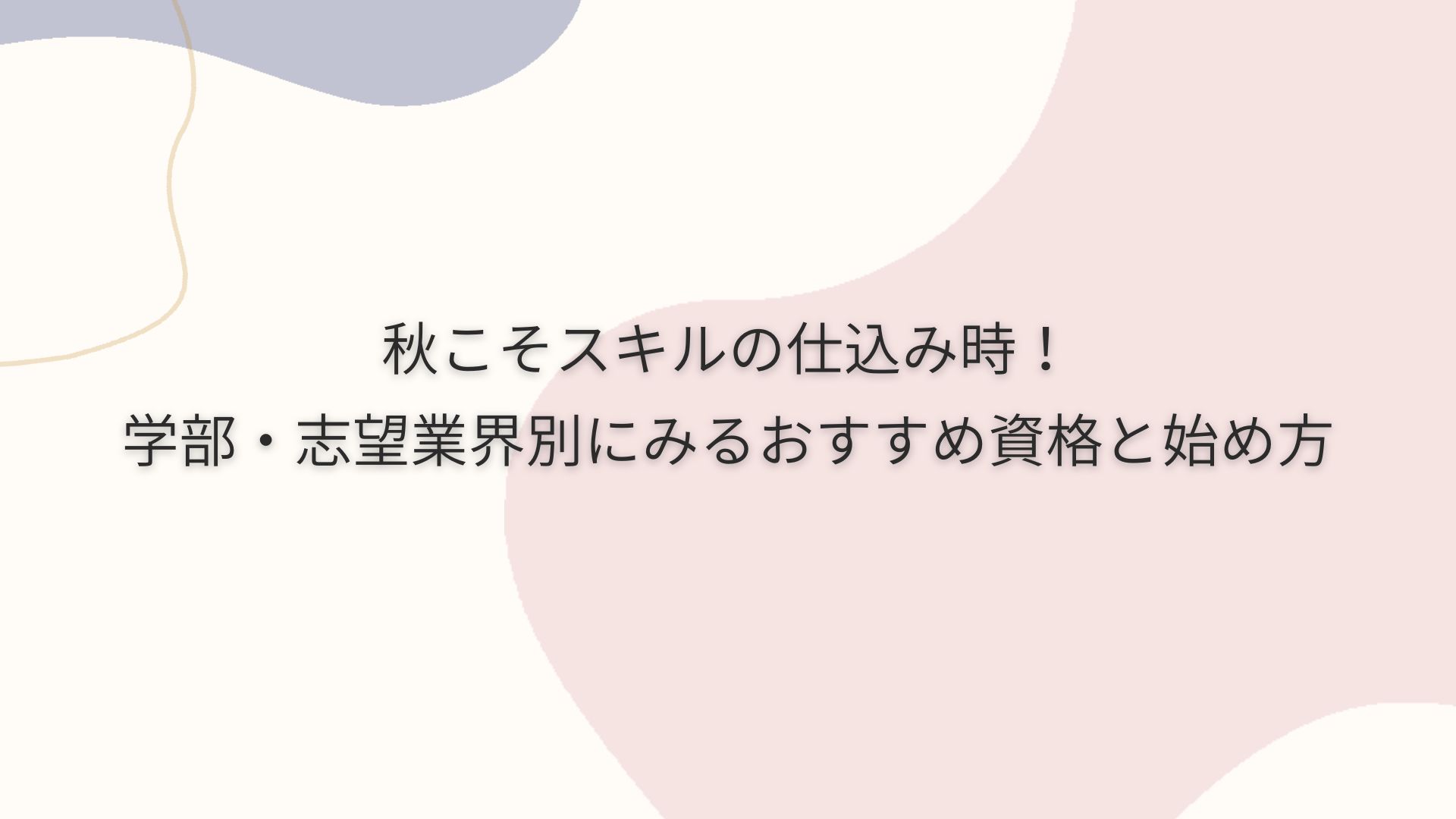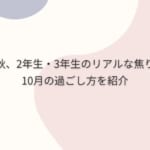こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。
夏休みが終わって少し涼しくなってくると、キャンパスの空気もどこか落ち着いてきます。サークルの合宿や学園祭準備も一段落して、「何か新しいことを始めたいな」と感じるのが、ちょうどこの秋の時期。
私は現在、ITパスポートとTOEICを勉強中ですが、実際にやってみると“秋から始めるメリット”を強く感じます。
気温的にも過ごしやすく、夏のイベント疲れも落ち着いて集中できる。なにより、年末までに一つの目標を立てやすいんです。
この記事では、私の経験も交えながら、「秋から始めやすい資格・スキル」を学部別・志望業界別に紹介します。
「この秋、何か新しいことに挑戦してみたい」「将来に向けて動き出したい」と考えている人に、現役大学生のリアルな視点からヒントをお届けします。
なぜ秋に資格・スキル学習を始めるのがいいのか
学園祭や夏行事が落ち着き、「自分の時間」が戻ってくる
大学生活の前半は、どうしてもサークルや友人との予定が中心になります。
特に早稲田の場合、夏休み〜秋のはじめにかけては合宿・新歓ライブ・学園祭準備などイベントが集中します。
でも、それが一段落する10月ごろからは、自然と「何かに打ち込みたい」と思えるようになります。
私もヨコシマ。の夏合宿や早稲田祭ライブの準備が終わったタイミングで、ふと「せっかく時間があるなら何か残ることをやりたい」と思い、資格の勉強を始めました。
「年内に1つ成果を出す」という目標を立てやすい
秋に勉強を始めると、ちょうど冬(12月〜2月)に多くの資格試験が実施されるため、「短期での成果」を狙いやすいのも大きな魅力です。
ITパスポートも年中受験できますが、3カ月ほど勉強して年内に合格、というスケジュールがちょうどいいペース感でした。
また、TOEICも毎月試験を開催しており、「秋から再スタートして、年内に目標スコアを更新する」といった区切りをつけやすい。
こうした“終わりが見える学習計画”を立てられるのは、秋に始める人の大きなメリットだと思います。
授業リズムが安定し、勉強時間を確保しやすい
秋学期の前半は、授業もまだ落ち着いていて、レポートやテストも少なめ。
そのため、平日の空きコマや授業後の1〜2時間を使って資格の勉強を続けやすいです。
私の場合、火曜と木曜の3限後が空いていたので、学生会館の自習室に行ってITパスポートの過去問を解くようにしていました。
特に文系の学生だと「理系的な勉強」に抵抗を感じる人も多いですが、少しずつでも続けていくと“知識が繋がる感覚”があり、勉強自体が楽しくなってくるのを実感しました。
「就活準備」の一環としても始めやすい
2年の秋といえば、ちょうど就職活動を意識し始める時期でもあります。
自己分析や業界研究を進める中で、「自分に何が足りないか」「社会で求められるスキルは何か」が少しずつ見えてくる。
私もIT業界志望ということもあり、「文系でもITリテラシーを証明できる資格を取ろう」と考えてITパスポートに挑戦しました。
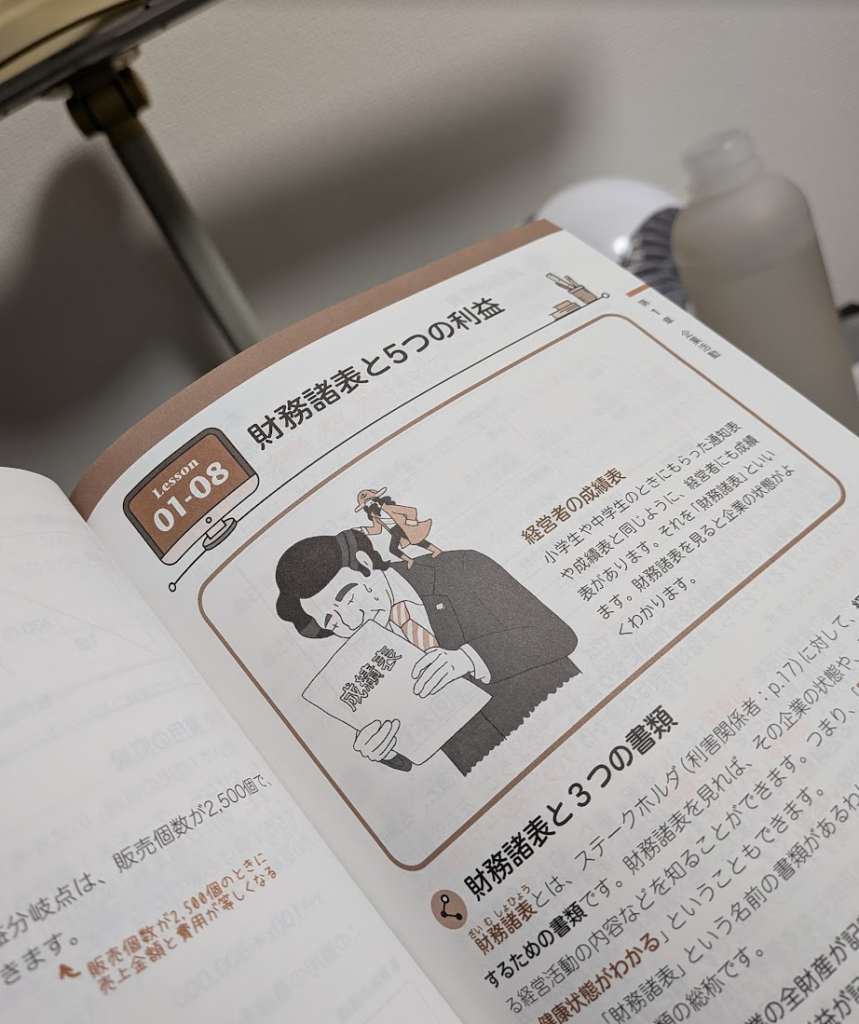
秋は“勉強=就活の準備”にもつながる季節。
「資格勉強=将来の投資」と考えると、モチベーションも保ちやすくなります。
小さく始めて、冬に“成果”を迎える理想のサイクル
秋から始めた学びは、冬に「試験」「成果」「達成感」という形で返ってくる。
このリズムがうまく回ると、次の春にも「また何か新しいことをやってみよう」という前向きなサイクルが生まれます。
私自身、ITパスポートを勉強しながら「次は基本情報を取りたい」と思うようになり、学びが自然と続いていきました。
秋は、そんな“第一歩”を踏み出すのに最適な季節です。
学部別おすすめ資格・スキル
政治経済・商・社会科学系|社会の“仕組み”を理解する力を武器に
政治・経済・社会といった学問を学ぶ学生は、社会の構造や制度を理解する力があります。
分野の学生にとっておすすめなのは、実務で活かせるビジネス系資格です。
たとえば、
- 日商簿記2〜3級
経済学部・商学部の学生に特に人気。企業会計の基礎がわかると、就活の自己PRにも活かせます。 - FP(ファイナンシャルプランナー)
金融・保険業界志望の人に最適。年金や税金の知識が身につき、社会人生活にも役立ちます。 - TOEIC/英検準1級
国際系企業や総合商社を目指すなら、英語スコアは今から磨いておきたいポイント。
私自身も政経学部ですが、「経済や法律の基礎を学ぶだけでは社会で戦えない」と感じ、ITパスポートの勉強を始めました。
情報リテラシーやセキュリティ、ネットワークの基礎を学ぶことで、文系でも“デジタル時代に対応できる力”がつく実感がありました。
特にIT業界やコンサル業界を目指すなら、文系でも取れるIT資格を1つ持っておくと差がつきます。
文学・教育・国際教養系|言語と文化を「使えるスキル」に変える
文学・教育・国際系の学生は、「言葉」「文化」「教育」に強みがあります。
秋から始めやすいのは、以下のような“語学×応用スキル”です。
- TOEIC/IELT
特に国際教養・文学系では王道。秋から毎日30分ずつ勉強するだけでも年内スコアアップが狙えます。 - 日本語教育能力
検定教育学部・語学系の学生に人気。難易度は高めですが、秋から通信講座でコツコツ始められます。 - SNS運用・Webライティング講座
発信力を活かした副業にもつながります。
特に文学や教育系は、卒業後の進路が幅広いため、「どんな形で自分の強みを生かせるか」を探る時期にも秋はぴったり。
語学を“勉強”から“スキル”に変える意識で、何か1つ始めてみるのがおすすめです。
理工・建築・情報系|専門知識を“資格”で証明する
理系学生の場合、秋は授業や研究が落ち着く前半に資格勉強をスタートできる絶好の時期。
特に就職に直結する資格が多く、「実務+資格」の両輪で進めると強いです。
- 基本情報技術者試験(FE)
プログラミングやネットワークの基礎を体系的に学べる。 - 応用情報技術者/Python・SQLなどのスキル
AI・データサイエンス志望の学生にも人気。 - CAD・建築士試験の学科対策
秋〜冬にかけて始めると来年度の受験に間に合います。
また、TOEICを並行して勉強しておくと、技術職でも海外プロジェクトや外資系企業で評価されやすいです。
法学系|「制度・ルール」を理解する力を形にする
法学部の学生は、理論や制度を整理する力に長けています。
この強みを活かせる資格として、「法律系・実務系資格」がおすすめです。
- 行政書士/宅地建物取引士(宅建士)
学部で学んだ知識を活かして挑戦できる代表格。 - ビジネス実務法務検定
企業法務やコンプライアンスに関心がある人に最適。 - 公務員試験対策
秋から少しずつ始めれば、春の模試にも間に合います。
法学部の知識は「暗記」ではなく「思考」に近いので、資格勉強と相性が良いのも特徴です。
秋のうちに1つの資格をやり切ると、自信にもなります。
芸術・文化構想・スポーツ科学系|感性を“形にする”資格を
芸術・スポーツ系の学生は、感覚的な強みを持っています。
ただ、それを社会にどう生かすかを考えるとき、デザイン・健康・教育の資格が視野に入ります。
- Photoshop/Illustrator検定(クリエイター能力認定)
デザイン系学生のポートフォリオづくりに。 - スポーツ栄養・健康運動実践指導者
体づくりや教育分野を志す学生に。 - SNSマーケティング/動画編集
作品発信や副業としても人気上昇中。
秋は制作や展示の合間に、「次に活かせるスキル」を取り入れるのにちょうどいいタイミングです。
学部を超えて共通するおすすめ資格
どの学部の学生にも共通しておすすめできるのが、社会人としての基礎力+生きる力が身につく資格です。
大学生のうちに学んでおくことで、就活だけでなく将来の人生設計にも大きく役立ちます。
- ITパスポート:文系・理系問わず人気の国家資格。情報リテラシーやセキュリティ、DXなど、社会のデジタル基盤を理解できる。
- TOEIC:グローバル企業や外資系志望だけでなく、どんな業界でも評価される。秋からコツコツ続けると年内スコアアップも十分可能。
- MOS(Excel・Word):大学のレポートやゼミ資料作成にも直結。社会人1年目で求められるPCスキルを早いうちに身につけられる。
- 日商簿記(3級〜2級):お金の流れや企業会計の仕組みを理解できる、ビジネスリテラシーの基礎資格。文系学生だけでなく、理系でも「会社の仕組みを知る」ために取る人が増えています。
- FP:税金・保険・年金・投資など、生きるうえで必ず必要になるお金の知識が体系的に学べます。就職後の資産形成にもつながり、社会人になってから「取っておけばよかった」と感じる人が多い資格です。
特に簿記とFPは、「マネーリテラシーを高める」意味でも非常に有用です。
投資・保険・老後資金といったテーマは、社会に出てから誰もが直面します。
大学生のうちに学んでおくことで、将来の家計やキャリアを自分の頭で考える力が身につきます。
秋は新しいことを始めやすく、勉強のリズムも作りやすい時期。
“将来の自分を少しラクにするための学び”として、これらの資格に取り組むのはとてもおすすめです。

スキマ時間で続けるコツ
「まとめてやる」より「毎日少しずつ」が長続きの秘訣
資格勉強を始めたばかりの頃は、「休日に一気にやろう」と思いがちですよね。
でも実際は、1日30分〜1時間をコツコツ続ける方が定着しやすく、圧倒的に続けやすいです。
私自身、ITパスポートとTOEICの勉強を並行していた時期は、1日あたり1時間を目安にしていました。
夜にまとめて勉強するのではなく、通学中や空きコマなど、“生活のリズムの中に小さな勉強時間を埋め込む”感覚です。
例えば、
- 通学中(電車内) → スマホアプリでTOEICの単語チェック
- 昼休み → ITパスポートの過去問を1章だけ解く
- 就寝前 → その日の復習を5分だけ確認
これを続けるだけでも、1週間で5〜7時間分の勉強量になります。
「今日は忙しいから0分」ではなく、「5分だけでもやる」を徹底すると、“やらない日を作らない”習慣が自然と身につきます。
勉強する場所を固定すると集中力が上がる
どこで勉強するかを決めておくのも大事です。
私の場合は、早稲田大学学生会館や本キャンパス7号館の自習室をよく利用しています。静かで集中できる上に、周りにも勉強している学生が多く、「自分もやらなきゃ」という気持ちになります。
また、気分を変えたいときは高田馬場のカフェ(ドトールやベローチェなど)を利用することもあります。
勉強場所を日によって変えることで、マンネリ化を防ぎつつリズムを保てるのもポイントです。
スマホを“誘惑”ではなく“武器”に変える
スマホ=勉強の敵と思われがちですが、上手く使えば最強の味方になります。
たとえば、
- Studyplus で勉強時間を記録して達成感を得る
- 英語アプリ(abceed/mikanなど) で通学中にTOEIC対策
- ITパスポートの過去問道場サイト でスキマ時間にクイズ感覚で復習
特にITパスポートのような暗記中心の資格は、アプリ学習との相性が抜群です。
1問1答形式で進められるので、スキマ時間に“ミニテスト感覚”で知識を積み上げられます。
一緒に頑張る仲間を作る
一人で続けるのがつらいときは、資格勉強仲間を作るのも効果的です。
早稲田の友人の中にも、「TOEICの勉強報告を毎週しあう」「ITパスポートの問題を出し合う」など、ゆるく勉強会をしている人が多いです。
誰かと共有すると、“やらないと恥ずかしい”というほどよいプレッシャーが生まれます。
SNSやX(旧Twitter)の「#資格勉強垢」でモチベを保つのもおすすめです。
実際に始めてよかった体験談
ITパスポートで見えた「社会のしくみ」
正直、最初にITパスポートを勉強し始めたときは、「IT分野の基礎を学んでおこう」くらいの軽い気持ちでした。
でも、勉強を進めるうちに気づいたのは、この資格は単なる“ITスキル”の勉強ではないということです。
ITパスポートでは、IT用語やシステムの構造だけでなく、
- 企業がどうやって利益を生み出しているのか
- 経営と情報システムがどうつながっているのか
- 企画・開発・販売といった一連の流れがどう機能しているのか
といった、会社や社会の「動き方」そのものを学ぶことができます。
それまでの私は、「会社って何をどう回して利益を出しているのか」という感覚を、授業ではなんとなく理解していても、実際の構造まではピンときていませんでした。
でも、ITパスポートを学ぶ中で、“ビジネスの全体像”が頭の中でつながっていく感覚がありました。
「なぜ企業がDXを進めているのか」
「クラウド化やAI活用がどう経営効率に結びつくのか」
——そうしたニュースの背景が、自然と理解できるようになったのも大きな収穫です。
TOEIC学習で感じた「継続のリズム」と「成長の実感」
一方で、TOEICの勉強はITパスポートとはまったく違うタイプの挑戦でした。
英語は積み重ねが大切なので、“一気に覚える”より“毎日少しずつやる”ことを徹底。
最初の1カ月は単語帳を開くだけでもしんどかったですが、通学中の15分や寝る前の30分を続けるうちに、少しずつ英文がスムーズに読めるようになりました。
TOEICの学習を通して感じたのは、「努力が可視化される心地よさ」です。
前より速く読めた、リスニングで聞き取れた、スコアが少し上がった——そんな小さな成功が積み重なって、次のモチベーションにつながる。
資格勉強というと「就活のため」というイメージが強いですが、実際にはそれ以上に、自分の変化を実感できる時間だと思います。
秋に始めたからこそ、無理なく続けられた
そして何より、「秋に始めたこと」が大きかったと今では感じています。
夏の忙しさが落ち着き、サークルも授業も安定してくる時期。気温的にも過ごしやすく、夜に勉強していても集中しやすい。
最初は軽い気持ちで参考書を開いただけでしたが、徐々に“勉強が習慣化”していきました。
1日1時間だけでも、「やらないよりはマシ」を続けていたら、いつの間にか知識が定着していた。秋は、そんな「ゆるく始めて、確実に積み上げる」のに最適な季節でした。
「資格」は“結果”より“きっかけ”
ITパスポートもTOEICも、最初の目的は“資格取得”でした。
でも今振り返ると、得たものはそれ以上に、「社会を理解する力」や「学びを続ける姿勢」した。
ITパスポートを通して、会社や経済の流れに興味を持ち、
TOEICを通して、世界の情報にアクセスする力を養う。
どちらも“勉強したから終わり”ではなく、これからの社会で生きていくうえでの基盤になったと感じています。
まとめ|「秋スタート」が将来の差をつくる
もし今この記事を読んでいる高校生のあなたが、
「大学生って、資格とかスキルの勉強って本当にやるの?」
と思っているなら――答えは「やる人は、ちゃんとやる」です。
ただ、最初から完璧にやろうとする必要はありません。
大事なのは、ちょっとやってみようかなという気持ちを行動に移すこと。
私自身も、ITパスポートのテキストを買って最初のページを開いたときは、正直「最後まで続くのかな」と不安でした。
でも、1日30分でも続けるうちに少しずつ分かることが増えて、気づけば勉強が“日常の一部”になっていました。
秋は、そんな「はじめの一歩」を踏み出すのにぴったりな季節です。
夏の喧騒が落ち着いて、頭がすっきりしてくるこの時期に何か一つでも新しいことを始めてみると、その経験が数カ月後、きっと自信につながります。
資格を取ることは、ゴールではなく“きっかけ”です。
その過程で、「自分ってこういう分野が好きなんだ」「意外と得意かも」と気づくことが多い。そうした小さな発見が、進路選びや将来の仕事に生きてくるんです。
高校生のうちは、まだ将来のことを全部決める必要はありません。
でも、学ぶって意外とおもしろいと思える瞬間を、少しでも早く経験しておくと、大学に入ってからの世界がぐっと広がります。
だからこそ、秋という季節に、
「資格のテキストを1冊開いてみる」
「TOEICの単語を1日5個覚える」
そんな一歩を踏み出してみてほしいと思います。
あなたが今、ほんの少しだけ勇気を出して動いたことが、
未来の自分を助けてくれる“確かな力”になるはずです。