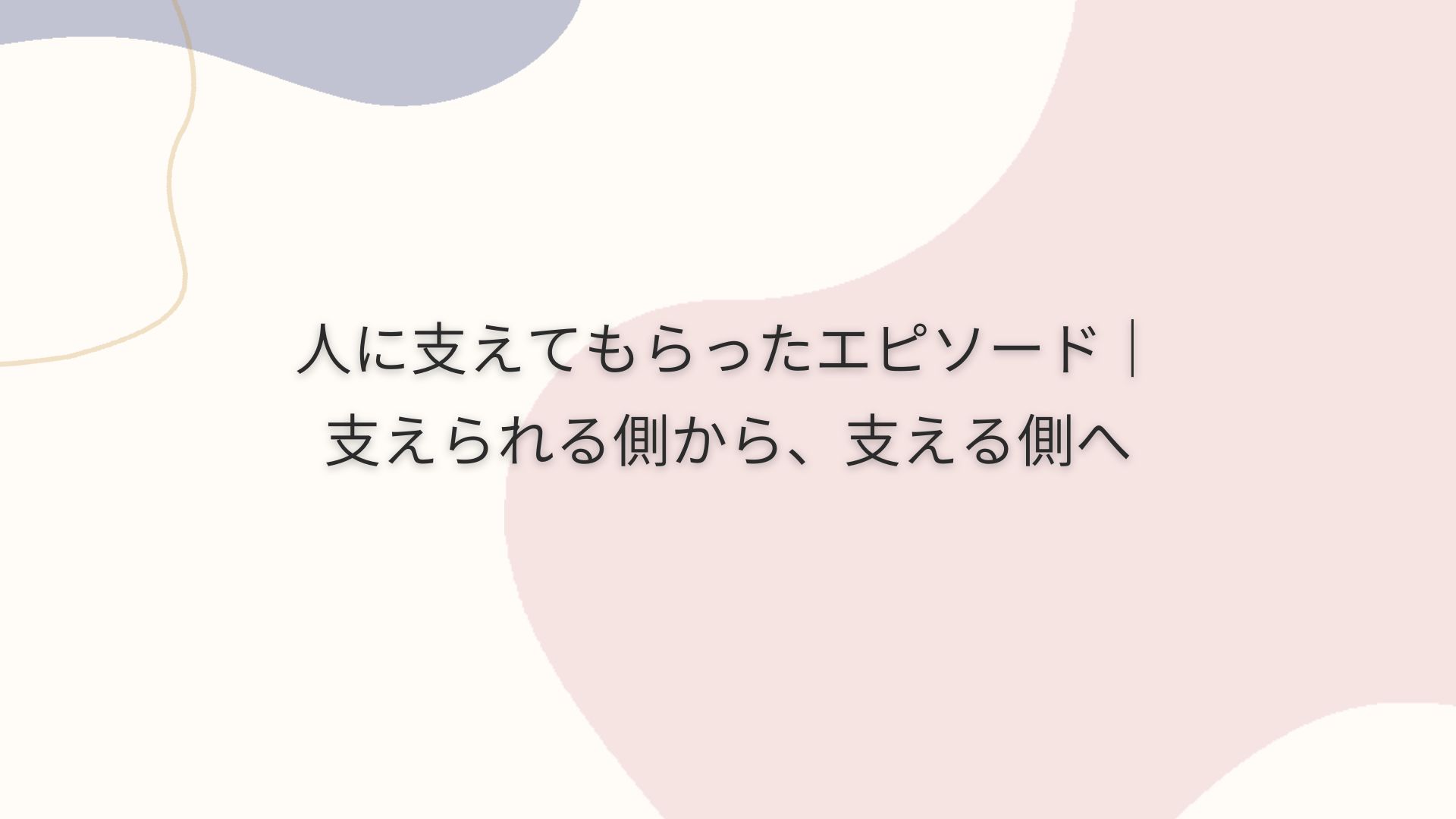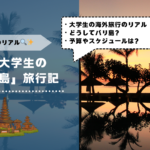私は早稲田大学の内部進学生として、受験を経験せずに大学へ進学しました。だからこそ、勉強の努力とは少し違う形で「人から学ぶ」経験を重ねてきたと思います。
高校時代の寮生活では、同級生や先輩に支えられながら初めての共同生活を乗り越えました。大学では、アコースティックバンドサークルで出会った先輩に憧れ、人との関わり方や感謝の伝え方を学びました。そして長期インターンでは、社員の方々から社会で生きるうえでの姿勢を教わりました。
こうして振り返ると、私の成長のそばにはいつも“人の支え”がありました。
誰かに助けてもらいながら学んだことは、やがて自分が誰かを支える力へと変わっていったと感じています。
高校の寮生活で学んだ「助け合いがある暮らし」
寮に入って感じた“孤独”と“支え”
高校進学と同時に、私は早稲田大学本庄高等学院の寮に入りました。
地元を離れての新生活。家族がいない環境で暮らすのは初めてで、最初の夜は正直かなり心細かったです。
寮の部屋は二人部屋ではなく一人部屋でしたが、トイレ・洗面所・お風呂・洗濯機などはすべて共用。
“自分の空間がありながらも、常に誰かの生活音が聞こえる”という空気に、最初は落ち着かず、なかなか新しい環境に慣れることができませんでした。
最初の頃は小さなことでよく失敗をしました。
洗濯機に洗剤を入れすぎて泡だらけにしてしまったり、使用時間を間違えて先輩に注意されたり。
また、夜に誰もいない廊下を歩くときは、ふと家族の声が恋しくなることもありました。
そんなとき、救いになったのが同級生と先輩の存在でした。
ある日、洗剤を切らして困っていると、隣の部屋の友人が「これ使っていいよ」と差し出してくれました。
それをきっかけに自然と会話が生まれ、一緒に食堂へ行くようになり、勉強や悩みを語り合う仲になっていきました。
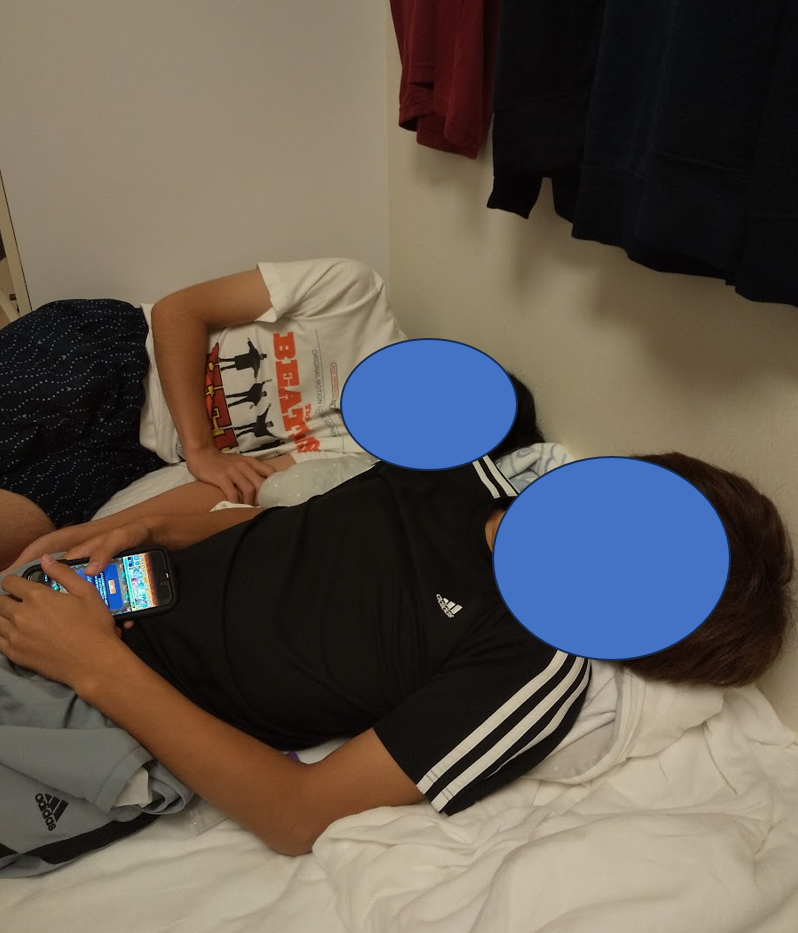
上級生の先輩たちもとても面倒見が良く、「最初の1カ月は誰でもつらいから大丈夫」と声をかけてくれたり、生活のコツを教えてくれたりしました。洗濯機の並び方や掃除当番のルールなど、寮での“暗黙のマナー”はすべて先輩に教わりました。
そんな温かい環境のおかげで、次第に寮が「家」のように感じられるようになりました。
当時はただ“助けてもらっている”という感覚しかありませんでしたが、今振り返ると、あのときの小さな優しさが、私の中に人と生きる感覚を育ててくれたのだと思います。
小さな助け合いが“生きる力”を育てた
寮生活で印象的だったのは、助け合いが特別なことではなく、“日常の一部”として根づいていたことです。
たとえば試験前、得意科目のノートを交換し合うのは当たり前。風邪をひいた友人がいれば、「食堂におかゆ取りに行こうか?」と誰かが声をかける。夜遅くまで残っている友達を見つけたら、「もう寝よう」と声をかけ合う。そんな小さなやり取りが、毎日の中に自然にありました。
また、寮には地方出身者が多く、価値観や生活リズムもさまざまでした。
朝型の人・夜型の人、几帳面な人・少しルーズな人――その違いを受け入れて共に暮らす中で、相手を思いやることの大切さを知りました。
たとえば、夜遅くまで勉強している人の邪魔にならないよう静かに動いたり、共有スペースの洗面台を汚したら次の人のために拭いたり。そうした気配りが、相手への“支え”になるということを身をもって感じました。
一方で、寮には厳しさもありました。
門限を破ったり、掃除当番を忘れたりすれば、上級生から注意を受けます。
でもその注意の裏には、後輩を思う気持ちがあることもわかっていました。「自分一人の生活ではない」という意識を持つことが、共同生活を円滑にする鍵だったのです。
ホームシックでつらかった夜、同級生とお菓子を分け合いながら語り合ったこと。試験前に「明日やばいな」と笑い合いながら夜更かししたこと。
そうした日々が、私にとっての“人とのつながりの原点”になりました。
この経験を通じて、私は「助け合いは生きる力になる」と学びました。
自分一人では気づけないことも、誰かと一緒なら乗り越えられる。
そして、人に頼ることを恐れず、相手に感謝を返していくことが、人間関係を豊かにしていく――そんな実感を得たのです。
大学に入ってからも、この“助け合いの精神”はずっと自分の中に残っています。
一人暮らしを始めてからも、友人同士で掃除や料理を分担したり、テスト前にノートを貸し合ったりと、自然と協力し合う姿勢が身につきました。
あの寮での生活が、私に「人と生きる強さ」を教えてくれたのだと思います。
サークルの先輩との出会いで学んだ「人への感謝の示し方」
憧れの先輩との出会いが変えた価値観
大学に入学してすぐ、私はアコースティックバンドサークル「ヨコシマ。」に入りました。
音楽が好きで入ったサークルでしたが、当時は大学生活そのものに不安もあり、最初のうちは周囲にどう馴染めばいいのか迷っていました。
そんなときに出会ったのが、二つ上の先輩でした。
その先輩とは偶然にも同じ地域・同じ高校出身で、さらに音楽の趣味まで似ていました。
初対面のときから気さくに話しかけてくださり、「今度、一緒に古着屋行こうよ」と誘ってくれました。
当時の私はファッションにあまり興味がなく、正直、服装は“大学デビュー前の高校生”の延長のような格好でした。
しかし、その先輩はセンスが良く、おしゃれで、何より人との距離の取り方がうまい人でした。
古着屋巡りの日、先輩は私の好みに合わせながら、「こういうシャツ、似合うと思うよ」「こういう色を着ると印象が変わるよ」とアドバイスをくれました。
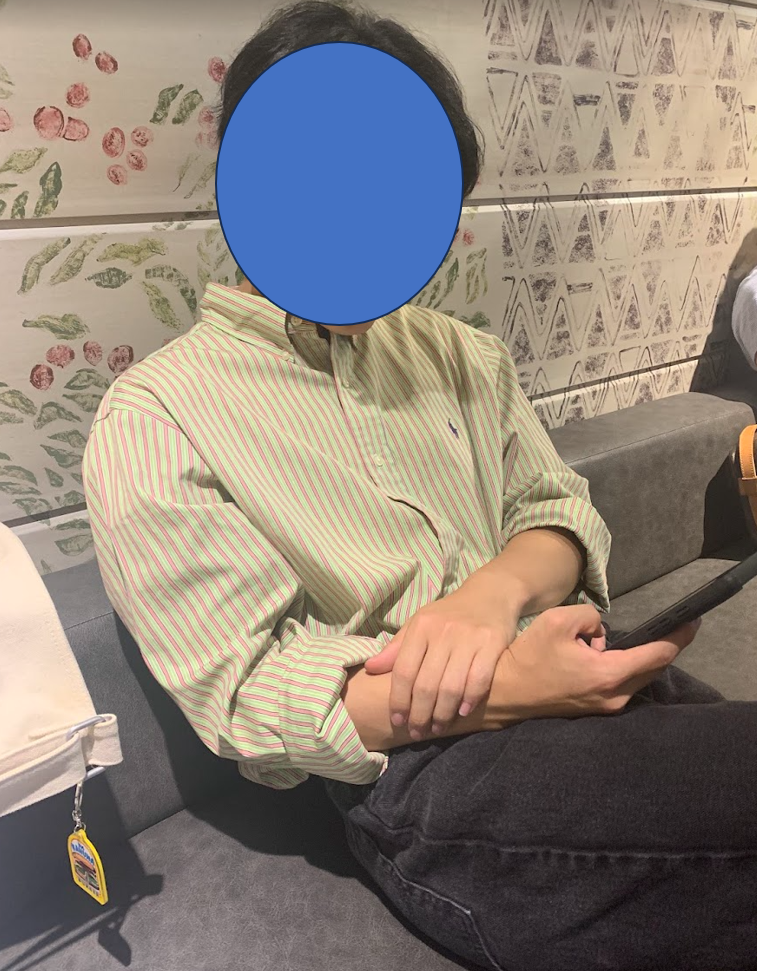
そして、買い物のあとに入ったカフェで、コーヒー代をさらりと奢ってくれたのです。
そのとき、私は少し驚きました。
私はそれまで“おごる・おごられる”という文化にあまり関心がなく、「お金は自分の分は自分で払えばいい」と考えていました。
けれどその先輩は、見返りを求める様子もなく、純粋に後輩を可愛がる気持ちで行動してくれたのです。
その優しさがとても印象的で、帰り道には自然と「こういう先輩になりたい」と思っていました。
「奢ること」は感謝と愛情の表現だった
それ以来、私は先輩にいろいろな面でお世話になりました。
ライブ前の緊張しているときには「大丈夫、誰だって最初は緊張するよ」と励ましてくれたり、大学生活の悩みを聞いてくれたりと、距離を超えて気にかけてくれました。
その姿を見て、「人に優しくすること」や「誰かの時間を少しでも使って寄り添うこと」が、どれほど相手を安心させるかを実感しました。
特に印象に残っているのは、先輩が何気なく言った一言です。
「後輩にはカッコつけたいし、こういうのは先輩の楽しみだから」
その言葉を聞いて、“奢る”という行為がただの金銭的な支払いではなく、感謝や愛情の表現であり、相手への思いやりなのだと理解しました。
それまで私は、「お金を出す=損をする」という考え方をしていたのかもしれません。
けれど、先輩の行動を見てからは、むしろ“気持ちを返すための投資”のように感じるようになりました。
今では、私もサークルの後輩にご飯を奢ることがあります。
それは単に先輩の真似をしているわけではなく、「自分もあのときの嬉しさを誰かに渡したい」という気持ちからです。
奢ることで「ありがとう」を伝えられる、支えてもらった分を次の世代に返せる――そう考えると、その行為の意味が何倍にも大きく感じます。
また、こうした関係は単なる“人の優しさ”では終わりません。
お互いを尊重し合い、感謝を伝え合う関係があるからこそ、チームとしての雰囲気も良くなり、ライブの準備や運営もうまくいくのです。
「奢り」ひとつを通して学んだのは、感謝の気持ちを“行動で示す”ことの大切さでした。
支えられた経験が「先輩としての在り方」を作った
この経験をきっかけに、私は「支えられる側」から「支える側」に意識が変わりました。
先輩が私にしてくれたように、今度は自分が後輩を安心させ、楽しませる番だと思うようになったのです。
ライブの準備で悩んでいる後輩がいれば声をかけ、一緒に練習したり、打ち上げで場を盛り上げたり。
先輩から受け取った優しさを、少しずつ自分の形で返すようになりました。
人との関わりは、相手から“受け取る”だけでは完結しません。
受け取ったものを次に“渡していく”ことで、優しさや思いやりは循環していくのだと感じます。
このサークルでの経験は、私に「人への感謝をどう行動で示すか」という生き方の軸を与えてくれました。
長期インターンで学んだ「社会で支え合う力」
社会の現場で学んだ“姿勢”の大切さ
大学3年の頃、私はWebライターとして長期インターンに参加しました。
業務内容は、SEO記事の執筆や取材記事のリライトなど。オフィスに出社し、別部屋の方や在宅の方とはSlackやZoomで日常的にやり取りをする環境でした。
最初は、プロの社会人と直接関わることに緊張していました。文章を書くこと自体は好きでも、「仕事として成果を出す」ことには責任が伴い、プレッシャーを感じていました。
そんな中、私が大きく影響を受けたのが、指導担当だった社員の方々の姿勢です。
ある日、作成した記事に誤字や表現のミスが多く、思うような評価を得られなかったとき、その社員の方はこう言いました。
「ミスをしたことより、次にどう直すかを考えることが大事だよ」
その言葉を聞いて、私はハッとしました。
学生のうちは“失敗=悪いこと”という意識が強かったのですが、社会では“次につなげる力”こそが求められるのだと感じました。
また、別の社員の方からは「どんな会社でも、大きな声であいさつし、明るくふるまうことが大切だよ」と教わりました。
オンラインの業務でも、Zoomの挨拶やチャットの一言に温かさを感じることがあり、それがチーム全体の雰囲気を左右することに気づきました。
そのとき初めて、社会での“礼儀”や“気持ちの伝え方”は、単なるマナーではなく「信頼をつくるための力」なのだと実感しました。
仲間と高め合う“チーム”のありがたさ
インターン先では、同じ大学生のメンバーが数名おり、社員の方々も含めて一体感のあるチームでした。
お互いの記事を読み合って意見を出し合い、時には励まし合いながら一緒に成長していく。
学生同士とはいえ、社会人と同じ基準でフィードバックを受ける環境はとても刺激的でした。
とくに印象的だったのは、ある社員の方の言葉です。
「このチームの強みは、“競い合う”より“高め合う”ことができることだと思う」
その言葉通り、誰かがミスをしても責めるのではなく、「どうすれば良くなるか」を皆で考える雰囲気がありました。
それぞれが違う分野を得意としていて、苦手を補い合うことでチームの全体が強くなる。まさに“支え合う職場”を体感した瞬間でした。
その経験を通じて、「支え合い」は学校やサークルの中だけでなく、社会の中でも大切な価値観なのだと理解しました。
一人で完璧を目指すよりも、互いにサポートし合うことで、より大きな成果を出すことができる。
高校時代の寮で学んだ“助け合い”が、社会の現場で“チームワーク”という形に変わったように感じました。
失敗を恐れない心が、成長を支える
インターンの中では、何度も壁にぶつかりました。
提出した原稿が差し戻されたり、想定よりも納期が早まり焦ったりすることもありました。
そんなときに心の支えになったのが、「失敗を恐れないメンタルが仕事を続ける力になる」という社員の方の教えです。
あるとき、重要な記事の構成をほとんど書き直すよう指示を受け、落ち込んでいた私にその方はこう言いました。
「完璧を目指さなくていい。失敗した分だけ、次は早く正確に書けるようになる」
この言葉がきっかけで、私は「失敗=成長のチャンス」と考えるようになりました。
その後は怖がるよりもまず“やってみる”ことを意識するようになり、結果的に作業スピードも安定して上がっていきました。
今振り返ると、この“メンタルの支え”こそが社会で働く上での最も重要な学びだったと思います。
どんなに能力があっても、挑戦を恐れていては前に進めません。
一歩踏み出す勇気をくれた社員の方々の言葉は、今でも自分の中に強く残っています。
“支えてもらう”から“支え合う”へ
この長期インターンの経験を通じて、私は社会では「支えられる側」と「支える側」が明確に分かれているわけではないと感じました。
先輩社員が私をサポートしてくれた一方で、私もチームの成果の一部を担い、誰かの役に立つ瞬間がありました。
つまり、仕事とは“支えられながら支える”連鎖の中で成り立っているのだと実感したのです。
寮での助け合い、サークルでの優しさ、そして社会でのチームワーク。
これらの経験がひとつにつながり、私は「人との関係性の中でこそ成長できる」という確信を持つようになりました。
「支えられる側」から「支える側」へ
支えられる経験が、自分を育てた
これまでを振り返ると、私の学生生活はいつも“人の支え”に恵まれてきました。
高校の寮では、同級生や先輩に助けてもらいながら生活スキルを身につけました。
大学のサークルでは、先輩の優しさや気遣いから、人との関わり方や感謝の示し方を学びました。
そして長期インターンでは、社員の方々の言葉や姿勢を通して、社会で支え合うことの意味を知りました。
どの経験にも共通していたのは、“人は一人では成長できない”ということです。
誰かの支えを受けて初めて、前に進む勇気が生まれる。
そしてその経験が、次に誰かを支える力へとつながっていくのだと思います。
私は決して特別な努力をしたわけではありませんが、支えてくれた人たちのおかげで少しずつ成長することができました。
“支えること”が喜びに変わった瞬間
大学生活の後半に入ると、私が支える立場になる場面も増えました。
サークルでは、ライブ運営で困っている後輩にアドバイスをしたり、練習方法を一緒に考えたりすることがあります。
そんなとき、ふと自分が先輩にしてもらったことを思い出します。
「かつて支えられた自分が、今は誰かの支えになっている」――そう気づいた瞬間、胸の中に温かい充実感が広がります。
また、後輩や友人に頼られるようになってから、人を支えるということは“教えること”ではなく、“寄り添うこと”なのだと感じるようになりました。
相手の立場に立って話を聞き、必要なときに背中を押す。その姿勢が信頼につながり、結果的に自分自身の自信にもなっていきました。
支えるという行為は、相手のためだけでなく、自分を成長させる行為でもあるのだと思います。
支え合う社会の中で生きていく
私はこれまでの経験を通して、「支えられる」ことと「支える」ことの両方を学びました。
どちらが上でも下でもなく、支え合うことで人は強くなり、社会は成り立っているのだと思います。
高校時代に学んだ助け合いの精神、大学での人とのつながり、インターンでのチームワーク。
それらはすべて、社会に出てからも私の根っこになる価値観です。
これから先、社会人として働く中でも、きっと壁にぶつかることがあると思います。
しかし、そのたびに私はこれまで支えてくれた人たちの顔を思い出し、今度は自分が誰かを支えられるように努力していきたいです。
「支えられる側」から「支える側」へ――その循環の中で、人とのつながりを大切にしながら生きていきたいと思います。