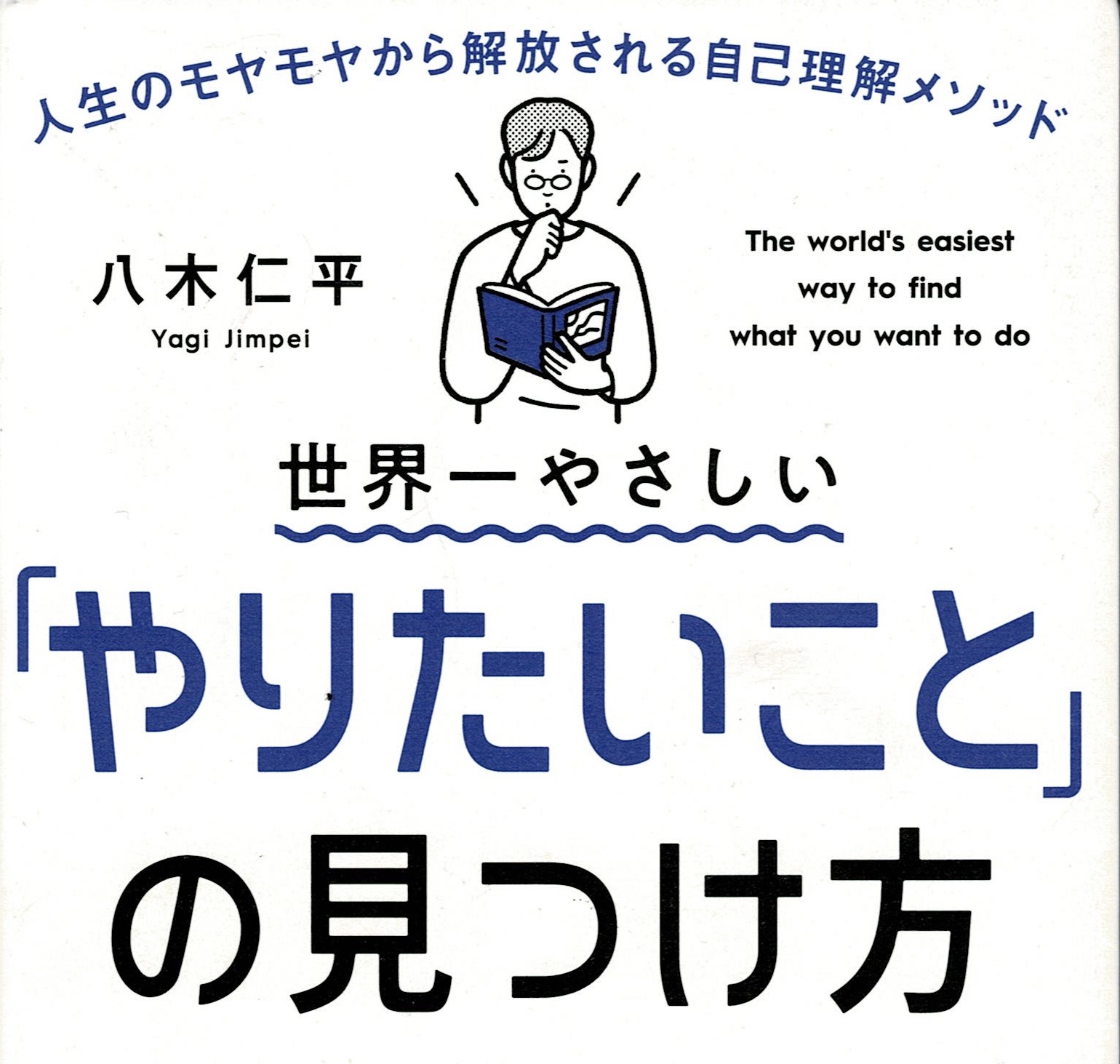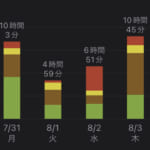「餅は餅屋に聞け」というありがたいことわざがありますよね。でもあれって、本当なのでしょうか…?
はじめまして!東京大学文学部3年のあっぱれです。
今回は『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』という本をご紹介します。
15分ほどで読めるようにまとめました。最後まで読んでいただけるとありがたいです。
文理選択。志望校選び。職業選択。
自己実現という目的のため、人は人生で様々な選択をします。
「好きなことで、生きていく」
一度きりの人生、たとえYouTuberでなくとも、自分のやりたいことをして生きていけたら素敵ですよね。
しかし現実には、何をしていいかわからない。最初の一歩が踏み出せない。
「あれ、じぶんの『やりたいこと』ってなんだっけ?」
自分の好きなことって、考えてみるとなかなか思いつかなかったりしませんか?実は私もかつてその一人でした。
しかし、この本はそんな我々の悩みを清々しいほどに払拭してくれます。
なんとこの本にかかれば誰でも、すぐに、しかも論理的に、「やりたいこと」を見つけられてしまいます。しかも必要なのはたった2つのシンプルな公式……?
今回はそんな魅力満載のこの本を解説していきます。
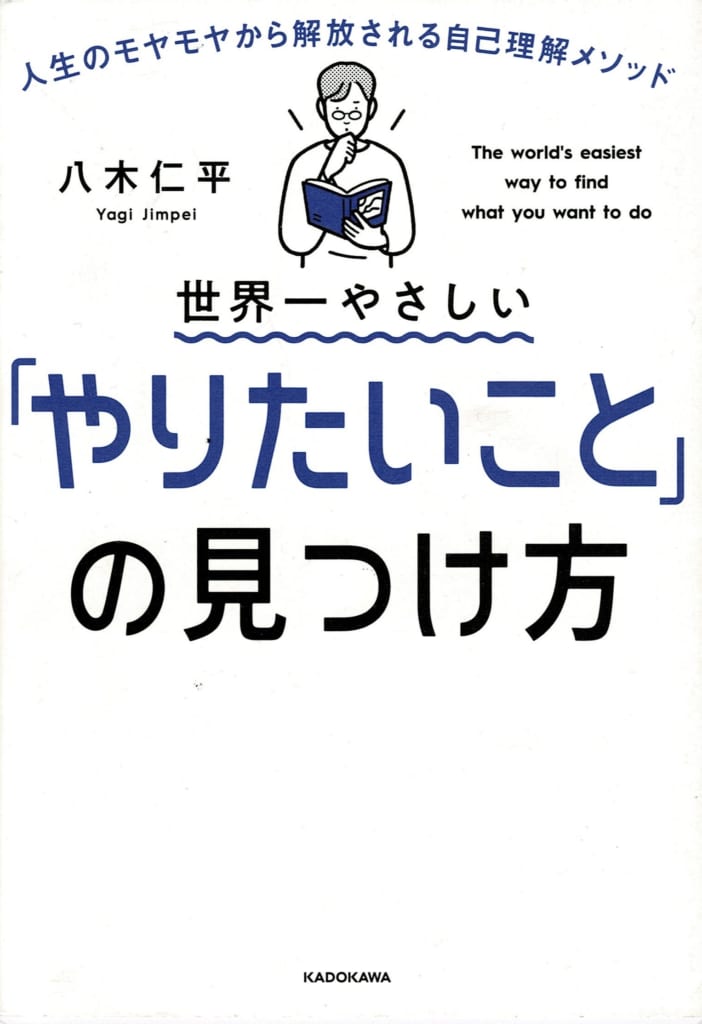
目次
「やりたいこと」がみつからない最大の原因
「可能性を広げたい!」は逆効果
考えてみれば不思議な話です。自分の好きに選んでいいはずなのに、なぜ人はやりたいことを見つけられないのでしょうか?
まだ人生経験が少ないから?
たしかに学生なんて季節で言えばまだ春、青春真っ只中です。
それとも今はまだ準備期間だから?
「選択肢を増やしたい」
「将来の可能性を広げたい」
行動力が重視されるご時世、とにかく行動を起こすことさえ心がければ、可能性が広がったように感じて何だか一安心してしまいますよね。
しかし、それこそが実は落とし穴だと筆者は主張します。
つまり、
「与えられた選択肢が多すぎること」
これこそがやりたいことが見つからない最大の原因です。
選択肢が多すぎるから人は迷い、時間を無駄にしてしまうのです。
できるだけ早くやりたいことが見つければ、そこに自分の持てるエネルギーのすべてを注ぎ込み大きく成長できる。
対して、闇雲に行動ばかりしていても、エネルギーや時間が分散される一方ですよね。
「増やす」ではなく「捨てる」
じゃあ結局何が大切なの??
それは自分の中の揺るぎない判断軸です。筆者はこれを「自分軸」と名付けます。
「やりたいことを見つける」のは選択肢を増やす作業ではなく、むしろ不要な選択肢を捨てる行為だということです。
「断ることを決める」と書いて「決断」という言葉を作った人も、そのような物事の本質を捉えていたのかもしれませんね。
「自分軸」をみつけるたった2つの公式
当たり前のことですが「自分軸」をみつけるには自分自身を深く理解する必要があります。
けれどそんなことをいきなり言われたって何から始めていいか分からない。
結局また初めの一歩が踏み出せなくなってしまう。
なにか足がかりになるものが欲しいですよね。
そんなあなたにぴったりの「公式」を2つ、ご紹介します
「好きなこと」×「得意なこと」=「やりたいこと」
「好きなこと」×「得意なこと」×「大事なこと」=「本当にやりたいこと」
たったこれだけ。物事の本質は常にシンプルです。
これなら自分でもできそう!そう思えてきますよね!
しかしながら、
「好きなこと」と「やりたいこと」って何が違うの?
「大事なこと」ってなに?
シンプルゆえにどこかぼんやりして掴みにくい感じがあるのも事実。
「好き」「得意」「大事」これらはいったいどういう意味なのか?
やりたいことをみつけるためにはここを正確に理解する必要があります。

「好きなこと」とは?
「好き」とは「知りたい」である。
あの人のことが好き!
身近な人、テレビの中の人、はたまた二次元の世界の中の人…
相手は誰にせよ誰しもそういう感情が芽生えた経験はあるでしょう。
でもその感情は言語化しようとすると案外難しい。途端に得体の知れないものになる。難しいですね、恋愛。
そもそも恋愛感情は一般化できるものではないのかもしれません。
しかし、「相手のことをどうしても知りたくなってしまう」
そこだけはどんな人にも共通するのではないでしょうか?
少々脱線してしまいましたが「好きなこと」もそれと同様です。
知りたくてたまらない
疑問を疑問のままにしておけない
そんなふうに、「意識せずとも自然と学びたくなる分野や物事」が、あなたの「好きなこと」であり、やりたいことを見つける上では「何をしてはたらくのか?」という”What”の要素になります。
どこが「好き」?
好きなこととはたらくことを関連づける上で重要なのが、
好きなことの中でもどんなことをしている時が充実しているか?
という部分まで考え抜くことです。
例えばスポーツが自分の好きなことだったとして、スポーツの何が好きなのか?
自分がプレイするのが好きなのか?
それとも観るのが好きなのか?
プレーの分析が好きなのか?
チームメイトや周りの観客との一体感が好きということもあるかもしれないですね。
このように「好きなこと」を細分化すると自分がなぜそれを好きなのかが見えてきます。
それはあなたにとって好きなものを好きたらしめているコアの部分。原因です。
この分析ができていなければ、せっかく好きなことを職業にできてもなんだか楽しくない。そんな事態に陥ってしまいます。
これはパートナーを選ぶときも同じですね。
ビジュアルだけで選んでしまうときっと長続きしないんだと思います。
いつかどこかで破綻します。知らんけど。
「得意なこと」とは?
才能=クセ
なんでそんなことできないの?
なんでそんな馬鹿なことしちゃうの?
他人に対してつい心の中でそう思ってしまった経験はありませんか?
でもそれって、裏を返せば自分には「ごく当たり前に」できてしまっているということですよね。
そういった無意識な行動や思考のパターン、つまりはクセが実はあなたの「得意なこと」であり、生まれ持った才能です。
無意識にできてしまうということはそれだけ他の人よりも優れているということであり、
クセはあなたのかけがえのない武器になります。
「得意なこと」はやりたいことを「どのような方法でやるのか?」という”How”の部分です。
才能は自分にとってあまりにも当たり前であるため、意識しないと気づきにくいです。
自分の普段の行動を注意深く観察しましょう。才能はあなたに見つかるのを待っています。
長所と短所は表裏一体
よく「自分には長所がない」という人がいます。
かくいう僕も、生まれて20年、自分に長所なんてない。それどころか短所ばっかりだ。どうすれば他の人みたいになれるのだろう。と本気で悩んできました。
ですがこの本を読んで考えが一変しました。
才能の本質は「他者との差別化」です。他の人と違うことそれ自体が才能であり、
長所・短所というのは捉え方による違いに過ぎません。
なぜなら、他者と違う=自分にしかできないことだからです。
例えば僕は様々なことをいっぺんにやる、いわゆるマルチタスクができません。
しかし見方を変えると、一つの物事に没頭できる集中力はある、ということに気付けました。
重要なのは他の人との違いを客観的に把握し、それをどのように生かしていくか、という考え方です。
「丸くなるな。☆になれ。」
これはサッポロビールのCMキャッチコピーで使われていた言葉なのですが、この本を読んだ後だと心に刺さります。他人に合わせるのではなく、自分の個性をどんどん尖らせて代わりのいない唯一無二の存在になれたら、すごくかっこいいですよね。
「大事なこと」とは?
「大事なこと」は心のコンパス
「まっすぐ自分の言葉は曲げねェ…それがオレの忍道だ」
マンガ『NARUTO』の中に登場するワンフレーズです。
僕は「大事なこと」=忍道だと思っています。
人生を通して、自分はどうありたいのか。何を大切にしたいのか。
「大事なこと」とは迷った時に進むべき方向を示してくれるもの。心のコンパスです。
先程の例で言えば、自分自身に正直でありたいというのが大事なことということになりますね。
「大事なこと」とは自分が理想だと考える状態のことであり、やりたいことを「なぜやるのか?」という理由の部分。すなわち”Why?”に対する答えになります。
マンガは人生の教科書
自分の大事なことを見つける上で僕が役立つと思うのはマンガを読むことです。マンガにはさまざまな名言が登場します。そのなかで、自分の心が激しく動かされたり、共感できるものに注目してみてください。
様々な背景を持ったキャラクターが放つセリフにはそれぞれの価値観が乗せられています。つまりそのセリフに心が動かされるということは同じような価値観を持っている可能性が高いです。
実際に「やりたいこと」をみつけてみる
自己理解メソッド(簡単3ステップVer.)
言葉の定義を自分なりに解釈できたら、実際にやりたいことを見つけてみましょう!
本では筆者の方が独自に開発された自己理解メソッドが紹介されていてそれに従って進めていけばじぶんの「本当にやりたいこと」を見つけることができます。しかし、ここで全て紹介してしまうと長くなるので、僕なりに要点を捉えた簡易版の自己理解メソッドを簡単3ステップでご紹介します。
①自分の「好きなこと」「得意なこと」「大事なこと」をキーワードで書き出す
まずは掛け算に必要な要素をどんどん出していきます。
「好きなこと」「得意なことに関しては」質より量を意識してどんどん出していきましょう。
対して「大事なこと」は自分軸の根幹です。
似たものはまとめて、上位5つほどに絞るのが理想的です。
要素をあげる時のコツとしては、自分の過去を振り返り心が動かされた瞬間に着目すると考えやすいです。
また、自分の力ではどうしても思いつかないときは思い切って友人や家族に聞いてみましょう。才能の部分でも触れたように、自分のことって案外周りの人の方がわかっていることも多いです。
②「好きなこと」×「得意なこと」でやりたいことの仮説をたくさん出す
次は「好きなこと」と「得意なこと」で出したキーワードをかけあわせて、
どんなことができそうかのアイデアを出します。
可能性にとらわれずいろいろな組み合わせを試してみましょう。
例えば僕が実際にやった例では、
「表現」×「共感力」「聞き上手」=「人から面白い話を引き出して発信する」
「教育」「人生観」×「状況整理」「計画力」「目的志向」=「人の人生設計の手助けをする」
などが出ました。
このように仮説は具体的な職業でなくて全く構いません。可能性を狭めずにたくさん仮説を出しましょう。
③やりたいことの仮説を「大事なこと」のフィルターにかけてみる
最後に仮説案の選定作業に入ります。
「大事なこと」はいわば人生の目的、あなたの理想状態です。
先ほどの仮説と照らし合わせ、
「それをやることで自分の大事なことを達成できそうか」
という判断基準で選別していきます。
いくつかの案に絞り込むことができたら、今度は「周りの人々にどのような影響を与えることができるか」という判断基準を使ってみましょう。
はたらくとは相手に価値を提供してその対価としてお金を受け取る行為です。ただ自分がやりたいから、という自己満足の頑張りでは周囲の人に価値を与えることはできません。
自分軸はアップデートし続ける
いかがでしょうか、だいぶ簡略化されてはいますが、自分の本当にやりたいことが今までよりも数倍はっきりと像を結んできたのではないでしょうか?
でもまだこれが本当にやりたいことなのか確信できない…
問題ありません!この自己理解メソッドは自分のエネルギーを向ける大まかな方向性を提示してくれるものに過ぎないからです。
あとは実際に行動あるのみ!細かな軌道修正は行動を起こす中で適宜行っていきましょう。
Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)
これはPDCAサイクルと呼ばれます。実行に対するフィードバックの繰り返しで人は成長します。
たとえまた道に迷ったように思えても、今のあなたには揺るぎない自分軸があります。ただ、自分軸は揺るぎないですが「不変」ではありません。
自分の変化に合わせて常にアップデートし、ほんとうにやりたいことを探求し続けましょう。
終わりに
いかがでしたでしょうか?
今回は『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』を解説しました。
内容を簡単にまとめると、
・重要なのは選択肢を増やすことではなく捨てるための判断軸を身につけること
・判断軸はあなたの「好きなこと」「得意なこと」「大事なこと」でみつかる
・判断軸が備わればあとは行動するのみ!PDCAサイクルを回していく!
ということになります。
自分の人生を豊かにするために一番理解しなくてはいけないのは間違いなく自分です。
でも、自己理解って簡単なようで意外と奥深いものなのです。
自分のことは自分に聞いても意外とよく分かりません。
だからこそ専門家が書いた本や周りの人に頼ることは自己理解において想像以上に有意義なことだと僕は考えています。
「餅は餅屋」
当たり前のように思えることも案外そうとは限らないのではないでしょうか。