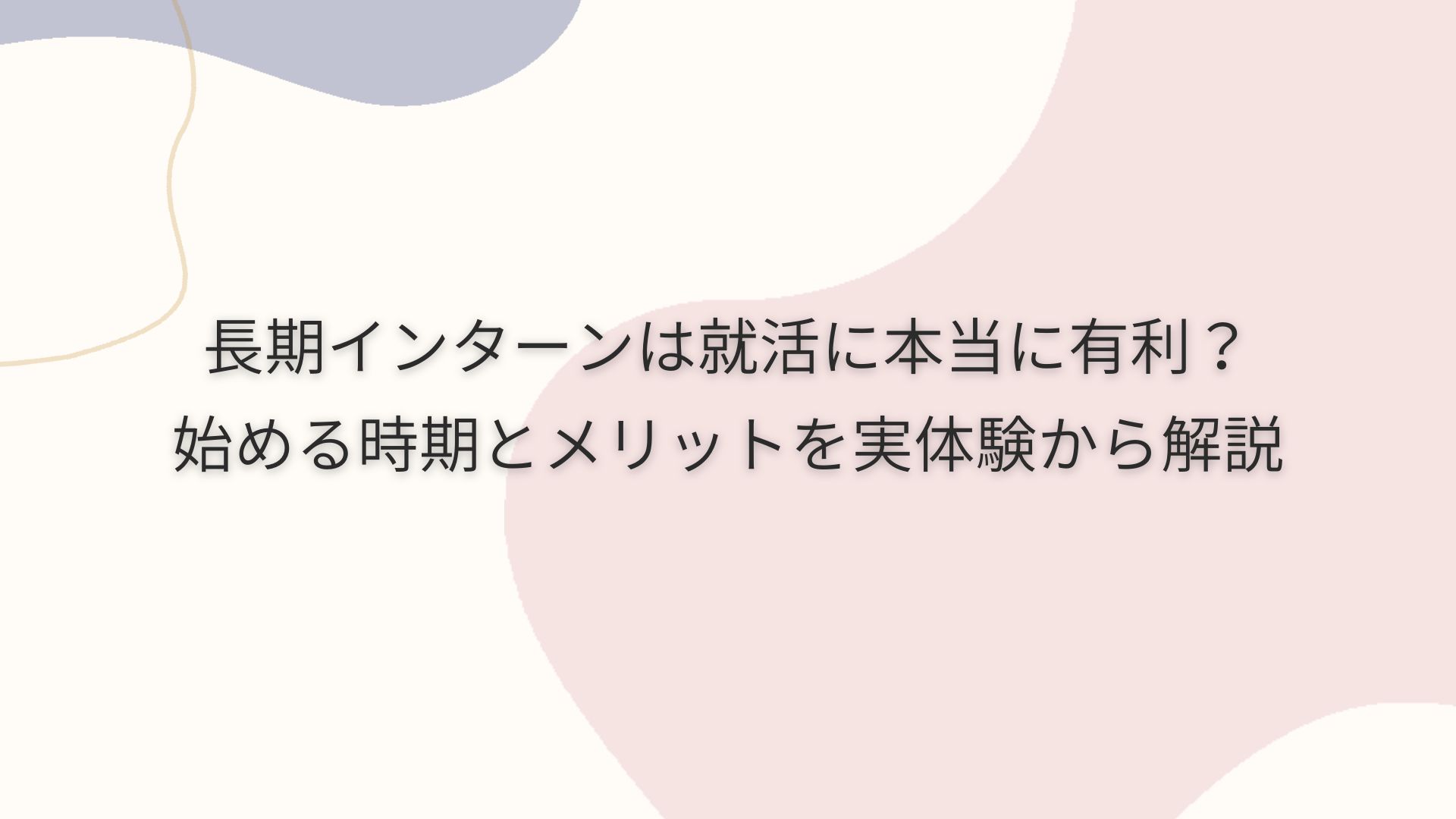こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。
「長期インターンって就活に有利なの?」
この質問、大学生になれば一度は耳にするはずです。
実際、僕も大学2年の夏にWebメディアの長期インターンを始めたとき、そんな下心がゼロだったとは言いません。

だけど、実際にやってみて思ったのは、「就活に有利になるかどうか以上に、得られる経験の中身がとてつもなく濃い」ということでした。
就活で多くの企業が重視するのは、「チームで協力しながら成果を出した経験」や「自ら考え、行動した経験」です。
そういった力は、アルバイトでも得られないわけではありませんが、長期インターンではより実践的で責任ある立場での挑戦ができるため、就活の場でも語りやすいエピソードに繋がります。
ただし、長期インターンに飛びつけばいいというわけでもありません。やりたいことが他にあるなら、サークルや学内の活動に打ち込むことだって立派な選択肢です。
大切なのは、「自分がその経験から何を得たいか」を考えること。
この記事では、就活のリアルな場面で長期インターンがどう役立つのか、逆に「意味がない」と感じたことは何か、何年生から始めるのがベストなのかなどを、実体験と周囲の事例を交えて詳しく紹介していきます。
目次
長期インターンは就活に有利?|企業が見ているのは“中身”
「インターンをやっていれば就活で有利になる」
これは半分本当で、半分は誤解です。
企業の採用担当者が重視しているのは、「インターンをやったかどうか」ではなく「インターンで何を学び、どう行動し、どう考えたか」という部分。
つまり、形式よりも“中身”です。
協調性・主体性・リーダー経験は就活の定番評価項目
ほとんどの企業が選考でチェックするのが、次のような資質です。
- チームの中で周囲と協力しながら動ける力(協調性)
- 自ら課題を見つけ、考え、行動に移せる力(主体性)
- 他人を巻き込みながら何かを前に進める力(リーダーシップ)
これらは、「会社に入ったら活躍できるか?」という視点から問われるものであり、どんな企業・業界でもほぼ共通して見られます。
特に、「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」の質問では、アルバイトでの頑張りやサークルでの経験がよく語られますが、その内容が“受け身”に終始していた場合、面接での印象はやや弱くなってしまうこともあります。
長期インターンは「語れる経験」が生まれやすい
長期インターンの強みは、より実践的な環境の中で、自分の役割と責任を持って動く経験ができることです。
僕が参加していたWebメディアの長期インターンでは、記事の執筆だけでなく、構成提案や編集会議への参加など、「考えて動くこと」が求められる場面が日常的にありました。
特に印象的だったのが、2023年に生成AI(ChatGPT)が話題になり始めた頃のことです。
当時、インターン生同士で「記事執筆にAIを活用できないか?」という話になり、僕を含む数人でAIツールの特性を調べ、「構成案の叩き台づくり」や「見出し案のブレストへの活用方法」などを資料にまとめて、社内チャットに提案しました。
ただ言われたことをこなすだけでなく、社内の課題を見つけ、自分たちで考えて提案する——そんな経験が学生でできる機会は、そう多くありません。
この経験は、後の就活の面接で「主体的に動いた経験を教えてください」と聞かれたときにも、自信を持って具体的に話すことができました。
インターンは、「自分で考えて動いた経験」が自然と蓄積する場
バイトやサークルでも頑張ることはできますし、評価される経験を積むこともできます。
ただし、与えられた枠の中で動くことが多く、自分で意思決定をする場面は少ないのが現実です。
その点、長期インターンでは、
- どう進めるか自分で考える
- 意見を出すとフィードバックが返ってくる
- チームの中で「○○担当」として責任を持つ
こうした経験が自然と積み重なっていきます。
僕自身、記事のテーマを考える際に「今このジャンルで何が読まれているか」を徹底的にリサーチし、上司に提案したことがありました。
その記事が公開後、検索順位で上位に入り、多くのPVを集めたときには、ただ嬉しいだけでなく、「自分の考えが誰かの役に立った」という手応えをはっきり感じることができました。
これは、バイトではなかなか得られなかった感覚でした。
就活で問われるのは、「どういう行動をして、どう学んだか」
就活では、「なぜそう考えたのか」「なぜその選択をしたのか」「そこから何を学んだのか」という“プロセス”が見られます。
長期インターンではそのプロセスに主体的に関われる機会が多く、だからこそ、就活の場面でも深みのあるエピソードとして語ることができるのです。
長期インターンとバイト、どちらが就活で有利か?
「アルバイトでも就活で語れる経験になる」とよく言われますし、それは事実です。
でも、長期インターンと比べたとき、どちらがより“就活の武器”になるかと考えると、やはり違いははっきりと存在します。
ここでは、就活という視点から、アルバイトと長期インターンそれぞれの特性を比べてみます。
「役割の深さ」が大きく違う
まず大きな違いは、仕事上の“役割”の深さです。
アルバイトでは、マニュアルに沿って決まった作業をこなすことが多く、どんなに真面目に取り組んでいても、「チームの戦略を考える」「何かを改善する提案をする」といった場面はほとんどありません。
僕が大学1年のときにやっていた「カクヤス」の配達バイトもまさにそうでした。
ルートを回って商品を届ける、空いた時間は品出しやレジ対応。責任感は求められますが、自分で判断して行動する場面はほとんどなく、「任された仕事を確実にやる」ことが第一でした。
一方で、長期インターンは違います。
業務に慣れてくると、「こうした方がいいかも」「次はこんな記事を提案してみよう」といった“自分から動く余地”が大きく、行動次第で役割の幅も広がっていきます。
実際、僕はライターインターンとして働く中で、他のインターン生と一緒に「社会情勢の変化に合わせて求められる記事の内容も変わってくるのではないか」と考えて調査を行い、新たなジャンルを発掘すること社内で提案したことがありました。
これはバイトでは絶対に経験できなかった、「チームとして何かを生み出す」経験でした。
就活で問われる“深掘り質問”に強くなれる
就活では、「ガクチカ」のエピソードが聞かれた後に、必ずといっていいほど深掘り質問が飛んできます。
- なぜその方法を選んだの?
- チームメンバーとの対立はなかった?
- あなた自身の役割は何だった?
- 成功した要因は何だったと思う?
こうした質問に対して、アルバイト経験だけだと「ただ頑張った」「丁寧に接客した」という抽象的な回答になりやすい傾向があります。
それに比べて、長期インターンでは、「自分が何を考え、どんな工夫をして、どう周囲と動いたか」というストーリーが自然に生まれやすく、質問にも具体的に答えられることが多いです。
僕の場合、面接で「その提案はどうやって社内に共有したんですか?」と聞かれたとき、Slackでの社内発信や、AI活用のリスクもあらかじめまとめて提示したことを詳しく話せたことで、面接官の表情が変わったのを覚えています。
バイトでも活かせる経験はあるが、“打ち手の多さ”が違う
もちろん、バイトでも評価される経験はあります。
例えば、
- 飲食店で新人教育を任された
- 繁忙期のオペレーション改善を提案した
- 常連のお客様と信頼関係を築いた
こうした経験は就活でも十分に武器になります。
ただ、それは“限られた枠の中で”どこまで工夫したかという話であり、長期インターンの方がそもそも任される領域や裁量が大きい分、挑戦できる打ち手が多いという違いがあります。
「どうせ働くなら、少しでも成長につながる方がいい」
そう思うなら、長期インターンを検討してみる価値は十分にあると思います。
どんな場面でインターン経験が活きるのか?
「インターンって、就活でどう役立つの?」
という疑問はとても多いです。特に、学年が上がるにつれて「この経験をどうアピールに変えるか」を意識するようになります。
実際に就活を経験してみて、僕が感じたのは、長期インターンでの経験は想像以上にいろいろな場面で活きるということ。
ここでは、具体的にどんな場面で強みになるのかを紹介していきます。
エントリーシート(ES)の「ガクチカ」欄での説得力
ES(エントリーシート)では、必ずと言っていいほど「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」が問われます。
このとき、長期インターンの経験は非常に“語りやすい”エピソードになります。なぜなら、仕事の中で達成した成果・工夫した点・チームとの関わりなど、ESに必要な構成要素が自然と揃っているからです。
たとえば僕の場合、ESでは「生成AIの導入を提案し、記事構成の効率化に成功した経験」をガクチカとして書きました。
このエピソードは以下のように構成できます。
- 背景:ChatGPTが話題になり始めた2023年春
- 課題:構成づくりに時間がかかっていた
- 行動:チームでの調査と提案資料作成、社内共有
- 結果:実際に一部導入され、作業の効率化につながった
このように、「課題→行動→結果」という一貫したストーリーが作りやすいのが長期インターンの強みです。
面接での深掘りにも強くなれる
ESを通過しても、次に待っているのが面接です。
ここでは、「あなたが書いたこの経験について詳しく教えてください」と、深掘りされることがほとんど。
その際、長期インターンでの経験があると、実際に自分が下した判断や乗り越えた壁について具体的に語れるため、説得力が一段違います。
たとえば先述のAI導入の話では、「チーム内で意見が分かれたとき、どうやってまとめたのか?」「リスクはどう管理したのか?」といった質問に対して、Slackでのやりとりやリスク整理の具体例を挙げて答えることができました。
単なる「いい経験でした」ではなく、リアルな判断や試行錯誤を話せるのが、面接での大きな強みです。
志望動機や業界選びの「根拠」になる
長期インターンの経験は、自分がどんな仕事にやりがいを感じるのか、どんな環境で力を発揮できるのかを考えるうえでも大きなヒントになります。
実際、僕自身はこのライターインターンを経験したことで、「情報を整理し、伝えること」に面白さを感じるようになり、コンテンツ制作や広報・編集といった分野に関心を持つようになりました。(最終的な入社先は別業界ですが…)
こうした背景があると、志望動機を問われたときにも、
「大学2年からWebメディアで長期インターンを行い、読者目線で記事を設計する面白さを感じました。自分の言葉で誰かに価値を届ける仕事に、本気で向き合いたいと感じています。」
というように、“経験に基づいた動機”を語ることができます。
これは、調べただけの志望動機とは明確に違う、説得力のあるアピールになります。
自己理解の材料にもなる
さらに言えば、就活は“自分を知ること”の連続でもあります。
長期インターンを経験すると、自分が得意なこと・苦手なこと・頑張れる環境・合わない働き方などがリアルに見えてきます。
「ひとりで黙々と作業するよりも、チームで進める方が好きかも」
「短期集中より、じっくりやる仕事の方が向いている」
こうした自己理解があると、ミスマッチの少ない志望先選びにもつながるのです。
「やればいい」わけじゃない?|意味が薄れるケースとは
ここまで、長期インターンのメリットや就活での活かし方を紹介してきましたが、「長期インターンは必ずやるべき」「やれば誰でも就活に強くなる」というのは、やや過剰な期待です。
実際、周囲を見渡すと、「インターンやったけど就活では全然使えなかった」「むしろサークルや学内活動の方が印象が良かった」というケースも少なくありません。
では、どんなときに“意味が薄れる”のか? そして、どうすればそうならずに済むのか?そのポイントを見ていきます。
ただ「作業をこなしただけ」では武器にならない
インターンに参加していても、ルーティン作業だけで終わってしまい、「何を考えて、どう動いたか」が語れないままの人は少なくありません。
たとえば、SNS投稿をひたすら予約するだけ、記事をマニュアル通りに書いて提出するだけ――こうした業務に慣れるだけで満足してしまうと、就活の場で問われる「主体性」や「工夫」「成長のプロセス」を語るのが難しくなります。
これは、僕自身もインターン初期に痛感した部分です。
最初の頃は「言われた通りに仕上げればOK」と思っていたのですが、それではいつまで経っても“自分の視点”が入らない。
「なんのためにこの記事を書くのか?」「どうすればもっと読まれるか?」を考え始めてから、ようやく提案や議論ができるようになり、チームの中で役割が生まれ、責任感も変わっていったのを覚えています。
目的がズレると、ただの“消耗”になりやすい
「就活に有利って聞いたからなんとなく始めた」
そんな動機でインターンを始めると、途中でモチベーションが続かなくなることがあります。
長期インターンはたしかに貴重な経験ができますが、地味な作業も多く、地道に継続しないと評価されるまで時間がかかることも多いです。
成果がすぐに見えるわけではないため、「これって本当に意味あるの?」と不安になることもあります。
実際に僕の知人でも、興味のない業界でインターンを始めてしまい、「全然面白くないし、時間がもったいなかった」と言って半年で辞めた人がいました。
無理してやるくらいなら、サークル活動やアルバイトでしっかり責任あるポジションに挑戦する方が、満足度も就活効果も高い場合が多いです。
サークルや学内行事でも十分な“語れる経験”は作れる
就活対策だけを考えるなら、長期インターンだけが正解ではありません。
たとえば、早稲田のようにサークル活動が活発な大学では、サークルでイベント運営をしたり、広報を担当したり、代表を務めたりする経験が、十分に“就活で語れる”内容になります。
実際、僕の周囲でも、サークルの早稲田祭企画運営や、ボランティア活動、ゼミのプロジェクトなどで内定を勝ち取った人はたくさんいます。
要は、「長期インターンをやっているか」ではなく、「自分の意志で行動して、その中でどんな壁を越えたのか」というストーリーが大切なのです。
長期インターンを選ぶなら、「やってみたい」で選ぼう
だからこそ、長期インターンを選ぶ基準は「就活に有利そう」よりも、「この仕事、ちょっと面白そう」「やってみたいかも」の直感でいいと、僕は思っています。
本当にやってみたいと思える内容であれば、自然と工夫もするし、成果にもつながる。そして結果的に、就活で話したくなるような“自分だけの経験”になっていくのだと思います。
いつから始めるのがベスト?|学年別のメリットと注意点
長期インターンに興味を持ったとき、多くの学生が気になるのが「いつから始めればいいのか?」というタイミングの問題です。
その答えは人によって異なりますが、“何のためにインターンをやるのか”という目的を明確にすることが、最も大切なポイントです。
特に知っておきたいのは、長期インターンと短期インターンの“選考直結度”の違い。
この違いを理解しないまま動くと、「頑張ったけど志望業界に直結しなかった」と後悔することもあります。
長期インターンは“ベンチャー志望・起業志望”向きの選考直結ルート
長期インターンは、スタートアップや中小のベンチャー企業で募集されているケースが圧倒的に多いです。これらの企業は、インターン生を“即戦力”として育成し、将来的に採用に繋げることを前提にしている場合もあります。
実際に、僕のインターン先でも、編集業務やメディアディレクター業務を経て、そのまま内定を出された先輩がいました。
特に、以下のような学生は長期インターンの現場で評価されやすく、選考直結になるケースが多いです。
- 将来的に起業やフリーランスを考えている
- ベンチャー企業のスピード感・裁量の大きさに魅力を感じる
- 特定の職種(エンジニア・マーケ・ライターなど)で早期に実力をつけたい
このように、長期インターンは「採用に繋がることもある」実践の場です。
一方、大企業志望なら“短期インターン”が選考直結になる
一方で、商社・メーカー・金融・広告・ITなど、いわゆる「大企業」志望の学生にとっては、長期インターンは直接的な採用ルートにはなりにくいのが現実です。
大手企業の多くは、選考直結の枠を夏・秋・冬に実施される1day~1weekの“短期インターン”に集中させており、エントリーシートやWebテストを通過しないと参加すらできないこともあります。
つまり、大企業志望の学生にとって、長期インターンはあくまで“ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)”の材料や、「自分の適性や興味を試す場」としての役割が大きいのです。
もちろん、長期インターンの経験が大企業の選考でまったく無意味ということではありません。
リアルな業務経験を語れることは大きな強みになります。ただし、採用に直結する“ルート”は短期インターン側にある、という違いは押さえておくべきです。
学年別に見る、インターンの目的と始めどき
ここまでの違いを前提としたうえで、学年別に「どう動くべきか」を考えてみましょう。
【大学1〜2年生】将来の軸を探る“お試し期間”
- 時間の余裕があるので、興味のある業界や職種を試すにはベストタイミング
- 長期インターンで自分の「向き・不向き」に気づけることも多い
- 「何となく就活に有利そう」という理由で選ばず、“やってみたい”という気持ちを大切に
【大学3年生】就活本番前の“戦略的な時期”
- 夏から冬にかけて、大手企業の短期インターン選考が本格化
- 大企業志望なら短期インターン対策に注力すべき時期
- ただし、志望業界とマッチした長期インターンを並行できれば、ESや面接で語れる経験としては非常に有効
- ベンチャー志望者にとっては、この時期の長期インターンが「最終選考」に繋がる可能性もあり
【大学4年生】実務経験を深めるor最後のチャンス
- すでに内定を得ている場合は、入社前にスキルを伸ばす“プレ就業”として活用
- 未内定の人にとっては、“長期インターン経由での逆転内定”を目指せる貴重な期間
- ただし、卒論や就活本番と重なるため、体力的にはややハード
目的と志望業界に合わせて、最適な動きをしよう
長期インターンを“就活に直結する手段”とするか、“経験と成長の場”とするかは、志望業界・職種・自分の志向次第です。
- ベンチャー志望、または起業・独立志向 → 長期インターンが選考直結になりやすい
- 大企業志望(総合職や本部職) → ガクチカ作りに活用しつつ、本命は短期インターン対策
どちらを選ぶにせよ、「とりあえずやる」ではなく、自分の目的と照らし合わせて動くことが成功の鍵です。
長期インターンで得られた本当の価値
ここまで、長期インターンが就活にどう役立つのか、いつ始めるのがいいのか、どんな注意点があるのかを見てきました。
でも、振り返ってみて僕が一番実感しているのは、「長期インターンをやってよかった」と思える理由は、就活に役立ったこと以上に、“自分自身の変化”にあるということです。
自分の「得意」や「好き」が見えてくる
僕がインターンを始めたきっかけは、「文章を書くのが好き」という漠然とした感覚でした。

でも、実際にライターとして何十本も記事を書いていく中で、読者のニーズを考えたり、情報を調べて構成を作ったり、SEOを意識したタイトルを考えたり――そうした工程に意外なほど夢中になっている自分に気づきました。
「これ、意外と向いてるかも」
そう思えた経験は、自分の中で大きな自信になりました。
インターンを通じて、「仕事」としての文章作成を経験したことで、「趣味」だったものが「キャリアの軸」になり得ることを初めて実感できたのです。
社会人の思考や姿勢に触れることで、自分の“甘さ”にも気づけた
インターンをしてみて気づいたのは、社会人の考え方や責任感は、大学生のそれとは全然違うということです。
締切を守ること、相手の立場を考えて発信すること、スピードとクオリティの両立――当たり前だけど、難しい。
最初のうちは何度も修正を求められ、納期に間に合わずヒヤッとしたこともありました。
でもその分、少しずつ「人に迷惑をかけない」「結果を出すために動く」ことを意識できるようになり、社会人としての土台ができた気がしています。
面接で“話せる”ようになっただけでなく、“自信を持って話せる”ようになった
もちろん、長期インターンの経験は就活でも大いに役立ちました。
ESで語れる「ガクチカ」ができたことも、面接で「チームで動いた経験」や「自ら考えて提案したエピソード」を話せたことも、評価につながったと思います。
でも、それ以上に大きかったのは、「あ、これは本当に自分がやってきたことだ」と、胸を張って話せる経験ができたこと。
言葉に“重み”が出る。
質問されても、焦らず自分の言葉で語れる。
これこそが、就活において一番の強みになると感じました。
「やってよかった」と言える経験は、就活の“その先”でも活きる
長期インターンで得た経験は、就活が終わった後も自分の中に残り続けます。
どんな職場に入っても、初めての業務、初めてのチーム、初めてのプレッシャーに直面することはあるでしょう。
そんなとき、「あのとき、インターンで乗り越えたじゃん」という過去の自信が、“これから”を支えてくれるのだと思います。
最後に:就活のためにやるんじゃない。“やってよかった”と思えるかどうかがすべて
就活のために長期インターンをやるのもいい。
でも、本当の意味で自分の成長や発見につながった経験こそ、結果的に就活でも、人生でも武器になる。
そう実感しています。
迷っているなら、まずは気になる企業のインターン募集をのぞいてみるだけでもOK。
もし「やってみたいかも」と思えるものがあれば、ぜひ一歩踏み出してみてください。
大学生活に、“働く”という新しい視点が加わったとき、自分の未来が少しずつ見えてくるはずです。