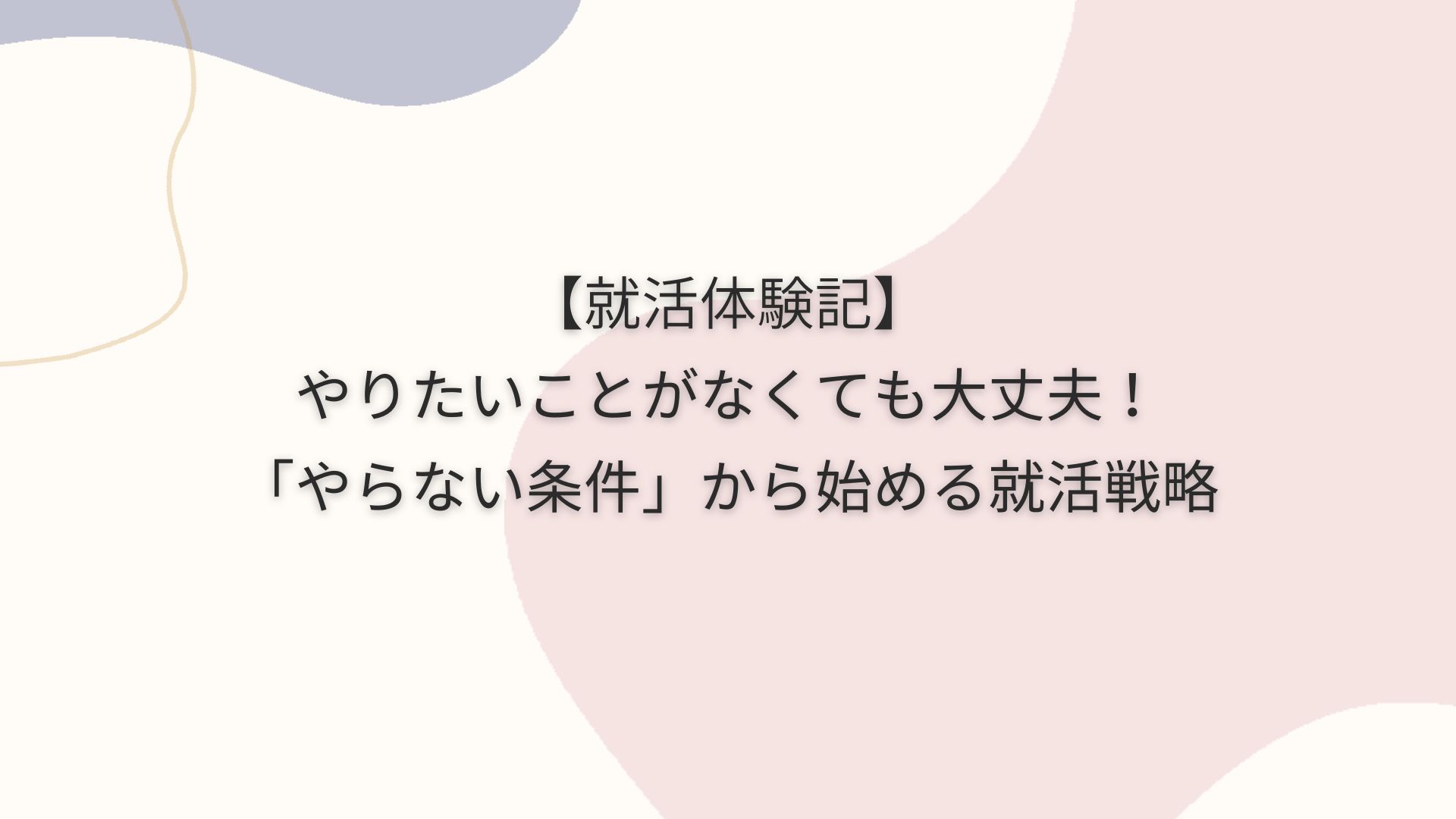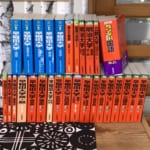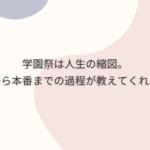「就活」という言葉を耳にすると、多くの高校生は「やりたいことが見つかっていないと大変そう」と不安になるのではないでしょうか。
大学に入れば自然と夢が見つかると思いきや、実際はそう簡単ではありません。私自身も、就活を始める大学3年の春になっても「自分は何がやりたいのか」と問われると、正直なところ答えられませんでした。
そんな中で救われたのが「やりたいことを探すのではなく、やらないことを決める」という考え方でした。
世の中には無数の業界・職種がありますが、自分が絶対に避けたい働き方を先に言語化すると、驚くほど視界がクリアになります。
たとえば私は「全国転勤は嫌」「営業でノルマを追い続けるのは向いていない」「ブラックな働き方はしたくない」というNG条件をリストにしました。
すると、残された候補の中に“自分が納得できる働き方”が自然と浮かび上がってきたのです。
この方法は、特に「やりたいことがない」という学生にとって大きな武器になります。
この記事では、私が実際に経験した「やらない条件から始める就活戦略」について詳しくお話しします。
目次
「やりたいことがない」は普通のこと
大学生の多くは「明確な夢」を持っていない
高校のとき「大学に進学すれば、自分が一生やりたい仕事が自然と見つかるだろう」と思っていました。
しかし、実際に早稲田に入学してみると、必ずしもそうではありませんでした。
もちろん「国際機関で働きたい」「弁護士を目指す」といったはっきりした夢を持つ友人もいましたが、それは全体のごく一部。
3年生の春になり、就活の話題が周りでどんどん出てくるようになると、ようやく「自分は何をしたいんだろう?」と焦りを感じ始めたのです。
「やりたいことがない=就活で不利」ではない
「やりたいことが見つかっていないと、エントリーシートや面接で答えられないのでは?」と不安に思う人は多いでしょう。
確かにESや面接の場では「将来の目標」「入社後にやりたいこと」を問われるため、「転勤が嫌です」「営業は苦手です」といった本音をそのまま伝えるのはNGです。
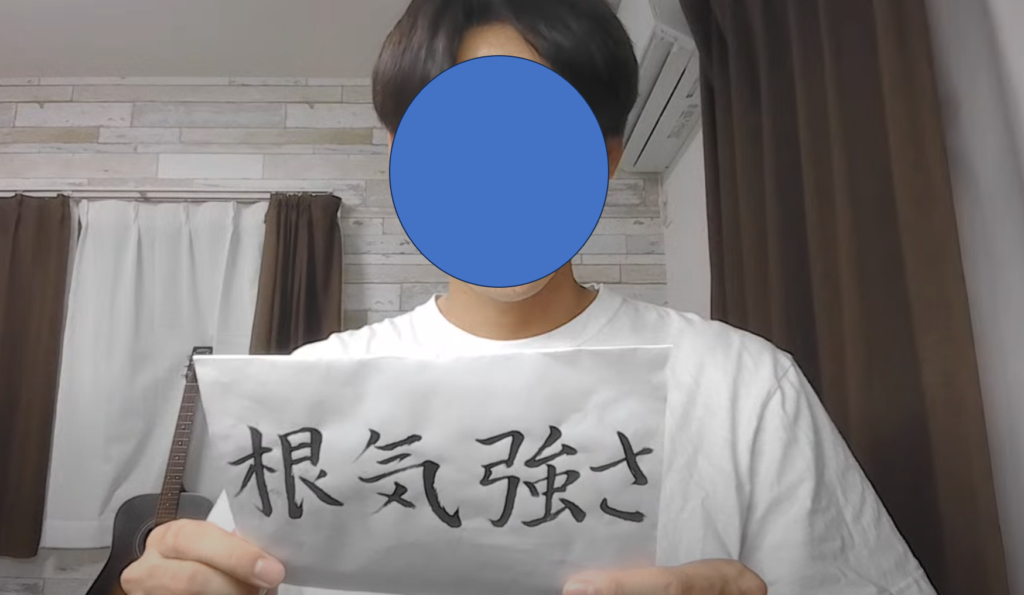
では「やりたいことがない」学生はどうすればよいのでしょうか。
企業探しの段階では本音の条件(転勤は避けたい、残業は少ないほうがいい等)で絞り込むことが大切です。
そのうえで、候補に残った企業については「その会社が目指す方向性」と「自分の強み・価値観」を掛け合わせて、志望動機や将来像を“逆算して作る”ことが必要になります。
私自身も、就活序盤では「リモート勤務があるか」「全国転勤がないか」といった条件で候補を絞り込みましたが、面接の場では「ITを通じて社会課題を解決したい」「首都圏で腰を据えてキャリアを築きたい」という形に言い換えて伝えました。
こうした表現に直すことで、企業の求める人物像と自分の本音を矛盾なくすり合わせることができたのです。
大切なのは、本音で候補を絞り込み、建前では前向きな志望動機として語るという切り替え方を知っているかどうか。
これを理解していれば、就活を不安に感じる必要はありません。
「やりたいことがない」からこそ広く見られる強み
それは、特定の業界に固執せず、フラットな目線で多様な企業を見られることです。
私は、当初は「文系だから金融かメーカーに進むのかな」と漠然と考えていました。
しかし、実際に企業研究を進める中で「転勤が少ない」「リモート勤務が可能」「ワークライフバランスが取れる」という条件を大切にしていった結果、意外にもIT業界やコンサルティング業界と相性がいいことに気づきました。
最初から「この業界しか見ない」と決めつけていたら、おそらくその選択肢にはたどり着けなかったでしょう。やりたいことが決まっていないからこそ、柔軟に業界を見比べられたのだと思います。
友人たちも「ゼロからのスタート」だった
特に印象に残っているのは、同じ学部の友人Aのケースです。彼は部活に全力を注いでいたため、就活解禁の3月1日まで企業研究を全くしていませんでした。そのため本人も「自分は完全に出遅れている」と不安を抱えていました。
しかし、彼は就活を始めてから「やりたくないこと」を整理することに集中しました。転勤の多い業界は避けたい、営業ノルマが厳しい職種は向いていない、と条件を定めていったのです。すると自然に候補が絞れ、大手メーカーの事務系職種に的を絞ることができ、最終的には内定を獲得しました。
もう一人の友人Bは、逆に「やりたいことがある」と言っていたタイプでした。彼は「広告業界に絶対行きたい」と言って何社も受けていましたが、倍率が非常に高く、結果的に全滅。途中で方向転換を余儀なくされていました。
対して「やりたいことゼロ」からスタートした友人たちは、柔軟に志望先を広げられたため、意外と早い段階で納得できる内定を得ていました。
このように、「やりたいことがない」ことは決してハンデではなく、むしろ視野を広く持てる強みになるのです。
「やらない条件」を洗い出す
就活を始めると「志望動機を語れ」「やりたいことを言え」と言われますが、最初からスラスラ出てくる人はごくわずかです。
そんなときに役立つのが、逆に「やりたくないこと」を明確にしていく作業です。
私自身、大学3年の春に就活を始めたときは「やりたい仕事」が全く見えませんでした。
でも「これは嫌だ」という気持ちはすぐに浮かんできました。

一見ネガティブに聞こえるかもしれませんが、むしろこうした“違和感”を言語化していくことが、就活の最初の一歩になります。
NG条件をリストアップしてみる
具体的にどんな「やらない条件」があるのか、私が実際に書き出した例を紹介します。
- 全国転勤がある会社は避けたい
- 体育会系のようなノルマ営業は自分には合わない
- 毎日出社必須よりも、リモートや柔軟な働き方がある方がいい
- 残業だらけで「寝るためだけに帰宅」という生活はしたくない
- 初任給が極端に低い会社は不安
このようにリストアップしてみると、自然と「候補外の業界・職種」が浮かび上がってきます。逆に言えば、それを除いた残りの中から探せばいいわけです。
たとえば「転勤なし」を条件にすると、全国に支店を持つ総合商社や大手メーカーは候補から外れました。
一方で、首都圏中心で働けるIT業界や金融系、コンサルティング会社が残る。こうして選択肢が少しずつ整理されていきました。
条件を絞ったら見えてきた意外な業界
当時の私は、正直「IT業界は理系の世界」と思い込み、ほとんど興味を持っていませんでした。
でも「転勤がない」「リモート可能」「ワークライフバランスが取りやすい」という条件で探していくと、自然にIT企業が候補に残るようになったのです。
実際に説明会やインターンに参加してみると、想像していた“難しいプログラミングをひたすらやる世界”ではなく、文系でも活躍できる企画やマネジメント系の仕事も多いことを知りました。
結果的に、そこからSIerや通信系の企業に興味を持ち、最終的に内々定をもらうことができました。
逆に、最初は憧れていた不動産ディベロッパー業界は「転勤が0ではない」「激務になりやすい」という理由で自分には合わないと判断しました。もし「やりたいこと」だけで動いていたら、入社後に後悔していたかもしれません。
周囲の友人のNG条件エピソード
- 友人C(文系男子):彼は「営業だけはやりたくない」と強く思っていました。その結果、最初はメーカーの事務職を志望していたのですが、説明会を受けるうちに「社内SE」や「コンサル」のほうが合っていると気づき、最終的にシステム会社に進みました。
- 友人D(理系女子):研究室が忙しく「ハードな働き方は無理」と考え、「残業時間」を最優先で条件にしました。その結果、平均残業20時間以下の会社を中心に受け、大手インフラ系企業に就職しました。
NG条件から見えてくる業界の候補
営業が嫌なら…「企画・コンサル・技術系」が見えてくる
特に文系学生は「とりあえず総合職=営業スタート」が定番の会社が多いので、営業が嫌だと一気に候補が狭まるように感じるかもしれません。
私自身も「数字のノルマに追われて精神的にすり減るのは避けたい」と思っていました。その結果、営業色が薄い業界や職種を探すようになり、自然と IT系のSE職 や コンサルティング会社のアナリスト職 に興味を持つようになりました。
これらは数字を追うよりも、課題解決やシステム運用のような形で価値を出す仕事です。
実際にSIerのインターンに参加したとき、社員の方から「うちの会社は営業部門もあるけど、文系出身で技術やマネジメント側に進む人も多い」と聞き、「自分の適性はこっちかも」と感じました。
営業を避けたいという気持ちが、結果的に新しい業界を知るきっかけになったのです。
転勤が嫌なら…「IT業界」や「首都圏特化型企業」
「転勤なし」という条件を加えると、業界はかなり絞られてきます。たとえば総合商社や大手メーカー、メガバンクなどの金融機関は全国・海外に支店や拠点があるため、基本的に転勤は避けられません。
一方で、首都圏にオフィスが集中している IT業界 や コンサル、金融の中でもカード系は転勤が少ない傾向があります。
私が実際に選考を受けた企業の中にも「基本的に東京勤務」「希望があれば一部出向はあるが、全国転勤はなし」という会社があり、それが大きな安心材料になりました。
サークルの友人でも「地元から離れたくないから」と条件を決めていた人がいました。
彼は地方銀行や自治体関連の仕事を志望していましたが、最終的には「転勤なし」が明示されている都内の中堅IT企業に入社しました。「やりたいことはなかったけど、働き方で選んだ結果、納得できる会社に出会えた」と話していたのが印象的です。
ブラック企業を避けたいなら…「働き方改革」に注目
私も「深夜残業や休日出勤が常態化している会社は絶対に避けたい」と思っていました。
この条件を軸に業界を見ていくと、働き方改革を積極的に進めている企業 が候補に浮かび上がってきます。
たとえば通信業界や大手IT企業の中には、リモートワークやフレックス制度を導入しているところが多くありました。インターンシップ中の座談会で「残業時間の実態は?」と質問したときに「平均20時間以下」と答えてくれた会社は、安心感がありました。
反対に、不動産営業や一部の広告代理店などは「華やかに見えるけど労働時間が長い」と噂され、私の中では候補から外れました。ここでも「やらない条件」が業界選びを後押ししてくれたのです。
初任給や待遇を重視するなら…「安定系」や「外資系」も候補に
私の場合は「初任給が極端に低い会社は避けたい」という基準を入れました。結果的に、一定水準以上の給与を提示している 大手通信会社 や コンサルティング会社 が候補に残りました。
一方で、待遇を最優先にする友人もいました。彼は「給与が高ければ激務でもいい」と割り切り、外資系金融に挑戦していました。最終的に内定はもらえなかったのですが、「条件で選んだから納得できる」と話していたのが印象的でした。
“やらない条件”を決めることで、どんな結果でも後悔しにくくなるのです。
自分のNG条件から浮かび上がった業界像
私自身、最初は「やりたいことがない」状態で手探りでしたが、NG条件を整理していった結果、以下のように業界が絞れていきました。
- 営業ノルマは嫌 → IT業界(SE職)、コンサルティング会社が候補
- 転勤は嫌 → 首都圏中心の通信会社やSIerが残る
- ブラックは嫌 → 働き方改革を進めている大手企業に注目
- そこそこ給料は欲しい → 通信・IT・コンサルなど給与水準が安定している企業
このフィルターを通したことで、最終的に内々定を得た会社は「ホワイトでリモート可、東京近郊勤務、給与も安定」という条件に合致していました。
つまり「やらない条件」こそが、私のキャリアを決める軸になっていたのです。
「やりたいこと探し」ではなく「納得できる働き方探し」
私のケース:「ホワイト・リモート・東京近郊・そこそこ給料」
最終的に私は、4つの会社から内々定をもらうことができました。
そのとき共通していたのは、すべて「やりたい仕事」ではなく「納得できる働き方」に合致していたことです。
- ホワイト:極端な残業や休日出勤がなく、プライベートも確保できる
- リモート可:出社だけでなく柔軟な働き方ができる
- 東京近郊勤務:全国転勤がなく、生活基盤を安定させられる
- そこそこ給料:平均年収800万円以上
この4つの条件を満たす会社を中心に受けていったところ、結果的に「ここなら安心して働ける」と思える企業から内々定を得られました。
「やりたいこと」探しで迷走するより、条件を固めるほうが早い
私の周りでは「やりたいこと探し」にこだわりすぎて迷走した友人もいました。
たとえば「広告業界に入りたい」と決め打ちしていた友人は、倍率の高さや業界特有の激務に苦戦し、なかなか内定が出ませんでした。
結局、途中で志望業界を変更することになり、本人も「最初から働き方を基準に考えておけばよかった」と言っていました。
一方で、「やらない条件」や「働き方の希望」から逆算して業界を選んだ友人は、比較的早く納得のいく内定を得ていました。
つまり「やりたいことを探す」よりも「自分が納得できる働き方を見つける」ほうが、効率的で現実的な就活戦略になるのです。
「働き方の条件」がやがて「やりたいこと」につながる
不思議なことに「やらない条件」や「働き方」を基準にして企業を探していくと、いつの間にか「やりたいこと」に近づいていく感覚もありました。
たとえば私は「リモート可でホワイトな環境」を重視していたのですが、その条件を満たすIT企業やコンサルの仕事に触れる中で、「課題解決を支援する」という仕事そのものにやりがいを感じるようになりました。
結果的に、最初は「やりたくない条件」から始まった就活が、「自分はこういう分野で成長したい」という前向きな気持ちに変わっていったのです。
体験談:友人の納得できる働き方探し
- 友人E:地方出身で「地元から離れたくない」という強い気持ちがある。そのため「転勤なし」の会社に絞って就活を進め、最終的に地元の優良中小企業に入社。給与は大手ほど高くないものの、「地元で暮らせる安心感」が最大の納得ポイントになっていました。
- 友人F:研究室生活で多忙だったため、「定時に帰れる会社じゃないと続かない」と考え、残業時間を最重要視。その条件で探した結果、大手インフラ系企業に就職しました。本人は「仕事内容に強いこだわりはなかったけど、働き方の安心感がモチベーションになる」と話していました。
まとめ
「やりたいことがなくても大丈夫」
就活というと「夢がないと始められない」「やりたいことを語れないと不利になる」と思い込んでしまいがちです。
私も大学3年生の春まではそう信じていて、友人が「商社に行きたい」「広告業界を目指す」と口にしているのを聞いては焦っていました。
しかし、実際に就活を終えてみると、「やりたいことがなくても問題ない」というのが本音です。
むしろ、やりたいことに縛られて選択肢を狭めるよりも、柔軟に業界を見られるという強みがあります。
「やらない条件」がキャリアの軸をつくる
今回の記事で何度も触れたように、大切なのは「やらない条件」をはっきりさせることです。
NG条件を一つひとつ整理していくと、自然と残る選択肢が「自分に合った働き方」につながります。
最後に
就活は「完璧な夢やキャリアプランを持っている人だけがうまくいく世界」ではありません。むしろ、多くの学生は手探りのままスタートし、その中で「やらない条件」から逆算して自分に合う会社を見つけています。
だからこそ、「やりたいことがない」と悩む必要はまったくありません。
大切なのは、自分にとって「納得できる働き方」を見つけること。その第一歩は、ネガティブに聞こえるかもしれない「やらない条件」を整理することから始まります。
そしてその作業は、高校生のうちからでも少しずつできることです。
進路選びや将来を考える際に、ぜひ「自分はどんな働き方をしたくないか」という視点を持ってみてください。きっと数年後、就活を迎えたときに役立つはずです。
就活に困っているなら相談するのも手
現在就活で困っている大学生の方もいらっしゃると思います。
また、将来どのように就活を進めていこうか考えている大学1,2,3年生の方もいらっしゃると思います。
そういう方はまずは、オンラインで就活のプロに相談に乗ってもらうのも手です。プロの言葉から、気づくこともあると思います。
キャリセン就活エージェント
専任のキャリアアドバイザーが、個別面談を通して希望や適性に合った企業紹介や 選考アドバイスを実施し、多くの学生の就活をサポートしています。
キャリアアドバイザーとの個別面談を通して、新たな視点で自分の強みなどの整理することもできます。
くわしくはこちらUZUZ 新卒
プロのカウンセラーの「ES添削」が受け放題。独自のシステムで、プロのカウンセラーから直接ESを何度でも無料で添削してもらえます。
くわしくはこちらMatcher(マッチャー)
大学関係なくOB・OG訪問ができる、国内最大級の就活相談アプリ。 約42,000人の社会人が学生の就活相談にのってくれます。
企業からスカウトも貰え、自分に合った企業を見つけることもできます。
くわしくはこちらBaseMe(ベースミー)
独自AIによって、ESの作成・添削ができるサービス。
さらに、プロフィールを充実させておけば、自動で企業からスカウトが届くことも。
くわしくはこちら