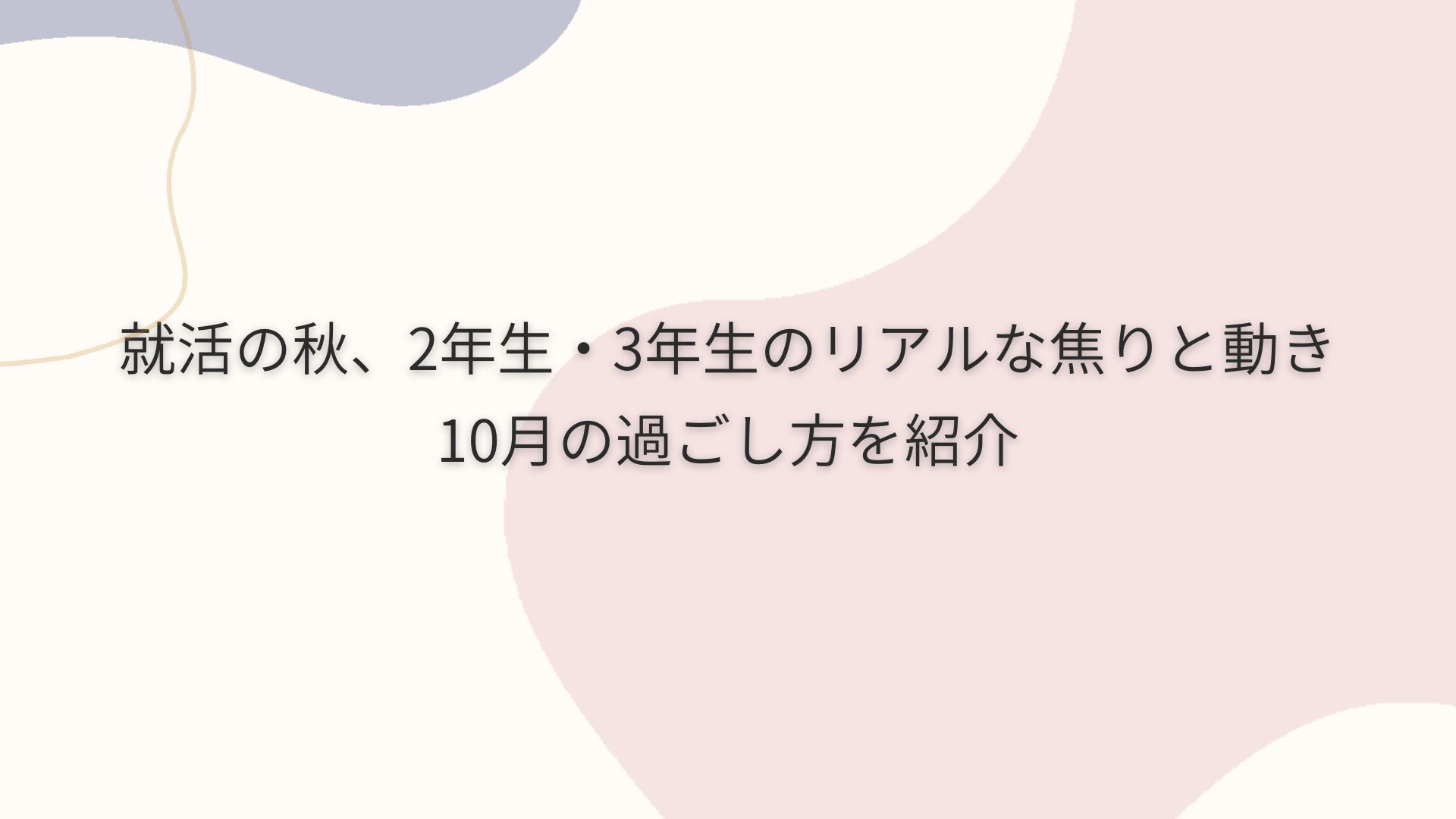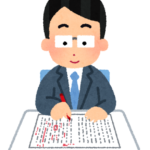こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。
10月に入ると、学内の空気が少しずつ変わってきます。
ゼミや授業の合間に「冬インターンどうする?」「そろそろES書いた?」なんて会話がちらほら聞こえるようになり、就活という言葉が一気に“他人事”じゃなくなる季節です。
ただ、2年生と3年生では感じている温度差も大きく、まだピンときていない人も多いはず。
「何から始めればいいの?」「もう動いてる人もいるけど、自分は大丈夫?」——そんな不安や焦りを抱えるのは自然なことです。
僕自身も、3年生の秋までは「就活って何から手をつければいいのかわからない」と感じていました。最初のうちは、とにかく情報を集めたり、自己分析ノートをつけてみたり。そんな小さな一歩の積み重ねが、後から大きな自信につながりました。
この記事では、大学2年生・3年生それぞれが10月にどんな不安を抱え、どんな行動をしているのかをリアルに紹介します。
“就活の秋”をどう過ごすかで、冬以降の動き方が少しずつ変わっていきます。今のうちに、自分のペースで準備を始めましょう。
目次
「就活を意識し始める時期」は人によって違う
大学生活も半ばに差しかかる2〜3年の秋。
周りを見渡すと、「まだ全然意識してない人」と「すでに何社もインターンに応募してる人」が混在しています。
就活の始まり方は本当に人それぞれ。早すぎても遅すぎても良くないですが、「どんな業界を目指すか」で動き出しの時期が大きく変わるのが現実です。
大学2年の10月は“情報収集期”が中心
多くの学生にとって、2年の10月は「そろそろ就活の準備を始めようかな」と意識し始める時期。
大学のキャリアセンターでも就職ガイダンスが始まり、マイナビ・リクナビ・ワンキャリアなどの登録を済ませる人が増えます。
ただし、この時期に“全員が同じスピードで動く”わけではありません。
大学の学部や志望業界によって、進み方の早さに明確な差があります。
外資・難関業界は驚くほど早い
たとえば、外資系コンサルティングファームや外資系投資銀行(外銀)など、いわゆる「最難関業界」と呼ばれる分野では、1年生からキャリアを意識して動く人も珍しくありません。
早ければ大学2年の春〜夏にはサマーインターンの選考が始まり、3年春には本選考直結のインターンが行われるケースもあります。
実際、外資志望の学生の中には、1年生のうちから英語面接の練習やケース面接の対策を始めている人も。
この世界では「早く準備した人ほど有利」と言われるのも納得です。
同様に、総合商社やデベロッパー(不動産開発)などの人気業界も早めの情報収集が必要。これらの業界は倍率が高く、OB訪問や業界研究の深さが結果を左右します。
3年の夏から本格的に選考が始まるため、遅くとも3年の春には“志望業界を絞る”段階に入るのが理想です。
一方で、一般的な日系企業は「3年の秋〜冬」から
多くの学生が受ける日系企業の多くは、3年の秋以降に説明会やインターン募集が本格化します。
このタイミングで焦らず「自己分析」「業界研究」「ガクチカ整理」を進めるだけでも十分間に合います。
特に、SIerやメーカー、金融、インフラ系などは、じっくりと準備を進めるタイプの選考が多く、秋に基礎を固めておくのがちょうどいいペースです。
大学2年生は“キャリアの助走期間”として捉える
2年生のうちは、「就活準備」というより自分の興味を広げる時期。
長期インターンやボランティア、サークルでの活動など、社会とつながる経験を少しずつ積んでいくのがおすすめです。
僕自身も、2年の終わり頃にWebライターの長期インターンに応募しました。
最初は就活とは関係ないと思っていたけれど、「自分の言葉で考えを発信する」経験が、後のESや面接で大きく役立ちました。
動き出しは人それぞれ。でも「知っておく」だけで差がつく
就活の始まり方は人それぞれで、早ければ偉いというものではありません。
ただ、どの業界がどんな時期に動くのかを知っておくことは大きなアドバンテージになります。
「まだ自分は関係ない」と思っていても、10月は一度立ち止まって将来を考えてみるタイミング。
大学2年生は“キャリアの助走”を始め、3年生は“情報収集と準備”を進めていく。その一歩が、冬以降の自信につながります。
【大学2年生】リアルな不安と動き出しのきっかけ
2年生の秋といえば、まだ授業やサークル、アルバイト中心の毎日。
就活の話を聞いても「自分にはまだ関係ないな」と感じる人がほとんどだと思います。
でも、SNSや大学のガイダンスなどで“インターン”“OB訪問”といった言葉を耳にするようになると、少しずつ「そろそろ準備したほうがいいのかな…?」という気持ちも芽生えてくる時期です。
不安①何から始めればいいのかわからない
多くの2年生が最初にぶつかるのはこの悩み。
「就活の準備って具体的に何をすればいいの?」「インターンってどこで探すの?」と、情報の多さに戸惑う人が大半です。
キャリアセンターのガイダンスに参加してみても、「自己分析」「ガクチカ」「業界研究」といった言葉ばかりが並び、結局どれから手をつければいいのかわからない。
そんなときは、“自分の過去を整理する”ところから始めてOKです。
たとえば、サークルやバイト、大学の授業などで「頑張ったこと」「悔しかったこと」を思い出し、ノートに書き出してみる。
それだけでも、将来の自己分析につながる大事なステップになります。
不安②周りとの温度差に焦る
もうひとつよくあるのが、周りとの温度差です。
友人の中には「長期インターン始めた」「OB訪問した」と言い出す人もいて、SNSを開けば「就活アカウント」で情報発信している同級生もちらほら。
でも、ここで焦る必要はありません。
2年生のうちはまだ、「就活モード」に入らなくてもまったく問題ない時期です。
むしろ、焦って何も考えずにインターンや資格勉強に手を出すと、自分の軸が定まらないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。
僕自身も、2年生の夏頃は「とりあえず何か始めた方がいいのかな」と焦っていましたが、秋に少し時間を取って“自分が好きなこと・得意なこと”を整理したことで、ようやく方向性が見えてきました。
10月のリアルな動き方
2年生の10月は、「情報収集+小さな行動」を意識するくらいで十分です。
具体的には、
- 大学のキャリアセンターで開催されるガイダンスに1回参加してみる
- マイナビ・ワンキャリアなどのサイトを登録だけしておく
- 興味のある業界や企業を調べてみる
- 自己分析ノートを作ってみる(“自分年表”を書くのがおすすめ)
- 興味があれば、長期インターンやボランティアを調べてみる
このくらいの小さな行動でも、十分「一歩前に進んでいる」と言えます。
僕は実際、2年の終わり頃にWebライターの長期インターンに応募しました。
最初は「文章を書くのが好き」という単純な理由でしたが、結果的に「企画を考えて人に伝える」というスキルを身につけられ、就活でも大きな武器になりました。
ポイント:就活準備より“経験の棚卸し”を
2年生のうちは、「就活準備」というより“自分の経験を増やす・整理する時期”です。
授業、サークル、アルバイト——どれも将来のガクチカ(学生時代に力を入れたこと)につながる可能性があります。
大切なのは、「どんな経験を、どんな思いでやってきたか」を自分の言葉で話せるようにすること。
それが、3年生で本格的に自己分析やESを書くときの“素材”になります。
大学2年の10月は、焦らず“自分と向き合う”時間を取るのがベスト。
まだ就活サイトを見たことがない人も、少しずつキャリアに意識を向けてみるだけで十分です。
今のうちにいろんな経験を積み、心のどこかで「将来どんな働き方をしたいか」を考え始める。それだけで、来年の自分がぐっと楽になります。
【大学3年生】リアルな不安と10月のスケジュール
10月——大学3年生にとっては、「本格的に就活を意識し始める時期」と言われます。
周りでも「インターン行ってきた」「ES書き方わからない」「そろそろ本選考だね」など、急に“就活”という言葉が身近になってくる頃です。
とはいえ、焦りを感じる人も多いはず。
「もう遅いのでは?」と思う人もいますが、結論から言えば10月から動き始めても大手企業の内定は十分可能です。
早稲田のような上位大学では“春から準備”が定番に
早稲田をはじめとする上位大学では、3年生の春ごろから就活準備を始める人が多いです。
夏には外資コンサルや総合商社、広告代理店などのサマーインターンシップに挑戦する学生も多く、周囲の動きが早い分「自分は出遅れてるのでは」と不安になることもあります。
実際、僕の周りでも春学期から自己分析ノートを作り、5月にはES練習会や面接対策講座に参加していた友人がいました。
夏には外資系コンサルのインターンに参加し、「やっぱり自分には違う業界かも」と気づいたという人もいます。
でも、ここで知っておいてほしいのは、“早く始めた=有利”ではないということ。
10月以降にしっかり軸を固めて行動すれば、就活本番には間に合います。
不安①「出遅れた」ように感じる焦り
3年の10月、最も多いのはこの不安です。
夏インターンに行った友人たちが「内定直結だった」「選考慣れした」と話しているのを聞くと、つい自分と比べてしまう。
でも、実際には多くの企業が秋以降に本格的な選考や説明会をスタートします。

特に日系大手やメーカー、金融、IT系などでは、冬インターンや本選考のエントリーが年明け以降になるケースも多く、10月からの準備でも十分に間に合います。
焦るよりも、「ここから何をどんな順序で進めるか」を整理することが大事です。
不安②授業・ゼミ・サークルとの両立
秋学期は、授業・ゼミ・学園祭・サークル行事が重なる時期。
僕自身も、ちょうどこの時期は「ヨコシマ。」でのライブ運営や新歓動画の撮影、ゼミ論文の準備などで忙しく、正直就活どころではありませんでした。
ただ、就活の準備は「長時間まとめてやるもの」ではなく、日常のスキマ時間で積み上げるものだと感じました。
授業帰りに説明会の録画を見たり、サークル仲間と一緒にESのネタを出し合ったり。
そうした小さな積み重ねでも、確実に前進できます。
10月の理想的な動き方
10月は、“就活の方向性を整える時期”。
早く動いていた人は振り返りと戦略の見直しを、まだ動けていない人は基礎固めを始めるタイミングです。
▶ 早めに動いていた人の場合
夏インターンを経験した人は、まず振り返りを。
- どんな企業文化・働き方が合っていたか
- 自分の強み・弱みをどんな場面で感じたか
- 選考で苦戦したポイントは何か
これらを整理したうえで、次に何を磨くべきかを明確にするのが理想です。
たとえば、
- ガクチカをブラッシュアップする
- 自己分析をさらに掘り下げ、志望動機を具体化する
- 面接対策を始め、想定質問をまとめる
といった“能力の底上げ”に時間を使うのがおすすめです。
実際、僕も10月は「インターンで思うように話せなかった」反省から、先輩にESを添削してもらい、自分の強みを言葉にする練習をしました。
この時期に自分を客観視できると、冬以降の成長スピードが一気に上がります。
▶ これから始める人の場合
もし10月時点で何もしていなくても、本当に大丈夫です。
まずは次の3つから始めてみましょう。
- 自己分析:これまでの経験を書き出し、頑張った理由を言語化
- 業界研究:興味のある業界を3つに絞って基本情報を集める
- ES練習:大学のキャリアセンターやワンキャリアなどで例文を読む
これを10月〜11月の間にやっておくと、冬インターンや本選考にスムーズに入れます。
10月は“再スタート”のタイミング
3年生の10月は、就活を本格化させるきっかけの月。
すでに動いていた人は振り返りと戦略の再構築を、これから動く人は基礎固めと方向性決めを。
早稲田のように周囲が早く動く環境でも、焦る必要はありません。
就活は「いつ始めたか」ではなく、「どれだけ自分を理解しているか」で結果が変わります。
ここからの1か月を、自分のキャリアを整える時間にできれば、冬インターンや本選考を安心して迎えられます。
筆者が感じた「動いてよかったこと・後悔したこと」
就活を始めてみて痛感したのは、「情報」と「経験」は早めに動くほど得やすいということ。
ただ同時に、早く動いたからといって、すべてが順調にいくわけでもありません。
ここでは、僕自身が就活を通して「やってよかったこと」と「後悔したこと」を率直に振り返ります。
動いてよかったこと①“実際に動く”ことで見えてくることが多かった
就活を考え始めたばかりのころは、正直なところ「自己分析って何?」「ガクチカって作るものなの?」という状態でした。
でも、ESを書いてみたり、OB訪問で先輩に話を聞いてみたりするうちに、少しずつ“自分の中の軸”が見えてきました。

最初は形だけでも、とにかく行動してみるのが大事だと思います。
たとえば、OB訪問で先輩から「仕事って結局、誰と何をしたいかで決まるよ」と言われたことがあり、そこから僕は「人と関わる仕事」「チームで何かを作る仕事」に興味を持つようになりました。
頭の中で考えているだけではわからなかったことが、実際に動いてみることで少しずつ明確になっていく。
これが、3年秋〜冬にかけて一番実感したことでした。
動いてよかったこと② 経験を「言葉にする」ことで成長を実感できた
就活を進める中で、ESや面接では“自分の経験をどう語るか”が問われます。
最初の頃は、頑張ったことをただ時系列で説明するだけで、「それで何を学んだの?」と聞かれて言葉に詰まることもありました。
そこで、自分のサークルでの取り組みを改めて紙に書き出し、「課題→行動→結果→学び」の順に整理しました。
すると、これまで“何となく”でやっていた努力が、ちゃんとしたロジックとして形になっていきました。
それをきっかけに、自己分析の深め方も変わりました。
単に「頑張ったことを思い出す」のではなく、「そのときなぜ動こうと思ったのか」「その経験で何を得たのか」といった自分の思考プロセスを掘り下げるようになったんです。
その結果、面接で話しても自然と一貫性が出るようになりました。
後悔①“情報を詰め込みすぎて行動が止まった時期”があった
就活初期には、とにかく焦って情報を集めすぎていた時期がありました。
インターン情報サイトを毎日チェックし、SNSの就活アカウントをフォローしすぎて、どれが本当に自分に必要な情報なのかがわからなくなってしまったんです。
それで気づいたのは、情報よりも経験が自信を生むということ。
1社でもインターンや説明会に行ってみる、1人でも先輩に話を聞いてみる——そうした小さな行動のほうが、確実に自分を動かしてくれました。
後悔②“自己分析を途中で止めていた”
夏ごろ、「ガクチカも書けたし、自己分析は終わりかな」と思ってしまった時期がありました。
でも、秋以降に志望動機を作る段階で、「自分が本当にやりたいことって何だろう」とまた悩むことに。
そこで改めて、自分の過去を掘り返してみたんです。
すると、サークルでの経験やチームで何かを作り上げる過程が、自分の価値観の根底にあることに気づきました。
この“再分析”の時間があったからこそ、後に志望業界をIT・SIer系に絞る決断ができたと思います。
学び:就活は「正解探し」ではなく「再構築のプロセス」
就活を進める中で感じたのは、就活は自分を新しく作り直す時間だということ。
ガクチカを語るたびに、「自分がどう考え、どう動く人間なのか」が少しずつ明確になっていきました。
そして、過去の経験を客観的に整理することで、今後どんな環境で成長していきたいのかも見えてきました。
焦って完璧を目指す必要はありません。
大切なのは、「今の自分」を材料にしながら、少しずつ“なりたい自分像”に近づけていくこと。
そのために10月は、動きながら考え、考えながら修正していくのにちょうどいいタイミングです。
行動して失敗したことも、後から見ればすべて“自己理解の材料”でした。
僕にとっての就活は、「評価されるための期間」ではなく、「自分という人間を掘り下げて再構築する時間」。
過去の経験を整理し、次につながる行動に変えていく。
それができるようになった今、ようやく「就活をしてよかった」と心から思えます。
今からできる準備チェックリスト(学年別)
就活を意識し始めた今の時期。
「まだ何もできていない」「どこから手をつければいいのかわからない」と感じる人も多いはずです。
でも、やるべきことを少しずつ整理すれば、焦らず進めていけます。
ここでは、大学2年生・3年生それぞれにおすすめの10月以降の動き方をチェックリスト形式で紹介します。
【大学2年生編】“キャリアの土台”を作る時期
| やること | 目的・ポイント |
|---|---|
| 自己分析ノートを作る | 高校〜現在までの経験を時系列で書き出し、「頑張れた理由」を整理する。就活本番の素材になる。 |
| サークル・バイト・授業の経験を振り返る | どんな場面で達成感を得たかを言語化しておくと、将来の強み発見につながる。 |
| キャリアセンターのガイダンスに1度行く | 雰囲気をつかむだけでもOK。早いうちに相談窓口の存在を知っておくと後で安心。 |
| 興味のある業界を調べる | 深掘りより“ざっくり”でOK。「どんな仕事があるのか」を知るところから始めよう。 |
| 長期インターンやボランティアを検討 | 就活というより、社会を覗く体験として挑戦してみるのがおすすめ。 |
| 将来像をぼんやり描いてみる | 「どんな人になりたいか」「どんな生活を送りたいか」を考えるだけでも十分。 |
ポイント:まだ“走る時期”ではなく、“素材を集める時期”。
この時期に少しでも「自分の得意」「苦手」「価値観」を意識しておくと、3年生になってからの動きが格段にスムーズになります。
【大学3年生編】“自分の軸を固める・実践に移す時期”
| やること | 目的・ポイント |
|---|---|
| 自己分析の“再整理”をする | 夏までにやった分析を見直し、志望動機と一貫性があるか確認。まだ浅いと感じたら再掘り下げ。 |
| ガクチカをブラッシュアップ | 実績よりも「どう考えて動いたか」を伝えられるように。先輩や友人に見てもらうと改善が早い。 |
| 志望業界を2〜3に絞る | 「なんとなく全部受ける」は危険。業界研究を深め、優先順位をつける。 |
| 冬インターン・本選考準備 | 10月から応募が始まる企業も多い。ESや面接練習は今のうちに。 |
| OB・OG訪問を始める | ビズリーチキャンパスやMatcherなどを使い、現場のリアルな話を聞く。1人でも行けば世界が変わる。 |
| 面接対策を始める | 友人と模擬面接を1回でも経験しておくと、冬以降の緊張感が大きく違う。 |
| スケジュールを“見える化” | Googleカレンダーなどで予定を一元管理。僕はPixelの音声入力で登録していて、想像以上に便利だった。 |
ポイント:10月は「戦略を整える月」。
春や夏に動いていた人は振り返りと修正を、まだ始めていない人は基礎の固めを。
どちらにしても、今から動けば十分間に合います。
【共通】10月から意識したい3つの行動
- 「話す力」を磨く
→ 友人や先輩に自分の話をしてみる。フィードバックをもらうだけで表現力が伸びる。 - 「自分の言葉」を使う
→ テンプレではなく、自分の感情を交えて語ることで面接官に伝わりやすくなる。 - 「考える時間」を確保する
→ 情報に流されすぎず、週に一度は“就活を振り返る時間”を作る。
焦らず、でも確実に一歩ずつ
10月の時点では、誰もが不安を抱えています。
SNSでは「インターン受かった」「内定出た」といった言葉が目立ちますが、見えているのはほんの一部です。
大切なのは、「今の自分ができること」を一つずつ進めていくこと。
行動の大きさではなく、継続して考え続ける姿勢が後の自信につながります。
2年生は“キャリアの土台づくり”、
3年生は“自分の軸を固める”。
どちらも、10月からの一歩があなたの就活の未来を変えていきます。
まとめ:焦らず、自分のペースで「就活モード」に
10月という時期は、就活を始める人・まだ動いていない人の差が一番大きく見える時期です。
でも、そこで感じる焦りや不安は、みんなが一度は通るもの。
「自分だけ遅れている」と思っても、実際には多くの人がまだ“準備段階”にいます。
就活は「競争」ではなく「自己理解のプロセス」
就活という言葉を聞くと、どうしても「周りより早く」「たくさん内定を取る」といった“競争の場”を想像しがちです。
けれど本質的には、自分の経験を見つめ直して、“どう生きたいか”を考える時間なんですよね。
僕自身、就活を通して「組織をより良くするために動くことが好き」「人と協力して課題を解くことにやりがいを感じる」という価値観を再確認しました。
こうした気づきは、誰かと比べて生まれるものではなく、自分と向き合う中で少しずつ見えてくるものです。
焦らず、“動きながら考える”でOK
2年生は、まず「自分を知る」ことから。
3年生は、「自分をどう見せるか」を少しずつ考える時期です。
大切なのは、完璧な計画を立てることではなく、“今できる一歩”を積み重ねること。
ガクチカの整理、業界研究、OB訪問——どれも最初の一歩は小さくて構いません。動いてみることで、少しずつ方向性が定まっていきます。
「10月」は、就活を“生活の一部”にしていくスタートライン
この時期は、就活を「特別なイベント」ではなく、大学生活の延長線上にあるものとして捉えるのがポイントです。授業やサークル、バイトの経験すべてが、後で“語れる素材”になります。
だからこそ、就活のために生活を削るのではなく、日常の中から学びを見つける視点を持ってみてください。
最後に:あなたのペースで、確実に前へ
就活に“正しい始め方”はありません。
人それぞれペースもきっかけも違っていい。
10月から少しずつでも意識を向けていれば、それはもう立派なスタートです。
焦らず、自分のペースで準備を進めていけば、必ず「やってきてよかった」と思える瞬間が来ます。
大学生活の延長にある“未来への一歩”として、就活を自分らしく歩んでいきましょう。