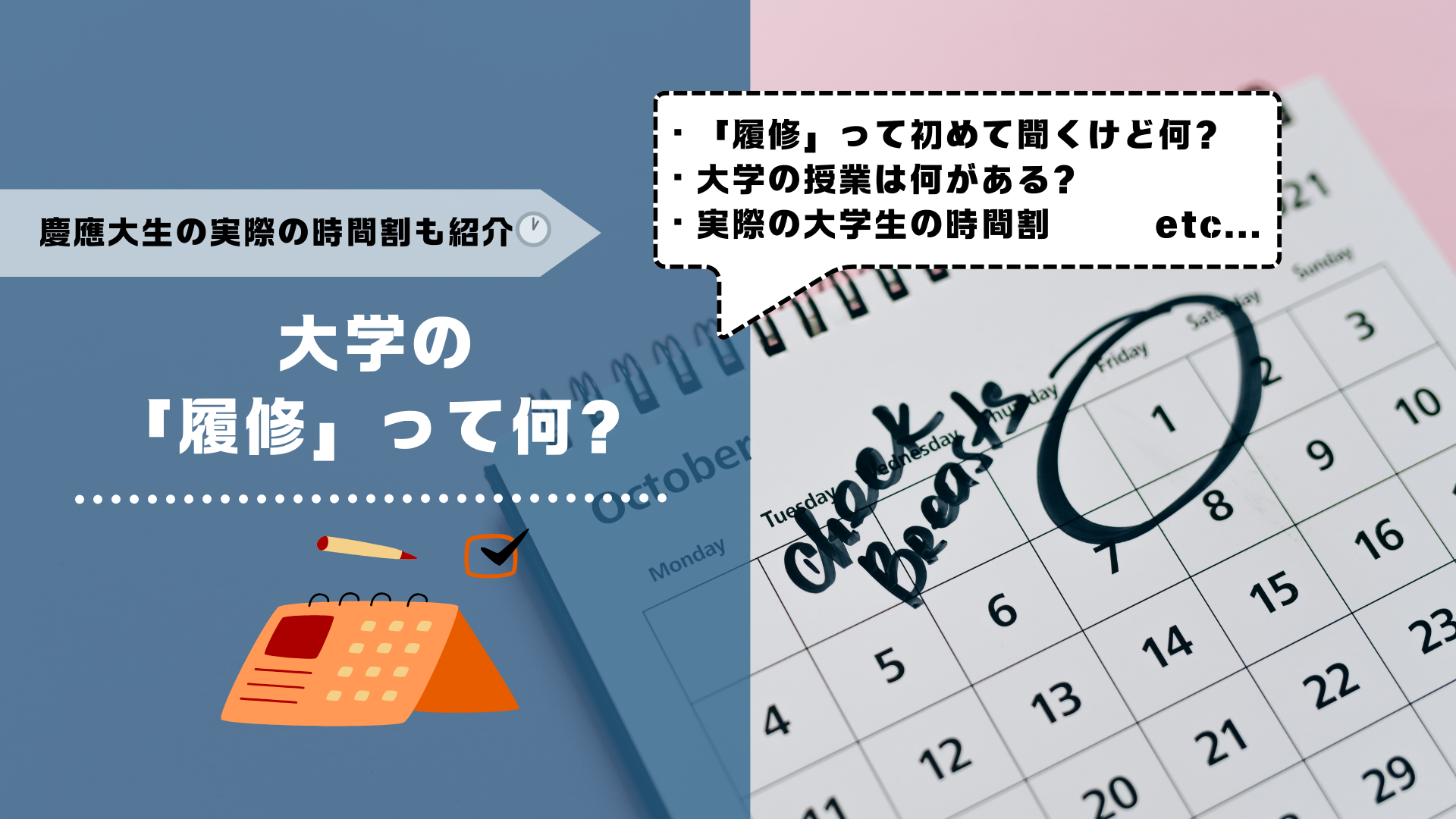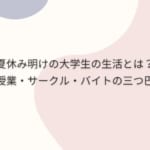目次
はじめに
こんにちは、慶應義塾大学経済学部3年生のたくです!大学生活って想像と違う部分も多いですよね。高校まではクラス単位で時間割が配られて、「今日は1限が数学、2限が英語で…」っていうふうに、ある程度決まったカリキュラムに沿って授業を受けていたと思います。でも、大学生になると、いきなり「履修登録」というものが待ち構えているんです。
「履修登録?何それ??」と最初は戸惑う人も多いはず。大学生が口をそろえて言う「履修ガチャ」とか「単位落としそう…」なんて言葉も、入学前の高校生にとっては「???」ですよね。私自身もそうでした。高校3年生のときは「とりあえず慶應大学に合格しなきゃ!」という気持ちばかりで、入学後のことなんてほとんど考えていませんでしたから…(笑)。
ところが、入学してから早々に履修登録のシステムやら、“自分で時間割を組む”ことの難しさや楽しさや大変さやらを思い知らされます。でも、その反面、自分の興味ある授業を選べる自由度の高さは、大学の大きな魅力でもあるんです。
そこで今回の記事では、「大学の『履修』って何?慶應生の実際の時間割も公開!」と題して、
1. まずは大学における「履修」とは何かを解説し、
2. 実際に時間割を組むときに気をつけたいポイントを紹介し、
3. 私自身のリアルな時間割を、1年生春学期と2年生秋学期の2パターン公開、
4. さらには履修登録で失敗しないための小ワザ・Tipsをお伝えし、
5. そして履修を組むうえでの心構えとまとめ
…といった流れでお話ししていこうと思います!高校生のみなさんが「大学生活って面白そう!」って思ってくれたら嬉しいですし、今後の進路を考えるうえで参考になれば幸いです。では、ここからちょっと長いですが、じっくり読んでみてくださいね!
大学における「履修」って何?
「履修」の一般的な概要
まずは「大学でいう『履修』って何なんだろう?」というところからお話しします。
高校までは、基本的に学校が組んだカリキュラムに沿って、授業科目が自動的に決まっていましたよね。数学とか英語とか国語とか、固定された時間割が配られて、それをベースに受業をこなしていくイメージだったと思います。でも、大学では自分で授業を選択して、“自分だけの時間割”を作るんです。これが履修登録の醍醐味であり、最初の関門でもあります。
• 必修科目: 卒業するために“必ず”履修しないといけない科目。
• 選択必修科目: いくつかある科目リストの中から、“どれかを選んで履修”しないといけない科目。
• 自由選択科目: 自分の興味や将来のプランに合わせて好きに選べる科目。
ざっくり言うと、この3種類があります。大学によって呼び方や分類が少し違うこともありますが、基本的にはこのように科目が分かれているんですね。履修登録の時期になると、大学のシステム(慶應だと「K-LMS」や「keio.jp」など)を使って、自分が受けたい授業をポチポチ登録していくイメージです。そして、最終的に何曜日の何限にどの授業をとるかを自分で決めて、時間割を完成させます。
しかし、最初に言ったとおり、これは楽しさと同時にけっこうな難しさもあります!慣れていないと、必修科目を入れ忘れてしまうとか、ガチガチに授業を詰め込みすぎて火・水・木がハードスケジュールになるとか、いわゆる“履修爆死”な状態になる人も…。私も1年生の頃はよくわからないまま履修を組んで、後々になって「しまった…この授業落としたら必修だから来年もう一回…?」なんて焦ったりした経験があります(苦笑)。
慶應義塾大学の特徴
そして私が通っている慶應義塾大学では、学部ごとに履修のルールが微妙に違います。もちろん共通して「体育」とか「語学」などはあるものの、経済学部ならではの専門科目もたくさんあります。1年生のときに履修した「マクロ経済学初級」や「ミクロ経済学初級」はいわゆる“導入科目”なので、基本的な経済学の知識を学ぶのに必須でした。
また、慶應の場合は語学が結構充実していて、英語だけじゃなくて第二外国語も全員何かしら選ぶんですね。私は中国語を選択したんですが、中国語Ia、中国語IIIa、中国語IVb…みたいな感じで学年が上がるごとにレベルが段階的に変わっていきます。これが地味に大変ですが、終わったときの達成感も大きいのでおすすめです。大学によってはドイツ語やフランス語、スペイン語など幅広い選択肢があるので、ここは「どの言語を選ぶか?」という点も一つの楽しみですよね。
それから、“履修の順番”が大学や学部で決まっている科目もあるので要注意です。たとえば、慶應経済学部の場合作品詞として(※あくまで私の経験上の一例ですが)、「経済数学I」「経済数学II」などは順を追って取りたいところですし、「ミクロ経済学初級I → ミクロ経済学初級II → 中級」という流れがあったりします。「先にこっちを履修しないと、後の科目を取れない」というケースもあるので、「履修申告要項」などをしっかり読んでおく必要があります。ここを軽視すると後々「しまった…」となりがち。
こういった履修登録のシステムは大学や学部によってさまざまなので、自分が進学する(あるいは進学したい)大学・学部の履修ルールを事前にチェックしておくと安心ですよ!高校のときにはなかなか意識しづらいかもしれませんが、「大学生になったら“どんな科目”があるのかな?」「将来やりたいことがあったら、それに関連する科目をどんな感じで取ればいいのかな?」という視点でパンフレットやシラバスを見てみると、イメージも沸きやすいはずです。
時間割を組む際に知っておきたい3つのポイント
ここでは、実際に履修登録をする際に私が意識してきた3つのポイントをお話しします。もちろん、人それぞれにやり方があるので正解はひとつじゃないですが、少なくとも「これは押さえておいたほうがいい」という定番ポイントがありますので、ぜひ参考にしてみてください!
① 単位数と卒業に必要な要件
まず最初に、大学卒業に必要な単位数を把握しましょう。たとえば「4年間で○○単位取れば卒業できます」と決まっているはずです。慶應経済学部の場合も126単位(時期によって多少変わるかもしれません)くらいが卒業要件だったりします。必修科目や選択必修科目の単位はもちろん埋めなきゃいけないし、余裕があれば興味のある自由科目もどんどん取っていける感じ。
ただ、注意すべきは「1年生のときは最大○○単位まで」とか、学年ごとに登録できる単位数の上限がある場合もあること。何も考えずに「あれもこれも取っちゃえ!」と詰め込みすぎると、システムで弾かれたり、あるいは自分の体力や時間管理が追いつかなくなったりします…笑。なので、卒業要件と学年ごとの上限をチェックして、それを踏まえて上手に履修計画を立てるのが大切です。
あと、学部によっては「ゼミ」の単位数とか「卒業論文」の単位数がどうなるかってところも重要。ゼミは通年で取る場合が多いですし、卒論を書かなきゃいけない学部・学科だと最終学年にどれぐらい時間が必要かとか、逆算しておくと安心ですね!
② 興味のある授業の探し方
次に、「どの授業を取るか」を探す方法。高1・高2のみなさんにはまだピンと来ないかもしれませんが、大学生になると数えきれないほどの科目が用意されています。慶應経済学部だけでも、「経済学」関連の専門科目だけじゃなくて、他学部の授業を取ることができる「他学部履修」制度があったり、全学共通の教養科目があったり…。もう「おもちゃ箱や~」状態です(!)。
そこで私が実践しているのは、オンラインシラバスをひたすら眺めてみたり、先輩におすすめの科目を聞いてみたり、大学の授業評価サイト(非公式の口コミサイト的なやつもあるんです)を活用してみること。あとは学事担当のオフィスへ行って、疑問点を相談したりもします。特に1年生のうちは大学やシステムに慣れていないので、率直に「この必修科目は秋から取っても大丈夫ですか?」「語学はどんな時間割が可能ですか?」なんて質問するのは全然アリ!教授やアドバイザーの先輩に聞いてみるのもいいと思います。
また、興味を大切にするのはもちろんなんですが、「先生の教え方」とか「成績評価の基準」を見ておくのもポイントです。テストが期末1発勝負なのか?それとも毎回のレポートや出席で評価されるのか?中には毎週小テストがある授業もあります。そこに自分が耐えられるかどうか…笑。受講人数が多いと抽選の可能性もありますし、人気の授業はサイトが込み合ってすぐ定員オーバーになることもあるので、「希望通りの履修が通るとは限らない」っていうのも頭に入れておきましょう。
③ 時間管理(空きコマの活用やサークル・バイトとの両立)
最後に、時間管理について触れておきます。大学は1限から5限(大学によっては6限、7限もある)、または朝9時スタート~夕方までというかたちで授業が設定されているところが多いですよね。慶應は日吉キャンパス、三田キャンパス、矢上キャンパスなど複数あって、学年が進むとキャンパス間の移動が発生することもあります。そうなると移動時間も考慮しないといけないんです。
• 空きコマ(授業と授業の間が1コマ空く状態)
• サークルや部活との兼ね合い
• アルバイトのシフト
• プライベートの時間
こういったスケジュール全体を見ながら、自分の生活スタイルを整える必要があります。私なんかは、1年生のころはとにかく英語と経済学の基礎必修を詰め込みすぎて、連続5コマ入れてしまったことがあって、昼ごはんを食べる暇もなく終日授業、というハードスケジュールでした(泣)。後から友達に「空きコマ作って休まないとしんどいよ?」って言われて気づきました。
ただし、空きコマが多すぎても逆に効率が悪くなることもあるので、程よいバランスが大事です。大学によっては空きコマの教室で自習したり、外のカフェでバイトの準備(オンラインバイトとか)をしたり、友達とおしゃべりしたり、うまく活用している人が多いですね。サークル活動が夕方からある場合は、その時間に被らないように授業を組むとか、一人暮らしなら家賃を節約するためになるべくバイトに時間を割きたいとか、それぞれの事情に合わせてスケジューリングする感じです。
【実例】大学1年生 春学期の時間割紹介
さて、ここからは私の実例として、大学1年生の春学期に組んだ時間割をざっくり公開していきます!少しでもイメージが湧いてもらえれば幸いです。下の画像がこの春学期の時間割で、こんな感じになっています。

1年生春学期の時間割(概要)
• 月曜日
• 1限(9:00~10:30)中国語Ia
• 2限(10:45~12:15)体育実技A(サッカー)
• 火曜日
• 休講!!!
• 水曜日
• 1限(9:00~10:30)中国語IIIa
• 2限(10:45~12:15)英語(Study Skills)
• 3限(13:00~14:30)統計学Ⅰ
• 4限(14:45~16:15)微分積分入門
• 木曜日
• 1限(9:00~10:30)—(空き)
• 2限(10:45~12:15)マクロ経済学初級Ⅰ
• 3限(13:00~14:30)物理学Ⅰ(実験を含む)
• 4限(14:45~16:15)物理学Ⅰ(実験を含む)続き
• 金曜日
• 1限(9:00~10:30)—(空き)
• 2限(10:45~12:15)英語(Study Skills)
• 3限(13:00~14:30)社会学Ⅰ
• 4限(14:45~16:15)地理学Ⅰ
• 5限(16:30~18:00)中国語Ⅱa
• 土曜日
• 1限(9:00~10:30)—(空き)
• 2限(10:45~12:15)—(空き)
• 3限(13:00~14:30)倫理学Ⅰ (J19)
• 4限(14:45~16:15)線形代数 (D308)
こう見ると、1年生の春って必修科目が多いのが特徴で、英語(Study Skills)とかマクロ経済学初級Ⅰ、物理学(理系の教養科目として履修可能)などが固まっています。さらに語学(中国語)は必修ですね。火曜日が空いてたり、逆に月曜日や水曜日は朝から昼過ぎまで詰まっていたりと、ちょっとアンバランスな時間割になっているのがわかります。
【授業名や受講理由の簡単な説明】
• 中国語Ia/Ⅱa/IIIa:
慶應経済学部の語学必修です。私は英語以外の第二外国語に中国語を選択しました。理由は、なんとなく身近に感じたからと、これから経済面でも中国は大事だよね~というフワッとした動機です(笑)。授業は4技能(読む・書く・聞く・話す)をバランスよくやるので、毎回宿題が結構出ました。でも、クラスメイトと一緒に学べるので案外楽しかったですね。
• 体育実技A(サッカー):
慶應は1~2年の間に体育の単位が必要です。サッカーは高校の授業で少しやってたので選んだら、そこまで本格的な感じではなく、体力づくりメインでワイワイやるイメージでした。朝早いときはちょっときついけど、周りと仲良くなる機会にもなるので、割と楽しめました。
• マクロ経済学初級Ⅰ:
経済学部ならこれは外せない!という必修科目です。高校の政経とはまた違って、経済学の理論を体系的に学ぶ入り口でした。最初は「GDP?失業率?経済成長?」と頭がパンクしそうでしたが、少しずつ用語を覚えると面白くなってきましたね。試験対策は少し大変だったけど、将来の就活や社会への理解にもつながるので良い科目だと思います。
• 統計学Ⅰ:
こちらも経済学では欠かせない統計の基礎。確率や統計分布の話から入っていくんですが、数学が苦手だった私は最初かなりビビりました。とはいえ、公式をそのまま覚えるだけじゃなくて、先生が身近な例を出してくれたおかげで「へぇ~」と思うことも多かったです。思ったよりレポートが多い科目だったかもしれません(笑)。
• 英語(Study Skills):
高校までの英語とは違って、リスニングやスピーキング、エッセイライティングなど、より実践的なスキルを磨く授業でした。先生によって授業の進め方が違うので、そこはシラバスや先輩の話を参考に選びましたね。授業名に「Study Skills」とあるように、勉強法についても少しアドバイスしてもらえる科目でした。
• 物理学Ⅰ(実験を含む):
経済学部でも理系科目を選択する必要があって、私は物理を選びました。実験を含むといっても、本格的な実験装置を組むというよりは、基礎的な観察や測定を通じてレポートを書くことが中心でしたね。正直、授業中に居眠りしそうになるときもありましたが(笑)、実験やグループワークは楽しかったです。
• 倫理学Ⅰ、社会学Ⅰ、地理学Ⅰなど:
いわゆる人文科学や社会科学の分野で、幅広く教養を身につける目的。私の場合、経済学だけじゃなくて社会全体のことも知りたい!と思ったので選びました。これは慶應の総合教育科目(または教養科目)みたいな位置付けで、他の学部生とも一緒に受けることが多かったです。大学生らしい幅広い学問に触れられるのは、すごく新鮮でした。
【大学1年生ならではの基礎科目や語学、体育の履修ポイント】
1年生の春学期は、やはり「必修が多い」というのがポイント。特に語学と体育は学年が若いほど集中して取るのが一般的なので、どうしても時間割がガチガチになりがちです。あまり余裕がないスケジュールになる反面、大学生活のリズムを掴むという意味でも大事な時期でした。また、そこに経済学の基礎科目(マクロやミクロ、経済数学など)も重なるので、最初の半年が勝負と思って臨むと良いと思います。
【実際に受けてみての感想】
最初は授業が多くて、「え、こんなに詰め込むの?」と戸惑いました。でも、ちゃんと欠かさず出席してレポート出していれば単位は取れるので、変に身構えすぎず、“まずは大学に慣れる”ことを意識しましたね。サークルや友達との交友も同時に始まるので、「授業だけじゃない大学生活」が突然始まるのが1年生春学期の醍醐味でもあります。ある意味、一番忙しくて楽しい時期!
【実例】大学2年生 秋学期の時間割紹介
次に、私が大学2年生の秋学期に組んだ時間割を公開します!こちらが下の画像になります。1年生と比べて、履修する科目のジャンルやレベル感が変わっているのがわかると思います。やっぱり、大学2年生になると少し専門的な授業や、興味のある分野に絞った科目選択が増えていきました。

2年生秋学期の時間割(概要)
• 月曜日
• 1限~5限…(空き!)
• 火曜日
• 2限(10:45~12:15)ミクロ経済学初級II
• 3限(13:00~14:30)中国語IV b
• 4限(14:45~16:15)政治学II
• 水曜日
• 2限(10:45~12:15)経済史入門II
• 4限(14:45~16:15)計量経済学概論
• 木曜日
• 1限(9:00~10:30)経済と環境
• 3限(13:00~14:30)21世紀の実学 (J11) ←教養科目
• 5限(16:30~18:00)天文学II
• 金曜日
• 1限(9:00~10:30)経済数学II (D412)
• 土曜日
• 基本なし
【大学2年生になると変わる科目選択の幅】
見ていただくと、1年生のときに比べて空き時間が結構増えているのがわかります。これは、必修科目を1年生のときにある程度消化したからですね。その代わり、「ミクロ経済学初級II」「計量経済学概論」「経済史入門II」など、経済学部らしい専門科目がしっかり入ってきています。大学2年生になると、基礎を終えた上で中級レベルの科目を履修できるようになるんです。
さらに、2年生秋学期あたりからは他学部や教養系の科目を積極的に取る余裕が生まれやすいですね。私の場合、「経済と環境」なんていうちょっと珍しい授業を選択してみました。これは環境問題を経済学的観点で考えるといった内容で、持続可能性やエコノミクスの観点が面白かったです。「21世紀の実学」や「天文学II」も、いわゆる文系学部生でも取れる理系教養科目として人気がありました。
また、空き時間にサークルの活動を入れたり、平日昼にバイトに行けたりするので、大学生らしい自由度がぐっと増す時期でもあります!ちなみに月曜日は丸々空けている人も多くて、「月曜休みだから3連休だ!」と喜ぶ声もよく聞きます(が、テスト前はその分詰め込み勉強になることも…笑)。
【経済学部ならではの専門科目の履修例】
• ミクロ経済学初級II:
1年生で「初級I」を取っていた人はだいたい「初級II」に進みます。企業や消費者の行動、需要供給分析、価格弾力性、独占競争など、より実践的なミクロ経済理論を学ぶことが多いですね。ここを基礎にして中級・上級へとステップアップしていくので、結構重要な科目です。
• 経済史入門II:
経済史は私が個人的に好きな分野です。世界経済の変遷や、日本の産業革命期、戦後復興期の経済発展などを、歴史的背景と絡めて学ぶ授業でした。「経済」と一口に言っても、過去の出来事を知ることで現在の国際関係や市場の成り立ちが見えてきます。最初は暗記要素が多いかな?と思いましたが、先生が丁寧に講義してくれたので楽しかったです。
• 計量経済学概論:
経済学を統計や数学を用いて分析する「計量経済学」の基礎を学ぶ科目です。回帰分析とか相関係数とか、データを使って経済現象を読み解く力を養う感じですね。将来、経済分析や金融系の仕事をしたい人はここをしっかり押さえると就活でも話題にしやすいです。私もちょっと苦手意識ありましたが、演習問題を地道にこなすうちにだんだん慣れました(笑)。
• 経済数学II:
こちらも1年生で「経済数学I」をやった人が進む科目。微分や積分、行列、最適化問題など、経済学のモデルを理解するために必要な数理を学ぶイメージです。文系出身でも講義についていけるようになってるはずですが、やっぱりちょっと難易度は高め…。ちゃんとノート取って、演習問題をこなしましょう!(私も苦労しました)。
【学年が上がるときの注意点】
大学2年生に上がるときに私が失敗した点としては、「抽選漏れ」が挙げられます。人気の科目ほど抽選があるので、希望していた授業が全部通るとは限らないんですよね。それを見越して「第二候補、第三候補」を確保しておくのがコツです。また、ゼミを選ぶ人は2年生~3年生にかけて準備が必要だったりするので、タイミングを逃さないようにしましょう。慶應の場合はゼミの募集が大体春頃とか秋頃とか、先生によって違うので注意です。
履修登録で失敗しないためのTips
ここからは、履修登録でよくある“やらかし”を防ぐためのちょっとしたTipsをお伝えします。私自身、1年生のころはいろいろ失敗したので、その経験も踏まえてお話ししますね!
履修登録前の情報収集の大切さ
「先輩に聞く」「シラバスを熟読する」「口コミサイトをチェックする」
この3つは鉄板です。どうしても「面倒だなあ…」と思いがちですが、授業ごとのレポートや試験の形式は本当に千差万別。先輩が「この授業はテストなしでレポート評価だから、レポート苦手ならやめといた方がいいかも?」とか、「この先生、出席点が重いからしっかり行かないと単位ヤバいよ…?」なんていう生きた情報を持っていたりします。
特に慶應のようなマンモス大学だと、同じ経済学部でもクラス数が多いので、先生によって雰囲気やシラバスがまったく違うことがよくあるんですよね。だから、情報収集を怠らないというのは、履修登録成功のカギだと思います。
シミュレーションのすすめ
私がやっているのは、「Excel(スプレッドシートでもOK)」で時間割を自分で作成してみる方法です。公式の履修登録システムにいきなり打ち込む前に、まずは手動で仮の時間割を組んでみるんです。そうすると「木曜の3限と4限に授業入れすぎたな…」とか、「水曜は昼休みゼロで動き続けなきゃ」とか、ビジュアルで分かるので、失敗が少なくなります。
• 空きコマをどこに作るか
• 試験が重なりすぎないか
• 課題提出やグループワークが同時進行で被りすぎないか
などなど、先回りしてシミュレーションしておくと、後々焦らなくて済むはずです!
授業選びの際の注意点
• 受講人数制限: 事前申込や抽選がある場合は、きちんと期限を守ることが大事。抽選漏れしたときのバックアップ授業も考えましょう。
• 教室の場所確認: 慶應の日吉キャンパスや三田キャンパスは広いので、教室の移動時間が意外とバカになりません。隣り合うコマでキャンパス移動があるとヤバい!
• 試験やレポートの時期: 最終試験が一斉にやってくる科目ばかり取ると、テスト期間が死ぬほど忙しくなるなんてことも…。あえてレポート型評価の科目を織り交ぜて、試験負荷を分散させる人もいます。
履修を組むうえでの心構え
迷ったら興味を優先してみる
大学は、高校までとは比べものにならないほど「自分の興味」を探求できる場所です。教養科目から専門科目まで、本当にいろいろな授業があります。どうしても「就職に有利そうだから」とか「単位が取りやすそうだから」といった理由で科目を選びがちですが、やっぱり一番大事なのは「自分が本当に知りたいことかどうか?」だと思うんですよね。
もちろん、卒業要件を満たすのも大切だけど、自由選択で1つでも「すごく面白そう!」って思った科目を入れておくと、モチベーションが違います。私も「天文学II」を取ったのは、「星や宇宙の話が好きだから」っていう単純な理由でしたが、結果的にすごく充実した学びになりました。レポートを書くのも楽しかったです。
学習スタイルを確立しよう
大学に入ると、高校のように毎日同じメンバーで授業を受けるわけじゃないし、授業によって教授の進め方や課題のスタイルもバラバラ。だからこそ、自分のペースで「どうやってノートを取るか」「いつ復習するか」「レポートを書くときのコツは?」など、学習スタイルを確立するのが重要です。慶應は課題が結構多い方だと思うので(先生にもよるけど)、計画的に進めないと締切ラッシュで大変なことになることもしばしば…。
私のおすすめは、「毎授業ごとに15分だけ復習する」とか、「週末に1回全科目をおさらいする時間をつくる」こと。高校までは部活や塾で自然と勉強リズムがあったかもしれませんが、大学は自由すぎて逆に自己管理が難しいんです。履修を組んだら、それに合わせて学習リズムを作るのも意識してみると良いですよ!
将来や就活を意識した科目選択
高1・高2のみなさんには少し早い話かもしれませんが、就活も視野に入れると「この科目取っておけばよかった!」となるケースもあります。例えば、プログラミング(PythonやR)系の授業があるなら、経済データを扱うときにも役立つし、ITリテラシーが高いと就活で話題になることも多いです。語学はもちろん、TOEICやIELTS対策が授業で組み込まれていることもあるので、興味があるなら履修してみると◎。
また、慶應は「ビジネスコンテスト」をやってるゼミや、「国際ボランティア」に行けるプログラムもあったりするので、そういう課外活動と授業を絡めて考えるとより充実した大学生活になりますよ!
まとめ
長々と書いてきましたが、ここまで読んでくださったみなさん、本当にありがとうございます…!最後に、ざっくりおさらいをしておきましょう。
1. 大学の「履修」とは?
→ 自分で科目を選んで時間割を組むこと。必修や選択必修、自由選択などをうまくバランスよく組み合わせるのが重要。
2. 慶應義塾大学経済学部の特徴
→ 語学(英語+第二外国語)が充実、経済学の基礎科目を1年次から履修。ゼミや他学部授業も魅力がある。
3. 時間割を組むときの3つのポイント
① 卒業要件と単位数の確認
② 興味のある授業の探し方(シラバス、先輩、口コミ)
③ 時間管理(空きコマ、サークル、バイトとの両立)
4. 【実例】1年生春学期の時間割
→ 必修科目が多く、「マクロ経済学初級」「語学」「体育」などでスケジュールがガチガチ。最初は苦労するが、大学生活のリズムを掴む大切な時期。
5. 【実例】2年生秋学期の時間割
→ 専門科目(ミクロ経済学初級II、計量経済学概論、経済史入門IIなど)+教養科目(環境、医学、天文学)も履修。空きコマが増え、大学生らしい自由度がアップ。
6. 履修登録で失敗しないためのTips
→ 「情報収集」「シミュレーション」「授業選びの注意点」の3点を意識。
7. 履修を組むうえでの心構え
→ 「興味」を優先しつつ、学習スタイルを確立し、将来の就活も見据えて考える。
大学生にとって、履修登録は毎学期やってくる最大のイベント…といっても過言じゃありません。特に新入生の時期はわからないことだらけだと思いますが、周りに相談できる先輩や友達がいれば一気にハードルは下がるはずです。
逆にいえば、履修計画次第で大学生活の充実度がだいぶ変わってくるということでもあります。自分が興味のある分野に力を入れるのもアリだし、他学部に潜り込んで全然違う世界を知るのもアリ。もちろん卒業に必要な単位はしっかり抑えつつ、自由度を活かして“自分だけのカリキュラム”を作っちゃいましょう。
最後に一言、「迷ったら、まずはチャレンジ!」をおすすめします。大学は本当に色んなことに手を出せる時期です。失敗しても再チャレンジできるし、周りには同じように悩んだ経験のある先輩が必ずいます。高校生のみなさんには、ぜひ大学入学後に履修登録でワクワクしながら自分の時間割を作ってほしいなと思います。慶應に限らず、どの大学でも応用できる考え方なので、ぜひ参考にしてくださいね!
それでは、ここまで読んでくださりありがとうございました!もし少しでも、みなさんの大学生活のイメージづくりに役立ったなら嬉しいです。慶應に進学を考えている方はもちろん、ほかの大学に進む予定の方も、履修登録のポイントや大学生活の楽しみ方のヒントがあったら幸いです。
またお会いしましょう~!