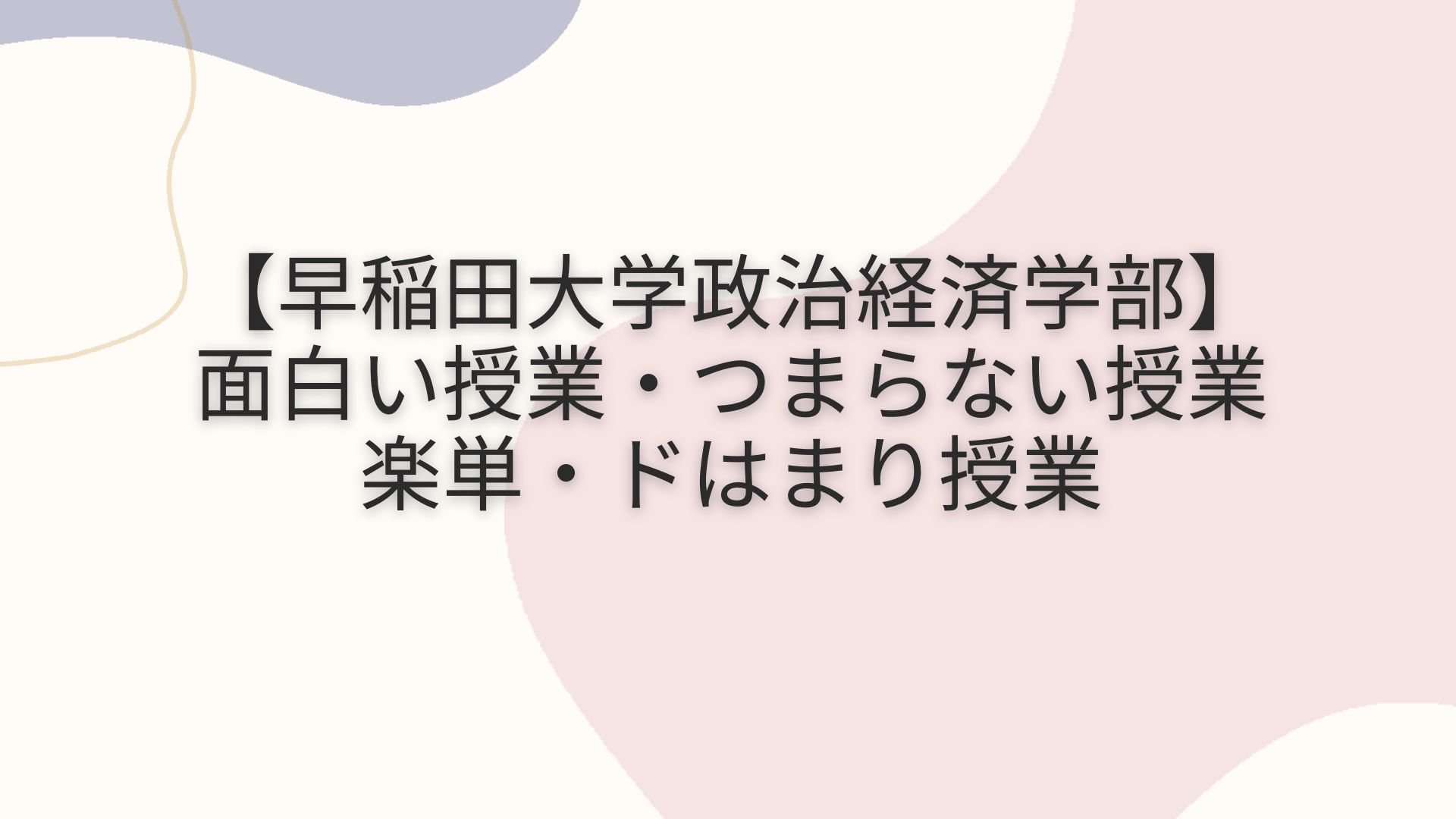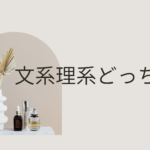早稲田政経って、やっぱり授業もハードなの? 面白い授業とつまらない授業の差って?
今回は、実際に通ってみないとわからない「早稲田大学授業選びのリアル」を、政経4年の僕が本音で語ります!
楽単だった授業、地獄みたいに難しかった授業、思わず唸った神授業まで、4年間の経験をもとに紹介。
※紹介している授業は年度によって内容・教員が変更される場合があります。履修の際は必ず最新のシラバスを確認してください!
目次
政経の授業ってどんな感じ?
早稲田大学政治経済学部、通称「政経」は、名前の通り政治学・経済学・哲学や歴史など、社会科学を幅広く学べる学部です。
1・2年次には「基礎演習」や「データリテラシー」、統計やプログラミングの初歩を学ぶ科目が必修化され、早い段階でリサーチ能力を育成。
3・4年次にはゼミ形式で専門性を深める「演習」科目があり、政治・経済・国際関係など多様なテーマから選ぶことができます。また、英語で提供される授業(英語PSE)も用意されており、留学生とも一緒に学ぶ環境が整っています。
加えて、1年生のうちは「基礎演習」「政治系・経済系基礎科目」「第二外国語」などの必修科目が多く、ほとんどの授業が自動登録されるため、自分で自由に選べる科目はかなり限られています。
特に第二外国語(僕は中国語を選択)の単位数が思ったより多く、文法や会話の小テスト、週2回の授業などで想像以上に負担が大きかったのをよく覚えています。
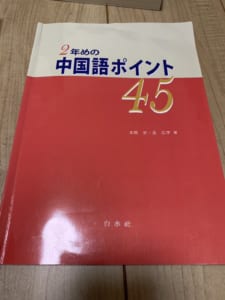
最初のうちは「思ってたより自由じゃない…!」と感じるかもしれませんが、2年次以降は選択の幅が一気に広がるので、そこまでは基礎力をしっかりつける期間だと思って乗り越えるのがコツです。
僕自身、付属校からの進学だったので、入学前は「大学の授業ってどんな感じなんだろう」とぼんやりとしたイメージしか持っていませんでした。けれど、4年間通ってみて思うのは、「授業によって全然違うし、先生次第で天国にも地獄にもなる」ということです。この記事では、そんな政経の授業について、僕の経験をもとにリアルに語っていきたいと思います。
面白かった授業ベスト3
ミクロ経済学入門(田中久稔先生)
1年次の必修科目として履修した「ミクロ経済学入門」は、正直最初は「難しそう…」という印象でした。
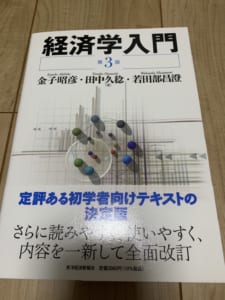
でも実際に受けてみると、経済の考え方が日常生活にどう結びついているかがわかる瞬間が多く「経済学って面白い!」と思えるきっかけになった授業です。
需要と供給、限界効用、価格弾力性など、教科書の中の理論が「スーパーでの商品価格」や「サブスクサービスの値付け戦略」などと結びついて、身近なものとして感じられるようになりました。先生の説明も丁寧で、初学者でも安心して学べる設計だったのが印象的です。
特に印象的だったのは、早稲田キャンパスの近くに「高田牧舎」というイタリアンレストランがあるのですが、そこの名物ピザを食べるときの「一口食べるごとにおなかいっぱいに近づき、一口当たりの満足度が減少していく。これが限界効用逓減だ」という説明でした。理解しやすいような、しにくいような…笑。
ちなみに、この面白いたとえ話を織り交ぜながら授業をしてくれる田中先生はかなり政経の中でも有名な方で、Twitterも解説しており万バズしたこともあるようです。
実験経済学(上條良夫先生)
この授業は、本当に「授業っぽくない授業」でした。
経済学の理論を実際の実験で検証するスタイルで、毎回の授業で実際にゲームや意思決定のシミュレーションを行い、その結果をクラスで分析します。
例えば、「囚人のジレンマ」や「公共財ゲーム」などを実際に学生同士でプレイして、その場で結果を可視化し、なぜそういう行動になるのかを理論的に解説していく流れがとてもスリリングでした。講義だけでなく体験を通じて学ぶことで、経済行動への理解が格段に深まりました。
公共政策(稲継裕昭先生)
「経済政策がどう社会を変えるのか?」という視点から、さまざまな政策の設計・評価方法を学ぶ授業でした。
税制や社会保障、環境政策といったリアルなテーマを扱いながら、「どんな政策が望ましいのか?」をデータと理論に基づいて考える姿勢が身につきます。
僕が特に面白かったのは、「政策に正解はない」ということを前提に、異なる立場の人々の意見をシミュレーションしながら議論を深めていくスタイルでした。授業内でのディスカッションや、政策提案のプレゼンなどもあり、知識を“使う”面白さを実感できる授業でした。
正直、つまらなかった授業
正直「つまらなかった」と感じた授業ももちろんあります。
経済史入門A
名前からして「経済×歴史=面白そう!」と期待して履修したのですが、実際はひたすら年表や出来事の流れを追っていくようなスタイルで、正直眠くなってしまうことが多かったです。
先生の話も真面目で堅実なのですが、どこか“読み上げ授業”に近い雰囲気で、メリハリに欠ける印象を受けました。
個人的には、もう少し具体的な人物エピソードや、現代経済とのつながりなどを交えながら講義してもらえると、もっと頭に入ってきた気がします。逆に言えば、淡々と知識を積み重ねるのが得意な人や、地道に学ぶことが好きな人には向いているかもしれません。
国際政治学
国際関係に興味があった僕にとって、この授業はとても楽しみにしていたものの一つでした。
でも、実際はリアリズム・リベラリズム・構造主義…といった国際関係論の理論をとにかく暗記・整理していくような内容で、想像していた“ダイナミックな国際情勢を分析する”感じとは少し違っていました。
もちろん理論を学ぶことは重要なのですが、授業中のインタラクションも少なく、試験対策が中心になってしまった印象です。「理論→ケーススタディ→ディスカッション」みたいな構成だったらもっと面白くなったのでは?と少し残念な気持ちになりました。
現代政治分析
この授業では、政治学における用語や概念をしっかり定義し、体系立てて理解していくことが求められます。
ただ、その“しっかり”がとにかく重たく感じました。専門用語が次々に出てくる一方で、実際の政治的出来事とのつながりがあまり語られず、抽象的な議論が延々と続くような印象です。
また、指定文献の量がかなり多く、内容も堅めだったため、授業についていくのが精一杯という週も何度かありました。
ディスカッションも控えめで、自分の意見をアウトプットする場が少なかったのも、学ぶモチベーションが上がりにくかった理由かもしれません。
とはいえ、今振り返ると、ゼミや卒論で理論的な背景を理解する際には役立っている実感もあり、「つまらなかったけど無駄ではなかった」タイプの授業だったと思います。
これらの授業は内容そのものは重要なんですが、「授業スタイルが合うかどうか」は本当に大事です。
逆に言えば、同じテーマでも先生が違えば全く印象が変わる可能性もあるので、履修選びではシラバスだけでなく口コミや先輩の話を聞くのがオススメです。
楽単だった授業(取りやすさ重視の人へ)
大学の授業には、「しっかり学ぶけど評価は取りやすい」という、いわゆる“楽単”な授業もあります。
ここでは、僕が実際に受けた中で「これは取りやすかった!」と感じた授業を3つ紹介します。もちろん、学年やカリキュラム変更で内容や評価方法が変わる可能性があるので、その点は注意してください!
社会心理学
この授業は、内容自体もとても面白く、かつ評価が小テスト100%という明快さが魅力でした。
毎回の講義で学ぶ心理学の理論や実験が、日常生活に直結するような話題ばかりで、「なぜ人は他人に流されるのか」「集団心理とは何か」といったテーマに引き込まれました。
小テストも授業内での内容をしっかり聞いていれば解けるレベルで、きちんと出席してメモを取っていれば特別な試験対策は不要でした。心理学に少しでも興味がある人には、楽しく学べて単位も取れる、おすすめの授業です。
線形代数
理系っぽくて難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はこの授業はとても合理的な構成でした。
毎回の課題が成績の中心で、課題の答えは基本的に授業スライドに載っているため、しっかり確認すれば十分対応できます。
数学が得意でない僕でも、詰まったらスライドや配布資料を見返しながら取り組めたので、安心感がありました。
「演習中心でがっつり計算する授業」とは違い、丁寧に基礎を押さえるスタイルなので、数式が苦手な人にも取り組みやすい内容だと思います。
科学技術論
この授業の最大の特徴は、期末試験の出題範囲が事前に明確に告知されること。しかも授業内で先生が何度もヒントをくれるため、しっかり出席していれば対策に困ることはほとんどありません。
授業内容は「科学技術と社会の関係性」に関するもので、たとえばAIや遺伝子操作など、現代的な話題も多く登場します。
理系・文系問わず楽しめるテーマが多く、考えさせられる部分もありつつ、評価は比較的優しめ。知的な刺激もありつつ、単位取得も安心な授業でした。
難しかった授業(だけど学びは深い)
「難しいけど得るものは大きい」──そんな授業に出会うことも大学生活の醍醐味です。
評価が厳しい、課題が重い、試験がハード…。正直、履修中はかなり苦労しましたが、それでも終わってみれば「受けてよかった」と思える授業を2つ紹介します。
政治理論史
この授業は、近代以降の政治思想の変遷を扱う内容で、ホッブズ、ロック、ルソーからハンナ・アーレントまで、多様な理論家たちの思想を深掘りしていきます。
ただし、その学びの深さと引き換えに、毎回のブリーフレポート提出が本当に大変でした。
講義の内容をただまとめるだけでなく、自分なりの視点で問いを立て、批判的に分析することが求められます。しかも締切が週1ペースで来るので、気を抜くとすぐに追われる感覚に。
でも、この訓練を通して「文章で考える力」がかなり鍛えられたのも事実です。政治思想に少しでも関心があるなら、覚悟して飛び込む価値は大いにある授業です。
公共哲学
個人的に大学生活で一番苦労した授業がこれです。
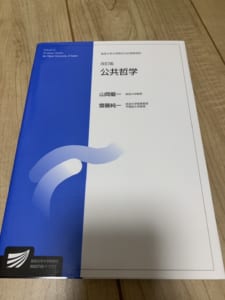
現代社会における「公共性」とは何か、という極めて抽象的かつ複雑なテーマに挑む授業で、哲学・倫理・政治・社会理論などが入り混じった高度な内容でした。
何よりも大変だったのは評価方法。
授業で配布されるレジュメは全10回で合計200ページ以上にもなり、それをもとにした持ち込み不可の記述式試験で成績が決まります。つまり、ただ暗記するだけでは太刀打ちできず、膨大な内容を“理解して構造化”し、自分の言葉で表現する力が求められました。
授業中も先生の語りが止まらないスタイルで、必死にメモを取りつつ、帰宅後にレジュメと格闘する日々…。でも、この授業を乗り越えたことで、自分の中で「難解な理論を自分の頭で考え抜く力」が少しずつついたと感じています。まさに「学びの重み」を感じる授業でした。
授業選びは「相性」と「目的」で変わる
ここまでいろんな授業を紹介してきましたが、結局のところ「自分に合う授業かどうか」がすべてだと思います。
楽に単位を取りたい時期もあれば、しっかり学びたいテーマに出会う時期もある。どちらも大学生活において自然なことだし、それぞれのタイミングで自分にとってベストな授業選びができれば、それで十分です。
大学の授業って、思っていた以上に“先生によって全く印象が変わる”というのがリアルなところです。だからこそ、「この科目が面白いかどうか」は、内容だけでなく教員の講義スタイルや評価方法との相性にも左右されます。
今回取り上げた授業についても、年度によって教員や授業内容、評価方法が変更になる可能性があるので、シラバスや最新情報を必ず確認してください。
高校生の皆さんに伝えたいのは、大学の授業は想像以上に自由で、想像以上に深いということ。
興味のあることにどっぷり浸かれる授業もあれば、「これは自分に合わないかも」と気づける機会もあります。そのすべてが、大学でしかできない“学びの経験”なんじゃないかなと、ほとんどの単位を取り終えた今感じています。
少しでも、「大学って楽しそう」「早稲田政経って面白そう」と思ってもらえたなら嬉しいです。授業選びに迷ったときは、ぜひこの体験談を参考にしてみてくださいね!