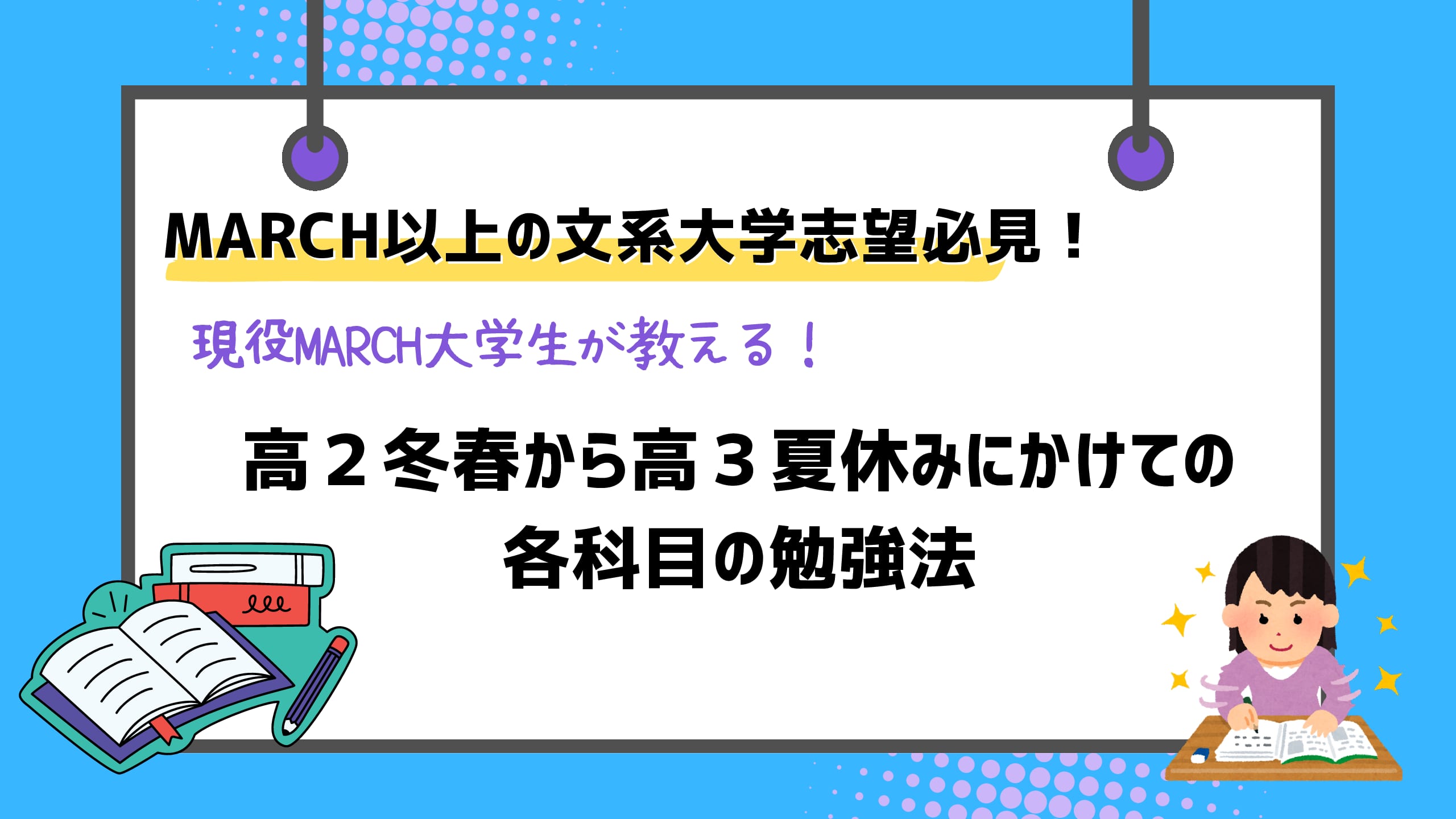Warning: Undefined array key "file" in /home/ukarumemedia/ukaru.me/public_html/wp-includes/media.php on line 1774
高校2年生の冬休みから春休みくらいをお過ごしの皆さんの中で、「そろそろ受験勉強を始めないとな」と考え始めている人も多いと思います。
とはいえ、やる気はあるものの何から勉強すればいいのかわからない・・・。
どの科目をどう勉強すればいいのかよくわからない・・・。
てかそもそも勉強自体が続かないんだけど!!!(´;ω;`)
なんて悩んでいる人も多いことでしょう!
この記事では、
・「国語」「英語」「社会科目」の3科目それぞれで今やるべき勉強
・勉強すべき科目の優先順位
・受験勉強の「考え方」
の3つを、2年前MARCHを受験して合格した筆者の実体験をもとに解説していきます!
【筆者の紹介】
大学:立教大学
学部・学科:経営学部国際経営学科
サークル:最近自分で創作系サークルを作ろうと計画中
趣味:一人旅、youtube、動画編集、ピアノ・ギター演奏、温泉巡り、英語学習
【この記事がおすすめな人】
・MARCH以上文系大学を目指している人
・高校2年生の冬休み~春休みの時期をお過ごしの人
・これから大学受験の勉強を本格的に始めようとしている人
・受験勉強を始めるにあたって何をすればいいか迷っている人
・最近受験勉強を始めたけどなかなかうまくいかずに困っている人
【関連記事】
・進路選びに迷っている人向け、おすすめ自己分析サイト3選
進路ややりたいこと選びに悩むあなたへ!おすすめ無料自己分析サイト3選|ウカルメ~アコガレから探す私の将来~先輩の大学生活を覗き見できるウェブメディア
・これから受験勉強を始める人向け、塾選び・受験勉強の心得
これから受験勉強を始める君へ「受験で後悔しないために気を付けること」|ウカルメ~アコガレから探す私の将来~先輩の大学生活を覗き見できるウェブメディア
英検準1級(スコア2449)の私が教える英検準1級勉強法
英検準1級(スコア2449)の私が教える英検準1級勉強法|ウカルメ~アコガレから探す私の将来~先輩の大学生活を覗き見できるウェブメディア
目次
受験勉強っていつから始めるべき?
そもそも、受験勉強はいつはじめるべきなのでしょうか。
一般的に、MARCH以上の大学を目指す場合、多くの人が高校2年生の冬から春にかけて本格的に勉強を始めている人が多いとされています。
実際私が受験を意識して勉強に取り組み始めたのは高校2年生の冬頃で、過去の学校の定期テストを復習したり、学年末テストに向けて特に気合を入れて勉強したりといったことをしていました。
本格的に「受験勉強」を始めたのは、高校2年生の3月で、予備校に通い始めてからでした。予備校から出される課題をひたすら取り組んでいました。
私の周りでMARCHに合格した人も、だいたい同じような時期に勉強を始めています。
時々、「夏に部活を引退して、その後本格的に勉強を始めて早慶合格!」といった人もいますが、そういう人は基本1年生や2年生の早い時期からコツコツと基礎を固めてきた人や、切り替え能力・要領がよい少数派の人なので、「自分も夏から頑張れば・・・」なんてことを今の時点で考えるのは絶対にやめましょう。
大学受験において、最終的に自分の行きたい進路を実現できるのは、定期テストで一夜漬けで高得点をとれる人では決してありません。
「油断・慢心しない人」です。
私の周りで早慶上智やMARCH以上に合格している人で共通する特徴はそこだと思います。
逆に、どこか油断している人、何とかなるでしょうと考えている人ほど最終的に困っている人が多いです。
今の時期から、決して受験勉強をなめることなく、着実にやるべきことをこなしていけばあなたが希望する進路に必ず合格することができます。
今やるべき勉強の優先順位
MARCH以上の文系大学を目指す人が1番優先して今勉強するべき科目は「英語」で、中でも「英単語」「英文法」「英語長文」に取り組みましょう。
この時期「早いうちに社会系の科目を全部自分で終わらせないと!」などと考えて、とりあえず歴史の教科書を読み始めようとする人が大量発生しますが、この時期は「歴史」より「英語」を優先して勉強しましょう。
というのも、英語は比較的点数を伸ばすのに時間がかかるからです。
今から英語の基礎を固めて、受験当日までに大学受験レベルの問題を解けるようになるためには、かなりの勉強量と時間が必要なんです。
それに対して、社会科目系の暗記科目は、比較的短期間で得点を伸ばしやすい科目です。
一般的に、高校3年生の直前期は授業がなくなって各自家で勉強をするように促す学校も多く、たくさん勉強時間をとることができます。
しかし、その時期から大幅に英語の得点を伸ばすことは難しく、多くの受験生は社会系の暗記科目を中心に勉強します。
だから、今からわざわざ社会科目ばかりに時間をとる必要はなく、どちらかというと英語の勉強に力を入れることをおすすめします。
この時期から高校3年生の夏休み前にかけての英語の勉強法
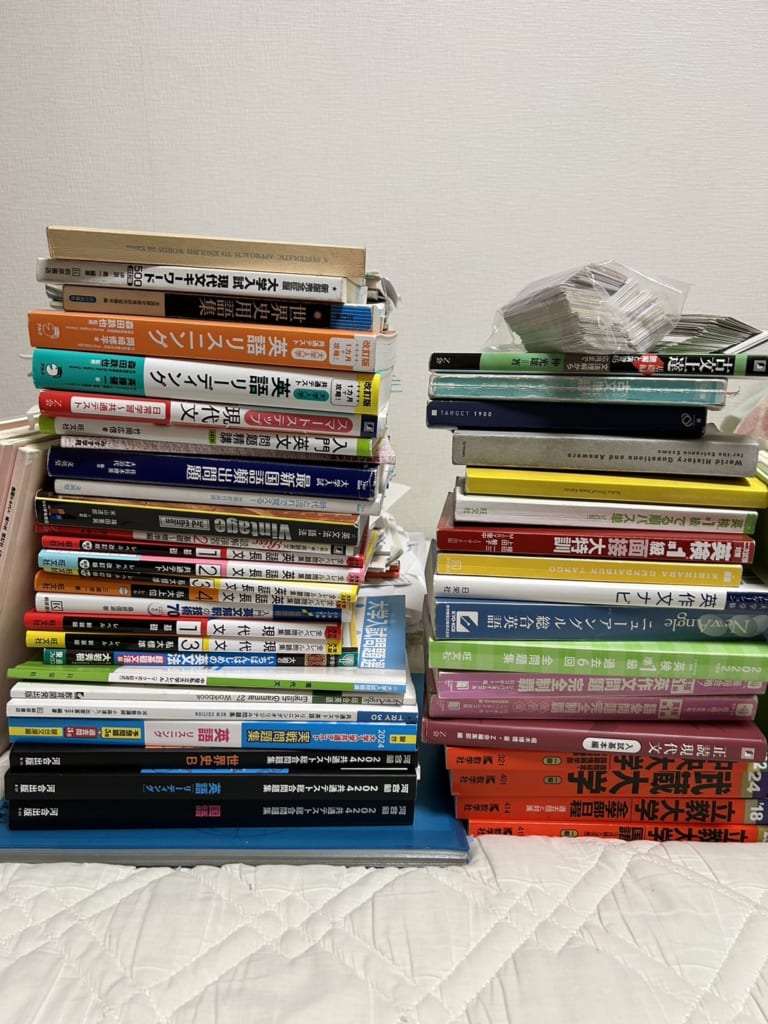
みなさんの最終目標は、「志望校の英語の問題で合格点を上回る得点を獲得すること」です。
まずは自分の第一志望校や、何となく気になっている大学の過去問をぺらぺら眺めてみるか、一度解いてみるかしてみましょう。
「なんじゃこりゃあ!なんもわかんねえぜ!」「あれ?意外といけそうじゃない?」
どんな感想を抱くかは人それぞれですが、約1年後それを皆さんは自力で解くわけです。
みなさんの志望校に太刀打ちできる力を身に着ける上で、今やるべき勉強は、「単語力を固めること」「基礎的な文法をマスターすること」「英文に慣れること」の3つです。
【単語の勉強法】
・単語を勉強すべき理由と、おすすめの単語帳
まず、案外侮りがちな単語力ですが、英語の問題を解く上で基礎中の基礎の力です。出てきた単語が瞬時にわかることで、英文を読むスピードも上がり、問題で聞かれている内容をしっかり理解する力が格段に上がります。
有名どころの単語帳だと、「システム英単語」や「ターゲット1900」なんかが挙げられますね。
基本的に単語帳は自分が好きなデザインのものを使って大丈夫だと思います。
もし学校や塾で指定されていて、その単語帳に合わせた定期的に小テストが開催されるなら、その単語帳を使いましょう。
少なくとも、MARCHレベルの英語なら「システム英単語」や「ターゲット1900」などの単語帳1冊を極めれば十分なので、色々な単語帳に手を出す必要はありません。むしろどの単語帳もうろ覚えになってしまうので、危険です。
ただ、英検対策など英語試験を別で受ける場合はその資格に特化した単語帳を使うことをおすすめします。
私は塾でターゲット1900を指定されていたので、ターゲットを使っていました。
Amazonで見る Amazonで見るあとは、英検対策で英検準1級完全制覇を使っていました。英検準1級を目指す人には1番おすすめの単語帳です。この単語帳は、ターゲットをだいたいマスターした後だとだいぶ楽に解けます。
Amazonで見る・具体的な勉強法
①英単語を見たときにぱっと日本語訳を思い浮かべられるように、繰り返し単語覚える
②先生や友達、家族に英単語を言ってもらって、日本語訳を自分が答える単語テストを繰り返しやる。
③一通り覚えてきたら、なかなか覚えられない単語だけ単語カードに書いて何度も繰り返し覚える
よく、とりあえず単語カードを作ろうとする人がいますが、途中で挫折したり使わなくなる人が多いので、まずは覚えられない単語だけをピックアップしてから単語カードを作りましょう。
そうすることで、特に英語力が伸びるわけでもない、無駄な作業の時間を減らすことができます。
【英文法の勉強法】
単語が読めても、文法がわからないと文章の意味を正確に理解することはできません。
なので、まずは文法の基礎を固めましょう!
英文法の参考書で私が使っていたのは、この2冊です
①大岩の1番初めの英文法
Amazonで見る今までしっかり文法の勉強をしていなかったり、文法に苦手意識がある人はまずこの参考書でざっとおさらいしましょう。
色々な予備校や参考書紹介動画などでも紹介されていて、文法初学者のピッタリな参考書です。
大学受験で必要な文法が網羅的・かつわかりやすく解説されています。
ざっとこの参考書を見てみて、自分の理解に穴がないか、そしてどこが理解できていないかをあぶりだし、重点的に勉強しましょう。
この参考書を使う上での注意点は、初学者向けというだけあって易しめの内容であること、そして演習にはあまり向いていないことです。
この1冊だけでは大学受験用の問題に太刀打ちできるほどの文法力を身に着けることはできないので、もう1冊演習長の参考書を使いましょう。
イメージとしては、文法に不安がある人が、分厚くて難し目な演習に取り掛かるその前に踏む1ステップ用の参考書だと捉えてください。
②Vintage
Amazonで見る大岩の英文法を使い終わった後、取り組んだのが「Vintage」という問題集です。
左側のページに問題が載っていて、右側に解説が載っているというもの。
似たような参考書にNext Stageや、Ever Greenの問題集などがあると思いますが、多分そんなに内容は大きく変わらないはずです。
学校で指定されているものがあれば、それを使いましょう。
ただ、私が学校で配られたBright Stageという問題集は、Vintageなどの問題集に比べて易しめらしいです。(私は予備校でvintageに乗り換えた方がいいよ!といわれたので、Bright Stageは使いませんでした。)
特に特別な使い方はせず、私は3周しました。
間違えたところだけしるしをつけて、翌日復習。何回やっても間違えなくなったらしるしを消す。
2周目でまた忘れている箇所があったらまた印をつける・・・というのをひたすら繰り返します。夏休み前くらいまでずっとこれを繰り返していました。
特にVintageのような分厚い参考書は、全部を繰り返そうとすると挫折しがちなので、自分が間違えたところ、苦手なところを印をつけてチェック!そこを中心にやる!逆に、何度やってもできるところはやらない!といった取捨選択が大切です。
できるところをいくらやっても点数は変わりませんし、苦手なところをできるようになれば大幅に点数が上がります。
何においてもそうですが、受験勉強をする上で重要ことなので胸に刻みましょう。
【英文に慣れるには】
みなさん多少学校のテストや授業などで英語の長めの文章を読んでいると思います。
ところが、皆さんの志望校や共通テストなどの過去問を見てもらえればわかるように、普段触れているであろう英文の量とは比にならないくらい、英文の量が多いんですよね。共通テストなんてどんどん文章が長くなっていますし。
大学入試レベルの英文を読めるようになるには、さっき紹介した
「単語力」×「文法力」×「持久力・集中力」が必要になります。
持久力や集中力は、英文に触れる量を増やし、「慣れる」ことで身に着けることができます。
私が使っていた参考書はこちら
①全レベル別問題集 英語長文シリーズ①~④
Amazonで見るレベル別に色々な大学の過去問から抜粋された英語長文問題が載っている参考書です。
「私はMARCH志望だから④を解けばいいんだ!」
なんてなめた真似はせず、①か②のレベルから初めて、それぞれ3周くらいして使い倒した上で次のレベルに進んでいきましょう!
②英語長文 Rise シリーズ ①から③
Amazonで見る全レベルシリーズの英長文をやっていて、もう少しこのレベルの問題を解いておきたいな・・・という人や、全レベル問題集を解ききってしまった人にはRiseシリーズもおすすめです。
だいたい全レベル問題集の数字の番号と難易度はリンクしているので、並行して取り組むことをおすすめします。
・英語長文の勉強法
今まで私はいろいろな英語の先生や第2外国語の先生に習ってきたのですが、みんな口をそろえて言うのが
「語学は使っただけ、触れただけ上達する」
ということ。
特に英語の長文は読めば読むほど、読むスピードも理解度も上がっていくといいます。
なので、これらの参考書を使って「1日1題」を「毎日」続けていきましょう!
地道な努力を続けていくうちに、突然結果が付いてきます。
英語の勉強法(高2冬から高3夏休み前のまとめ)
高校2年生の冬から高校3年生の夏休み前までは、大学受験レベルの英語問題に太刀打ちできるくらいの基礎を固めましょう!
この時期はいきなり焦って過去問を解きまくったり、難しい問題集に取り組む必要はありません。(だいたい秋くらいから赤本などの過去問演習を始めることをおすすめします)
夏休み前までの具体的な勉強の目安として、
①単語帳1冊を8割がたぱっと答えられるようにする。
②Vintageなどの文法書を3周ほどして、8割がたわかるようにする。
③全レベル問題集3くらいまでを3周ほどして、英語長文に慣れる。
この3つを達成できていれば、順調です!
周りでもっと難しい問題集を使っている人や、既に難関校の赤本なんかを開いてどや顔してる人もいるかもしれませんが、よっぽど基礎が固まってもいない限りこの時期にそんなことしてる場合じゃありません。
とにかく高校3年生の夏休み前までは基礎に徹してください!
この時期から高校3年生の夏休みにかけての国語の勉強法

①現代文
国語を選択した人は全員解く必要がある、「現代文」。
つい、なんとなく勘で解いている人多いんじゃないでしょうか。
そんな、「なんとなく」の解き方だと、受験当日大きく失点してしまうかもしれません。
現代文の勉強は1番受験生からなめられがちですが、侮るなかれ!
とても重要なんです。
現代文こそしっかり解き方をマスターし、演習を積む必要があります。
塾で古典と現代文どっちかの講座をとろうとしているなら、現代文の方を圧倒的におすすめします。なぜなら、それだけ現代文は独学でマスターするのが難しい科目だからです。
私は塾で現代文の先生のもとで解法を学んだうえで演習をしていたのですが、塾に通っていない人はスタディサプリの講座をとることをおすすめします。
私の周りで塾に通っていない人は、スタディサプリで現代文の解法を学んだうえで演習している人が多く、実際それでMARCH以上の大学に合格しているからです。
まずは塾に通うなり、スタディサプリを受講するなりして現代文のプロからちゃんとした解法を学びましょう。
【現代文のおすすめの参考書】
①全レベル別問題集①~④
Amazonで見る私は英語と同じく、塾で指定された全レベル別問題集を使っていました。
現代文は特に、「意味ないでしょ!」とか甘ったれた謎の持論を掲げて解きなおしや復習をしない人が多いですが、現代文こそ演習・復習をしてください。
塾やスタディサプリなどで習った解法をしっかり再現できているかちゃんと復習して、なぜ間違えたのか、どうすれば解けるのかをちゃんと理解しましょう。
②現代文単語
現代文の単語帳、これもまた「いらなくね?」とか言ってなめられがちですが、大学入試レベルの現代文の問題だと、語彙力がものをいう問題も多く出題されます。
例えば、現代文の問題でよく出るのが、この1文の意味に近い内容のものを選択しから選びなさい系の問題。指定された1文と選択肢の1文、同じ内容を指している選択肢を選ぶとき、別の単語で言い換えられているけど同じ意味を指す単語を見つけたら、それが答えになっていたりします。
単語の意味や類似語を覚えておくと、そういった問題はちゃんと根拠をもって答えられるようになります。
なんとなく聞き覚えがある単語でも、自分が思っていた意味と違ったり、別の意味があったりもします。ましてや、MARCH以上の大学の問題になると、そもそもの出てくる単語の難易度も上がって、ちゃんと対策していないと答えられないような単語も出てきます。
そのため、英単語や古典単語と同様に、ちゃんと現代文の単語も勉強しておきましょう。
③漢字
漢字の書き取り問題、読み取り問題は色々な大学で出題されていますし、ここで合否の差が決まってしまう場合もあります。それくらい意外と漢字って重要なんです。
漢字ばかりやる必要はないですが、ちゃんと漢字もマスターしておきましょう。
意外とうろ覚えで、普段から使っている漢字が間違えていたなんてこともあります。
私は立教大学の受験当日の国語で「裏」という漢字を書きなさいをいう問題が出て、ここで初めて私が「裏」を正確に書けないことに気が付きました真ん中が「里」ではなく「田」だと勘違いして覚えていたんです。
意外とこういうことってあるので、「漢字はだいたい大丈夫でしょう」と思っている人ほどしっかり復習しておくことをおすすめします。
漢字の問題集は割となんでも大丈夫だとは思いますが、特に学校などで指定府がない人は漢字マスター1800が評判いいし、使っている人が多いみたいなので使ってみるといいと思います。
私は塾で指定された塾オリジナルのものを使っていました。
② 古文
古文は夏休み前までは、読解よりも「古典文法」と「古典単語」の基礎をがっちり固めることに集中することをおすすめします。
なぜなら、これらの基礎ができていない段階で問題を解いても、遠回りになってしまうからです。
【私が使っていた参考書】
①古典単語330 KEY POINT
Amazonで見る私は単語帳は学校で指定されたものを使っていました。
予備校でもそれで十分だと言われていたので、多分既に持っているものを使えば大丈夫だと思います。
これを片っ端から覚えていくのですが、英単語より断然数少ないので比較的すぐ覚えられると思います。
私も友達とふざけて日常遣いしてたら覚えられました。
当時の友達と恋バナをしているときも、「○○、いとらふたげなり(○○、超かわいい)」とか言って一種の暗号ツールとして使っていました笑
1つの単語でたくさん意味があるものは、4コマ漫画を描いてストーリーで覚えていました。意外とストーリーにしてみるとすんなり覚えられるんですよ。
暗記系は楽しく覚えたもん勝ちなので、自分がわくわくするやり方で覚えることをおすすめします。
②古典文法ジャンプアップノート
Amazonで見るこれです!!!!!!!
みなさんこれですよ!この緑のやつ!!!!!!!!!!!!
これ超おすすめです。
割と薄めな問題集で、毎日やったら1か月もしないで1周できるんじゃないでしょうか。
この問題集さえマスターすれば、古典文法は基本的に怖いものなしです。
この問題集を夏休み前までに最低3周しましょう。
間違えた問題に印をつけて復習して、1通り解いたら2周目、3周目とやっていきましょう。
そうすれば、古典文法は一通りマスターできます。
大学入試の問題では、ここの1文はどういった意味ですか、訳しましょう。あるいは、選択肢の訳の中から正しいものを選びましょうといった問題がたくさん出題されます。
訳の問題のほかにも、ここの助動詞単語は、どういう意味を指しますか。といった直接的な文法の知識を問う問題も多く出題されます。
そのため、文法がわかるだけでだいぶ古典の入試問題を解けるようになるんです。
ぱっと見古典って難しそうに見えるし、なんとなく苦手視する人が多いのですが、古典の文法や単語を一通り覚えれば全然入試レベルの問題は解けます。
そもそも古典の文章の意味なんてほとんどの大学生がよくわかんないまま受験合格していますし、「全部理解する」のではなく「問題に答えられるようになる」ことが重要です。
全部理解したい人は、大学の学部で古典を極めましょう。
むしろ古典って、文法と単語さえ覚えれば得点源にさえなりえるんですよ。
なので、既に「古典読めねえよー」「なんか意味わかんねえよー何語なんだよー」とか思って苦手意識を持っている人は、まずは古典単語帳とジャンプアップノートをマスターしましょう。
③ 漢文
すみません。私は漢文を入試で使っていないので、漢文については他の人の記事を参考にしてください。
ただ1つ言えるのは、私の周りで漢文を選択していた人は、夏休み以降漢文の勉強に取り組み始める人がほとんどでした。
というのも、どうやら漢文はそんなにマスターするのに時間がかからない上、多くの大学で漢文の問題の割合・得点に比が小さめなので、そこまでがっつりと対策しないみたいです。
目指す学校や学部などにもよるかもしれませんが、どちらかというと今の時期は現代文や古典の対策に力を入れた方がいいと思われます。
国語の勉強法(高2冬から高3夏休み前のまとめ)
現代文は感覚で解かず、しっかりとした解法を学ぶことが重要!独学が難しいため、塾や「スタディサプリ」などを活用するのがおすすめです。
問題演習と復習を重ね、間違えた理由を分析!!!!
語彙力も重要なので、現代文単語帳を活用し、類義語や言い換え表現を覚えておくと得点力が上がります。
さらに、漢字対策も忘れずに。試験本番での失点を防ぐため、頻出漢字を確実に書けるようにしておきましょう。
また、古文は夏休み前は、読解よりも「古典文法」と「古典単語」の基礎固めに集中しましょう。
単語は日常で使う、ストーリーを作るなどして楽しく覚えると定着しやすいのでおすすめ!文法は「古典文法ジャンプアップノート」などの参考書を活用し、最低3周することで定着させましょう。
文法と単語が身につけば、古文は得点源になります。
漢文は、私は受験で使いませんでしたが、多くの受験生は夏以降に対策を始めていました。比較的割合が小さい大学も多いため、今は現代文と古文の対策を優先するとよいでしょう。
社会系科目(日本史・世界史・政治経済など)のこの時期の勉強法
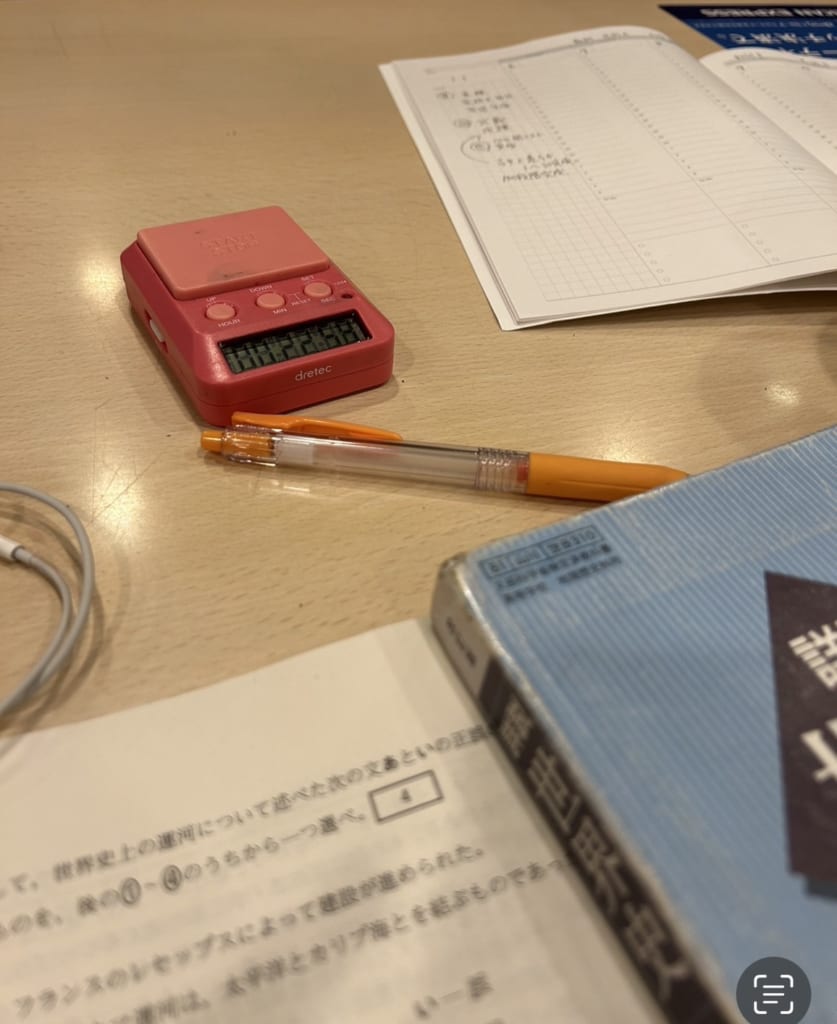
特に歴史系の社会科目を選択している人は、「とりあえず教科書全部読む・・・?」「通史を早く終わらせた方がいいのかな?」なんて考える人も多いと思います。
今は特に新しい範囲を自分でやるのではなく、これまで習ってきた範囲の復習をすることをおすすめします。
さきほど少し言及した通り、歴史系の科目は比較的点数を伸ばすのに時間がかからず、直前期に十分時間をとれば受験当日に間に合わせることができます。
とはいえ、油断してほしいわけではありません。
もちろん、歴史系科目を選択している人は特に、大学受験レベルの問題となるとただ暗記しただけの知識では難しいような問題も多々出てきます。
特に、年号や同じ年代に起きた事件・物事の組み合わせを問う問題や、その前後を問う問題など、ちょっと勉強したくらいじゃ解けない問題がたくさん出てきます。
だからなおさら、時間をかけて「深く理解」「正しく理解」することが必要なんです。
とりあえず通史を自分で終わらせよう!習ってない範囲を自分でやっちゃおう!と思ったり、それを促す受験系youtuberもいますが、私はおすすめしません。
うろ覚えの知識をざっと詰めるよりも、深い知識・そして歴史の場合は歴史的背景などをしっかり理解しながら順を追って勉強していく方があとあと圧倒的に点数を伸ばしやすいです。
うろ覚えな知識を直前にしっかり詰めるのはかなり大変です。一度しっかり覚えておけば、あとは直前の復習や演習でそれを思い出す作業さえできればいいので、今の時期は今まで習ってきた内容の復習に力を入れ、うろ覚えな箇所をなくすことに集中しましょう。
【社会系科目のおすすめな勉強ツール】
①youtube
youtubeには質の高い講義動画や、時代・分野ごともまとめ動画がたくさんあります。
私は世界史選択だったのですが、苦手なところはトライの講義動画を見て理解を深めていました。
図やイラスト、アニメーションなどでストーリー仕立てでまとめてある動画が多く、楽しく学べる上にわかりやすいので、社会系科目は特にyoutubeでの学習をおすすめします。
②教科書
基本的に教科書に載っている内容が大学受験では出題されます。(特に共通テストはそう)
教科書の太字の部分を覚えたり、授業やyoutubeの講義動画などで教科書の内容を自分で補足した書き込みをしていくと、パッと自分の苦手な箇所や復習したい分野を開いた時にわかりやすいです。
それに、私は教科書に書き込みをすることで、「私勉強頑張ってるじゃん!」と達成感を得ることができたので、ビジュアル的に自分の努力がわかりやすくてこの方法は好きでした。(書き込むことを目的にして覚えることをおろそかにしたら本末転倒なのでだめですよ!)
③資料集
教科書だけだと文章中心でなかなかイメージが付きにくいので、資料集は積極的に使っていました(特に歴史選択の人は、地図の問題などのビジュアル系の問題にも対応できるように資料集要チェックです)
④今まで受けた定期テスト
社会系の科目の場合、1番定期テストの勉強がそのまま受験勉強になるので、過去に受けた定期テストをやり直してみると良い復習になります。
先生によって多少癖があったりもしますが、社会の先生がじっくり考えて作ったテストはよく復習しておくと受験勉強にもつながるんです。
今までの問題を持っている人は復習してみましょう。
⑤一問一答
一問一答は早めに手を付けておいて損はないと思います。世界史・日本史・政治経済など色々な社会系目で対応しています。
私はこの時期「時代と流れで覚える世界史」という参考書を使っていて、その後に一問一答を使ったのですが、正直どちらか1つでよかったと思っています。どちらも中途半端になってしまったので。
東進の一問一答が人気ですが、私は個人的にデザインが好みだった斎藤の世界史一問一答を使っていました。
山川のを使っていた人もいますし、有名どころの「一問一答」なら割とどれでも大丈夫だと思います。
ただ注意してほしいのが、一問一答ってすごく分厚いうえにあんまり地図だったり、イラストや写真だったりが少ない傾向にあります。
写真や地図の問題は社会系科目では多く出題されるので、一問一答は基本的に資料集を開きながら勉強するようにしましょう。
また、もう一つ気を付けてほしいのが、自分の目指す大学レベルの問題までしかやらないことです。
斎藤(世界史)・山川・東進の一問一答には、難易度を示す星や過去に出題された大学が載っていあると思います。
いわゆる星3レベルは超難関校で稀に出題されるレベルで、場合によっては「捨て問」な場合もあります。
難関校を目指すみなさんはつい真面目に星3もしっかり覚えようとしますが、星3を覚えるくらいなら、星1レベルと星2レベルを先に完璧といえるくらいに仕上げた方がいいです。
受験においてライバルと差が付くのは、誰も解けない難しい問題ではなく、「みんなが確実に解ける問題」です。
みんなが解けない問題で落としてもそんなにダメージは大きくないですが、みんなが解けている問題が解けなかったら合格することができません。
だから、最初から律儀に全問題に取り組むのではなく、まずは星1と星2のレベルから取り組み、何度も解いて基礎が固まってきた直前期くらいに星3レベルの問題に取り組みましょう。正直それでも全然間に合います。
社会科目の勉強法(高2冬休みから高3夏休み前のまとめ)
社会系科目の勉強では、まずはこれまで習った範囲の復習に力を入れることが大切です!
焦って通史や、習っていない範囲を終わらせるよりも、深く理解することを優先しましょう。特に、年号や出来事の前後関係を問う問題は、暗記だけでは対応しにくいため、背景を含めた理解が重要です。
おすすめの勉強ツールとして、YouTubeの講義動画は視覚的に分かりやすく、楽しく学べます。
また、教科書は基本情報が詰まっており、書き込みながら学習すると効果的です。同時に資料集を活用すると、地図や写真を通じて理解を深められますし、過去の定期テストの復習はアウトプット教材としておすすめです。
一問一答は早めに取り組むべきですが、資料集と併用し、ビジュアル問題にも対応できるようにしましょう。
最初は**基礎レベル(星1・2)の問題を完璧にし、その後、難問(星3)に挑戦するのが効果的です。受験では、「みんなが解ける問題」を確実に得点することが合格への鍵となります!
まとめ
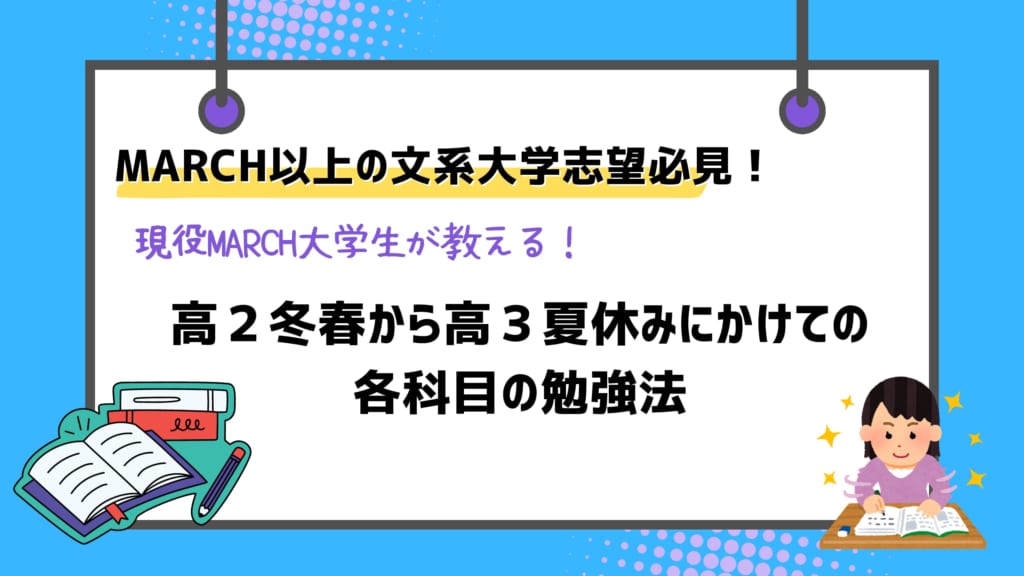
いかがだったでしょうか!
この記事では、MARCH以上の文系大学を目指す人向けに、高校2年生の冬休みから高校3年生の夏休みまでにかけて取り組むべき勉強をそれぞれ紹介しました!
少しでもこの記事が良いと思ったらいいね!お願いします。