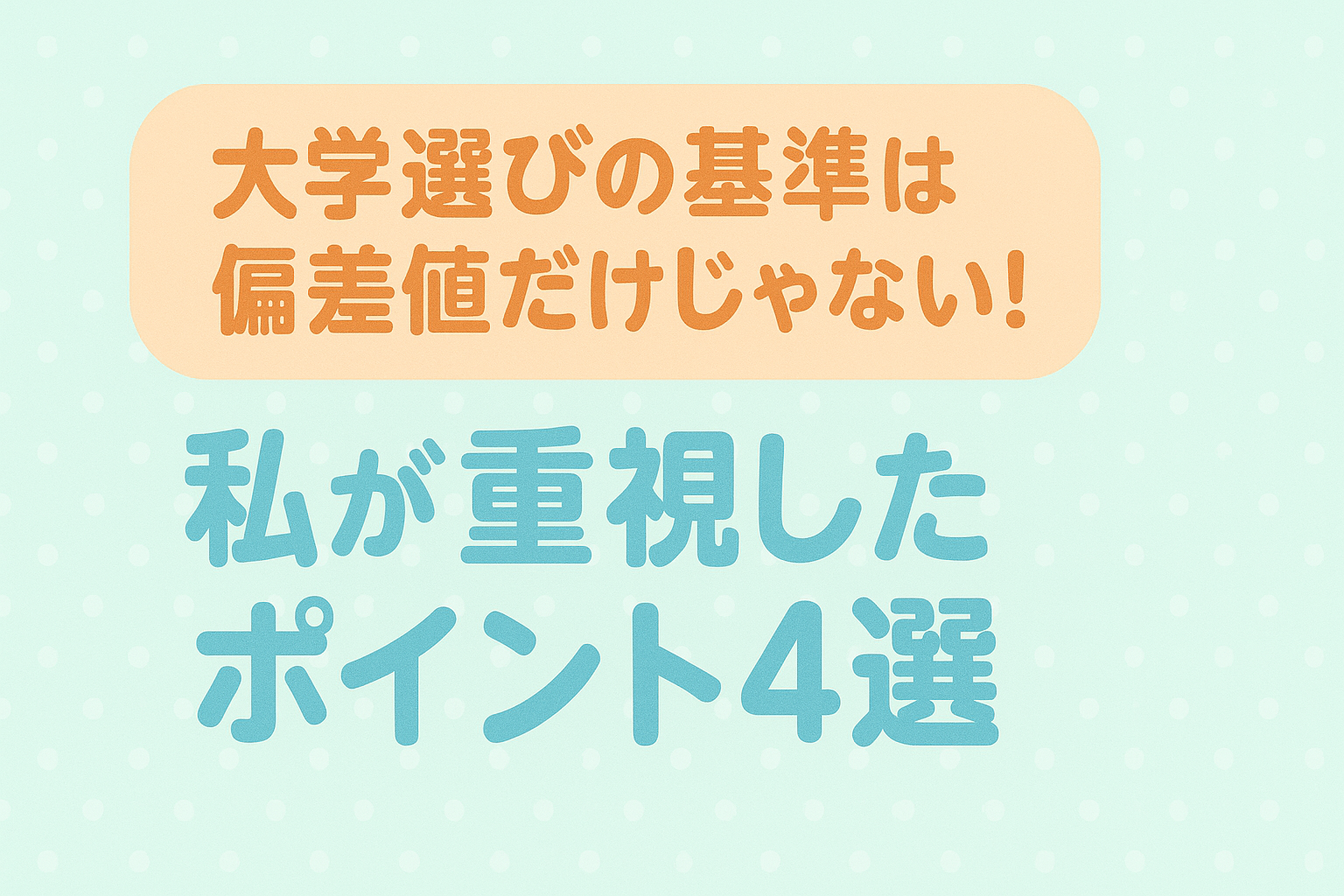こんにちは!早稲田大学国際教養学部4年のせうです!
もうすぐ卒業を控えた今、大学選びから大学生活まで振り返ってみると、「あの時の選択は正解だったな〜」って思うことが多いんです。でも同時に「もっと早くこれを知っていれば…」という後悔もちょっとだけ。
高校生の頃って、進路について考える時に「偏差値」「有名大学」「親や先生の意見」などに振り回されがちですよね。私も例外ではなかったです。でも今思うと、大学選びってこれからの4年間だけじゃなく、その先の人生までに大きく影響するすごく重要な選択なんです!
この記事では、ただ偏差値だけで選ぶんじゃなく、「自分にとって本当に大切なポイントは何か」を見つけるヒントになればと思って書いています。特に「海外に興味がある」「文系だけど具体的にやりたいことがまだ見つかってない」という高校生には、私の経験が少しでも参考になると嬉しいです!
正直に言うと、大学受験って人生で一番つらい時期かも…。でも、その先にある大学生活は自分の世界をめちゃくちゃ広げてくれるチャンスでもあります。だからこそ、自分に合った大学選びができるように、私の体験談をシェアしたいと思います💕
目次
私の進路選択までの道のり
私の海外への憧れは、小学生の頃から始まっていました。休日の朝、ディズニーチャンネルでやっていたアメリカンコメディドラマを見るのが日課だったんです。「ハンナ・モンタナ」とか「ウィザーズ・オブ・ウェイバリー・プレイス」とか…懐かしい(笑)。アメリカの高校生活や、友達との何気ない会話、ファッション、すべてが輝いて見えていました。
「いつか私もあんな風に英語でペラペラ話して、海外で生活してみたいな」
この小さな憧れが、その後の私の進路選択に大きく影響することになります。中学3年生の時に、修学旅行でニュージーランドに3週間滞在する機会がありました。ホームステイ先のファミリーとの会話は最初ぎこちなかったけど、だんだん意思疎通ができるようになっていくのが嬉しくて。でも、同時に「もっと英語が話せたら…」という悔しさも感じました。
その経験から、高校1年生の時には思い切って3ヶ月間のアメリカ留学にチャレンジ!これが私の視野を大きく広げてくれたんですが、一つだけ後悔が…。現地で日本人グループに頼りすぎて、結局日本語ばかり話していたんです。「せっかくの機会なのに、もっと積極的に現地の友達と関わるべきだった」と強く思いました。
この経験から、「次は絶対に長期間、本気で海外に飛び込みたい」という気持ちが固まりました。大学選びでも「留学プログラムがしっかりしている大学」を最優先することに決めていました。
実は私、理系科目がとにかく苦手で(特に物理と化学は本当に理解できなかった😅)、文系を選んだのは自然な流れでした。受験科目は得意な国語と英語、そして大好きだった世界史。世界の歴史を学ぶのが本当に楽しくて、授業中はいつも夢中になっていました。フランス革命からルネサンス、中国の王朝交代まで、教科書を読むのが小説を読むみたいに面白かったんです!
そんな中で早稲田大学の国際教養学部を知ったときは、これだ!と思いました。全ての授業が英語、1年間の海外留学が必須、世界中から集まる留学生と一緒に学べる環境…私の求めていたものが全部詰まっていました。偏差値的にも高くてチャレンジだったけど、絶対に楽しい大学生活が送れるはず!という直感を信じて、猛勉強しました。
振り返ると、小さな頃のテレビドラマへの憧れが、少しずつ具体的な進路選択につながっていったんだなぁと感じます。みなさんもなんとなく好きなこと、小さな頃からの憧れを大切にしてみてください。それが意外と将来の自分を作っていくかもしれません!

留学プログラムの充実度
早稲田大学国際教養学部を選んだ最大の理由は、やっぱり留学プログラムの充実度でした!SILSでは全員が1年間の海外留学を経験するシステムになっていて、これは他の学部や大学にはなかなかない特徴なんです。
入学前は「1年間も海外で過ごせるなんて、夢みたい!」と思っていましたが、実際に留学準備が始まると、たくさんの選択肢に圧倒されました。SILSが提携している大学は世界中に100校以上もあって、アメリカやイギリス、フランス、ドイツはもちろん、アジアや南米、オーストラリアなど本当に多種多様。どこを選ぶか悩みすぎて夜も眠れない日々が続きました笑。
結局私はアメリカのボストンにある大学を選びました。高校生の留学では日本人に甘えてしまった反省から、「今度こそ本気で英語環境に飛び込もう」と決意。ボストンは学生の街として有名で、ハーバードやMITなど名門大学がひしめく知的な環境に惹かれたのも理由の一つです。
留学前は不安でいっぱいでした。授業についていけるかな、友達できるかな、ホームシックにならないかな…でも、実際に行ってみると想像以上に充実した日々が待っていました!
現地の授業は本当に刺激的で、日本の大学では教授の話を一方的に聞くスタイルが多いですが、アメリカでは「発言しないと単位がもらえない」くらい学生の参加が求められます。最初は緊張で胃が痛くなるほどでしたが、だんだん慣れてくると、自分の意見を英語で伝える楽しさを感じるようになりました。
また、寮生活では様々な国の学生と一緒に暮らすことで、本当の意味での「国際交流」を体験。ルームメイトはインド人とフランス人で、夜遅くまで人生観や文化の違いについて語り合ったのは一生の思い出です。「日本人はシャイ」というステレオタイプを壊したくて、イベントにも積極的に参加しました。ハロウィンパーティーで浴衣を着て行ったら大人気だったのは嬉しかったなぁ♪
留学を通じて、英語力はもちろん向上しましたが、それ以上に「異なる価値観を受け入れる柔軟性」や「知らない環境でもやっていける自信」が身についたと感じています。留学前と後では、明らかに自分の視野が広がりました。
ただ、留学にはデメリットもあります。1年間日本を離れるので、就職活動の情報収集で少し出遅れたり、日本の大学の友人関係が途切れてしまうリスクも。でも、SILSでは帰国後のフォローアップもしっかりしていて、「留学組」同士の絆も深まるので、総合的には圧倒的にプラスでした!
大学選びでは「留学ができるかどうか」だけでなく、「どんな留学プログラムか」「サポート体制は整っているか」「費用はどのくらいか」など、細かい点まで確認することをおすすめします。SILSの場合は授業料そのままで留学できるシステムだったので、経済的な負担が比較的少なくて済んだのも大きなポイントでした。
皆さんも、ただ「留学ができる」だけでなく、「どんな留学ができるのか」を具体的にイメージして大学を選んでみてください!
授業の形式と内容
大学選びで2番目に重視したのは授業の形式と内容です。高校までの授業といえば、先生が黒板に書いたことをノートに写して、テスト前に暗記する…というパターンが多かったですよね。でも大学では、自分がどう学びたいかによって選べる幅がぐんと広がります。
SILSの一番の特徴は、全ての授業が英語で行われること。入学当初はとても不安でした。全部英語で大丈夫かな、ついていけるかなって。実際、最初の授業では教授の言っていることの半分も理解できなくて泣きそうになったこともあります笑。
でも、この英語漬け環境が、結果的には大きな成長につながりました。毎日予習で英語の資料を読み、授業では英語で意見を言い、レポートも英語で書く…この繰り返しで、自然と英語で考える力が身についていったんです。1年生の終わり頃には、あれ?今の授業、英語だったっけ?と思うくらい、言語の壁を意識しなくなっていました。
SILSのもう一つの特徴は、少人数制の授業が多いこと。30人以下の授業がほとんどで、大教室での一方通行の講義はほとんどありません。これがどれだけ贅沢なことか、他学部の友達の話を聞いて初めて気づきました。彼らは300人くらいの大教室で教授の顔もよく見えないとか質問する機会がないと言っていたんです。
少人数授業の最大のメリットは、ディスカッションが中心になること。例えば「Media and Society」という授業では、毎回違うテーマについて徹底的に議論しました。「SNSは民主主義を強化するか、それとも弱体化させるか」というトピックでは、クラスが二つに分かれて熱いディベートに。自分の意見を論理的に組み立てる力や、反対意見を冷静に聞く姿勢が自然と身についていきました。
大学選びでは、ぜひどんな授業形式か、どんな学び方ができるかをチェックしてみてください。オープンキャンパスや大学のウェブサイトで実際の授業内容を確認したり、在学生の声を聞いたりすると良いかもしれません。この大学で、どんな学びができるのかを具体的にイメージできるかどうかが、満足度の高い大学選びにつながると思います!
キャンパスライフの多様性
3つ目のポイントとして、「キャンパスライフの多様性」について書きたいと思います。授業や勉強ももちろん大事だけど、大学生活の大半は実は授業外で過ごす時間なんですよね。そのキャンパスライフがどれだけ充実しているかは、大学選びではすごく重要なポイント!
SILSの最大の魅力は、やっぱり国際色の豊かさ。学部生の約3割が留学生で、本当に様々な国からの学生と一緒に学べる環境があります。エレベーターで隣に立った人が突然フランス語で話し始めたり、カフェテリアでスペイン語の歌が流れてきたり…まるで小さな地球村のような雰囲気なんです。
入学して最初の友達は、実はドイツからの留学生のレナでした。オリエンテーションでたまたま隣の席になって、お互い緊張しながらも英語で会話したのが始まり。彼女とは今でも親友で、去年は彼女の地元ベルリンに遊びに行きました。現地の若者文化を体験できたのも、国際色豊かなキャンパスでの出会いがあったからこそ。
留学生との交流は、日本を客観的に見る視点も与えてくれました。例えば、ある韓国人の友人が日本人は本音と建前を使い分けすぎて、何を考えているか分からないと言ったことがあります。最初は少し傷ついたけど、よく考えると確かにその通りで…。そういう外からの視点に触れられるのは、国際的な環境ならではの特権だと思いました。
もちろん、日本人の友達も大切な存在です。SILSは全国から学生が集まるので、地方出身の友達も多く、彼らの地元の文化や考え方を知るのも新鮮でした。東京生まれの私にとって、秋田出身の友達のなまりや郷土料理は異文化交流のようで楽しかったです笑。
3年生からは学生寮のレジデント・アシスタント(RA)として働き始め、それも貴重な経験になりました。留学生のサポートや寮内イベントの企画を通じて、リーダーシップやコミュニケーション能力が鍛えられたと思います。特に「文化の違いによるトラブル」の仲裁役になることも多く、異文化理解の実践の場になりました。
例えば、日本人学生が「夜うるさい」と訴えてくる一方で、ラテンアメリカからの留学生は「こんなに静かな寮は窮屈だ」と言う…そんな時に両者の文化的背景を理解した上で解決策を見つけるのはとても難しかったけど、やりがいがありました。
大学のロケーションも見逃せないポイントです。早稲田は都心にあるので、授業後に友達と新宿や渋谷に遊びに行くことも簡単。インターンシップなどの社会経験を積むチャンスも多いのは大きなメリットでした。
ただ、キャンパスライフの「多様性」は自動的に得られるものではありません。積極的に新しい環境や人間関係に飛び込む勇気も必要です。入学直後は「みんな友達いっぱいできてるのに、私だけ…」と不安になることもありました。でも、少しずつ自分から声をかけたり、イベントに参加したりすることで、徐々に居場所ができていきました。
大学選びでは、どんな人たちと4年間を過ごせるか、どんなキャンパスライフが送れるかを具体的にイメージしてみることをおすすめします。大学のSNSをチェックしたり、在学生の声を聞いたりして、自分に合った環境を見つけてください。結局のところ、大学時代の一番の財産は「出会い」なのかもしれません。
将来の就職やキャリアパス
4つ目のポイントとして、「将来の就職やキャリアパス」について考えていきたいと思います。正直、高校生の時には「就職のこと」まで具体的に考えられていなかったんですが、今思うと大学選びはその後のキャリアにも大きく影響するので、ある程度視野に入れておくべきだったなと感じています。
SILSの就職状況は全体的に良好で、就職率はかなり高いです。卒業生の進路は多様で、外資系企業、商社、メディア、国際機関、大学院進学など様々。英語力と異文化理解力を武器に、グローバルに活躍する先輩が多いのが特徴です。
入学当初、私は漠然と国際的な仕事がしたいと思っていました。外交官や国連職員みたいな…でも、具体的なイメージはなくて。そんな私にとって、SILSでの出会いや経験が将来の選択肢を広げてくれました。
特に大きかったのは3年次の就活準備セミナーです。SILS卒業生が様々な業界から来てキャリアについて話してくれるイベントで、「こんな道もあるんだ!」と視野が広がりました。外資系コンサルティング会社で働く先輩、スタートアップを立ち上げた先輩、NPOでアジアの教育支援をしている先輩…多様なロールモデルに出会えたことで、自分の可能性も広がった気がします。
また、SILSでは1年間の留学が必須なので、就職活動のスケジュールがやや特殊になります。私の場合、3年後期に帰国して、すぐに就活モードに突入…というのは少し大変でした。でも、キャリアセンターのサポートが手厚く、「留学経験をどうアピールするか」などの個別相談に乗ってもらえたのは心強かったです。
さらに、SILSではインターンシップを単位として認定してくれるシステムがあり、私は3年の夏休みに国際NGOでのインターンを経験。難民支援の現場で働く貴重な体験ができました。このインターンがきっかけで、国際協力への関心が高まり、今は卒業後にその分野で働くことを考えています。
就職活動では、SILSの学生であることのメリット・デメリットを感じました。メリットは何といっても語学力と留学経験が評価されること。特に外資系企業の面接では、英語でのディスカッションもスムーズにこなせたのは強みでした。
一方、デメリットとしては専門性が広く浅いと見られがちなこと。SILSでは様々な分野を横断的に学べるのは魅力ですが、就活では結局何を専門に学んだの?と聞かれることも。これに対して私は学際的アプローチこそが現代のグローバル課題に必要とアピールしていました。
また、SILSの強みとして、卒業生ネットワークの存在も大きいです。OB・OG訪問で話を聞いた先輩たちは、みんな親身になってアドバイスをくれました。「SILS出身」という共通点があるだけで、社会人になった今でも繋がりを感じられるのは貴重だと思います。
将来のキャリアを考える上で、大学の就職実績だけでなく、その大学でどんなスキルや経験が積めるか、どんな人脈が広がるかも大切なポイントです。単に就職に強い大学を選ぶのではなく、自分が成長できる環境を選ぶことが、結果的に良いキャリアにつながると思います。
皆さんも大学選びの際には、卒業後のビジョンを少しだけ考えてみるといいかもしれません。明確な夢がなくても大丈夫です。私のように大学で様々な可能性に触れることで、自分の道が見えてくることもありますから!

失敗したこと・後悔していること
大学生活も残りわずかとなり、振り返ってみると「もっとこうすれば良かったな」と思うことも少なくありません。ここでは、私が経験した失敗や後悔について正直にシェアしたいと思います。皆さんの大学選びや大学生活の参考になれば嬉しいです。
まず最大の後悔は、「もっと早くから就活準備をしておけば良かった」ということ。留学から帰ってきてすぐに就活シーズンが始まり、かなり慌てました。特に1年間日本を離れていたため、就活情報や業界研究が十分にできていなかったんです。友達は留学中からオンライン説明会に参加したり、LinkedIn(ビジネス版SNS)でコネクション作りをしていたのに、私は留学を楽しむことに集中したいという気持ちが強くて、就活準備をほとんど後回しにしていました。
結果として、帰国後の数ヶ月は本当に大変でした。昼間は授業、夜は就活情報収集、週末はテスト勉強とESの作成…。睡眠時間が減って体調を崩したこともあります。留学を楽しみながらも、将来のことを少しずつ考える時間を作っておけば良かったと心から思いました。
2つ目の後悔は、専門性をもっと深められたはずということ。SILSの魅力は学際的な学びができることですが、裏を返せば何でも少しずつになりがちな面も。私の場合、国際関係、メディア研究、文化人類学など様々な分野の授業を取りましたが、どれも中途半端な知識で終わってしまった感があります。
今思えば、2年生くらいからこれを自分の専門にしようと決めて、集中的に学んでいれば、もっと深い知識や研究スキルが身についたかもしれません。就活でも結局あなたは何を専門に学んだの?と聞かれて、明確に答えられなかったのは痛い経験でした。
3つ目の後悔は、もっと学内の研究プロジェクトに関わっておけば良かったということ。SILSには教授が主催する様々な研究プロジェクトがあり、学生も参加できるチャンスがあったんです。でも、自分にはまだ早いかな、英語での研究なんてできるかなと躊躇して、結局参加しませんでした。
後から先輩の話を聞くと、そういうプロジェクトに関わることで、研究の進め方を学べるだけでなく、教授との人間関係も深まり、推薦状を書いてもらえたりといいいことばかり。大学院進学を考えている人には特に重要だったと知り、勇気を出して飛び込めば良かったと後悔しています。
4つ目は、日本人の友達ともっと深い関係を築いておけば良かったという後悔。私はどちらかというと留学生との交流に力を入れていたので、日本人の同級生とは表面的な関係になりがちでした。SILSはみんな個々に活動している雰囲気があって、クラスの団結力はあまり強くなかったんです。
でも就活が始まると、情報交換や励まし合いができる日本人の仲間の存在が重要だと痛感しました。留学から帰ってきた時、クラスの中でなんとなく浮いた感じがして寂しかったのを覚えています。国際交流も大事だけど、身近な仲間づくりも同じくらい大切ということを学びました。
5つ目の後悔は、もっと学外の活動にチャレンジすれば良かったということ。大学の授業やサークル以外にも、インターンシップやボランティア、アルバイトなど、様々な経験ができるチャンスがあったはず。特に1、2年生の頃は「まだ時間はたくさんある」と思って、あまり積極的に動きませんでした。
例えば、国際協力に興味があったのに、実際にNGOでボランティアを始めたのは3年生になってから。もっと早くから行動していれば、より多くの経験を積み、自分の適性や将来の方向性をもっと明確にできたかもしれません。
入学前のイメージと現実のギャップもありました。SILSなら全員が流暢な英語を話せて、国際的な議論が活発に行われていると想像していましたが、実際はもっと多様でした。英語が苦手な学生もいれば、留学生と積極的に交流しない学生もいて、「国際的な環境」は自ら作り出す必要がありました。
受験勉強についても後悔が。私はとにかく英語に力を入れて勉強していましたが、入学後に気づいたのは、論理的思考力や批判的読解力がもっと重要だったということ。単に英単語や文法を覚えるだけでなく、なぜそう考えるのかを説明する力を鍛えておけば、大学の授業にもっとスムーズに適応できたと思います。
ただ、失敗や後悔ばかり書いてきましたが、これらすべての経験が今の自分を形作っているとも感じます。完璧な大学生活なんてないし、試行錯誤の過程こそが成長のきっかけになるのかもしれません。
皆さんには、私の後悔を参考にしつつ、「自分はどんな大学生活を送りたいのか」をしっかりイメージして大学選びをしてほしいと思います。そして入学後も、このままでいいのかと時々立ち止まって考える習慣をつけると、より充実した4年間になるはずです。何より大切なのは、自分の選択に責任を持ち、積極的に行動することだと思います。
まとめ:自分に合った大学選びのために
この記事では、私が早稲田大学国際教養学部を選んだ理由や、実際の大学生活で感じたことをお伝えしてきました。最後に、大学選びで本当に大切なポイントをまとめたいと思います。
まず何より重要なのは、偏差値だけで選ばないということ。もちろん、学力レベルは一つの目安になりますが、それだけで決めてしまうと、自分に合わない環境に4年間も身を置くことになりかねません。
私が大切だと感じた大学選びのポイントは以下の4つ:
留学プログラムの充実度 留学に興味がある人は、単に「留学制度がある」だけでなく、「どんな形の留学か」「サポート体制は整っているか」「費用はどうか」など、具体的な内容をチェックしましょう。SILSの1年間の必須留学は大変でしたが、その分得られるものも大きかったです。
授業の形式と内容 「どんな学び方をしたいか」を考えてみてください。大教室での講義型が好きか、少人数でのディスカッション形式が好きか。また、専門を深く学びたいのか、幅広く学際的に学びたいのか。自分の学びのスタイルに合った大学を選ぶことが、4年間のモチベーション維持につながります。
キャンパスライフの多様性 「どんな人と過ごす4年間にしたいか」も重要です。国際的な環境を求めるなら、留学生の割合や国際交流の機会が多い大学がおすすめ。サークルや部活の充実度、キャンパスの立地なども、日常生活の満足度に大きく影響します。
将来の就職やキャリアパス 卒業後の進路も視野に入れて大学を選ぶと、後悔が少ないと思います。「就職実績」だけでなく、「どんなスキルが身につくか」「どんな人脈が広がるか」という観点で考えると良いでしょう。
これらのポイントに加えて、「自分の直感を大切にする」ことも忘れないでください。オープンキャンパスや大学説明会に行ったとき、「ここで学びたい!」と心から思える場所があれば、それは大きなサインです。私もSILSのオープンキャンパスで「ここだ!」と感じた直感を信じて、猛勉強した結果、志望校に合格できました。
振り返ると、SILSを選んだことは私にとって正解だったと思います。英語力や異文化理解力が身につき、視野が大きく広がりました。もちろん、後悔していることもありますが、それも含めて貴重な経験でした。
最後に受験生の皆さんへ。受験勉強は本当に大変だと思います。でも、その先にある大学生活は、自分自身を大きく成長させてくれる貴重な時間です。「自分は何を学びたいのか」「どんな人間になりたいのか」をじっくり考えながら、自分に合った大学を探してみてください。
偏差値や世間の評判に流されず、自分の心に正直に選んだ道は、きっと素晴らしい経験をもたらしてくれるはずです。皆さんの大学選びと、その先の大学生活が実りあるものになることを心から願っています!