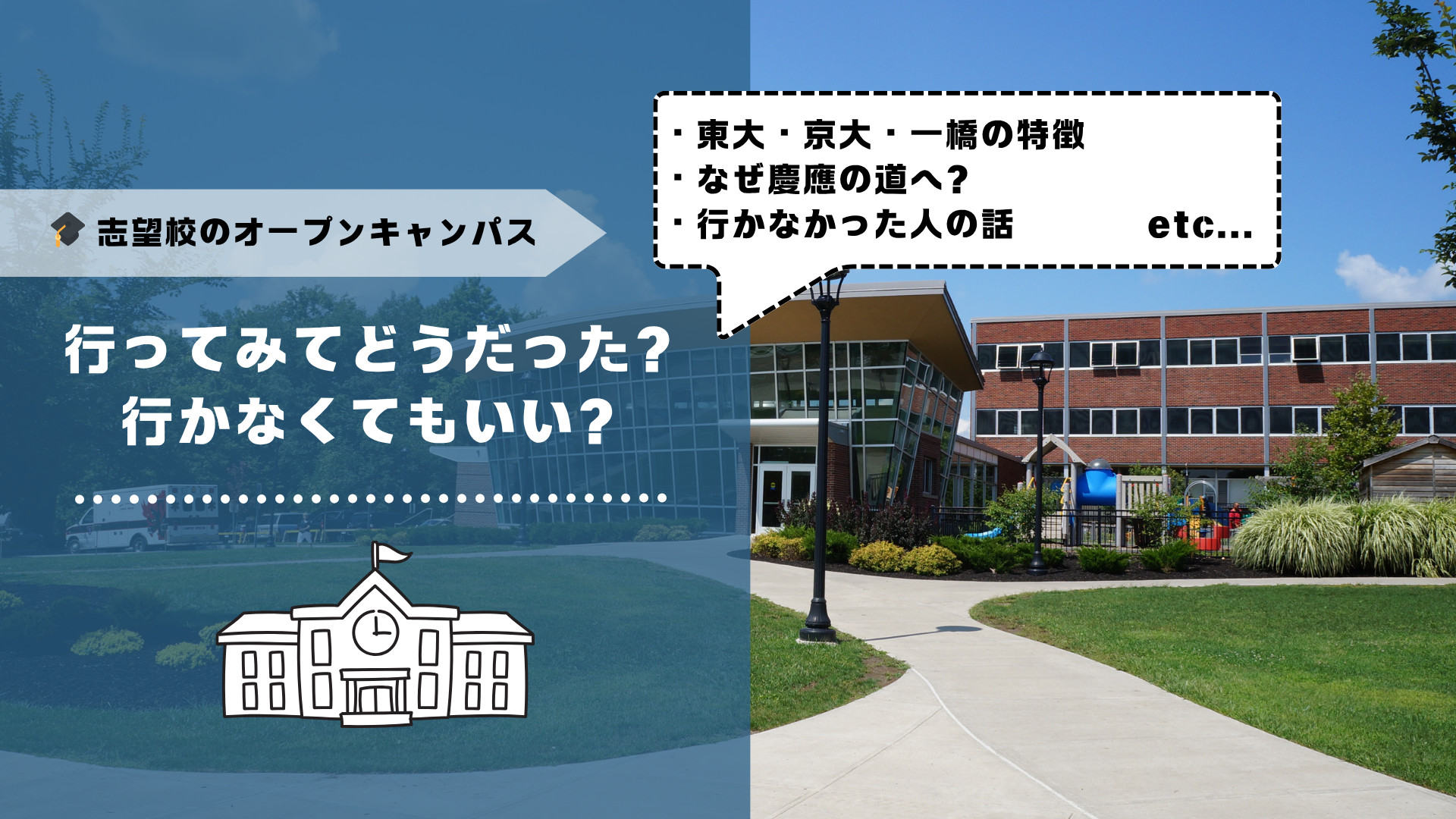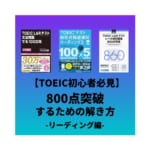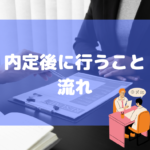目次
はじめに:オープンキャンパス、行くべきかどうか問題
高3の夏、進路のことを考え始めた頃、最初にぶち当たった疑問がありました。
それが、「オープンキャンパスって、行った方がいいの?」というやつです。
周りの友達の間でもこの話題はけっこうあって、
- 「行くとモチベ上がるらしいよ」
- 「でも、交通費とか時間がもったいなくね?」
- 「別にネットで調べれば良くない?」
みたいな感じで意見が割れてました。正直、自分も最初はそこまで前向きではなくて、
「いやいや、学校の雰囲気を見に行くだけで何がわかるんだよ?」って思ってました。笑
ただ、進路指導の先生とか親に「せっかくの機会だし行ってみなよ」って言われて、まぁたしかに…と思って、試しに行ってみたら、これが思ってた以上にいろんな気づきがあったんですよね。
オープンキャンパスに行く前に抱いてた本音
「自分にはまだ遠い世界だし、行っても意味ないかも?」
「そもそも東大とか京大とか、レベル高すぎて自分には関係ないのでは…」
「時間とお金がかかるし、部活もあるし、正直めんどくさい…笑」
高校って忙しいし、受験勉強だけで手いっぱいになりがちなので、こういう気持ちになるのはめっちゃわかります。
でも、行ってみて初めてわかることって本当に多かったんです。
行ってみたら想像以上に「リアル」だった
写真とか動画、大学のパンフレットだけでは分からない、「その場の空気感」とか「学生の雰囲気」って、やっぱり現地じゃないと伝わってこないんですよ。
たとえば、
- キャンパスがめちゃくちゃ広くて、「自分ここで4年間過ごせるのか?」って考え込んだり
- 学生の発表や講義にワクワクしたり、逆に「なんかピンとこないかも」って思ったり
- 休み時間に談笑してる学生の雰囲気を見て、「自分ここに馴染めるかな…?」って不安になったり
みたいな感じで、自分の中の価値観がめっちゃ揺さぶられる体験になったんです。
でも、行けない人が損するわけじゃない
ここまで読むと「やっぱオープンキャンパス行かなきゃ!」って思うかもしれませんが、行けない事情がある人もいると思います。遠方だったり、部活や塾でスケジュールが厳しかったり。
実際、僕の友達にも一度もオープンキャンパスに行かずに志望校を決めた人が何人もいました。
その人たちはどうしてたかというと、
- 先輩や先生から話を聞いたり
- SNSやYouTubeで大学紹介を見たり
- 模試の判定や学部の内容を徹底的に調べたり
って感じで、自分なりに「納得できる材料」をちゃんと集めてました。
行けるなら行くべき!でも、行けなくても焦らなくてOK!
オープンキャンパスって、受験の合否には直接関係しないかもしれません。でも、自分の中で「ここに行きたい!」っていうモチベーションが生まれるきっかけになるし、
「なんか違うかも…」って気づけるブレーキにもなる。
つまり、“判断の精度”を上げるツールみたいなものだと思ってます。
行ったからこそ見える世界があるし、行けなかったら行けなかったで、他の手段で情報を取りに行けば大丈夫。
大事なのは、「なんとなく」じゃなくて、自分で選んだって納得感を持つことだと思います!
次は、実際に僕が行った東大・京大・一橋のオープンキャンパス体験について、それぞれ紹介していきます!
それぞれ全然違う雰囲気だったので、これから行く人の参考になると嬉しいです!
【高3夏】東大・京大・一橋を巡る
高3の夏休みって、部活を引退してようやく「受験本気モード」に入る時期ですよね。
当時の僕もまさにそんな感じで、少しずつ志望校について真剣に考え始めていたころでした。
通っていた高校は、わりと国公立大学志向が強い学校で、なんとなく「まずは東大を目指す」っていう空気があったんですよね。
もちろん自分自身も、東大や京大ってどんなところなのか興味があったし、せっかくなら一橋も含めて実際に自分の目で見てみたい!と思って、夏休みの予定にオープンキャンパス巡りを組み込むことにしました。
◉ ルートは超ハード!?東京→京都→国立(くにたち)
今思うと、けっこう無謀なスケジュールでした。笑
ざっくり言うと、こんな感じ。
- 【Day1】地元→東京大学(本郷キャンパス)
- 【Day2】移動日&京都観光ちょこっと
- 【Day3】京都大学(吉田キャンパス)
- 【Day4】帰京して、一橋大学(国立キャンパス)
- 【Day5】地元へ移動
移動だけでも疲れるし、各大学のキャンパスがとにかく広くて歩きまくるので、地味に体力勝負。しかも猛暑。8月の都内と京都の暑さは、ガチでやばかったです。
でも、この「3校リアルで見比べた」経験は、今振り返っても自分の進路選択にめちゃくちゃ影響したと思ってます。
オープンキャンパスって何するの?って思ってた
当初は正直、オープンキャンパスで何をするのかよくわかってませんでした。
- 模擬授業を受ける
- キャンパスを案内してもらう
- 学生の話を聞く
- 入試やカリキュラムの説明を聞く
- パンフレットをもらう(笑)
ざっくり言うとこんな感じだったんですが、大学によって全然雰囲気が違う!
たとえば、東大は全体的に「厳かでアカデミック」な感じだったし、京大は「自由でちょっとクセ強め」な印象。一橋は「落ち着いてて、リアルな日常感がある」というか。
実際に行って、話を聞いたり校内を歩いたりしてみて、パンフレットやネットの情報だけじゃ分からないことが多すぎる!と痛感しました。
1人で参加するのが不安?僕もめちゃくちゃ緊張した
ちなみに僕は、ほとんどの大学を1人で見に行きました。正直、ちょっと怖かったです。笑
だって周りは友達と来てる人ばっかだし、親と来てる子も多くて、1人でウロウロしてる自分がちょっと浮いてる気がして…。でも、逆に1人だからこそ自分のペースで自由に回れたっていうメリットも大きかったです。
- 模擬授業も好きなものを選べる
- 気になる掲示板とかサークル勧誘もじっくり見れる
- 疲れたら休憩してスマホで調べながら校内を見て回れる
むしろ、大学生気分を先取りできた感覚があって、それが受験のモチベにもつながりました!
進路を「自分ごと」に変えるきっかけだった
このオープンキャンパス旅で一番大きかったのは、「大学受験=他人事」だったのが、「自分の人生の選択」なんだって気づけたこと。
それまでは先生とか親に言われるがまま、「とりあえず東大か京大目指す」って感じだったけど、実際にそれぞれの大学を見て、リアルな空気を感じて、「ここで4年間過ごしたいか?」「自分はどんな大学生活を送りたいか?」ってちゃんと考えるようになった。
この変化は、自分にとってめちゃくちゃ大きかったです。
行って疲れたけど、行かなかったらもっと迷ってたと思う
もちろん移動もハードで、暑さもえげつなくて、終わったあとは「もう歩けん…」ってなるくらい疲れました。笑
でも、だからこそ心に残ったし、進路の軸が「偏差値」だけじゃなくて「自分の感覚」になったのは本当に大きかった。
「めんどくさいな〜」「交通費高いしな〜」って悩む気持ちもめちゃくちゃ分かる。
でも、あの夏に動いたからこそ、最終的に自分が慶應を選ぶときも、ブレずに決断できたと思ってます。
次からは、実際に行ってみたそれぞれの大学について、感じたことやギャップをさらに詳しく紹介していきます!
「えっ、東大ってそんな雰囲気なの?」みたいな話もあるので、よかったら読んでみてください!
【東大オープンキャンパス】圧倒的「王者感」と自分の距離
「とりあえず東大」——
これは、僕が通っていた高校で何度も耳にした言葉です。
実際、進路指導室に貼られている進学実績も、圧倒的に「東京大学」が目立っていて、どこか“憧れ”というより“前提”になっていたような雰囲気がありました。
でも、実際に行ってみた東大のオープンキャンパスは、想像以上に衝撃的でした。
その衝撃は、「すげぇ……」っていう憧れの気持ちと、「いや、ここに自分がいるイメージが湧かない」っていう現実的な距離感が、両方同時に襲ってくるような感覚でした。
安田講堂の前に立った瞬間、静かに圧を感じた
オープンキャンパス当日は、朝から本郷キャンパスに向かいました。
駅を出て歩いていくと、赤門が見えてきて、テンションが自然と上がっていく。そしていよいよ、安田講堂の前に立った瞬間、ふわっと鳥肌が立ったんです。
「ここが、あの東京大学か……」と。
建物の重厚感、広々としたキャンパス、周囲にはそれぞれの目的意識を持って動いてるっぽい高校生たちと案内スタッフの学生たち。
言葉にはしづらいけど、“日本のトップ”ってこういう場所なんだなっていう空気を、肌で感じました。
模擬授業のレベルが高すぎて、思考が追いつかない(笑)
僕が参加したのは、東大経済学部の模擬授業。
テーマはたしか、「行動経済学と意思決定」みたいな内容で、興味はめちゃくちゃあったんです。
でも、講義が始まって10分後くらいに悟りました。
「これは……完全に置いていかれてる」と。笑
教授の話し方がめっちゃ早口というわけではなかったんですが、前提知識のレベルが高くて、例え話も専門的で、“理解しようとする頭”に負荷がかかる感じ。
周りの学生はメモ取りながら「うんうん」ってうなずいてて、それ見て「マジでみんな天才じゃん…」って思ってました。
正直、自分がここで4年間学ぶ姿が想像できない…って、そのとき思ってしまったのを覚えています。
在学生の「圧倒的自信」と、そこに感じたギャップ
説明会のあと、東大生との座談会にも参加しました。ここでは、何人かの学生が大学生活について語ってくれていて、雰囲気はかなりオープンでした。
でも、話の内容がやっぱりすごい。
- 「ゼミで海外の研究論文読んでます」
- 「休みはスタートアップ企業のインターンしてます」
- 「将来は官僚か、起業も考えてて…」
……うん、すごいんだけど、自分とは別世界の人たち感がすごかった。
別に東大生全員がそういう人ってわけじゃないのは分かってたけど、やっぱり「入る人が違う」「価値観が違う」って、ひしひしと感じてしまって。
そのときの自分はまだ、「すごい人たちの中に飛び込む勇気」が持てなかったんだと思います。
自分の中で生まれた“違和感”が、ある意味で収穫だった
東大に行ったこと自体はめちゃくちゃ良い経験でした。刺激もあったし、自分がどれだけ知らないかを痛感したし、
「自分ももっと勉強しなきゃ」って背中を押してくれるエネルギーをもらったのは確かです。
でも同時に、「この場所は、たしかにすごいけど、自分が自然体でいられるかは別だな」っていう感覚が残ったのも事実。
まわりの空気やプレッシャーに飲まれず、自分のやりたいことを貫けるほどの覚悟が、当時の自分にはまだ足りなかったのかもしれないな…と。
この“違和感”をちゃんと受け止められたからこそ、後の進路選択でも冷静になれた気がします。
「憧れの場所」と「自分に合う場所」は違うかもしれない
これは東大に限らず、すべての大学に言えることかもしれませんが、どれだけ有名でも、偏差値が高くても、「自分がそこに通う姿」がイメージできないと意味がない。
東大は間違いなく素晴らしい大学で、行って損はないです。
でも、行ったからこそ「ここは自分の場所じゃないかも」と気づけたのは、めちゃくちゃ大きな収穫でした。
次は、京大のオープンキャンパスについて書いていきます!
東大とは真逆な“ゆるさ”にびっくりした話や、自由すぎる授業に笑ったエピソードもあるので、ぜひ読んでみてください!

【京大オープンキャンパス】自由すぎる空気と「ゆるさ」に戸惑い
東京から新幹線に乗って京都へ。
東大オープンキャンパスを終えて、その足で向かったのが京都大学のオープンキャンパスでした。
正直、「東大と同じくらい賢い大学だし、似たような雰囲気なのかな」と思ってたんですが…
結論:全然違いました。
いや、ほんとにびっくりした。笑
京都駅からのんびりバスで、いざ吉田キャンパスへ
まず、京都大学ってアクセスの時点でちょっと独特です。最寄り駅から少し歩くし、観光地のど真ん中にあるわけでもない。
僕は京都駅から市バスで向かったんですが、バスの中には観光客と受験生が混在してて、なかなかカオスな空気感でした。
ようやく到着した吉田キャンパス。
入ってすぐ感じたのは、なんか静か。のんびりしてる。空気がゆるい。
東大の「ピシッとした王者感」がまだ体に残っていた僕は、そのギャップにちょっと戸惑いました。
建物が古い、でもそれが味わい深い?
京大のキャンパスって、見た目でいうとけっこう“味”があります。
近代的な建物は少なくて、歴史を感じる木造の校舎や、ちょっとボロめの研究室が点在してました。
「えっ、ここ大学の本部なの?」って思うような建物もあって、ある意味衝撃。
でも、それがまた「学問って、こういう空間で黙々とやるものなんだな」って納得できる雰囲気で、
妙に落ち着いたし、親しみを感じたのも事実です。
模擬授業が“自由すぎて”思わず笑った
僕が参加した模擬授業は、経済学部のものだったんですが、テーマはたしか「貨幣と信用の歴史」とかだったと思います。
これがまた、めちゃくちゃ面白いんだけど、脱線が多すぎる。笑
先生が、
「この話、ちょっと横道それるけど…まあええか(笑)」
って言いながら、関係ありそうでなさそうな話を延々としてくれて、最終的に本筋に戻ってくる…みたいな感じ。
普通だったら「話長くない?」ってなるのかもしれないけど、なぜかそれが京大っぽいというか、「この自由さが逆に信頼できる」って思えたんです。
在学生とのトークで分かった「自分に厳しい自由人」たち
在学生のトークセッションにも参加しました。そこで話してくれた京大生の雰囲気は、とにかく“自由人”が多い。
- 「サークル入ってないけど、代わりに詩を書いてます」
- 「教授と友達みたいな関係で、たまに一緒に飲みに行く」
- 「単位はギリギリだけど、図書館にずっとこもって個人研究してます」
こんな話を、みんなマイペースに淡々と語るんです。
「え、それ普通の大学生活?」ってびっくりしたけど、よく聞いてると、自分の軸をしっかり持ってて、誰かに流されることがない人ばかり。
つまり、京大の“自由さ”って、ただゆるいわけじゃなくて、「自分に甘くない人だからこそ、自由にできる」ってことなんだなと、ちょっと感動しました。
校門の落書き、そして伝説の「折田先生像」
あと、これは完全に余談なんですけど(笑)
京大といえば、毎年勝手に現れる謎の「折田先生像」で有名なんですよね。
僕が行ったときは残念ながら見られなかったんですが、キャンパスの塀にチョークで落書きが残っていたりして、「なんか大学全体がひとつの文化祭みたいだな」と思いました。
東大との一番の違いは、こういう“遊び心”が堂々と存在してるところかもしれません。
いい意味で“はみ出してる”というか、「それもアリ」って許容する土壌がある感じ。
「自由にやっていいよ」って言われたとき、動ける自信があるか?
京大に行って感じたのは、
「自由=楽そう」じゃなくて、「自由=自分で全部決めなきゃいけない世界」だということ。
高校までって、何かと“型”があるし、「これをやっとけば正解」みたいなものが存在しますよね。
でも、京大はその型すら自分で作らなきゃいけない雰囲気がありました。
僕自身、「そこまで自分で決められるタイプかな…?」って考えたとき、ちょっと迷いが生まれたのも事実です。
ゆるいけど強い、それが京大
結果的に、京大のオープンキャンパスは、一番“心に残った”大学だったかもしれません。
派手なキャンパスでもないし、説明会もゆるっとしてるけど、そこにいる学生たちの言葉や姿勢に、芯の強さを感じた。
「大学って、こういう場所もアリなんだな」って新しい価値観に触れられたし、東大とはまた違った意味で、「ここに通う自分」を考えるいい機会になりました。

【一橋オープンキャンパス】「リアルに行けそう」感と落ち着き
東大の「王者感」、京大の「自由すぎるゆるさ」を経て、最後に訪れたのが一橋大学のオープンキャンパスでした。
正直、当時の僕にとって一橋は「すごい大学」ってことは知ってるけど、東大・京大に比べてあまり情報がないし、印象もふわっとしてたんですよね。
でも、実際に行ってみたら――
「ここ、ちょっと現実的にアリかも」
って、素直に思えたのが一橋でした。
国立駅からすぐ、アクセス最高
まずアクセスの良さにビビりました。国立(くにたち)駅から歩いて5分もかからない。
東大や京大が「都市の中の知の城」って感じだったのに対して、一橋は街にすっとなじんでるんです。
キャンパスも、駅から続く大学通りの並木道の奥に静かに広がっていて、“都会すぎず、田舎すぎず”なちょうどいい空気感。
あの落ち着き具合は、本当に印象的でした。
模擬授業で感じた「地に足のついた学問」
僕が参加したのは、社会学部と経済学部の模擬授業。
どちらもテーマは「社会課題と政策」みたいな内容で、めちゃくちゃ今っぽいし、何より“実社会とつながってる感じ”がすごく新鮮でした。
教授の話し方も、良い意味でフラット。
難しい専門用語を使いすぎず、でも中身はしっかりしていて、「大学って、こうやって“考える力”を養うんだな」って、ストンと腹落ちした瞬間でした。
特に印象に残ってるのは、ある先生が言ってたこの言葉。
「一橋は“社会の中でどう役立つか”を問いながら学問をやっていく大学です。」
この一言に、一橋の教育姿勢そのものが詰まってる気がしたんですよね。
「社会と近い」って、こんなにも安心感があるのか
東大や京大の授業はどこか「研究者向け」の色が強くて、「これって就職とか仕事にどうつながるんだろ?」って思う部分も正直ありました。
でも一橋は、模擬授業でも在学生の話でも、「社会とどう関わるか」「就職をどう考えるか」がめちゃくちゃリアルに語られてたんです。
特に、商学部の学生が話してくれた、
「3年のゼミで企業訪問して、実際の課題に対してプレゼン作ったんですよ」
というエピソードを聞いたとき、「あ、ここなら自分も“働く自分”をイメージしながら学べるかも」って思えました。
キャンパス全体に漂う「品のある静けさ」
一橋の吉祥寺キャンパス(※注:経済学部などの主要学部は国立キャンパス)は、どこを歩いても“落ち着いた静けさ”が漂ってるんです。
東大みたいな威圧感もないし、京大みたいな個性の大爆発もない。
だけど、どこか凛としていて、「知的な人たちが静かに日々を積み上げている場所」という感じがしました。
そしてそれが、自分にとって“居心地がいい”と感じられたのが、一橋の一番の魅力だったのかもしれません。
一橋生とのトークで見えた「堅実だけど熱い人たち」
在学生の座談会では、意外な発見もありました。
一橋って“真面目でお堅い”イメージがあったんですけど、話を聞いてみると、みんなめっちゃ情熱的。
- 「ビジコン(ビジネスコンテスト)で優勝目指してがんばってます」
- 「NPOの立ち上げに関わってます」
- 「金融系のインターンに行って、将来のビジョンが見えました」
みたいに、自分の将来に対してちゃんと向き合っていて、でもその語り口は落ち着いてて、堅実で、背伸びしてない感じ。
東大・京大の“天才”オーラとはまた違う、「努力と現実を重ねて夢を描いてる」姿勢に、共感しまくりでした。
「ここなら、自分も自然体で学べるかも」と思えた
一橋を訪れて一番大きかったのは、
「ここでなら、自分が無理せずに頑張れそう」って思えたことでした。
もちろん東大や京大のような“ブランド”はある意味で魅力です。
でも、「頑張るために自分を変える」のではなく、「今の自分をベースにして、頑張れる場所」を見つけることって大事だなと実感しました。
そして、自分の進路に変化が…?
東大に憧れて、京大にワクワクして、でも一橋で初めて「現実的に通いたい」と思った。
この“一橋体験”を通じて、僕の中で「自分に合う大学って、ブランドじゃなくてフィーリングかもしれない」という考えが芽生え始めました。
この気づきが、やがて僕が慶應義塾大学に進むことを選ぶ、大きなヒントにもなっていきます。
次は、僕がなぜ国立志望から私立・慶應へ進路を転換したのかのお話です。

じゃあなんで慶應?国立→私立への心境の変化
「東大にも京大にも一橋にもオープンキャンパス行ったのに、なんで慶應なの?」
これ、大学に入ってからも何度か聞かれました。
正直、自分でも当時は「なんでだろ?」って思うこともありました。でも今振り返ると、あの決断には、“自分の本音”と“現実”がせめぎ合って出した、人生で一番素直な選択だった気がします。
今回は、そんな進学校の“国公立至上主義”にいた僕が、どうして私立の慶應を選んだのか。その心の動きと、実際の決断までをリアルに書いていきます。
進学校あるあるの“空気”
僕が通ってた高校、いわゆる地方の中堅進学校だったんですが、雰囲気は完全に「国公立神話」。
- 「センター試験(今の共通テスト)を軸に受験プランを組む」
- 「私立はすべり止め。行くとしても早稲田まで」
- 「慶應は推薦組か浪人して再チャレンジした人が行くとこ」
…みたいな空気がどことなくあって、私立を第一志望にする=弱気 or 妥協って雰囲気、ぶっちゃけあったんです。
僕自身も最初は完全にその影響を受けてて、志望校欄にはずっと「東京大学→一橋大学」と国公立オンリー。
慶應や早稲田は「受けるかもしれないけど…まぁ、最終的には行かないかな」くらいの感覚でした。
高3秋、思ってたより“自分の実力”が…
ただ、現実はそんなに甘くなかった。
高3の夏までは「模試でB判定」「過去問も解いてるし、まあ大丈夫でしょ」っていう自信、あったんです。
でも、秋になって本番が近づくと…
- 模試の判定が急に下がる
- 共通テスト模試の点が安定しない
- 私大の問題形式を見たら意外と手応えある
という事実が次々と襲ってきて、「あれ、もしかして国公立きつい?」という現実がチラつき始めました。
特に精神的にキツかったのは、周りの友達が「東大A判定!」「一橋安定!」って盛り上がる中で、自分だけ浮いてる感覚。
「俺、このまま突っ込んで落ちたらどうするんだろ」って不安が、ふとした瞬間に襲ってくるようになりました。
偶然手に取った、慶應経済のパンフレット
そんなとき、進路指導室でなんとなく手に取ったのが、慶應義塾大学経済学部のパンフレット。
たぶんあれが転機だったと思います。
表紙はちょっとカッコよくて都会っぽくて、「あ、なんかオシャレだな」って印象。
中を読んでみると、
- 数学や統計を使った実証研究
- マクロ・ミクロの本格的な理論
- 海外大との連携やダブルディグリープログラム
…と、“自分がやりたい”と思ってた経済学が、むしろここに全部あるやん!って感じだったんです。
それまでどこかで「私立は軽いんじゃない?」って思ってたのをぶっ飛ばすくらい、慶應経済の内容はハイレベルで、しかも実践的。
「逃げ」じゃない。「新しい選択肢」としての慶應
そこからは早かったです。
慶應について、ネットで調べたり、YouTubeで学生の話を聞いたりしていくうちに、次第にこう思うようになりました。
「あれ、これ逃げじゃなくて、“勝負”としてアリじゃない?」
特に決め手になったのは、将来像をイメージできたこと。
- 経済学を専門的に学びながら、ビジネスや政策にも関われる
- キャリアパスが多様(商社、金融、官僚、スタートアップ、何でもあり)
- 自分で動けば、チャンスが無限にある
「ここなら、大学生活そのものを武器にして、自分を成長させられるかもしれない」って、強く思いました。
決断のとき。「プライドを捨てる」勇気
一番大きな壁は、“自分の中のプライド”でした。
「国公立じゃないと親に申し訳ない」とか、「私立を第一志望にしたら、周りから“落ちた”と思われるんじゃないか」とか。
そういう「見えない圧」みたいなものが、自分の頭の中にずっとあったんです。
でも、何度も考えた結果、こう思いました。
「これからの4年間、自分がどう過ごしたいか。それを真剣に考えたとき、一番ワクワクしたのが慶應だった。」
それならもう、偏差値とか他人の目とか、どうでもいい。「ここで勝負してみたい」って、ようやく本気で思えました。
最終的に、自分の意思で決めたからこそ
親に伝えるのも緊張したけど、ちゃんと話したら理解してくれました。
「最後まで自分で考えたなら、それが一番いい選択だよ」って。
学校の先生はびっくりしてたけど、「慶應なら間違いないな」と納得してくれて、むしろ応援してくれました。
結局、第一志望校を慶應に据え、共通テスト・東大前期試験、京大後期試験は受け、慶應経済に進学しました。
そして今、慶應で4年間を過ごしてみて、心の底から思います。
「あのとき、自分で選んでよかった。」
次回は、オープンキャンパスに行かずに決めた友人たちの話。
“行かない”ってどういうこと? 何を基準に選んだの?
僕とはまた違った進路の決め方をした友人たちのストーリーを、紹介していきます!
「行かなかったけど決めた」人たちの話
ここまで読んでくれた人の中には、
「オープンキャンパス行かなきゃダメなの?」
「部活や塾で時間がなくて行けなかった…」
そんな不安を抱えている人もいると思います。
でも、ちょっと安心してほしい。
実は、僕の高校の友達で“オープンキャンパスに行かずに進路を決めた人”って、めっちゃ多いです。
むしろ、「行ったけど決定打にならなかった」って人よりも、「行かなくても、自分なりに納得して選んだ」って人のほうが、結果的に後悔してない印象すらあります。
ということで今回は、実際に「行かずに決めた」数人の友人のエピソードを紹介しつつ、
オープンキャンパスに行けなかった人、行くか迷ってる人へのヒントを共有していきます。
Case①:部活引退が秋。「そもそも行く余裕がなかった」タイプ
最初に紹介するのは、僕の同級生で野球部だったTくん。
強豪校ではなかったけど、3年の夏の大会までガッツリ活動してたので、
夏休み=「勉強リスタート期間」で、正直オープンキャンパスどころじゃなかったらしい。
「オーキャン?知らん、行ってる暇なかった笑」
「大学のことは全部、塾の先生とパンフで決めた」
って感じで、最終的にTくんは千葉大の工学部に現役合格。今ではバリバリ研究室でAI系の研究をしてて、「別に行かなくても困らなかったよ」って笑ってました。
ポイントは、時間がなかった分、他の情報でカバーしたこと。
- 大学の公式サイトを読み込む
- オンライン説明会や動画をチェック
- 進路指導の先生に話を聞きまくる
など、「行かなくても調べる姿勢さえあれば、自分なりに見えてくるものがある」と教えてくれました。
Case②:遠方すぎて物理的に無理。でも「ブランド」で決めた
次は北海道出身のMさん。
オープンキャンパスに行ける大学は札幌圏内だけで、本州の大学なんて物理的に無理。でも彼女は最終的に早稲田に進学しました。
「ブランド?うん、それが一番大きい(笑)」
「早稲田なら就職にも困らないし、親も安心するし」
確かにリアルな選択かもしれない。
地方出身者にとって、大学選びは「現地に行けるかどうか」じゃなく、「どれだけ信頼できるか」が基準になる。
彼女は「卒業生の話」や「ネットの体験談」「YouTubeのキャンパスツアー動画」をフル活用して、“行かずに行った気になる”戦略で志望校を固めていったそうです。
Case③:とにかく学部重視。「どの大学か」より「何を学ぶか」
もう一人は、理学部に進んだSくん。
Sくんは「キャンパスなんて、勉強できればどこでもいい」って考えの持ち主で、完全に「学問ベース」で大学を選んだタイプ。
「物理やりたい」→「じゃあどこが強いか」→「名大、東北大、京大」
「実験設備が充実してるところを優先」
「キャンパスの雰囲気は二の次」
実際にオープンキャンパスには1校も行かなかったけど、彼は今、自分のやりたい研究に全力投球してて、「大学生活、めっちゃ楽しい」って言ってました。
これは、「大学名」や「立地」「雰囲気」に左右されがちな人にとって、“学問ドリブン”というもう一つの選び方があることを教えてくれるケースだと思います。
行かなくても決められる。でも、“何か”は見るべし
もちろん、オープンキャンパスに行けるなら行ったほうがいいと思います。
空気感、人の雰囲気、設備、街並み――
五感で感じることって、パンフやWebじゃ伝わらない部分が多いから。
でも、行けなかったからって焦る必要はまったくありません。
今回紹介したように、
- 「別の情報源で補う」
- 「価値観の軸をしっかり持つ」
- 「自分が何にワクワクするのか考える」
このあたりがしっかりしていれば、むしろブレない志望理由が作れることだってある。
自分なりの「決断の仕方」を見つけよう
結局のところ、「どの大学に行くか」よりも、「自分がどう決めたか」が大事。
なんとなく周りに流されて選ぶよりも、自分なりに調べて、考えて、腹落ちして出した答えなら、たとえ迷っても後悔はしづらいです。
オープンキャンパスに行った人も、行けなかった人も。「どこに行くか」じゃなく、「どう行くか」で、進路は大きく変わっていくと僕は思います。
おわりに:結局、オープンキャンパスって行くべきだった?
ここまで読んでくれた人に、最後の問いを投げかけます。
「で、オープンキャンパスって、行ったほうがいいの?」
答えを言ってしまうと、僕の結論はこうです。
「行けるなら、行っとけ。でも、行けなくても全然大丈夫。」
ちょっとズルい答えに聞こえるかもしれないけど、これは僕が大学4年間を経て、心から思ってる本音です。
行ってよかったこと、確かにあった
実際、高3の夏に東大・京大・一橋のオープンキャンパスを巡った経験は、僕の「進路に向き合うきっかけ」になったと思います。
- 東大の“圧倒的感”に自信を失ったり、
- 京大の“自由すぎる空気”に戸惑ったり、
- 一橋の“等身大な雰囲気”にホッとしたり…
こういう感情の起伏をリアルな現場で感じたことが、結果的に「自分にとっての居場所はどこだろう?」って真剣に考えるきっかけになったんです。
やっぱり、行かなきゃわからない“空気”ってある。
キャンパスの雰囲気、学生の表情、建物の匂い(←意外と印象に残る笑)、学食のにぎわい。
その全部が、自分の未来を具体的にイメージさせてくれる材料になります。
でも、行ったからと言って「答え」が出るわけじゃない
とはいえ、行けば必ず進路が決まるわけじゃない。
僕自身、3つのオープンキャンパスを回ったけど、最終的に選んだのは慶應。つまり「行ってない大学」に進んだんです。
これは僕だけじゃなく、他の友達もそう。
- オープンキャンパスに行った大学を蹴って別の大学に進学した人
- 行ったけど「イマイチだった」と感じた人
- 行ってないけど今「ここで良かった」と言ってる人
いろんなケースがありました。
結局、最後の決断に必要なのは「現場」より「納得感」だったりします。
「行けるなら、行っとけ」には理由がある
それでも僕が「行けるなら行っとけ」と言うのは、オープンキャンパスは“進路の判断材料”の一つとして、めちゃくちゃ有効”だからです。
- 興味がある学部がどんな雰囲気か?
- 学生はどんな空気感か?
- その大学に自分が4年間通うイメージが持てるか?
こういうのって、ネットじゃわかりにくいんですよね。
1日でもキャンパスに足を運ぶことで、「なんとなく自分に合いそう」「うーん、違うかも」みたいな、肌感がつかめる。
それって、実は受験勉強より大事な「自分との対話」だったりします。
大事なのは“行ったかどうか”じゃなく“どう決めたか”
まとめます。
- オープンキャンパスは、「自分に合う大学を考えるきっかけ」になる。
- でも、行けなくても「別の方法で考えること」はできる。
- 大事なのは、“行ったかどうか”より、“自分の頭でどう決めたか”。
つまり、どんな方法を取っても、「自分なりに考えて選んだ」ことが何より価値あることなんだと思います。
ここまで読んでくれてありがとうございました!
この記事が、皆さんの進路選択の一助となれば幸いです。