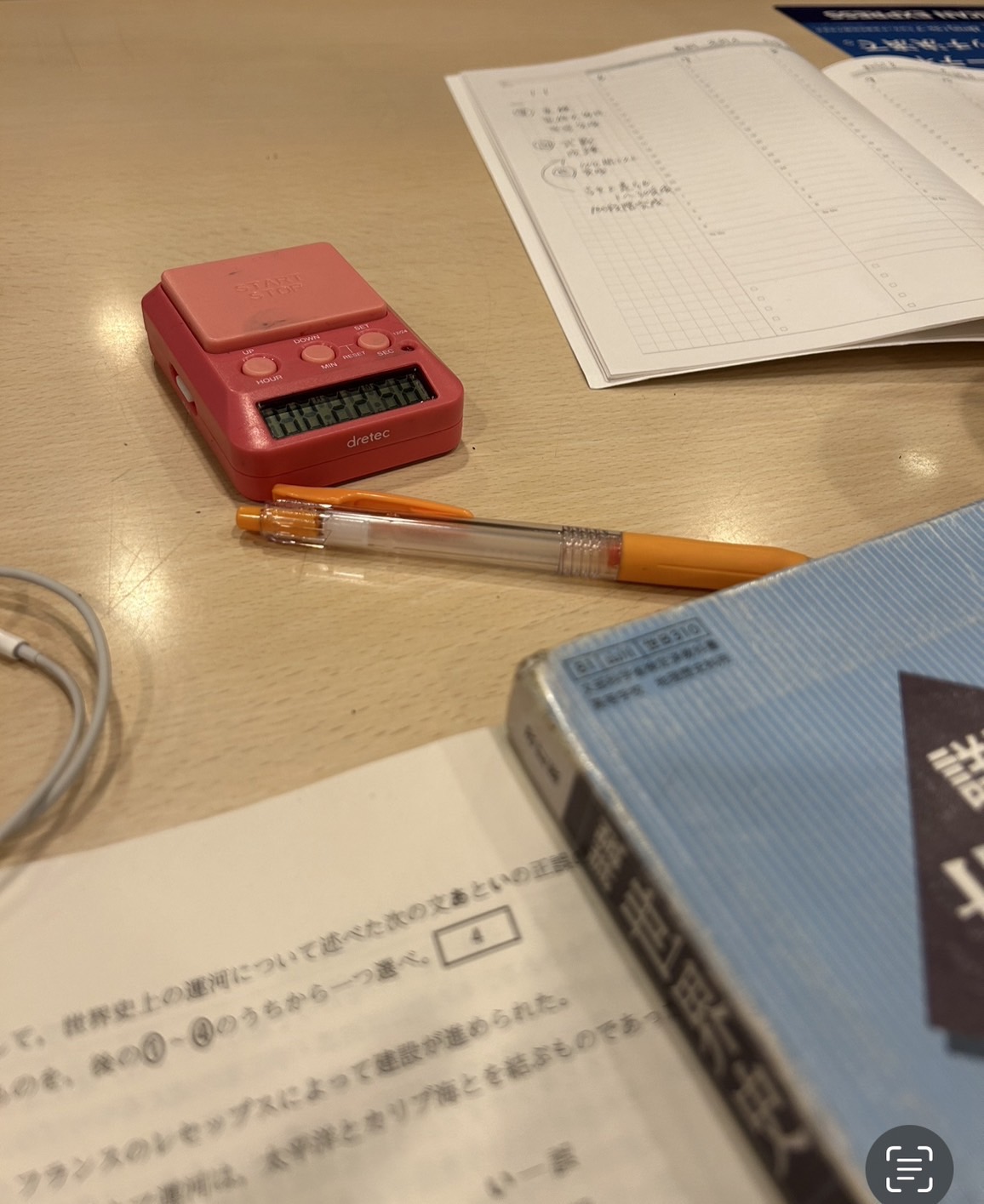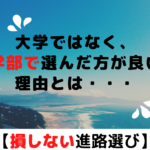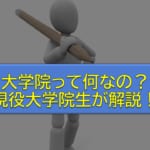夏休みが終わって、多くの高校生は学校行事で忙しい時期を過ごしていることでしょう。
それと同時に夏休みや学校行事での燃え尽きや、受験が近づいてきたことによる焦りを感じ始める人も多い時期ではないかと思います。
今回は、現役立教生の私が直面した秋の時期の悩みなんかを実体験を基に書いていこうと思います。
1.鬼の夏期講習を終えて
少し夏休みのことも触れておこうと思います。
大学受験、特に夏は「天王山」なんて言われて、誰もが死に物狂いで勉強する時期ですよね。私も例にもれず、この夏を乗り越えるべく、予備校の夏期講習に申し込んでいました。
背伸びして選んだのは、当時の私の学力より少し上の「ハイレベルクラス」。このクラスに入れば、周りの優秀なライバルたちに囲まれて、きっと学力もグングン伸びるはずだ!と、自ら少し厳しい道を選びました。
でも、この選択が、私にとっての地獄の始まりだったのです。
「できない子」としてのレッテル
クラス初日、先生が授業を進めていく過程で、生徒に次々と質問を投げかけていきました。
「この問題の答えは?」 「どうしてその答えになった?」 「この英文法の根拠は?」
優秀なクラスメイトたちは、淀みなく質問に答え、授業はテンポよく進んでいきます。一方の私は、先生に当てられても何も答えられず、ただただ黙っていることしかできませんでした。
答えられないと先生の無言の圧をかけられ、周りからも「あーあ」みたいな同情の目を向けられます。そしてしまいには「これわかんないのやばいよ?」などと詰められ、他の人に振られ、その振られた人が秒速で答える。
そうして次第に「できない子」として扱われるようになっていきました。別にこれといって差別されるとか、あからさまな嫌がらせをされるとかありません。先生にあてられなくなったり、あるいはあてられても誰でもわかるような超easyな問題のみを聞かれるようになったり、どこか疎外感を感じるようになりました。
周りのクラスメイトたちも、私の存在をまるで透明人間のように扱います。できる子の周りには人が集まる。友達ができていく。一方私は一番後ろの端っこで小さくなって授業を受けている。
今思えば全然気にするようなことではないし、別に誰かに嫌がらせをされていたというわけではないけど、受験を控えてただでさえナーバスになっている当時のメンタル的にはつらかったです。
毎日泣いていた夏
授業中、私は毎日泣いていました笑
悔しさ、情けなさ、そして孤独。あらゆる感情がごちゃ混ぜになり、涙が止まらなくなるのです。当時はコロナ禍で、塾内でもマスクが必須だったのですが、私はマスクで顔を隠して、人知れず泣いていました。
でも、泣いていることは、すぐにバレてしまいます。 毎日、涙と鼻水でマスクがびしょびしょになり、マスクに跡が残るので、教室を出てすれ違う生徒たちに、いつもぎょっとした顔をされていました笑
「あいつ、いつも泣いてるな」 「マスク、ぐちゃぐちゃじゃん」
そんな声が聞こえてくるような気がして、さらに塾にいるのが嫌になりました。
挫折から生まれた、私だけの勉強法
「負けっぱなしでは終われない!」
それが私の人生です。(え?)
嫌でも自分の未熟さを突き付けられる環境。プライドも心もボロボロでしたが、逆に言えば優秀な人や先生に囲まれて、この上ない学びのチャンスでもありました。
「逃げちゃだめだ!」(シンジ?)
ある日心を入れ替えて以来、私は先生が授業中に質問した内容や、長文に出てきた重要な文法、英文解釈の根拠、周りの生徒の回答などをすべてメモに書き留めることにしました。
授業が終わると、そのメモを読み返して、完璧に理解するまで復習しました。時にはスマホや参考書で自分が理解できるように情報を補足して簡単にまとめました。
そして、そのメモを肌身離さず持ち歩き、通学中や休憩時間にも繰り返し見るようにしました。
最初は辛かったこの習慣も、次第に私の武器となっていきました。 メモを見返すうちに、知識が定着していくのが実感できたからです。
「つらかったこと」が、私の合格への道しるべになった
あの夏期講習で、「挫折」を経験しました。 でも、その挫折があったからこそ、「自分だけの勉強法」を見つけることができたのです。
「メモって持ち歩く」という習慣は、受験が終わるまでずっと続きました。 そして、この習慣が、今の大学生活にも活きています。
特に、受験直前期は、今まで書き溜めてきたメモを読み返すだけで、効率よく復習することができ、自信を持って本番に臨むことができました。
2.夏休みめっちゃ勉強したのに成績が伸びない

夏休み、私は毎日10時間前後の勉強を続けていました。(波はあったが)
「これだけ頑張れば、夏休み明けの模試では、きっと模試でもまあまあな結果が出て、志望校合格に近づいているはず!」
そんな淡い期待を胸に、模試の結果を待っていました。
夏が終わったのに、なぜ?
でも、返ってきた結果は、まさかの現状維持。 いや、むしろ、点数が下がっている科目までありました。
「どうして?こんなに頑張ったのに…」
私は絶望しました。 夏休みの頑張りは、一体何だったんだろう。 あれだけつらかった毎日が、すべて無駄だったような気がしました。
勉強へのモチベーションは急降下し、次第に勉強が手につかなくなっていきました。 夏休みの燃え尽きと、9月の学校行事ラッシュも重なっていたのもあると思います。
努力が報われない秋
周りの友達が、少しずつ成績を伸ばしていく中、私だけが取り残されていくような感覚。 「このままでは志望校に合格できない」という焦りと、「もうどうにもならない」という諦めが入り混じり、私は秋の夜長をひたすら病んで過ごしていました。
参考書を開いても、頭に入ってこない。 集中力は続かず、気がつけばスマホを眺めている毎日。
夏まではあれだけ頑張れたのに、どうしてこんなにも変わってしまったんだろう。 私は自分を責め続け、自信を完全に失っていました。
突然、光が見えた11月
そんな、出口の見えないトンネルをさまよっていた11月。 私の状況が、一気に好転しました。
まず、受験で使える英検準1級の対策をしていたのですが、結果が返ってきて、なんとハイスコアでの合格!3回落ちた末、スコア2449をで合格しました。
そして、併願校の過去問を解いてみると、だんだんと合格点近くの点数が取れるように。
「あれ?なんでだろう…」
もちろん、第一志望校の過去問が安定するまでは、もっと時間がかかり、1月頃まで点数が安定しない状態が続いていましたが、それでも少しずつ、手応えを感じられるようになっていきました。
点と点が繋がり、線になった瞬間
私は、この突然の成績向上を「点と点が繋がり、線になった瞬間」だと考えています。
夏までは、ひたすら基礎力を伸ばすことに集中していました。 単語を覚えたり、文法を固めたり、英文解釈の練習をしたり。
これらは、まさに「点」を増やす作業だったんですよね。
「点」が増えただけでは、点数は伸びません。(駄洒落みたい!)
秋になって、過去問や問題集など、実践的な演習を繰り返すうちに、夏に培ったバラバラだった「点」が、繋がり始めました。
「あの文法知識は、この長文のここに使われているのか!」 「この単語は、この問題でこういうふうに出るのか!」
一つひとつの知識が、まるでパズルのピースのようにカチッとはまり、大きな「線」となったのです。
焦らなくて大丈夫
もし今、あなたが「夏休み、あんなに頑張ったのに、どうして成績が伸びないんだろう…」と悩んでいるとしたら、安心してください。
それは、あなたの努力が足りないわけではありません。 ただ、まだ「点」が「線」になっていないだけです。
焦らず、やるべきことを続けていけば、必ずいつか、その「点」が繋がり、あなたの目の前に合格への道が開けます。
諦めずに、自分を信じて、もう一歩踏み出してみてください
3.夏休み後の燃え尽き症候群
夏休みが明けると、学校の行事が目白押し。文化祭や体育祭が終わっても、なかなか受験モードに切り替えられず、勉強時間は激減しました。
毎日3時間前後しか勉強できない日もあれば、全く手につかない日もありました。夏休みにあれだけ頑張ったのに、どうしてこんなに集中力が続かないんだろう。そう自分を責め、焦れば焦るほど、勉強が手につかなくなる負のループに陥ってしまったのです。
負のループを断ち切るには?
そんな私がたどり着いた解決策は、「優先順位を立て直すこと」でした。
模試や過去問の結果を徹底的に分析し、自分の弱点を洗い出しました。そして、今自分に一番足りていない勉強は何か、探すことにしました。
例えば、もし英単語力が足りていないなら、英単語だけをやる。 世界史のフランス革命で失点が多いなら、フランス革命の部分だけを見直す。
それだけでいいんです。
「あれもこれもやらなきゃ」と焦る気持ちは分かります。 でも、その気持ちやメンタル状態のままあれこれ手を出してしまうと、結局何もできなくなってしまいます。
だからこそ、まずは1つか2つに絞って、徹底的に取り組んでみましょう。
そうやって、目の前の課題を一つずつクリアしていくうちに、次第に勉強の調子が戻ってきます。そして、その努力は必ず成績にも繋がります。
焦りは禁物。自分を信じて、一歩ずつ進もう
受験勉強は、長距離走のようなもの。 時には立ち止まったり、思うように進めない時期もあるでしょう。
でも、そんな時こそ、焦らず、自分のペースで進むことが大切です。 夏休みの頑張りは、決して無駄ではありません。 その頑張りが、あなたの中に確実に基礎力をつけてくれています。
だから、自分を責めないでください。 「今、自分にできること」を一つずつクリアしていく。 この繰り返しが、合格への道を拓いてくれます。
あなたの努力は、必ず報われます。
4.過去問マウント
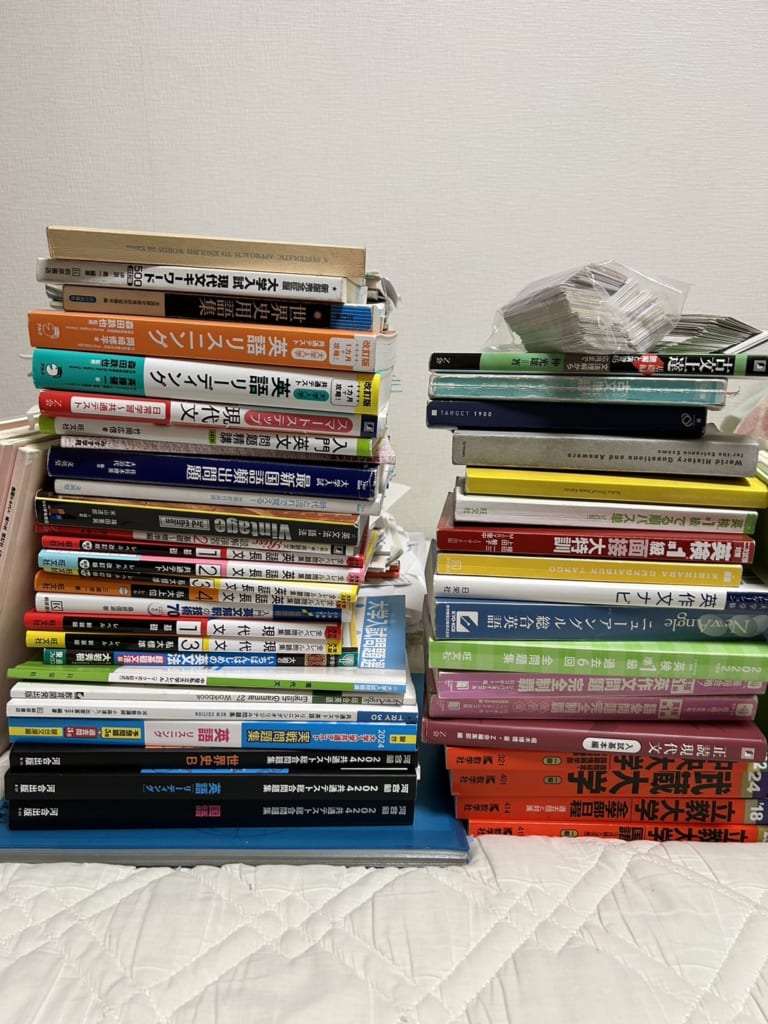
過去問の点数、それは新たな地獄の始まり
秋が深まり、受験生たちの話題は自然と「過去問」に移っていくと思います。 夏休みの頑張りが報われず、勉強へのモチベーションが下がりきっていた私は、友達が過去問を解いているのを見るのが怖くてたまりませんでした。
それでも、いつまでも逃げてはいられない。 意を決して、過去問に挑戦してみることにしました。
結果は、散々。 併願校ですら合格点には届かず、自信をさらに失ってしまいました。
そんな私を追い詰めたのが、「過去問マウント」です。
「マウント」をとってくる友達との遭遇
友達と話していると、話題は自然と過去問の点数になります。 「〇〇大学、解いてみたんだけど、英語は安定して合格点取れてるんだよね〜」 「△△大学の数学は、満点近く取れた!」
友達は悪気なく話しているのかもしれません。 でも、当時の私には、その一言一言が、鋭いナイフのように突き刺さりました。
わざわざ自分が成績よかった時だけ「何点だった?!」とか聞いてくるクラスの男子とか、嫌でしたね。
周りを気にせず、自分のやるべきことに集中する
そんな苦しい状況を乗り越えるために、私がやったことは、「周りを気にせず、自分のやるべきことに集中すること」です。
過去問の点数で一喜一憂するのはやめました。 代わりに、過去問を「自分の弱点を知るためのツール」と割り切ることにしたのです。
そしてこの時期からスタディプラスを使わないようになりました。
過去問を解く→丸付けをする→できなかった問題の解説を徹底的に読み込む
このプロセスを繰り返しました。 点数は気にしません。 「この分野はまだ理解が足りてないな」「この問題は解くのに時間がかかりすぎるな」といった、自分の弱点を知ることができれば、それでいいのです。
そうやって、地道に弱点を克服していくうちに、少しずつ点数が伸びていきました。 そして、いつしか周りの過去問マウントも、気にならなくなっていました。
過去問は「敵」ではなく、「味方」
受験生にとって、過去問は「最後の味方」です。
焦って点数を競い合う必要はありません。 大切なのは、過去問を徹底的に分析し、自分の弱点を克服していくことです。
周りの言葉に惑わされず、自分を信じて、一歩ずつ進んでいけば、必ず合格への道は開けます。 あなたの努力は、決して裏切りません。
5.ずっと眠い、体調が悪い・・・
夏休みまではある程度計画通りに勉強を積み重ねることができ、問題集の正答率も上がっていたため、「このまま努力を続ければきっと合格につながるはずだ」と自分に言い聞かせていました。
ところが、秋の訪れとともに、体調が不安定になり、思うように机に向かえない日々が増えていったのです。
具体的には、常に身体が重く、朝から強い眠気に襲われ、授業中も集中できないことが頻繁にありました。
帰宅後は机に向かうつもりで椅子に座るものの、すぐに眠気に負けて机に突っ伏してしまうことも少なくありません。
睡眠時間はそれなりに確保していたつもりでしたが、質の良い眠りをとれていなかったのか、朝起きた時点ですでに疲れが残っているような感覚に悩まされました。その結果、勉強時間を確保できない焦りと、「自分は他の受験生に比べて大きく遅れてしまっているのではないか」という不安が心を支配していったのです。
体調が優れないとき、人はどうしてもマイナス思考に傾きます。私も例外ではなく、「今日はこれしかできなかった」「周りの友達はもっと努力しているだろうに」と自分を責める気持ちが大きくなり、自己肯定感をどんどん失っていきました。本来ならば勉強に集中すべき大切な時期に、心身の不調が重なったことで、気力さえ奪われてしまったのです。
しかし今振り返ってみると、当時の私は体調管理を甘く見ていた部分が大きかったと感じています。若さゆえに「多少無理をしても大丈夫だろう」と考えてしまい、生活習慣を整えることを二の次にしてしまっていました。けれども、受験勉強は長期戦です。秋以降の数か月間、心身の調子を整えられるかどうかが合否を大きく左右するのだと、身をもって学びました。
改善のために意識したこと
では、どのようにして私は体調不良や眠気の問題を乗り越えていったのか。当時の経験をもとに、いくつかの改善策をご紹介いたします。
1.生活リズムを徹底的に見直す
まず最初に取り組んだのは、起床・就寝時間を一定にすることでした。
受験生の中には「夜遅くまで勉強した方が集中できる」という方もいるかとは思いますが、私の場合は夜更かしが翌日の体調不良につながる原因でした。逆に極端な早起きも同じく、体調不良の原因でした。
そのため、どんなに勉強が途中であっても、深夜には必ず切り上げて眠るようにしました。睡眠の「量」だけでなく「質」を上げるため、寝る前のスマートフォン使用を控え、就寝前は軽くストレッチをして体をリラックスさせる習慣をつけました。
勉強の時間を「長さ」より「質」でとらえる
体調が悪いと、長時間机に向かい続けるのは難しいものです。そこで私は「一度に一時間集中するよりも、二十分を三回繰り返す」といった短時間集中法を取り入れました。
タイマーを活用して区切りをつけることで、眠気に負ける前に切り上げ、少し休憩してから再び集中する。この繰り返しは、思いのほか効率的で、結果的にトータルの勉強量を確保できました。
体を動かしてリフレッシュする
長時間座りっぱなしで勉強すると、血流が悪くなり余計に眠気を感じやすくなります。そこで、私は意識的に散歩や軽い運動を取り入れました。
たとえば、朝学校へ行く前に10分だけ外を歩くだけでも、日光を浴びて体内時計がリセットされ、眠気が軽減されました。また、家で勉強していてどうしても集中できないときは、ストレッチや腕立て伏せを数回するだけでも頭がすっきりしました。
「できたこと」を記録して不安を減らす
体調が悪いと「何もできなかった」と感じがちですが、実際には小さな積み重ねが必ずあります。そこで私は、一日の終わりに「今日やったことリスト」をノートに書き出すようにしました。
たとえば「英単語を30個覚えた」「世界史のこの分野の文化史を少し理解できた」といった些細なことでも記録することで、自分の努力を可視化でき、自己否定の気持ちが和らぎました。この習慣は精神的な支えとなり、翌日のモチベーションにもつながりました。
秋以降に体調を崩したり、眠気に悩まされたりするのは決して珍しいことではありません。季節の変わり目や寒さによる疲労、精神的なプレッシャーが重なることで、誰しも同じような経験をする可能性があります。そのとき大切なのは、「自分だけが弱いわけではない」と知ることです。
そして、焦って無理を重ねるのではなく、一歩立ち止まって生活習慣や勉強の方法を調整することこそが、長期的には合格への近道になるのです。
私自身、秋から冬にかけて体調不良に苦しみ、思い描いていた勉強量には到底届きませんでした。しかし、その経験を通じて「勉強は量だけではなく質が大切」「健康は最大の土台である」という学びを得ました。この考え方は、受験だけでなくその後の大学生活や留学生活でも役に立っています。
まとめ
高校3年生の秋って地味に受験が近づいてきているけど、でもまだ少し時間がある。だからこそ出口が見えない焦りで気持ちが落ち込みがちなんですよね。
実際、私自身も受験期において一番つらかった時期は秋でした。特に9月、10月、11月あたり。
多くの受験生がドカンと成績が上がるのは12月から1月にかけてだと思います。それまであきらめずにコツコツ続けていたら、必ずどこかで報われます。
頑張る皆さんのこと、心から応援しています。