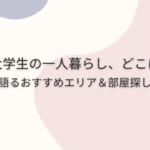こんにちは!ともみです。
前回の記事では、過去問演習の「戦略的な進め方」についてお話ししました。
そして今回は少し視点を変えて、受験後半戦で最も大切とも言える“メンタル”についてお話ししていきます。
共通テストまで残り100日を切り、いよいよ本番が近づいてきましたね。周りの友達が模試でいい結果を出したり、第一志望の判定が上がったという話を聞いたりして、
「自分だけ伸びていない気がする…」「このままで間に合うのかな…」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
私自身もこの時期は、毎日のように焦りと不安が入り混じっていました。
模試の結果が思うように出なかったり、計画通りに勉強が進まなかったりして、
「こんな気持ちで勉強を続けて大丈夫なのかな」と落ち込むこともありました。
でも、振り返ってみると、この秋から冬にかけての時期こそが精神的な踏ん張りどころだったと思います。
ここで自分のメンタルをうまく整え、焦りと上手に付き合うことができたからこそ、最後まで集中力を切らさず走り切ることができました。
受験勉強は、知識の勝負であると同時に、自分の心との戦いでもあります。
どれだけ努力してきた人でも、焦りや不安を完全になくすことはできません。大事なのは、それらの感情を無理に消そうとするのではなく、うまく受け止めて前に進む力に変えていくことです。
そこで今回は、私が受験生の頃に意識していた「秋から冬にかけてのメンタルの整え方」と「焦りとの向き合い方」についてお話しします。
焦りを感じながらも一生懸命受験勉強を頑張っている方に、少しでも前向きな気持ちを届けられたら嬉しいです。
目次
焦りの正体ってなんだろう?
まず最初に、「焦り」とは一体何なのかについて、少し立ち止まって考えてみましょう。
この時期になると、多くの人が「焦ってはいけない」と思いながらも、どうしても心が落ち着かなくなるものです。
けれども、焦りという感情をただ「悪いもの」として切り離してしまうのは、少しもったいないことです。焦りの正体を知ることができれば、今感じている不安やモヤモヤにどう向き合えばいいのか、きっと見えてくるはずです。
私の考える焦りの正体は2つあります。それは、①真剣な証拠、そして②行動のエネルギーの2つだと思います。それぞれについて、少し詳しくお話しします。
真剣な証拠
焦りや不安を感じるのは、それだけ「目標に真剣に向き合っている証拠」です。
「受験なんて適当にやって受かった大学に行けばいいや」と思っている人そもそも焦ることはないのではないでしょうか。自分の将来や結果に本気で向き合っているからこそ、「今のままで大丈夫かな」「もっとできるはずなのに」と感じるのだと思います。
私も10月〜11月の時期は、毎日のように焦っていました。
模試の判定が思うように上がらず、同じクラスの子たちが第一志望でA判定やB判定を取っているのを見て、「なんで私は伸びないんだろう」と自分を責めることもありました。
今思えば、そのように感じていたのも先生や親からの期待や自分の将来を背負って真剣に受験勉強に取り組んでいたからだと思います。
ですから、「焦っている自分=ダメな自分」ではありません。
焦りを感じるということは、それだけ真剣で、一生懸命に頑張っているという証なのです。
行動のエネルギー
もう一つ、焦りには「行動を起こすエネルギー」という側面もあります。
たとえば、締め切り直前に慌てて課題に取りかかって、驚くほどの集中力で終わらせた経験はありませんか?
実はそれこそ、焦りがエネルギーに変わった瞬間だと思います。焦りは、うまく使えば「自分を動かす原動力」になるのです。
しかし、焦りはマイナスの方向にも作用します。焦りによって頭が真っ白の状態で勉強に取り掛かってしまったり、そもそも手を動かせなくなったりしてしまうこともあるのではないでしょうか。
大切なのは、その焦りを「行動につなげられる焦り」に変えることです。
「このままじゃまずい」と思ったときに、焦りをきっかけに「じゃあ今日は何から手をつけよう?」と考え、手を動かす力に変えられるかどうか。それができる人ほど、この時期に大きく伸びていくのだと思います。
焦りは、敵ではありません。
自分の成長を後押ししてくれる、味方にもなり得る感情です。
だからこそ、「焦る自分を責める」のではなく、「焦っている自分を認めて、前に進む力に変える」ことを意識していました。
焦りとの上手な付き合い方
焦りの正体がわかったところで、次に「焦り」とどう向き合い、どう付き合っていくかについてお話ししていきます。
焦りを完全になくすことはできません。
しかし、焦りを“コントロールする”ことはできると思います。
ここでは、私が実際に意識していた2つの方法をご紹介します。
計画を立てる
1つ目は、計画を立てることです。焦りを感じる原因のひとつは、「先が見えないこと」です。
例えるなら、霧のかかった道を歩いているようなものですよね。どこに向かって進めばいいのかわからない状態で走り続けても、不安ばかりが大きくなってしまいます。
その結果、
「頑張っているのに成果が出ない」
「何をすればいいのかわからない」
と感じて焦りが増していきます。
そしてまた焦って手当たり次第に勉強してしまい、空回り…。この“焦りの負のスパイラル”に陥ってしまう受験生は本当に多いです。
この状態を防ぐためには、計画を立てることが何より大切です。
計画を立てることで、ゴールまでの道筋が見えるようになります。そのため、うまくいかない日があっても、「この部分を修正すればいい」と冷静に考えられるようになるため、焦りに振り回されにくくなります。
もし「どんな計画を立てたらいいかわからない…」という場合は、学校や塾の先生に相談してみるのがおすすめです。第三者かつ受験に関して自分より詳しい人の意見を取り入れることで、より現実的で、軌道修正しやすい計画を立てることができると思います。
不安を「見える化」する
2つ目は、不安を「見える化」することです。焦っているときほど、頭の中がごちゃごちゃになってしまいますよね。
「何から手をつければいいのか」「今の自分は何が足りないのか」など、考えれば考えるほど不安が膨らんでしまう。
そんなときにおすすめなのが、不安を“見える化”することです。頭の中でモヤモヤ考えるよりも、紙やノートに書き出してみるのがおすすめです。
「今自分が不安に感じていること」「今日・明日やるべきこと」などを具体的に書き出すことで、思考が整理され、気持ちが落ち着きやすくなります。
私も受験生のとき、夜寝る前に「明日はこれをやる!」とノートに書き出してから寝るようにしていました。
書き出すことで頭がすっきりし、翌朝はスムーズに勉強を始められるようになりました。
また、できた項目にチェックをつけることで達成感も得られ、「少しずつ進めている」という実感が焦りを和らげてくれました。
このように、私は①計画で先を見える化し、②不安を整理して自分を落ち着かせることによって焦りと上手に付き合いながら着実に勉強を進めていました。
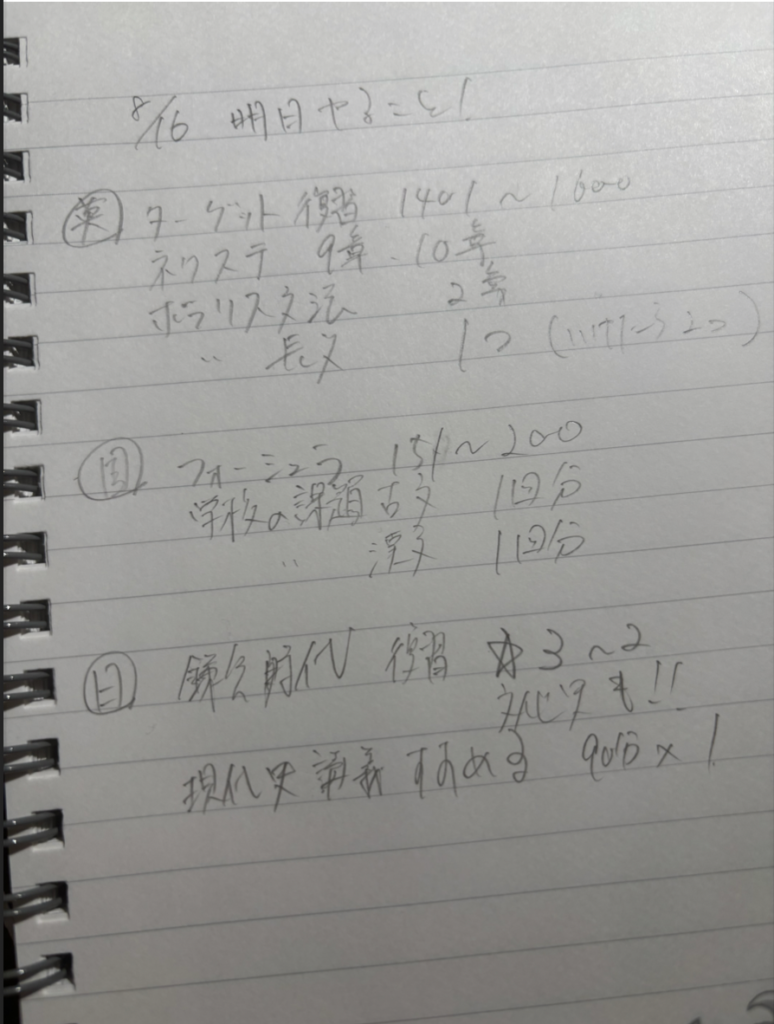
気持ちを安定させる日常の習慣
次は先ほどとは少し違う観点から、私が実践していたことをお伝えしていきます。
この時期は、受験が近づくにつれて心も体も疲れがたまりやすくなります。焦りや不安を感じるのは自然なことですが、そうした気持ちに振り回されずに過ごすためには、メンタルを安定させる日常の習慣づくりがとても大切です。
ここでは、私が受験生のときに意識していた3つのポイントをご紹介します。
生活リズムを一定に保つ
まず意識してほしいのは、生活リズムを一定に保つことです。
夜遅くまで勉強して朝寝坊してしまう日が続くと、体のリズムが崩れ、集中力が落ちやすくなります。すると、思うように勉強が進まず、さらに不安が大きくなってしまう悪循環に陥りがちです。
私は、できる限り同じ時間に起きて、同じ時間に寝るようにしていました。
どんなに遅くても夜1時には布団に入り、翌朝7時には起きる。朝日を浴びて体を目覚めさせることで、気持ちをリセットし、スッキリした状態で1日をスタートできました。
逆に、夜更かしをして昼まで寝てしまうと、「せっかくの貴重な時間を無駄にしてしまった…」と自己嫌悪に陥ってしまうこともありました。
体調面でもメンタル面でも、安定した生活リズムは受験期の土台になると感じています。
リフレッシュの時間をつくる
次に大切なのが、小さなリフレッシュ時間をつくることです。
長時間集中し続けようとしても、頭が疲れて効率が落ちてしまいます。私は1〜2時間勉強したら、5〜10分ほど勉強から完全に離れるようにしていました。
たとえば、好きな曲を聴いたり、ストレッチをしたり、温かい飲み物をゆっくり飲んだり。私は自宅で勉強していたので、気分転換にギターを弾いたり、ベランダでバットを振って体を動かしたりしていました。
たった数分でも、頭と心をリセットすることで次の勉強に集中しやすくなり、結果的に効率が上がりました。
リフレッシュというと「サボること」のように感じる人もいますが、決してそうではありません。むしろ、集中を維持するための戦略的な休憩だと思って、積極的に取り入れていました。
学校に行く
最後にお伝えしたいのは、学校に行くことの大切さです。
受験が近づくと、「学校に行く時間がもったいない」「自習していた方が効率的」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、私は学校には行くべきだと思います。
なぜなら、学校に行くことは勉強のためだけでなく、心の安定のためにもなるからです。
一人でずっと家にこもっていると、どうしても気持ちが内向きになってしまいます。友達や先生と話すことで、気持ちを共有できたり、「自分だけじゃないんだ」と安心できたりするものです。
たとえ授業の内容が復習中心でも、学校という環境に身を置くだけで、自然と生活リズムや気持ちが整うことも多いです。
受験期は、頑張れば頑張るほど「勉強時間=成果」と考えてしまいがちです。でも、どんなに効率的な勉強法を取り入れても、心と体が元気でなければ本当の力は出せません。
だからこそ、「生活リズム」「リフレッシュ」「人とのつながり」――この3つを意識して、毎日を少しでも安定した気持ちで過ごしてほしいです。
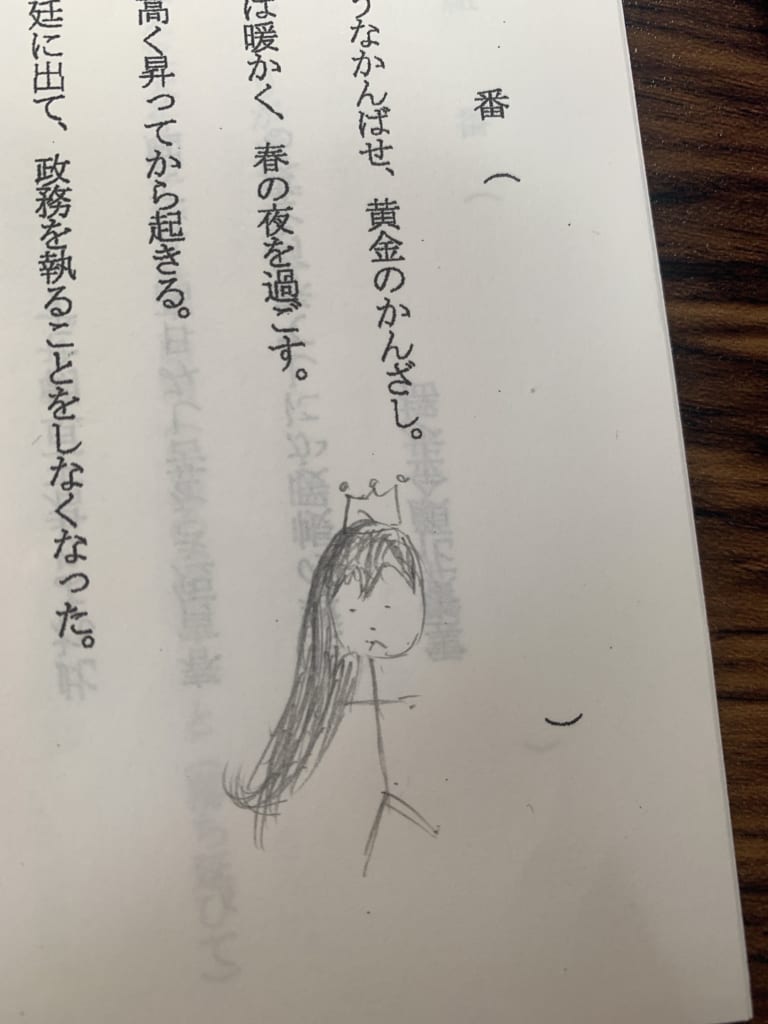
おわりに
いかがだったでしょうか。
ここまで、「焦りの正体」や「焦りとの上手な付き合い方」、そして「心を整えるための日常の工夫」についてお話ししてきました。
受験が近づくこの時期は、誰もが少なからず不安や焦りを感じるものです。
「周りと比べてしまう」「思うように結果が出ない」そんなときこそ、地に足をつけて着実に勉強に取り組むことで自分の実力を伸ばすことができると思います。
そのために、焦りとの向き合い方を意識してみてください。焦りは、決して悪いものではありません。それは“本気で頑張っている証拠”であり、“行動の原動力”にもなります。
みなさんが、来年の3月に「やりきった」と思える受験生活を送れることを願っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。