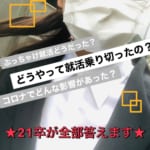タイ最北端の都市チェンライで、10ヶ月の交換留学中。
今回は、1学期に履修した授業の様子についてお届けします!
目次
私の留学情報
国:タイ
都市:チェンライ(タイ最北の都市)
大学:Mae Fah Luang University (MFU)(公立)
学部:Agro-Industry
学科:Innovagive Food Science and Technology
留学期間:大学3年の8月~翌年5月までの10ヶ月(2学期制の大学で、2学期=1年度分の留学中)
目的:語学留学ではなく、自分の専攻を学ぶ
・授業では英語が使用される
交換留学生の履修登録
登録プロセス
私の場合、留学前にやり取りをしていた留学先の担当の方から、学期が始まる1か月くらい前に、自分の学科のカリキュラムがメールで送られてきました。
大学HPのシラバスのページでも、どのような授業がどの時間に開講されているのかが分かるので、そちらも参考にして決めました。
どの授業を取るか決めたら、担当の方にどの授業を履修したいかメールで伝え、
その後 大学側の登録手続きが完了するまでに1週間くらいかかりました。
登録単位数
留学先の大学では、一般の学生は1学期あたり9~22単位を履修しなければらならい、という規定がありましたが、
交換留学生に関しては特に決まりはありませんでした。
また私が日本で通っている大学では、交換留学の際に何単位以上取らなければいけない、などの決まりはありませんでした。
そのため、興味のある授業を選びつつ、自分の時間もとれるように授業を選択していきました。
履修した授業
悩みに悩んだ挙句、最終的に履修した授業は↓
・Thai conversation:水曜 12:00~16:00
・Innovative Health Food Priducts:実験→水曜 9:00~12:00、講義→金曜 13:00~15:00
・Thai Traditional Food Recipes:木曜 16:00~19:00
この大学に来てびっくりしたのが、
日本の大学のように1限は何時から何時、2限は何時から何時、というふうには決められていないことです。
授業によって、2時間授業のものもあれば3時間授業のものもあるし、12:30~の授業もあれば13:00~の授業もあって、
授業時間が被らないように履修を組まなければなりません。
さらに、テスト期間も授業によってテスト日が異なります。
普段の授業は月曜日でも、中間や期末テストは水曜日、という風になっています。
そのため履修登録する際には、授業時間だけでなく試験日も重複しないように考える必要があります。
また、時間割では授業時間が3時間と決められていても、2時間で授業が終わることもよくあります。
反対に、座学ではなく実験のときには、9:00~12:00のはずが12:45までかかることもザラでした。
授業の様子
Thai conversation
この授業は、タイ語を母国語としない生徒が対象の授業でした。
先生はタイ人の女性の方で生徒は40人ほど、そのうち9割がミャンマー人で、
残りはインドネシア、ブルネイ、マレーシア、そして日本人の私という感じでした。
シラバス上は12:00~16:00だったのですが、12時まで授業がある学生も多く、先生が気を利かせて12:30~にしてくれました。
授業が途中15分休憩を入れて、だいたい15時に終わっていました。
授業はもちろん英語で行われ、使用していた教科書は先生のオリジナル教科書で、
タイ文字は書かれておらず、タイ語の発音記号(アルファベット表記に似た文字+声調記号)と英語で書かれていました。
授業の数日前に予習用の動画が送られてきて、それを見ておくように言われていました。
授業内では、教科書に沿って単語の発音や意味の確認、会話練習パートの音読などをし、
先生が一方的に教えるだけでなく、生徒が当てられて音読したり、簡単なクイズに答えたりしていました。
また、中間テストまでの期間は講義と小テストが各週で行われ、
中間から期末までの期間は、小テストがなくなって毎週 講義となり、課題としてグループワークが毎回割り当てられていました。
小テストは一人ずつ行うスピーキングテストで、1人10問ほどだったと思います。
前の週で習った内容からしか出ないので、きちんと対策すれば満点がとれる内容でした。
中間テストは、それまでに習った範囲全てから出題され、1人25問のスピーキングテストでした。
中間テスト以降のグループワークでは、その週に習ったトピックに基づいてストーリーや会話を自分たちで考え、実演して録画したものを提出するというものでした。
期末テストは2週に分けて行われ、1週目はライティング、2週目はスピーキングでした。
ライティングでは事前にトピックが知らされていて、それは最終週の授業で習ったテーマでした。
スピーキングテストは今までと同様の形式で、1人50問でした。
特別難しいというわけではなく、クラス全体としてみんな好成績でした。
大変だったこと
この授業で大変だったのは、タイ語の発音に慣れることです。
中国語は4つの声調がありますが、タイ語には5つあります。
さらにタイ語では p / ph、t /th の声の出し方が区別されており、
例えばタイ語ではkaaとkhaaは異なる発声をしますが、日本人からするとどちらも「かー」にしか聞こえないので、
耳が慣れるまでは非常に大変でした。
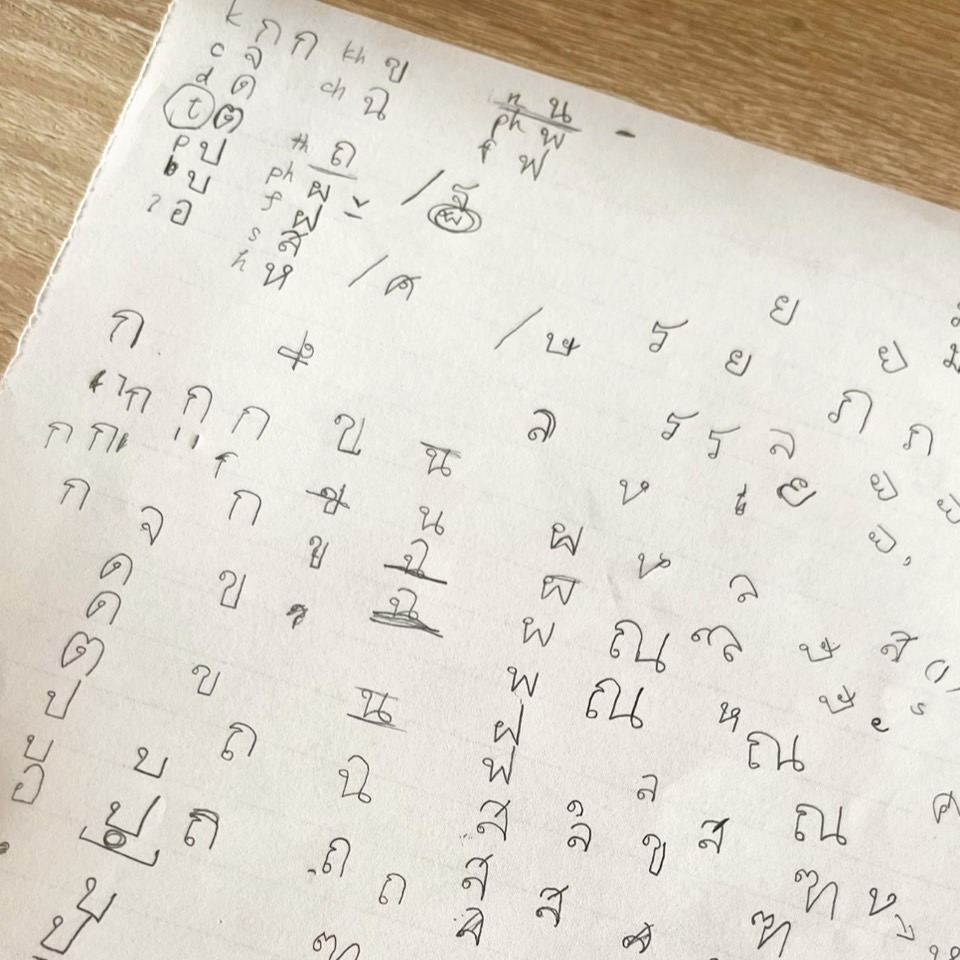
母音、子音の他に声調記号もあるし、本当に大変です…
Innovative Health Food Products
これは2年生の食品学科の学生が対象の授業でした。
主に加工食品の栄養成分について学ぶ科目で、座学と実験がそれぞれ週に1コマずつあり、オムニバス形式でした。
揚げる・蒸す・冷凍するなどの従来の加工方法や、電子レンジ・HPP法などの比較的新しい加工方法について学んだり、
加工によって栄養成分がどのように変化するのか、実験を通して確かめたりしました。
成績の評価方法は、中間と期末の筆記試験と、実験レポート、そして期末前のグループ発表の総合点でつけられました。
中間と期末の筆記試験は、選択問題が2割、記述問題が8割くらいで、記述問題はちゃんと復習をして臨まないと、かなり難しい内容でした。
実験は、6人1組のグループごとに行う形式で、実験レポートの提出もグループで1つでした。
期末前のプレゼンは実験グループごとに行い、各班が自分たちで考えたヘルシーなオリジナルメニューを12分で発表する、というものでした。
このプレゼンでは、3週間に渡って学生たちが自分たちで試作を重ね、プレゼン当日には先生や他の学生に試食をしてもらいながら発表を行いました。
大変だったこと
この科目で一番苦労したのは、グループワークです。
タイ人4人ミャンマー人1人+私、というメンバーだったのですが、タイの子同士がタイ語で会話していたり、タイ人の学生と先生がタイ語で会話することも多く、
さらに、他の学生は2年生ですが、私は交換留学でこの学科に入っているため、この学科での普段の実験の進め方?というか雰囲気?が全く分かりませんでした。
なかなかグループに馴染めず、実験の時間はほぼ見学者みたいなアウェー感がすごくて、肩身が狭いというか気まずいというか。
期末前のグループ発表でも、先生から提示された発表条件(英語で記載)が少し抽象的に感じていたのですが、恐らく他の学生たちは去年も同様の形式のグループ発表をしていて、この課題の条件についてもっと理解できているんだろうなと思ったり、
タイ人同士でタイ語で会話しているのをみて、情報弱者になってる気がするな、と思ったり。
この授業では、実験レポートやグループ発表などでグループワークが多く、その度に憂鬱な気分になっていました。
日本と違ってグループワークが多いなぁとも思ったし、
自分の使い慣れた日本語だったら・せめて全て英語でコミュニケーションが行われていたら、
もしかしたら もう少しグループワークに対する抵抗がなかったのかな、と思うこともありました。
Thai Traditional Food Recipes
これはタイの郷土料理について学ぶ講義で、北・北東・中央・南の4地域それぞれの特徴について学びました。
オムニバス形式でしたが、どの回も17:30くらいに終わることが多かったです。
元々食べ物に対する興味が人よりも強い私。
しかもこのような授業はタイの大学に来たからこそ学べるものだと思っていたので、非常に楽しみにしていた授業でした。
実際、この授業ではタイの各地域の郷土料理について知ることができ、
普段 屋台でご飯を買うときに「これは北タイの料理って習ったな」とか思いながら歩いていて、ひとりで興奮していました(笑)
この授業では、学期末に1グループ12人ほどの7分間のグループ発表がありました。
今までに習った料理の中で、2つの地域の料理を組み合わせて創作料理を考える、というものでした。
発表当日、実際に考えた料理を作って持ってきているグループもあり、日本だったらあまり考えられない光景だなと思っていました。

おわりに
授業は基本的に英語で行われるのですが、先生によってはタイ訛りが強い英語を話していて、耳が慣れるまではすっっごい大変でした。
・語尾を上げるようなイントネーション(茨城弁に似ていると聞いたことがあります)
・例えば maxなら「マックス」ではなく「マック」というように、xのsの音が消えたり、
scienceのceが消えて「サイエンッ」となったりする
・shとchの区別が難しいらしく、fishじゃなくてfichという発音になる
このようなクセがあり、最初は耳がストレスを感じていました(笑)
また私は3つの授業を履修し、実験と座学を区別すると週に4コマ授業がありました。
現地の学生は、学部によって異なりますが3~7コマほど授業があるようでした。
私の授業量だと、予習復習をしてもそれなりに自分の時間があり、タイでの生活を楽しんだり、語学の自学習に時間を割いたりしていました。
授業中心の留学生活ではなく、現地での生活も味わいたいと考えていたので、
自分の専門分野の勉強もしつつ適度に自分の時間もあり、ちょうどよかったなと思っています。