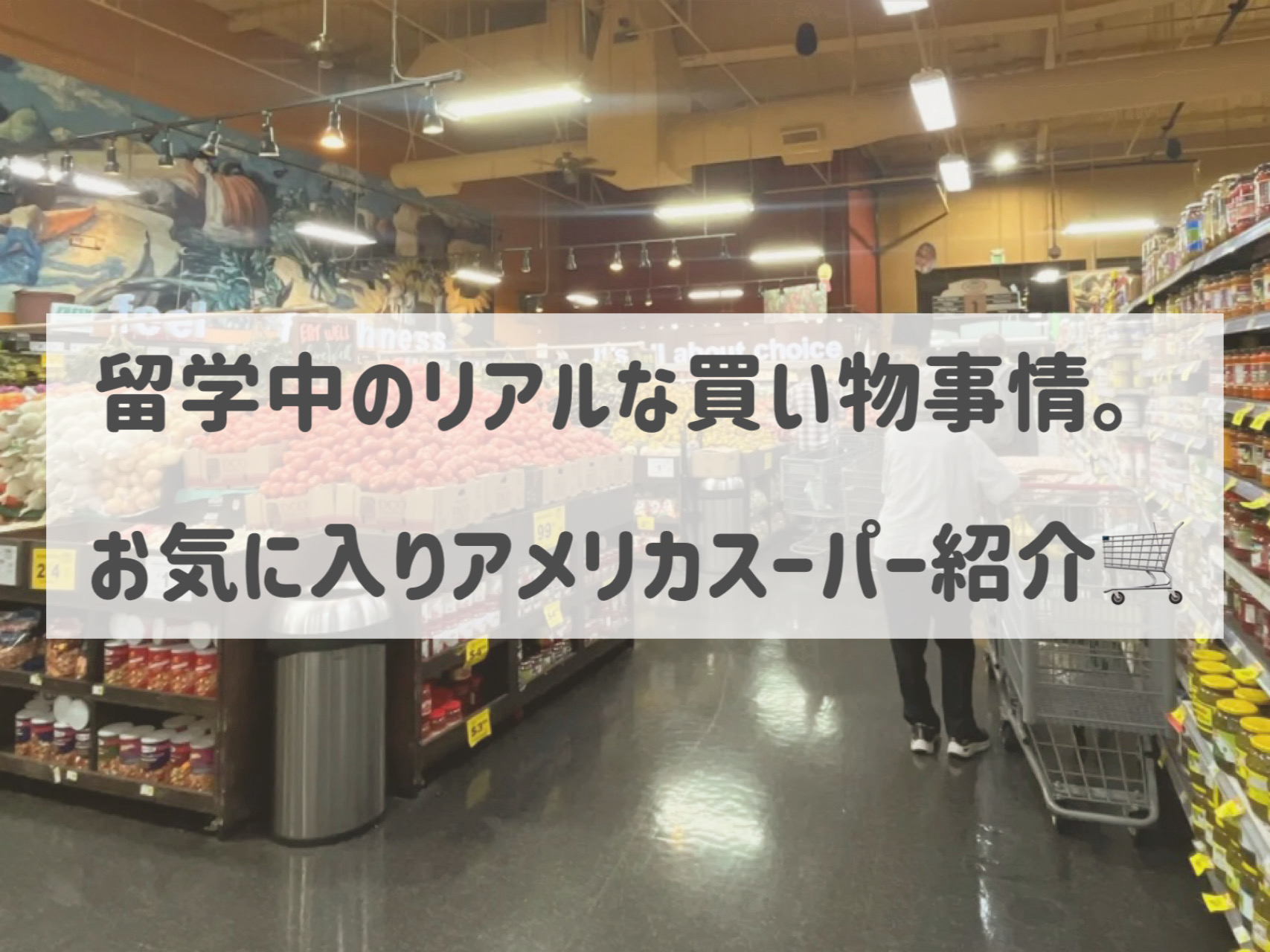みなさんこんにちは!早稲田大学文学部3年生のめろです。
私は現在、アメリカ・カリフォルニア州にて、留学をしています。アメリカに来てから、「え、こんなことで?」と思うような場面で、日常の中に潜む文化の違いを感じることがたくさんありました。中でも特に印象に残っているのが、スーパーでの買い物です。
一見どこにでもあるようなスーパー。だけど、アメリカではその空間に暮らしのスタイルや人との距離感、社会の価値観までがぎゅっと詰まっているように感じました。観光地ではなかなか見えない“リアルな生活”が、そこには当たり前のように広がっていて、買い物ひとつでも毎回新しい発見があります。
今回はそんな、アメリカのスーパーで私が実際に感じた驚きと気づき、そして少しずつ身につけてきた生活の工夫について書いてみました。これから渡米する方や、異文化にちょっと興味がある方に、少しでも“リアルな暮らし”のイメージが伝われば嬉しいです!
目次
はじめに:アメリカのスーパーってどんな感じ?
カルチャーショックの始まりは「スーパー」だった
アメリカに来て最初に感じたカルチャーショックのひとつが、「スーパー」でした。観光地やレストランとは違って、スーパーは観光客ではなく“そこに暮らす人たち”の日常がそのまま流れている場所。店内を歩いているだけで、「ここではこれが普通なんだ」と思うような瞬間が何度もあって、私にとってはまさに生活の入口のような存在でした。ちょっとした食材選びやレジでのやりとりにも、日本とは違う考え方や習慣がにじみ出ていて、買い物に行くたびに「へぇ~」と驚くことばかり。意外なことに、留学中いちばん最初に“異文化”を実感した場所は、教室ではなくスーパーだったかもしれません。
スーパーはその国の文化を映す場所
そして気づいたのは、「スーパーって、その国の文化が見える場所なんだな」ということ。売っているものや並べ方だけじゃなくて、人との距離感・買い物スタイル・お金の使い方や社会制度まで、そこにはアメリカの“ふつう”が凝縮されているように感じます。
たとえば、レジでのフレンドリーな会話は、「買い物=人とのふれあい」だという考え方のあらわれだし、EBTという支払い表示には、この国ならではの支援制度が見えてくる。日常の中にこそ、その国の価値観や暮らしの感覚がぎゅっと詰まっている気がします。何気ない空間だけど、だからこそ“リアルな文化”に触れることができる場所なんだなと気づかされました。

印象に残ったこと・日本との違い
▸ とにかく広い!カートも通路もビッグサイズ
最初にアメリカのスーパーに足を踏み入れたとき、一番に思ったのは「…広い!」でした。目の前にずらりと並ぶショッピングカートは、日本のものとは比べものにならない大きさ。もはや“買い物”というよりも“積み込み”に近い感覚。実際、周りの人たちは山のように商品をカートに積んでいて、まるで業者か何かのようでした。
さらに店内の通路も余裕で2~3人がすれ違える広さで、まさに「広さ=前提」という文化の違いを実感しました。この「スケール感」の違いには、単なる消費スタイルの違いではなく、生活全体のリズムや前提が異なることが反映されているんだなと感じました。車社会で移動距離が長く、毎日買い物に出かけるよりも、週末に1週間分をまとめて買う。効率重視&大容量が前提の生活が、カートや通路の設計にまでしっかりと反映されているのです。
▸ 話しかけてくるレジの店員さんにびっくり
次に驚いたのが、レジでのフレンドリーさです。
日本では「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」で終わる無言のやりとりが多いですが、アメリカでは店員さんとの会話が当たり前でとにかく話しかけてくる!「やあ!元気?」「そのクッキー、私も好きだよ」「今日暑いね〜」などなど、ちょっとした雑談を交わすのが普通で、まるで知り合いに会ったようなテンションで話しかけられます。言葉がうまく返せないことも多くて、何度も「Sorry?」と聞き返してしまったり、微笑むことしかできなかったり…。でも、何度か経験するうちに「たとえ言葉が完璧じゃなくても、“会話しようとする姿勢”を大切にしてくれてるんだ」と気づき、この温かさがアメリカの人との距離感なのかもしれないと思うようになりました。
買い物が単なる作業ではなく、“人とふれあう場”になるという感覚は、日本ではなかなか味わえなかった新しい発見でした。スーパーという日常の中に、ほんの少しのあたたかさと交流があることで、その日がちょっと明るくなる――アメリカのスーパーには、そんな魅力があるのかもしれません。
▸ なんでも大容量!買い物は“仕入れ”レベル
アメリカのスーパーを歩いていて、次に衝撃を受けたのが、商品ひとつひとつのサイズ感。とにかくすべてがでかい!多い!です。たとえばポテトチップスは枕サイズ、アイスもバケツみたいな容器に入ってます。“家庭用”ではなく“業務用”では?という感じ。
でも、よく考えるとアメリカでは家族単位での生活が中心であり、一度の料理量も多い。さらに週に1回まとめて大量に買い出しをするのが一般的。車移動が基本だから、重さや量はあまり問題にならないし、冷蔵庫や冷凍庫も大きいからまとめ買い・大量ストックが可能。だから“大容量”こそが合理的で便利なんですよね。つまり「このサイズ感にも意味がある」ことがだんだん分かってきました。
▸ シリアル&アイスの種類がとにかく豊富
お店の中でもテンションが上がるのが、シリアルとアイスのコーナーです。
どちらも棚1列どころか通路全体が丸ごと専用スペースになっているほどで、初めて見たときは思わず「多すぎるでしょ!」と声が出ました(笑)。
アメリカの「楽しければOK!」「甘ければ最高!」というノリが全面に出ていて、最初は買うのも勇気がいりましたが、今ではちょっとしたご褒美に毎回違う味を試すのが楽しみに。選ぶ楽しさ、冒険する面白さがここにはあるなと感じます。

↑ジュースの種類もたくさん!色とりどりのボトルがずらりと隙間なく並べられていて、まるでディスプレイのような美しさがあります。一列にぎっしりと並んだ様子は、どこか“圧巻”という言葉がぴったりで、商品棚というよりアート作品のような迫力。見ているだけでわくわくしてしまい、思わず写真を撮りたくなるような風景です。
▸ 単位のちがいに大混乱!「ポンド」って何グラム?
アメリカのスーパーで初めて「1lb(ポンド)」という表示を見たとき、「え、それって何グラム?」と頭の中が一瞬フリーズしました。日本ではグラムやキログラムが当たり前だったので、ポンドやオンス、ガロンというアメリカの単位にはなかなか慣れません。
たとえば、お肉コーナーで「$4.99/lb」と書かれていても、それがどのくらいの量なのか最初は全然ピンとこなくて、「とりあえずこれくらいかな?」と勘で選んでいたこともあります(結果、多すぎたり少なすぎたり…笑)。
少しずつ慣れてきた今では、1ポンド=約450gくらいだな、と感覚で分かるようになりましたが、最初のころはほんのちょっとの買い物でもGoogle先生とにらめっこしていました。こういう小さな違いの積み重ねが、「ああ、今自分は異文化の中にいるんだな」って気づかせてくれる瞬間でもあります。
▸ 思わず二度見。アメリカのスーパーで感じた物価の違い
アメリカのスーパーに通い始めて、まず驚いたのが商品の値段。
たとえば牛乳1ガロン(約3.8L)で5ドル前後、卵1ダースで5〜6ドル…。どれも「えっ、こんなにするの?」と、つい目を疑いたくなるような価格が並んでいます。特に円安が進んでいた時期は、1ドル=150円以上。
「え、これって日本円で700円超えってこと!?」「日本なら一食分買えちゃうよ…」と、レジ前でひっそり衝撃を受けたことが何度もありました(笑)。
もちろん、地域やお店によって差はあるし、安いものも探せばちゃんとあります。でも、暮らし始めてみると、「食費って思ったよりかかるな…」と感じることがしばしば。
その一方で、アメリカにはセールやクーポン、会員割引などを活用して“上手に節約する”工夫がたくさんあるのも面白いところ。最初は戸惑っていたこの価格感覚も、今ではすっかり“暮らしの知恵”として定着してきた気がします。
▸ EBTカード?アメリカならではの支援制度
そしてもうひとつ、日本にいたときには意識したことがなかった制度に出会いました。
それが「EBT」と呼ばれる、アメリカの公的食料支援制度です。
これは、収入に応じて給付される“食品購入専用のプリペイドカード”のようなもので、低所得者や生活支援対象の人々はスーパーでEBTカードを使って生活必需品(食品)を購入することができます。レジ横には「EBT Accepted」という表示があり、カードリーダーにも専用のボタンがついているほど、制度が生活の中に当たり前のように存在しているのを感じました。
こうした仕組みを知ったとき、「文化」だけでなく、「社会のあり方」もスーパーを通じて垣間見えるんだなと思いました。誰もが最低限の食生活を守れるように設計されたこの制度には、アメリカの“セーフティネットとしての仕組み”の一端が表れているように思います。日常の買い物の中で、こうした社会の仕組みに自然と触れられることも、留学のリアルな学びのひとつだと感じました。
よく行くお気に入りのスーパー紹介
▸ Trader Joe’s:おしゃれでコスパ最高。冷凍食品が優秀!
まず一番のお気に入りは、Trader Joe’s(トレーダー・ジョーズ)。
全米に展開している人気スーパーで、ローカルな雰囲気と遊び心あふれる品揃えが魅力です。
他の大型スーパーに比べると、店舗の広さはかなりコンパクト。だけどそのぶん、商品が厳選されていて無駄がなく、ほぼすべてがTrader Joe’sのオリジナルブランド。お菓子、調味料、冷凍食品、パン、お惣菜など、どれもパッケージが可愛くてつい手に取りたくなるものばかりです。店内のディスプレイや手書き風のポップにもあたたかみがあって、スタッフも笑顔でフレンドリー。どこか“ご近所の小さなお店”に来たような安心感があるのも、このスーパーの好きなところです。
なかでも私がハマっているのが、冷凍食品のクオリティの高さ。
たとえば、焼き餃子・冷凍ピラフ・マカロニチーズ・トマトクリームのパスタ・スープなど、レンジやフライパンであたためるだけでレストランレベルの味が楽しめるものがたくさんあります。しかも値段も手頃で、$3~5くらいで満足度の高いご飯が手に入るのはありがたい限り。自炊の時間がない日でも、「ちゃんと美味しいものを食べたい!」という気持ちに応えてくれる、心強い存在です。
そして何より楽しいのが、商品が頻繁に入れ替わること。季節限定のフレーバーや新作がどんどん登場するので、行くたびに「今日は何に出会えるかな?」とワクワクしています。

↑こちらは大人気のTrader Joe’sのキャンバストートバッグ。季節限定のカラーやデザインなどもあり、「今日はどれにしようかな?」とつい集めたくなってしまいます。このパステルカラーミニトートは特に人気で、開店前から長蛇の列ができていました!お土産としても大人気で、日本の友達に渡すといつも喜ばれます。買い物をしながらちょっと気分が上がる、そんな存在です。
▸ Whole Foods:ヘルシー志向にぴったりなご褒美スーパー
次に紹介したいのは、Whole Foods(ホールフーズ)。
アメリカではオーガニックや自然派食品を扱うスーパーとして有名で、「体にいいものを食べたい」「安心して選びたい」という人たちにとっては定番の存在です。正直、価格帯はやや高め。でもそのぶん、品質の確かさや原材料のこだわりが感じられて、私にとっては“ご褒美スーパー”という立ち位置です。
店内を歩くと、オーガニック野菜や自然派調味料、プラントベースのミート、グルテンフリーのお菓子などがずらりと並んでいて、健康志向な食生活を目指したくなるような商品ばかり。特に、ビーガン・ケト・ペスカタリアンなど、食の多様性にも柔軟に対応しているのがWhole Foodsのすごいところです。
特に私のお気に入りは、量り売りの惣菜・サラダバーコーナー。自分で好きなだけ取って、重さでお会計するスタイルなので、その日の気分や食べたい量に合わせてカスタマイズできるのがうれしいポイントです。私のお気に入りは、グリルされた野菜やクスクスのサラダ、ローストチキンなど。体にやさしくて、美味しいです。栄養バランスを考えながら自分好みのランチが作れるところがいいところ。
ただし、やっぱり全体的に値段はちょっと高め。でも、品質や安心感を考えると、「たまのご褒美」として利用するにはぴったりの場所。「今日はちょっとがんばったな」と思う日や、「しっかりしたものを食べたいな」という日に、Whole Foodsに立ち寄って食材やお惣菜を買うと、それだけで自分をいたわる気持ちになります。
ちなみに、Amazonのプライム会員だと店頭で割引を受けられるのも地味にうれしいポイント。アプリをかざすだけで割引されるので、よく行く人はチェックしておくとお得です。
▸ Ralphs:安くて便利、日常使いの強い味方
次に紹介するのは、Ralphs(ラルフス)。
アメリカ全土に展開する大手スーパーマーケットで、私が日常的にいちばんお世話になっているスーパーでもあります。食品から日用品、洗剤や文房具まで、生活に必要なものがひととおり揃っていて、文字通り「ここに来ればだいたいなんでもある」安心感があります。
Ralphsの一番の魅力は、とにかくお得に買い物できること。
セールやクーポンの種類が豊富で、特にアプリを使った買い物は節約派には最強の味方。会員登録(無料)をしてアプリを入れておけば、「今週の特売情報」や「あなたへのおすすめクーポン」が毎週更新され、対象商品が数ドル引きになったり、“Buy One Get One Free”(1つ買うと1つ無料)といった太っ腹なキャンペーンもよくあります。私は買い物の前にアプリをチェックして、必要なものとクーポンが合っていれば即カートイン!というスタイルで節約しています。
さらに、営業時間が長い店舗が多いのもありがたいポイント。深夜まで開いているところもあるので、遅くなった日や「うっかり牛乳切らしてた!」なんてときも、ふらっと立ち寄れる頼もしさがあります。学生や働く人にとっては、こうした“使い勝手のよさ”が何より大事だなと実感します。
アメリカ生活において、一番現実的で使いやすいスーパーかもしれません。

ちなみに季節のイベントが近づくと、スイーツ売り場が一気に華やかになります。これはバレンタイン前のある日。ピンクや赤のアイシングがたっぷり乗ったケーキやカップケーキが、ずらーっと並んでいて圧巻でした。味は…正直かなり甘め(笑)。でも、「甘さ=ご褒美!」という感じがして、疲れた日にはちょっと買ってしまうことも。アメリカの“見た目重視”スイーツ文化、ぜひ一度味わってみてほしいです。
▸ Walmart:圧倒的な安さと品揃え
アメリカに暮らし始めてしばらくすると、「あれもこれも必要…でもできるだけ出費は抑えたい」という場面が増えてきます。そんなときに頼りになるのが、Walmart(ウォルマート)。
全米に4,600店舗以上を構えるこの巨大チェーンは、「Everyday Low Price(毎日低価格)」を掲げていて、とにかく安い・広い・なんでもある!という三拍子が揃ったスーパーです。食料品や飲み物はもちろん、日用品、洋服、アウトドアグッズ、文房具、家電、医薬品まで本当に何でもあって、「生活に必要なものが一気に揃う」心強い存在です。
特に私がよくチェックするのは、プライベートブランド「Great Value」の商品。パッケージはシンプルだけど、値段はびっくりするくらい安くて、味や使い勝手も悪くない。節約したい時やまとめ買いにはぴったりのアイテムが揃っています。
そして何より、店内がとにかく広い。大きなカートを押しながら、現地の人たちと同じ空間で買い物をしていると、ちょっとしたローカル気分も味わえます。旅行中の忘れ物を探すときにも便利だし、「今日はなんでもいいからとにかく全部買いたい!」という日にぴったりの、アメリカらしさ全開のスーパーです。
▸ Target:使い勝手のよい“バランス派”スーパー
何かと便利でよく通っていたのがTarget(ターゲット)。食品だけでなく、日用品や衣類、家電、文房具、おもちゃ、ベビー用品まで幅広く取り扱っている大型店舗で、まさに「日常のあれこれが一気に揃う場所」といった感じです。
お店の中心は生活用品や雑貨の売り場で、食品コーナーは店舗によっては小さめ。とはいえ、冷凍食品やパン、飲み物、簡単な食材などは一通りそろっているので、ちょっとした買い物には十分。特に「洗剤切らした」「トイレットペーパー買わなきゃ」みたいなときに、ついでに食料品も買えるのがありがたかったです。
あと、個人的にはコスメ売り場もよくチェックしていました。ドラッグストアブランドがきれいに並んでいて、新商品もすぐに入荷されるので、見ているだけでも楽しくて。つい予定外のものまでカートに入れてしまうのはTarget“あるある”かもしれません。
「普段使いの便利さ」もありつつ、「ちょっと気分が上がる空間」でもあるのがTargetの魅力。気軽に立ち寄れて、生活が少し楽しくなるような、そんな存在です。
アメリカ暮らしに寄り添う、日系スーパーの存在
アメリカでの生活が始まってしばらくたった頃、ふと恋しくなったのが、日本の味や空気感でした。異文化の中での暮らしは刺激的で楽しいけれど、毎日が新しいことの連続で、気づかないうちに少しずつ心も体も緊張していたのかもしれません。
そんなときに見つけたのが、日系スーパーの存在でした。日本のお菓子や調味料、お弁当やお惣菜。お店に入った瞬間、漂ってくる“なじみのある匂い”や“聞き慣れた言葉”に、心がふっとゆるむのを感じました。
ここでは、私がアメリカ生活の中で出会った日系スーパーの魅力や、どんなふうに日常を支えてくれたかを紹介していきます。
スーパーを超えた、“小さな日本”
カリフォルニア州はアジア系の人口も多く、地域によってはアジア食材がかなり手に入りやすいのも特徴のひとつ。日系スーパーだけでなく、韓国系や中国系の大型スーパーも点在していて、アメリカにいながらにして本格的なアジア料理を楽しむことができます。中でも、日系スーパーとしてよく知られているのが、Tokyo Centra、Mitsuwa Marketplace、Nijiya Marketの3つ。それぞれに特色があり、「今日はどこに行こうかな」と選ぶのも、ひそかな楽しみになっています。
少し高くても、そこにある“安心”
もちろん、日本の商品はアメリカの現地スーパーの商品と比べると、どうしても少し割高です。、日本では気軽に買えるものが、こちらでは数ドル高い価格で並んでいたりします。それでも手が伸びてしまうのは、その商品に「安心感」が詰まっているからかもしれません。
たとえば、学校やインターンでくたくたに疲れた日の夜。冷凍のうどんを温めて、出汁のきいたスープをすすった瞬間、なんとも言えない安心感に包まれたことが何度もあります。
日系スーパーで買った“いつもの味”は、私にとって異国の暮らしの中で心を支えてくれるアイテムのひとつになりました。たとえ少し高くても、「また頑張ろう」と思えるきっかけをくれるなら、それはもう十分すぎる価値だと思います。
“帰れる場所”がある心強さ。日系スーパーは、生活の“支え”
レジで「こんにちは」と声をかけられたり、店内BGMで日本の音楽が流れていたり、日本語のポップが並んでいたり。日系スーパーにいると、少しだけ“肩の力が抜ける”感覚になります。どんなに異文化に囲まれていても、「帰れる場所」がある。それだけで、心の余裕が少し戻ってくるんです。
アメリカでの生活は、新しい発見と同じくらい、戸惑いもあります。そんな中で、日系スーパーの存在は、生活の“支え”になってくれました。ただ日本の食材を手に入れるだけでなく、心がちょっと疲れたときに寄り添ってくれる場所。日系スーパーは、アメリカでの暮らしにそっと寄り添う、そんなあたたかい存在です。
節約術・日常生活での工夫
アメリカに来てから、「食費ってこんなにかかるの!?」と何度も思いました。特に最初の頃は、物価の感覚がつかめず、「パンと卵と野菜しか買ってないのに20ドル超えてる…?」とびっくりすることも。もちろん、円安の影響や地域差もあると思うのですが、“ちょっとした買い方の工夫”が積み重なると、生活はぐっと楽になると感じています。
ここでは、私が実際にやっている節約&暮らしの工夫を3つ紹介します。
▸ 会員登録+アプリでクーポン活用(Ralphs)
アメリカ生活でまず覚えたのが、「スーパーの会員登録をすると本当にお得になる」ということ。特にRalphsは、会員になると価格が一気に変わります。「同じものを買っているのにこんなに差が出るの?」と最初はびっくりしました。
登録自体はすごく簡単で、ネットか店頭で電話番号を登録するだけ。あとはレジで「Do you have a phone number?」と聞かれたときに、自分の番号を伝えればOK。
アプリも必須で、セール情報や自動で適用されるクーポンが一覧で見られるので、事前にチェックしてから買い物に行くようにしています。クーポンを探すのも、ちょっとした“お宝探し”感覚で楽しいです!
▸ ファーマーズマーケットで新鮮&お得に
週末の午前中などに開催されているファーマーズマーケット(直売市場)も、節約とリフレッシュを兼ねてよく行きます。
ローカルの農家さんが直接出店していて、スーパーよりも新鮮な野菜や果物を安く買えることが多いんです。しかも、試食ができるブースや、生演奏している場所もあって、ちょっとしたイベント感があって楽しい!
見た目が不揃いだったり、小さかったりしてスーパーには出せないけど、味はしっかり美味しい!という“訳あり商品”も多く、そういうのを見つけるのも楽しみ方の一つです。見た目がちょっと不揃いな分、お得な価格で販売されていることもあり、「味と量で選ぶならここ!」という感じ。
なにより、生産者さんと直接やりとりできる安心感があるのが魅力。英語で話すのがまだ少し緊張するときもあるけれど、みんな優しくて、自然と会話も弾みます。現金しか使えないお店もあるのでちょっと注意は必要ですが、「買い物しながら現地の人と触れ合える」という面でも、留学生には嬉しい場所だと思います。
おわりに:スーパーから見えたアメリカの暮らし
戸惑いの中にあった、“暮らす”という感覚
アメリカでの生活が始まったばかりの頃、毎日が“わからないこと”だらけでした。街のルール、言葉の壁、人との距離感――どれも新しくて、どれも少し怖かった。でもそんな中で最初に「ここで私は暮らしてるんだ」と実感したのが、スーパーでの買い物でした。レジで何か聞かれても、とっさに返事ができなくて、笑ってごまかしてばかりだった日もあります。だけど、そうやって少しずつ試行錯誤するうちに、スーパーという場所が“生活の練習場”のように思えてきました。
日常の中で出会う、小さな発見と学び
日本でスーパーに行くときは「効率的に買って早く帰る」のが当たり前だった私にとって、アメリカのスーパーは「楽しみながら選んで、人と関わって、新しい価値観に出会える場所」になりました。買い物ひとつとっても、文化の違いって面白い。そう思えるようになった今、スーパーに行くのがちょっとした“冒険”のように感じられています。
もしこれからアメリカに来る予定がある人がいたら、ぜひ一度、近くのスーパーをのぞいてみてください!きっとそこには、その土地ならではの“暮らしのリアル”が詰まっていて、あなたなりの発見や気づきが待っているはずです。