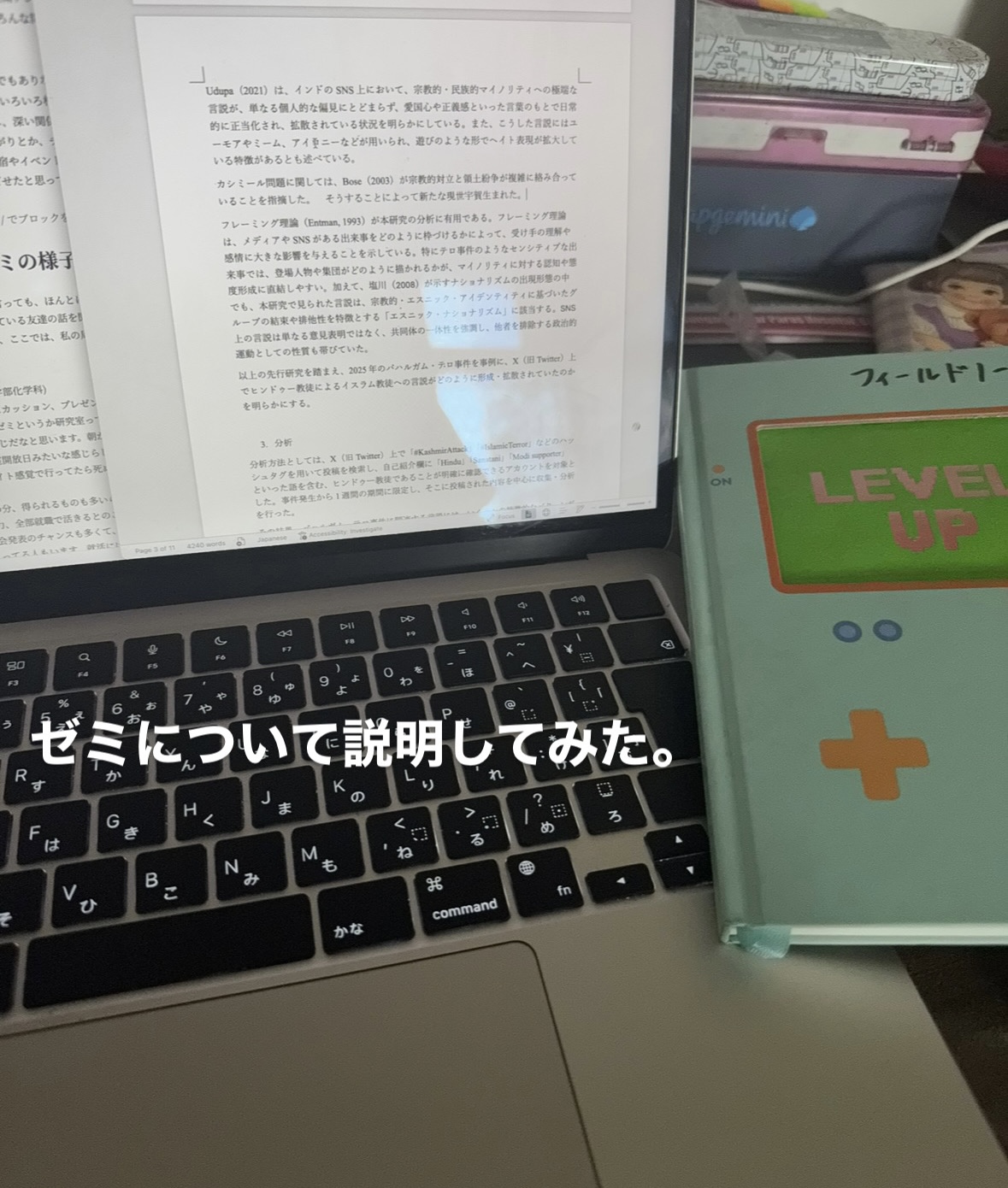目次
はじめに
ゼミって名前は聞くけど、ぶっちゃけ何するのか、入ったら大変そうだし、自分に合うかわからないという人は多いと思います。
しかも大学、学部によっては2 年間や3年間同じゼミだったりするので大学生活を締める比重は高いです。
私の場合ゼミが始まってみるとゼミは想像以上に面白くて、しんどいけど自分を成長させてくれるものでした。本記事では、国際協力ゼミに所属する私が感じたリアルなゼミライフをベースに、
- ゼミってそもそも何をするところ?
- 国際協力ゼミの具体的な1年間の流れ
- 理系・文化人類学・通訳翻訳系など他分野ゼミの生態
- ゼミ選びで後悔しないためのチェックポイント
- 実際に得られたスキルや人脈、そして“心のタフさ”
などを、学生目線でレビューします。
そもそもゼミってなんのため?
ゼミは自分の関心分野を深めて、自分から学ぶ場所です!受け身の学習というよりは自分で動くタイプの学習って感じです。
自分の興味のある国や文化、NGOなどフィールドなどに行って調査してまとめて、、、みたいな感じで受動的な講義と違って能動的な学習です。
一般的な講義とは違い、ゼミは少人数で行われるのが特徴!
ディスカッション、プレゼン、レポート、フィールドワークなどを通して、より実践的で対話的な学びができます。ただただ知識をインプットするのではなくて、自分で問いを立てて考え、それについて調べて、それを発信する力が求められます。毎週のゼミで進捗を発表してみんなからフィードバックをもらって研究を磨いていくことができます!
また、ゼミは個々というよりは仲間と学ぶ場でもあります。文系理系のゼミの差で一番大きいのはこれです。毎週同じメンバーと顔を合わせ、議論や共同作業を重ねていくうちに、自然と仲間意識や信頼関係が生まれてきます!
実際に私は、国際協力系のゼミに所属して、自分が何に関心があるのか、どんな社会課題に向き合いたいのかを深く考える機会になりました。
もちろん、ゼミによって雰囲気や内容、求められることは大きく異なりますし、全てのゼミが楽しいとは限らないし、合わないと感じることもあると思います。自分の興味に近いテーマを選び、少しでも主体的に関わろうとすることで、学びの深さも大学生活の充実度も大きく変わると感じました!
自分の問いだったり疑問と向き合う場として、ゼミをうまく活用してみてください。
私のゼミ(国際協力ゼミ)はこんな感じ!
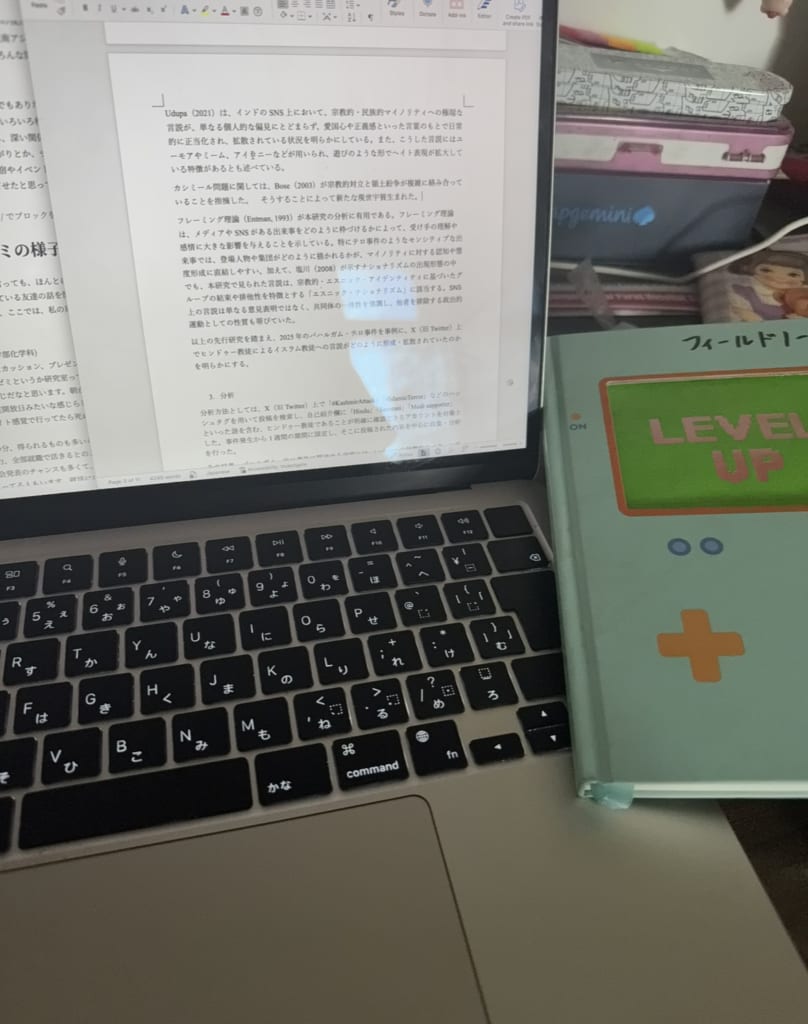
私が所属しているのは「国際協力ゼミ」で、毎週のゼミではそれぞれが研究の進捗を発表し、それに対して先生や他のゼミ生からフィードバックをもらいます。
私も対象地域は南アジアですが、アフリカの人もいたり東南アジアの人もいるので自分の知らないことを友達の発表によって学べます!
他の人の研究テーマを聞いてそんな視点があるのかと驚かされたり、自分では思いつかなかった問いや文献を紹介してもらったり一人で学ぶより、仲間と学ぶほうが深まるなと個人的には思います。
うちのゼミは特にフィールドワークを重視していて、ただ机の上で文献を読むだけじゃなくて、自分の足で現地に行って、自分の目で見て、観察やインタビュー、統計集めなどをして、一次データを集めることが求められます。
私も実際にインドのウッタル・プラデーシュ州のラクナウという地域を対象にして、どんな社会課題があるのか、どんな支援が求められているのかを自分なりに調査してまとめています。
そして、月に一度くらいの頻度で飲み会もあって、先生も含めてかなりフラットな関係性が築けているのも、このゼミの魅力です。真面目な話からプライベートな話まで、ゼミの枠を超えていろんな会話ができるので自然と仲も深まるし、このメンバーで学べてよかったなと思える瞬間がたくさんあります!中には卒業後もつながっている先輩もいて、進路の相談やアドバイスをもらえることもあります。
他のゼミと比べて、ただ知識を深めるだけじゃなく、自分が社会に対して何ができるのか?という問いを常に考え続けるゼミだと感じています。国際協力というテーマ自体がとても広く、難しさもあるけど、その分自分の価値観や将来像と真剣に向き合える貴重な時間になっています!
良かったこと・得られたもの
まず一番に感じたのは、ゼミに入ってなかったら、ここまで自分の興味分野に対して向き合うことってなかったなということです。
大学の授業は、基本的には与えられた課題をこなしていけば単位が取れるけど、ゼミってそうはいかないので自分でテーマを決めて、自分で調べて、自分の言葉で伝える必要があります。正直めちゃくちゃ大変です。
でもその分、これは自分の研究だ!と胸を張って言える感覚があって、大学での大きな学びになります。そして他の大学の友達や親戚などに異文化コミュニケーション学部って何を学んでいるの?と聞かれた際に答えやすいです笑
国際協力はテーマは広くて、何にフォーカスするかどこの地域を対象地域とするかなど決めることが多いのですが、その分深く考える力がつきました。この支援って本当にその地域に合ってるの?自分は外の立場としてどう関わるべき?」とか、自分なりのスタンスを見つけていく過程がすごく貴重でした。
私の場合は支援が上から目線になってしまうのではないかということが課題でした。特にフィールドワークで現地の人と話した経験は、単なる知識じゃなくて実感として記憶に残っています。
あと、発表の機会が多いので、人前で話す力・資料をわかりやすくまとめる力・相手に伝える力、全部鍛えられました。最初はめちゃくちゃ緊張して原稿ガチガチにみてという感じだったけど、ゼミで何度も発表してるうちに、自然と慣れてきて、自信もついてきました。これは間違いなく就活や社会に出てからも活きるスキルだと思います!
ゼミの仲間との関係性も、大学生活の中で本当に大きな支えでした。学年も背景も違うメンバーが、それぞれの視点で意見をくれるから、視野が一気に広がります。南アジア、アフリカ、東南アジアなど、みんなが違う地域に関心を持っていて、毎週のゼミが世界のいろんな問題を知る時間みたいで、ただの授業以上の価値がありました。

他のゼミの様子
理系ゼミ(理学部化学科)
ゼミ=ディスカッション、プレゼンと思ってた私には完全に違いました笑笑理系の友達は、ゼミというか研究室って感じとよく言ってます。
朝から実験、昼も実験、夕方も実験、そして土曜日も研究室開放日みたいな感じらしいです
週3〜4日は普通にラボにこもっていて、バイト感覚で行ってたら死ぬって言ってました笑
でもその分、得られるものも多いらしく、機材の扱い方、データ分析、論文の読み書き力、全部就職で活きるとのこと。ゼミというより職場に近い感じかもです。学会発表のチャンスも多くて、大学4年にしてプロの研究者みたいな雰囲気をまとってる人もいます。就活にはめちゃくちゃ強いです!!(羨ましい)
大学院進学する人も多くて、研究ガチ勢が集まっています。
文化人類学系ゼミ
フィールドワーク重視の傾向があります。日本でも海外でもOKで、人と文化に注目するゼミです。
たとえば「なぜ日本の若者は〇〇を恥ずかしがるのか?」とか「地方の伝統行事がどうやって変化してきたか」みたいな、ちょっと変わった視点から文化を掘っていく感じで面白そうです。Youtube を取ることが課題だったりとたまに羨ましかったりします
ある友達は、都内の純喫茶に通って常連客のふるまいをひたすら観察する研究をしてました笑「なんでそうするのか」を言語化するのがめちゃくちゃ難しいけど、そこに面白さがあるみたいです。インタビュー、街歩き、フィールドノートなどアナログな手法が多くて、文系っぽさ全開ですが楽しいと思います!!
通訳・翻訳系ゼミ
これはもうスキル重視の実践系って感じで通訳翻訳の資格なんかも取れます!
英語や他言語を使って実際に翻訳や通訳のトレーニングをするゼミで、将来そういう仕事を目指している人には超人気です。毎週の課題では映画字幕を訳してきたり、国連の公式文書を翻訳したりするそうです!内容も文体も難しいから、ひとつの文章にめちゃくちゃ時間がかかるらしくてテストもまるみたいです。
なんでその訳にしたの?ってゼミ中に詰められるらしく、ちょっとした公開処刑感もあるみたいですがそのぶん、語学力・表現力・読解力は段違いに伸びるそうで、みんなゼミ後には脳が筋肉痛状態になるけど満足感も高いって言ってました。
ゼミ選びで後悔しないために
たとえば、論文を読んで理論を学ぶよりもより人と関わるのが好き!って人なら、フィールドワーク系のゼミとか、議論中心のゼミが合うかもしれません。逆に、一人でじっくり考えるのが得意って人は、文献中心のゼミでこつこつ調べるのが合ってると思います。自分の性格や得意なことをゼミ選びの軸にしてみるのもすごくいいです!
まとめ
ゼミって最初はマイナスなイメージを持ちがちなんですが、振り返ってみると、大学生活の中で一番自分と向き合った場所だったなと思います。
締め切りに追われたり、プレゼンの準備に追われたり、他の人のレベルの高さに落ち込んだり、行きたくないな〜って日もありました。でも、それでも続けてきたからこそ、ちゃんとやってきてよかったと思える経験が積み上がった気がします。
ゼミは、知識を得るだけの場ではなく、自分が何に興味を持ち、何を大事にしたいのかを考える時間でもあります。そして、仲間にも出会える場所でもあります。
だからこそ、ゼミを選ぶときは、自分が何を学びたいのか、どんな風に学びたいのかを、考えてみてほしいです。なんとなく面白そうで一歩踏み出した結果、思いがけない方向に世界が広がることもたくさんあります。