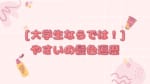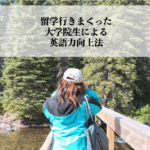こんにちは!早稲田大学4年のなおきです。
大学生活のハイライト――そう言っても過言ではないのが「学園祭」です。
サークル、ゼミ、有志団体など、さまざまなグループが一斉に動き出し、数か月かけて準備してきた企画を一気に披露する。
その熱量とスケールは、高校の文化祭とはまったく違う次元にあります。
僕自身、早稲田祭にサークルとして出演したり、企画運営に関わったりする中で、「人とのつながり」「新しい挑戦」「やり切った達成感」の3つを強く実感しました。
そしてその過程で、企画力・スケジュール管理力・統率力といった社会でも通用するスキルが自然と身についていたのです。
学園祭は、単なる“お祭り”ではなく、「チームで一つの目標を形にする」総合的な経験の場。
この記事では、そんな学園祭を通して得られる3つの学び――人脈・挑戦・達成感を軸に、企画から本番までのリアルな成長ストーリーを紹介していきます。
目次
学園祭は「出会いの宝庫」――人脈が広がる場
学園祭に関わる最大の魅力のひとつは、普段出会えない人たちとつながれることです。
クラスやサークルといった小さな枠を越えて、学部・学年・さらには他大学の学生まで、思いもよらない縁が生まれます。
たとえば早稲田祭では、出演団体だけで500以上。
模擬店、ステージ、展示、運営スタッフなど、立場も得意分野もバラバラな人たちが集まります。
その中で、一緒に企画を動かしたり、備品を貸し借りしたりするうちに、自然と人脈が広がっていくのです。
学部やサークルの垣根を越えた“チーム”が生まれる
学園祭の魅力は、「知らない人と本気で協力できる場」だということ。
同じ学部の友人とは違い、たまたま担当になった他学部の人と打ち合わせを重ねる中で、考え方や価値観の違いに刺激を受けることも多いです。
僕自身、サークル「ヨコシマ。」としてライブ出演をしたとき、音響担当の学生やステージ管理スタッフなど、これまで関わりのなかった人たちと協働することになりました。
「こういう人がいなければ、自分たちのライブは成り立たない」と気づいたとき、“裏方のすごさ”と“チームで動く大切さ”を実感したのを覚えています。
このように、学園祭は「サークル内のつながり」から一歩外に出るきっかけをくれます。
普段話さないタイプの人とも一緒に何かを作り上げる経験は、確実に自分の人間関係を広げてくれます。
SNS発信や広報活動で“外の世界”ともつながる
近年の学園祭では、SNSでの告知やプロモーションも欠かせません。
XやInstagramを通じて、一般の来場者や企業、OB・OGなど、多様な層に自分たちの活動を届けることができます。
たとえば早稲田祭では、協賛企業への提案を学生が直接行うケースもあります。
パンフレット広告をお願いしたり、企業ブースを設けたりする中で、社会人とのやり取りを学生のうちに経験できるのです。
実際に名刺交換やプレゼンをすることもあり、「学生でもここまで任せてもらえるんだ」と驚くことも多いです。
また、SNS経由で他大学のサークルや卒業生とつながることも珍しくありません。
「次は合同イベントをしよう」「映像コラボしてみよう」といった新しい関係が生まれることもあり、学園祭が終わってからも交流が続くケースが多いのです。
一度の出会いが“人生の転機”になることもある
学園祭の不思議なところは、たった数日の出来事が、その後の人生に影響することがあるという点です。
一緒に企画を進めた相手が、のちに同じインターンや就職先で再会したり、学園祭で仲良くなった先輩から社会人としてのアドバイスをもらったり。
そうした“偶然の出会い”が、後々の進路や人間関係にまでつながることもあります。
僕の友人の中には、学園祭で出会った他サークルの人と意気投合し、卒業後に一緒にイベント企画会社を立ち上げたという例もあります。
こうしたケースを見ると、学園祭が単なる行事ではなく、“人の可能性をつなぐ舞台”でもあることがわかります。
信頼関係が“学内ネットワーク”を広げていく
学園祭では、当日の出演だけでなく、機材の手配・設営・撤収などの細かい部分でも多くの協力が必要です。
その過程で「この人なら任せられる」という信頼が生まれ、次のプロジェクトでも声をかけてもらえるようになります。
つまり、学園祭のつながりは“その場限り”では終わらないのです。
大学生活は意外と短く、知り合う人の数には限りがあります。
だからこそ、学園祭のように大勢が同じ目標に向かって動く場は、人脈を広げる貴重なチャンスです。その中で築いた信頼関係は、ゼミ活動や卒業後の仕事にも必ず生きてきます。
学園祭で得られる人脈は、単なる「知り合い」ではなく、一緒に汗を流して何かを作り上げた仲間です。
協力して一つの目標を達成した経験があるからこそ、その絆は深く、長く続きます。
この出会いの連続が、大学生活をより豊かにし、自分の視野を大きく広げてくれるのです。
「企画」段階で試されるのは“発想力と提案力”
学園祭の準備は、まず“企画”から始まります。
どんな内容にするか、どうすれば来場者が楽しめるか――考えることは山ほどあります。
この段階では、発想力と提案力が問われると同時に、現実的な実行プランに落とし込む力も必要です。
僕が所属しているサークル「ヨコシマ。」と「Ws.dolce」でも、それぞれ違った形の企画がありました。
どちらも華やかに見えますが、実際は裏で地道な計画と調整の連続。
ここでは、その“企画の裏側”を少し紹介します。
ヨコシマ。の早稲田祭ライブ――2日間の大規模企画をどう形にするか
ヨコシマ。では、毎年の早稲田祭で2日間にわたるライブを開催しています。

出演者だけで百名以上、観客を含めればさらに多くの人が訪れます。
まずは両日の参加人数(演奏者+観客)を集計し、それに見合うライブハウスを予約するところから始まります。
ここで問われるのが、企画力と調整力。
キャパが小さすぎるとステージが窮屈になり、大きすぎると費用がかさむ。
そのため、複数の会場候補を比較し、立地・音響設備・料金のバランスを考えて最適な場所を選びます。
さらに、ステージ進行表の作成や各バンドのリハーサル時間の調整など、本番を見据えた緻密なスケジューリングも欠かせません。
僕が2年生のときにその調整を担当した際、特に大変だったのは「人の時間を動かすこと」でした。
ひとりの遅刻やリハ延長が全体に影響するため、全員の予定を事前にすり合わせ、当日は秒単位で進行管理。
まるで小さなフェスを運営しているような緊張感がありました。
ライブの成功は演奏の上手さだけでなく、裏方の企画力とチームワークの精度に支えられています。
限られた予算と時間の中で最大限のパフォーマンスを実現する――この経験が、後に他の活動でも活きてくるのを感じました。
Ws.dolceの屋台企画――「安全×魅力×効率」を両立させる戦略
一方、もうひとつのサークル「Ws.dolce」では、早稲田祭で手作りスイーツの屋台を出店しています。
僕たちの代では、販売したのは「フルーツ最中(もなか)」。

和と洋を融合させた新感覚スイーツとして、見た目も華やかで話題を呼びました。
まず最初に行うのは、大学が配布する衛生管理ガイドブックの確認。
火気の扱い、調理エリアの制限、保存方法などを事前に把握し、ルールに沿って運営できるよう準備します。
同時に、どんな商品を販売するか、必要な材料をどこから仕入れるかを具体的に決めていきます。
フルーツ最中の場合、あんこ・フルーツ・最中の皮といった食材を複数業者から仕入れなければなりません。
特に最中の皮は、一度に大量発注する必要があるため、在庫や納期の確認が重要でした。
また、いちごやキウイなどのフルーツは鮮度が命。前日や当日にどのタイミングで購入するかも細かく計画しました。
お菓子を“作る”だけでなく、材料のロスを減らすための数量計算、シフト表作成、当日のオペレーション設計、SNSでの広報まで、まるで小さな企業を運営しているような感覚です。
企画会議では「おしゃれで映える見た目」と「調理のしやすさ・安全性」の両立に苦労しましたが、結果的に“売り切れ”で完売。
試作と検討を重ねた企画が形になった瞬間の達成感は、今でも鮮明に覚えています。
アイデアを“現実に落とし込む”ことが最大の学びになる
企画段階では、意見の食い違いも少なくありません。
「もっと凝ったスイーツを作りたい」という理想と、「時間的に難しい」「コストが合わない」といった現実の間で、折り合いをつけなければならない。
その中で重要なのは、創造性と実行力のバランスを取ることです。
どんなに面白い案でも、準備やコストの面で実現できなければ意味がない。
逆に、現実的すぎても魅力がなくなってしまう。
その中間点を探すプロセスこそ、企画の醍醐味であり、チームで意見をすり合わせる訓練になります。
学園祭の企画とは、単に「何をするか」を決めるだけでなく、どうすれば実現できるかを考える力を育てる場です。
準備期間に育つ“社会的スキル”の土台
この時期に身につくスキルは、社会に出てからも通用します。
たとえば、締切から逆算して行動する「スケジュール管理力」、
人を動かす「統率力」、
トラブルが起きたときに即座に判断する「リスク対応力」。
どれも授業や座学では得られない、実践的な社会人基礎力です。
とくにスケジュール管理では、「誰かがやるだろう」ではなく「自分が動く」という意識が大切になります。
ひとりが油断すれば全体に影響が出るからこそ、全員が“リーダー意識”を持つ必要がある。
その感覚は、チームで働くうえで最も重要な土台です。
チームをまとめる難しさと、信頼でつながる喜び
準備期間は長く、時に面倒に感じることもあります。
予定が合わない、連絡が返ってこない、思うように進まない――そんなときに必要なのが、信頼関係と声かけです。
「大丈夫?」「ここ手伝おうか?」と一言添えるだけで、雰囲気が変わることも多い。
僕自身も、途中で疲れていた後輩に「当日が終わったら全員で食べに行こう」と声をかけたことで、チームの空気が一気に明るくなった経験があります。
リーダーシップとは、命令することではなく、人を前向きに動かす力なのだと感じた瞬間でした。
学園祭の準備期間は、ただの「作業時間」ではありません。
人をまとめ、時間を管理し、問題を乗り越える――そのすべてが社会に出てから生きる実践経験です。
最初はバラバラだったメンバーが、少しずつ同じ方向を向いて動き始めるとき、そこには確かな達成感と成長が生まれます。
地味だけれど、いちばん人を鍛えるのがこの“準備の時間”なのです。
「本番」で感じる“挑戦と責任”
いよいよ迎える学園祭当日。
数か月かけて準備してきた企画が形になる、まさに集大成の瞬間です。
緊張と期待が入り混じる中で、どんな立場の学生も例外なく“挑戦”の真っ只中にいます。
この本番では、想定通りにいくことはほとんどありません。
それでも、その不確実さの中で行動し、問題を乗り越えていく過程こそが、最大の学びになります。
ここでは、僕が所属するサークル「ヨコシマ。」と「Ws.dolce」で感じた“現場の挑戦”を紹介します。
ヨコシマ。のライブ本番――「ステージに立つ責任」と「運営の緊張感」
ヨコシマ。の早稲田祭ライブは2日間にわたってライブハウスを貸し切り、出演バンドが次々とステージに立ちます。
演奏者として出るときはもちろん緊張しますが、意外と大変なのが運営側としての責任です。
開場・転換・音響チェック・リハの順番など、どれかひとつでも滞ると全体の進行が崩れる。
音響トラブルが起きたときには、ステージ裏でスタッフが即座に対応し、別のマイクを差し替えたり、照明を調整したり。
その間に会場が静まり返ることもありますが、それでも焦らず場を繋ぐ――そんな冷静さが求められます。
僕が2年生のときに印象的だったのは、ある出演バンドのリハ中にケーブルが断線してしまったこと。
予定が10分以上押しそうになった瞬間、ステージ班・受付班・音響班が連携して次のバンドを先にリハへ回す“即興判断”を行いました。
結果的に、遅延を最小限に抑えて予定通り進行。
このとき初めて、「臨機応変に動けるチーム」がどれほど強いかを実感しました。
本番では、自分がステージに立つだけでなく、裏方として支える挑戦もある。
どちらの立場でも共通して言えるのは、“全員でつくる舞台”という責任感です。
Ws.dolceの屋台運営――瞬時の判断とチームワークが命
屋台を出す「Ws.dolce」でも、本番当日は緊張の連続です。
朝早くから仕込みを行い、開場時間に合わせてお菓子を並べ、客足の様子を見ながら販売量を調整します。
僕たちの販売した「フルーツ最中」は人気が高く、開始から1時間ほどで行列ができるほどでした。

しかし、想定以上の売れ行きで、あんこやカットフルーツの在庫が足りなくなり、途中で急遽買い出し班を出すことに。
その間、販売メンバーが手を止めるわけにはいかないため、全員で臨時対応に回るチームワークが求められました。
また、予想外に気温が高かったため、最中の皮が湿気を吸いやすくなり、保管方法をその場で変更。
「冷却バッグに分けて保管しよう」「少量ずつ出して入れ替えよう」と判断しながら販売を続けました。
このような現場判断の連続が、まさに“挑戦”そのものでした。
その一方で、お客さんから「かわいい!」「おいしい!」という声が聞こえたときの嬉しさは格別。
自分たちの手で企画したものが目の前の人に届く――その瞬間、準備の苦労が一気に報われました。
トラブルも含めて“学び”になる
学園祭の本番では、必ずと言っていいほど想定外の出来事が起こります。
天気の急変、音響トラブル、材料不足、メンバーの遅刻……。
しかし、そのたびに頭をフル回転させ、どうにか解決しようとする。
この“現場の瞬発力”が、後になって大きな糧になります。
実際、僕はこの経験を通して、「想定外に強くなる」ことの重要性を学びました。
事前に完璧な計画を立てても、現場では必ず何かがズレる。
だからこそ、そのズレを前提に考え、対応できる柔軟さが必要になるのです。
これは、社会に出てからも大切な資質だと思います。
やりきったあとの“達成感”と“喪失感”
本番が終わると、長い準備期間のすべてが報われるような達成感が押し寄せます。
ステージでの拍手、屋台の「おいしかったです!」という声、運営スタッフ同士の笑顔――どんな立場であっても、全員がそれぞれの形で「やりきった」と実感する瞬間があります。
けれど同時に、祭りの熱気が冷めていくと、少しずつ“喪失感”もやってきます。
それほど全力で取り組んだからこそ生まれる、静かな余韻です。
達成感の裏にある“喪失感”――終わりがあるからこそ尊い
学園祭が終わると、日常に戻ったときのギャップが大きく感じられます。
数週間、いや数か月もの間、学園祭を中心に生活してきた人ほど、その“祭りのあと”は静かに寂しい。
会議も連絡もなくなり、グループLINEが急に動かなくなったとき、「あの忙しさがちょっと恋しい」と思うことさえあります。
けれど、その喪失感は、全力で取り組んだ証拠でもあります。
本気で人と関わり、時間を費やして、何かをやり遂げたからこそ感じるもの。何もしていなければ、こんな感情すら生まれません。
学園祭のあとに訪れる静けさの中で、自分の成長をじっくり振り返る人も多いです。
「あのときもっとこうすればよかった」「来年はこうしたい」――そうした思考が、次の挑戦への原動力になります。
チームでやり遂げた経験が“自信”に変わる
達成感を超えて、もうひとつ心に残るのが「自分にもできた」という自信です。
大人数をまとめること、複雑な企画を成功させること、何百人もの前で演奏すること――最初は不安だらけでも、やってみると必ず得るものがあります。
ヨコシマ。のライブでは、練習の段階で「間に合わないかも」と焦った時期もありました。
でも、最終的に笑顔で終えられたことで、「努力すれば何とかなる」という感覚が身につきました。
それは、学業や就活、社会人になってからの仕事にもつながる大切なマインドです。
同じように、Ws.dolceの屋台運営では、限られたリソースの中で効率よく動く経験を積めたことで、後のインターンシップでも「リーダー的に動く勇気」が持てました。
学園祭の成功体験は、ただの思い出ではなく、次の行動を後押しする力になるのです。
学園祭の終わりには、達成感と喪失感の両方が残ります。
でも、その両方を味わえるのは、全力で取り組んだ人だけ。
仲間と過ごした濃密な時間、支え合って乗り越えたトラブル、最後に感じたあの静かな幸福感――それらが、大学生活の宝物になります。
そして、時間が経って思い返したとき、きっとこう思うはずです。
「また、あの頃みたいに何かに本気で打ち込みたいな」と。
学園祭で得た学びは就活にもつながる
学園祭で得た経験は、単なる「学生時代の思い出」では終わりません。
実は、就職活動で最も活かしやすいエピソードのひとつでもあります。
企業が学生に求めているのは、アルバイトの経験よりも、「チームで目標に向かって動き、課題を解決した経験」。まさに、学園祭の中で得られる力と重なります。
僕自身も就活を進める中で、早稲田祭でのライブ運営や屋台企画の話を面接で話したことがありました。
そのとき実感したのは、学園祭の経験は、社会で必要なスキルを“言語化できる形”で示せるということです。
自分の役割を“成果”として語れる
就職活動では、「自分はどんな役割を担い、どう貢献したのか」が重要視されます。
その点、学園祭では、役割分担が明確なため、アピールの具体性が出しやすいのです。
たとえば、ヨコシマ。のライブ運営なら、
- 出演者・観客数を踏まえて最適なライブハウスを選定した
- 全体スケジュールを作成し、当日の進行管理を担当した
- 音響トラブル時に他班と連携して迅速に対応した
こうした具体的な行動を挙げることで、「調整力」や「問題解決力」を面接で説得力をもって伝えることができます。
また、Ws.dolceの屋台企画なら、
- 販売商品を企画し、あんこ・フルーツ・最中の皮を仕入れ先と調整
- 当日のシフト管理や在庫確認を担当
- SNS広報で来場者を増やす戦略を立案
このように語ると、「企画力」や「実行力」「責任感」が自然に伝わります。
面接官が重視するのは「どんな活動をしたか」よりも、「どう考えて動いたか」。学園祭はその思考と行動のプロセスを語るのにぴったりなのです。
「困難をどう乗り越えたか」が差を生む
就活の面接では、よく「困難を乗り越えた経験を教えてください」と聞かれます。
そのときに、多くの学生が一瞬詰まってしまうのですが、学園祭に関わっていた人はこの質問に強い。
なぜなら、学園祭には必ず何かしらのトラブルがあるからです。
スケジュールの遅れ、機材トラブル、天候不良、メンバーの体調不良、在庫切れ…。
その一つひとつに対処してきた経験が、「自分はどう判断し、どう動いたのか」を語る素材になります。
たとえば僕は、ヨコシマ。のライブで機材トラブルが起きた際に、ステージ班・音響班・広報班の間で連絡を取り合い、進行を止めずに乗り切った経験を話しました。
「想定外の事態にも冷静に対応し、チーム全体を見渡せた」と評価され、実際に面接官から「まさに現場リーダー的な判断力ですね」と言われたこともあります。
このように、“困難”を“成長”に変えた体験として語れるのが、学園祭の強みです。
チームで動く力=どんな職場でも通用する力
どんな業界・職種でも、チームで仕事を進める場面は必ずあります。
そのときに求められるのは、「報連相」「役割分担」「モチベーション維持」など、まさに学園祭で培われた力。
ヨコシマ。のライブ運営では、100人規模のメンバーが関わる中で、報告や共有の重要性を痛感しました。
また、Ws.dolceでは、販売チームと調理チームの連携が取れないと、お客さんを待たせてしまう。
そうした体験を通じて、「チームで成果を出すとは何か」を肌で理解できました。
面接でこのような経験を話すと、単なる「協調性」ではなく、「チームに貢献できる実践力」として伝わります。
「主体的に動いた経験」としても使える
企業は、主体的に動ける人を求めています。
つまり、言われたことだけでなく、「自分で考えて行動した経験」があるかどうかが問われます。
学園祭は、まさにその代表例。
誰かに指示されて動くのではなく、「どうすればもっと良くできるか」を自分たちで考え、実行する。
その主体性をアピールできるのは、学園祭に深く関わった人の特権です。
たとえば、屋台で「フルーツのカットサイズを少し大きくしたほうが映える」と自発的に提案したこと。
ライブで「照明を曲の雰囲気に合わせよう」と工夫したこと。
そうした“小さな改善提案”も、企業から見れば「自ら考えて動ける人材」として映ります。
学園祭の経験は「ガクチカ」の王道
就活でよく聞かれる質問――「ガクチカ」。
実はこの回答として、学園祭経験は非常に汎用性が高いです。
理由はシンプルで、
- チームでの協働経験がある
- 課題解決のプロセスを語れる
- 成果や数字(来場者数・売上など)を示せる
この3点を兼ね備えているからです。
たとえば、次のように語ると非常に効果的です。
「学園祭で〇〇を企画・運営しました。準備段階では△△という課題がありましたが、メンバーと役割を分担し、□□の工夫を行った結果、目標の〇〇を達成しました。」
このように“課題→行動→結果”の流れを整理すれば、どの企業でも通用するガクチカに変わります。
学園祭で得た学びは、就活における“最高の自己PR素材”です。
どんな立場でも、そこには企画・実行・協働・改善といったプロセスがあり、それを言語化できれば大きな武器になります。
「楽しかった」だけで終わらせず、「自分は何を考え、どう動き、何を学んだか」まで落とし込むこと。
それができれば、学園祭はあなたの強みを最も自然に伝えられる経験になります。
「責任」と「自由」が両立する数少ない経験
学園祭の特別さは、自分たちの手で全部を決められる自由さにあります。
何を企画するか、どんな表現をするか、どう見せるか――全部、自分たちの判断で進める。
でも同時に、その結果に対しては自分たちが責任を取らなければならない。
だからこそ、学園祭は“責任ある自由”を体験できる貴重な場です。
社会に出ると、上司やクライアントが意思決定の最終権を持つことが多いですが、学園祭では学生が自分の力で判断し、実行し、結果を受け止める。成功も失敗もすべて自分たち次第――そのリアルさが人を成長させてくれます。
自分を知るきっかけにもなる
学園祭は、自分の得意・不得意を知る場でもあります。
リーダーシップを発揮できた人もいれば、裏方でサポートに徹した人もいる。
「自分は人前に立つより、支える方が向いている」
「時間管理が得意かもしれない」――そんな気づきが、自分の将来を考えるヒントになる。
実際、僕は学園祭の準備を通じて「調整や管理の仕事が好きだ」と感じ、それが今の就職先を選ぶひとつのきっかけになりました。
学園祭は、“自分の性格を映す鏡”でもあるのです。
終わったあとに残るものは「結果」ではなく「過程」
ステージが成功しても、売上が目標に届かなくても、最後に心に残るのは“どれだけ本気で向き合ったか”。
完璧な結果よりも、仲間と一緒に挑戦した時間の積み重ねが、自分の中に確かな経験として残ります。
学園祭は、誰かに評価されるためのものではありません。
「やってよかった」「自分、変わったかもしれない」と思えたら、それで十分。その感情こそが、大学生活最大の収穫です。
まとめ|学園祭は“青春”と“成長”の交差点
学園祭は、ただのイベントではなく、自分を試し、成長させる舞台です。
人との出会いを通して広がる世界。
挑戦を通じて得た自信。
達成感と喪失感の中で気づく、自分の限界と可能性。
そのすべてが、社会に出てからの力になります。
だからこそ、もしまだ迷っているなら、ぜひ学園祭に関わってみてください。
出演でも、運営でも、屋台でも、どんな形でも構いません。
きっと終わったあと、「あの数日間が、大学生活でいちばん濃かった」と思うはずです!